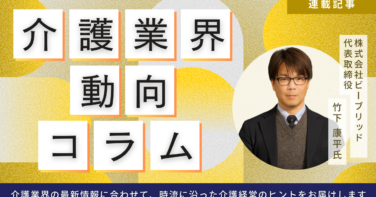【介護業界動向コラム】第13回 ICT導入から1年後に待っている現実~なぜ使われなくなるのか?補助金活用前に立ち止まって考えたいこと~
2025.07.30
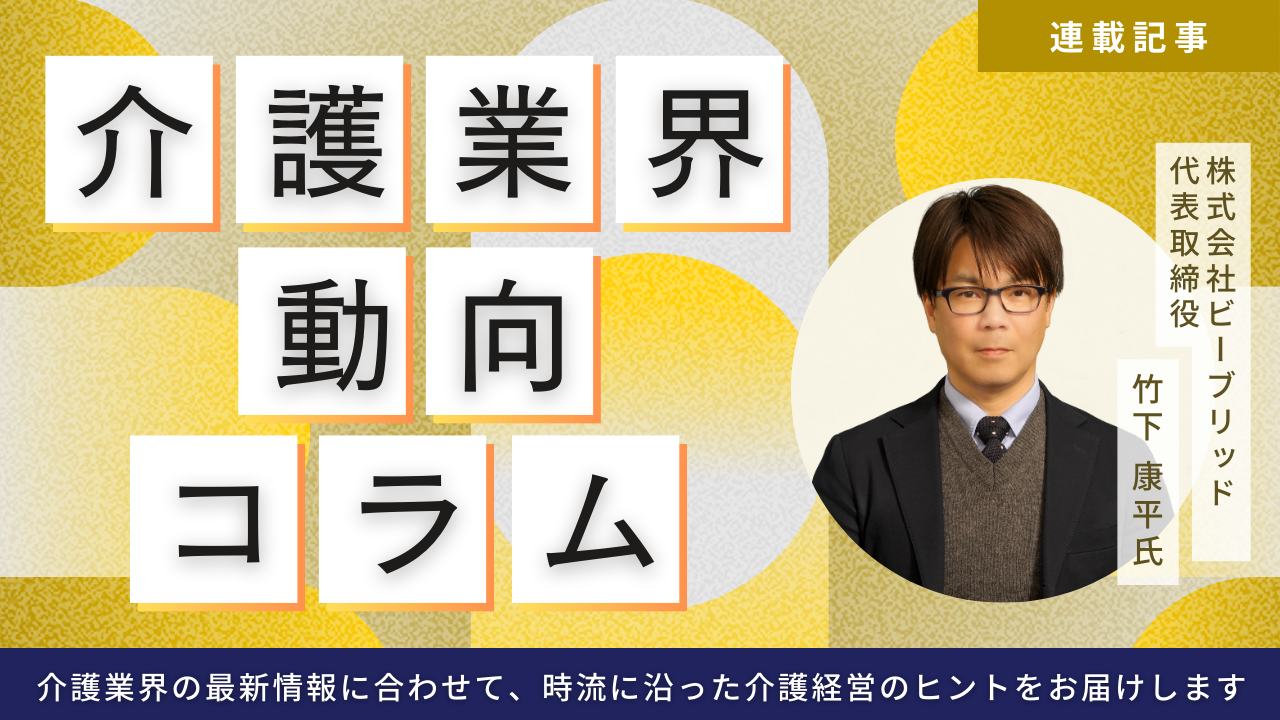
目次
ICT導入から1年後に待っている現実
なぜ使われなくなるのか?補助金活用前に立ち止まって考えたいこと
「昨年、補助金を使ってICT機器を導入した。でも、正直ほとんど使われていないんです」「しっかり効果を出せているのか不安です」
こんな声を、私たちは全国の現場で何度も耳にしてきました。今まさに、各自治体のテクノロジー導入補助金の申請が進められているこの時期。多くの介護事業者が「今年こそICT化を進めたい」と考えているのではないでしょうか。
ですが今だからこそ、あえてお伝えしたいことがあります。
「導入すればうまくいく」と思っていたICTが、1年後には“使われなくなっている”ことが少なくないという事実です。
なぜ、現場で使われなくなるのか?
ICT導入の失敗には、いくつかの共通点があります。
1つは、「何のために導入するのか」が曖昧なまま進んでしまったこと。
製品の機能や補助金の条件ばかりに気を取られ、導入の目的や課題の整理が不十分だった場合、「どう活用すればいいのか」が現場で共有されず、使われなくなっていきます。
2つ目は、初期教育の不足です。
ICTが苦手な職員もいるなかで、「わかる人が教えてあげて」と現場任せにすると、教えられない人も教える人もストレスを抱え、使うこと自体を敬遠する空気が生まれます。
例えば介護記録ソフトを導入しても、「使い方を聞く相手がいない」「エラーが出ても対処できない」といったことから、自然と元の手書きや紙の運用に戻っていくことも珍しくありません。
補助金は「買うための制度」ではない
近年のテクノロジー補助金では、単なる機器購入支援ではなく、「業務改善支援の導入」や「フォローアップ体制の構築」まで含めた取り組みが要件になってきています。
これは、国も自治体も「導入だけではICTは定着しない」ことを十分に理解しているからです。
つまり、補助金は「買う」ためだけではなく、「使いこなすまでを設計すること」そのものを支援する制度に変化してきています。
例えば、今年の要綱では、ICT導入の前に業務改善計画の策定や、第三者支援の受け入れが明記されている自治体も多く見られます。
今年の補助金活用、最初に考えるべきこと
申請書を書く前に、まずは次の3点を整理しましょう。
- なぜ導入するのか?(目的)
業務のどこに課題があり、何を改善したいのか?現場の声を必ず拾い上げて明文化しましょう。 - 誰が使うのか?誰が支えるのか?(体制)
ICTが得意な人に一任するのではなく、リーダーや教育担当を明確にし、属人化を防ぐ仕組みを。 - どのように使い続けるのか?(運用と改善)
マニュアルや研修計画、困ったときの相談窓口、改善点をフィードバックする委員会の設置なども含めて計画しましょう。
導入前の“ひと呼吸”が、1年後の景色を変える
「何を買うか」ではなく、「どう使い続けるか」から始める。
この視点をもって補助金申請を進めた施設は、1年後に「導入して良かった」と実感できています。
導入はゴールではなくスタートです。そしてその先にあるのは、ICTを通じて利用者にとっても職員にとっても働きやすく、ケアの質が高まる現場づくりです。
この夏、補助金活用をお考えの皆様へ。まずは一度立ち止まり、「導入後の運用」をイメージするところから始めてみてください。その一歩が、ICTの価値を“本当に活かす”鍵になります。

竹下 康平(たけした こうへい)氏
株式会社ビーブリッド 代表取締役
2007 年より介護事業における ICT 戦略立案・遂行業務に従事。2010 年株式会社ビーブリッドを創業。介護・福祉事業者向け DX 支援サービス『ほむさぽ』を軸に、介護現場での ICT 利活用と DX 普及促進に幅広く努めている。行政や事業者団体、学校等での講演活動および多くのメディアでの寄稿等の情報発信を通じ、ケアテックの普及推進中。