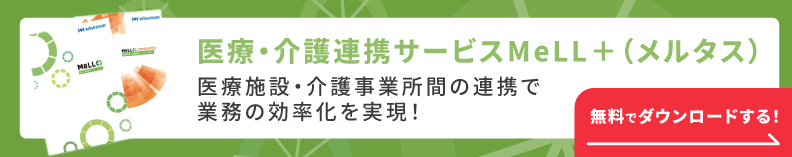バイタル自動入力の有用性|役立つツールや導入時の注意点などを解説
2025.11.07

バイタル測定と記録は重要な業務である一方、時間を要するため介護職員の負担になりやすい一面があります。
「手入力による転記ミスが怖い」「もっと患者や利用者と向き合う時間がほしい」と感じている職員も多いのではないでしょうか。
しかし、近年はバイタルを自動入力するシステムが登場しています。
適切に活用すれば、測定データが自動で電子カルテなどに記録されるため、業務の効率化が可能です。
また、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、医療・介護の安全性を高めることにもつながります。
本記事では、バイタル自動入力の基本的な仕組みや導入で失敗しないための注意点などを解説します。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。
目次
バイタル測定とは

バイタル測定とは、人間の生命活動における基本的な情報を数値化して把握することです。
医療や介護の現場ではバイタルサインとも呼ばれ、健康状態を評価するための重要な指標となります。
一般的に、以下の項目がバイタルサインとして測定されます。
- 体温
- 血圧
- 脈拍(心拍数)
- 呼吸数
上記の数値を定点観測することで、患者や利用者の状態変化を客観的に把握し、異常の早期発見や適切な処置につながります。
従来、バイタルサインの測定値はスタッフが手書きでメモし、後から電子カルテや記録システムへ手入力する方法が一般的でした。
しかし、この作業には多くの時間と手間がかかり、転記ミスといったリスクも伴います。
そのため、昨今はバイタルを自動入力できるシステムを導入する介護施設や医療機関が増えています。
バイタル自動入力の仕組み

バイタル自動入力とは、体温計や血圧計などの測定機器で得られたデータを、電子カルテや介護記録システムへ自動的に連携・記録する仕組みのことです。
手作業による入力や転記をなくすことで、医療・介護現場の業務を大幅に効率化できます。
基本的なデータ入力の流れは以下のとおりです。
| 測定 | 対応の機器でバイタルサインを測定します。 |
| データ転送 | 測定データが無線や有線などの方式でスマートフォン・リーダー・パソコンに転送されます。 |
| システム記録 | 転送されたデータが電子カルテや介護記録システムに自動で反映・保存されます。 |
上記の仕組みにより、現場のスタッフは記録作業から解放され、より専門的なケアに集中できるようになります。
また、電子カルテや介護記録システム等と連携できる機器であれば、バイタルデータのスムーズな共有も可能です。
バイタル自動入力の主な転送方式

バイタルデータを測定機器からシステムへ送る方法には、以下の方式があります。
- NFC
- Bluetooth/Wi-Fi
- 有線接続
施設の環境や運用フローに合わせて最適な方式を選ぶことが重要です。
本章では、代表的な3つのデータ転送方式について、それぞれの特徴を解説します。
NFC
NFC(Near Field Communication)はかざすだけで通信できる手軽さが特徴的な転送方式です。
交通系ICカードのように、測定を終えた体温計や血圧計をカードリーダーにかざすだけで、測定値がシステムに送られます。
複雑な操作が不要なため、IT機器に不慣れなスタッフでも直感的に使えます。
NFCは巡回型のカートにリーダーを設置し、各ベッドサイドで測定した機器をその場でかざして記録する、といった運用に適した方式です。
ただし、測定後に機器をリーダーに近づけてデータを転送する必要があるため、一度に多くのバイタルサインを測定するような運用には不向きです。
Bluetooth/Wi-fi
BluetoothやWi-Fiを利用した無線方式は、測定後の操作が不要で、スムーズに自働入力できる点が特徴です。
一度設定を済ませてしまえば、測定するだけでデータが自動的に指定の端末やシステムへ転送されます。
リアルタイムで情報が共有されるため、スタッフステーションにいながら患者や利用者の状態の把握が可能です。
また、ベッドサイドに機器を常設する場合や、訪問先で測定したデータを即座に事業所へ送りたい場合にも非常に有効です。
なお、BluetoothやWi-Fiはネットワーク機器の設定やペアリング(初期設定)が必要なため、ノウハウがある職員のサポートが欠かせません。
また、電波状況の影響を受けやすく、電波が悪いとバイタル測定が困難になる恐れがあります。
有線接続
USBケーブルなどを用いた有線接続は、もっとも確実で安定したデータ転送方式です。
電波状況に左右されることなく、大量のデータを高速に転送できます。
ただし、測定のたびにケーブルを接続する手間がかかるため、頻繁なバイタル測定には不向きです。
機器に溜まったデータを一括でパソコンに取り込む場合や、通信の安定性が最優先される場面で利用されます。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。
バイタル自動入力のメリット
バイタルデータの自動入力を導入すると、以下のようなメリットが期待できます。
- 業務の効率化
- ヒューマンエラーの防止
- 質の高いケアの実現
それぞれのメリットについて順番に解説するので、自動入力の効果のイメージを具体化する際の参考にしてください。
業務の効率化
最大のメリットは、記録業務にかかる時間の大幅な削減です。
手入力や転記作業が不要になることで、これまで記録に費やしていた時間を患者や利用者への対応・サービスの改善にあてられるようになります。
また、業務の効率化は労働時間や残業時間を短縮できるため、施設全体の膨大な人件費削減につながります。
人件費は施設を運営するうえで無視できないコストです。
収益を最大化するうえでも、業務の効率化は非常に重要な取り組みです。
ヒューマンエラーの防止
自動入力はヒューマンエラーの防止にも役立ちます。
手作業による記録には、読み間違い・書き間違い・入力間違いといったヒューマンエラーがあるものです。
ヒューマンエラーは、患者や利用者の健康状態を誤って評価し、重大なインシデントにつながる危険性をはらんでいるものです。
バイタルの自動入力システムは、測定された数値をそのままデジタルデータとして記録するため、こうした転記ミスを根本的に防止できます。
その結果、医療・介護の安全性が飛躍的に向上します。
質の高いケアの実現
質の高いケアを実現するうえでも、バイタルの自動入力は有用です。
記録業務から解放されることで生まれた時間は、患者や利用者と直接向き合うために使えます。
コミュニケーションの時間が増えることで、精神的なケアが充実したり、患者や利用者の些細な変化に気づきやすくなったりします。
観察・アセスメント・ケア計画の立案といった、スタッフが持つ本来の専門性を発揮する時間が増えるため、より質の高いサービスの提供が可能です。
施設全体のケアの質が向上すれば、患者や利用者の満足度向上にもつながります。
バイタル自動入力に対応する主な機器

バイタル自動入力システムは、さまざまなメーカーから提供されています。
自施設の電子カルテや記録システムと連携可能かどうかも、選定の重要なポイントです。
データの転送方式を踏まえて、事前に確認しておくことをおすすめします。
バイタル自動入力を導入する際の注意点

バイタル自動入力は非常に便利なシステムですが、導入を成功させるためには以下のような注意点があります。
- エラーリスクに配慮する
- セキュリティ対策を万全にする
- 費用対効果に注意する
「導入したもののうまく活用できていない」という事態を避けるため、事前に以下のポイントを確認しましょう。
エラーリスクに配慮する
バイタルの自動入力は有用である一方、エラーが全く発生しないわけではありません。
安定した運用のためには、起こりうるリスクと対策を理解しておくことが不可欠です。
想定されるエラーに備えて、以下のような対策を実施しましょう。
| エラーの種類 | 具体的なリスク | 主な対策 |
| センサーの誤作動 | 機器の故障や電池切れ、電波干渉で正確な値が測定できない。 | ・定期的に機器のメンテナンスを行う ・予備の機器やバッテリーを準備しておく。 |
| データ転送エラー | Wi-Fi環境の不安定さなどで、データがシステムに正しく送られない。 | ・院内のWi-Fi環境を整備・最適化する。 ・データが正常に転送されたか確認するフローを設ける。 |
| 人的ミス | 患者の認証ミス(AさんのデータをBさんに記録)など、操作上の間違い。 | ・導入時に十分なスタッフ教育を行う。 ・操作マニュアルを整備し、誰でも確認できるようにする。 |
特に自動入力に慣れていない職員はミスをするリスクが高いため、バイタルの自動入力を導入した際に念入りに指導することが不可欠です。
必要があれば研修を実施したり、担当者が直接指導したりするなど、丁寧なアフターフォローを実施しましょう。
また、ネットワークや電波の障害によって自動入力を行うシステム自体が機能不全を起こすリスクもあります。
安定的に運用するためにも、障害が発生した際の対策マニュアルは必ず用意しましょう。
セキュリティ対策を万全にする
バイタルの自動入力を運用するうえで、セキュリティ対策は重要です。
バイタルデータは、非常に機密性の高い個人情報です。
情報漏洩などのセキュリティインシデントを防ぐため、万全の対策が求められます。
特に無線でデータをやり取りする場合は、以下の対策が重要になります。
| ルール | 説明 |
| 通信経路の暗号化 | データが傍受されても内容がわからないように、TLSなどの強力な暗号化技術に対応したシステムを選ぶ。 |
| アクセス制御 | 誰がデータにアクセスできるのかを厳密に管理する。役割に応じて権限を設定できる(RBAC)機能が望ましい。 |
| 法令遵守 | 個人情報保護法や医療情報システムの安全管理に関するガイドラインなど、関連法規を遵守したシステムを選ぶ。 |
また、ネットワーク機器の選定にも注意しましょう。
ルーターや回線を安価なものにすると、セキュリティの脆弱性を突かれて不正アクセスやサイバー攻撃を受けるリスクがあります。
万が一不正アクセスやサイバー攻撃を受けると、施設が機能不全に陥るだけでなく、患者や利用者の生命に関わる事態になりかねません。
必要があれば外部から専門家を招くなど、セキュリティ対策は徹底しましょう。
費用対効果に注意する
バイタルの自動入力システムの導入には、少なくないコストがかかるため、費用対効果の測定が欠かせません。
投資が無駄にならないよう、事前に費用と効果を慎重に検討することが大切です。
なお、バイタルの自動入力システムは以下のような費用が想定されます。
| 費用の種類 | 主な内訳の例 |
| 初期費用 | ・測定機器(1台あたり数万円〜) ・データ転送装置やリーダー・ソフトウェアライセンス料、システム導入・設定費用 |
| 運用費用 | ・システム保守費用(年間) ・消耗品(センサーやバッテリーなど) ・ソフトウェアのアップデート費用 |
上記のコストに対して、どれだけの人件費削減効果や医療ミスの減少による間接的なコスト削減が見込めるかを試算します。
一般的に、3年〜5年程度で投資を回収できるかどうかが目安です。

本稿では、バイタル測定(体温・血圧・脈拍・SpO₂など)の自動入力システムが、介護・医療現場の業務効率化や記録精度の向上に大きく寄与することを紹介しています。測定から記録までの一連の作業を自動化することで、職員の負担軽減やヒューマンエラーの防止につながり、利用者の健康状態をより正確に把握できる点は大きなメリットです。
一方で、自動化の進展にはいくつかの注意点もあります。まず、異常値の見落としや個別性への対応です。センサーのズレや誤作動により正確でない値が記録される場合があり、利用者ごとの基礎体温や血圧の特徴を理解した上で判断する人の目が不可欠です。また、顔色・表情・発汗・声の調子など、機器では捉えられない観察も引き続き重要です。さらに、データの自動記録には個人情報漏洩のリスクも伴うため、適切なセキュリティ対策が求められます。
導入にあたっては、機器操作への抵抗感や知識不足にも配慮し、誰もが使いやすいシステムを選ぶことが大切です。技術に頼りすぎず、人の感覚と観察力を組み合わせた“安心のデジタル化”が理想と言えるでしょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。
バイタル自動入力はケアの質向上にもつながる

バイタルサインの自動入力は、日々の記録業務を効率化し、スタッフの負担を軽減する強力なツールです。
しかしその本質的な価値は、ヒューマンエラーをなくして医療・介護の安全性を高め、創出された時間でより質の高いケアを実現することにあります。
信頼できるシステムを選ぶことが、導入成功の鍵です。
必要があれば、外部から専門家を招き、適切なアドバイスを受けましょう。
バイタル自動入力の導入は、介護施設のDXを推進し、働きやすい環境を整え、最終的には患者や利用者の満足度向上へとつながる未来への投資です。
適切に運用すれば、より良いサービスを提供できる可能性が高まります。

星山 徹
介護福祉士
北海道の特別養護老人ホームにて、介護支援専門員(ケアマネージャー)として、通算19年勤務
【取得資格】
・介護福祉士
・社会福祉士
・主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)
・精神保健福祉士