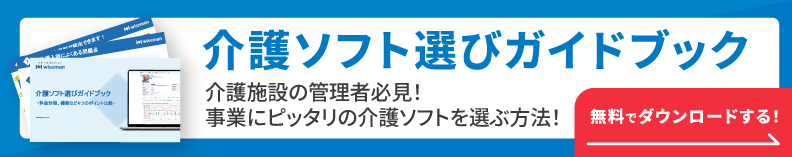ケアプランにおけるインフォーマルサービスとは|書き方などを解説
2025.05.22

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活するためには、 介護保険サービスだけでなく、 地域資源であるインフォーマルサービスの活用が不可欠です。
ただし、インフォーマルサービスを提供するうえで、ケアプランへの適切な記載は欠かせません。
本記事では、 ケアプランにおけるインフォーマルサービスの概要から、 具体的な種類・ ケアプランへの書き方・注意点までを解説します。
インフォーマルサービスを上手に活用して、 より質の高いケアプランを作成しましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて「介護ソフト選びガイドブック」を無料配布しています。
介護ソフトの導入時によくある問題と対策についても記載していますので是非ご活用ください。
目次
ケアプランにおけるインフォーマルサービスとは

本章ではケアプランにおけるインフォーマルサービスについて、基本的な知識を解説します。
インフォーマルサービスの概要
インフォーマルサービスとは、公的な制度に基づかない、地域住民やNPO、ボランティア団体などが提供する支援サービスのことを指します。
一方、介護保険サービス(フォーマルサービス)とは、介護保険に基づいたサービスを意味する用語です。
具体的には、近隣住民による見守り活動・ボランティア団体による配食サービス・NPOによる交流サロンなどが挙げられます。
インフォーマルサービスは、介護保険ではカバーしきれない、日常生活のちょっとした困りごとや、社会参加の促進などをサポートする役割を担っています。
また、介護保険サービスでは代替できない柔軟性や地域密着性を持っていることも、インフォーマルサービスの特徴です。
例えば、趣味のサークル活動への参加支援や、地域のイベントへの付き添いなど、利用者の個性や希望に合わせた多様な支援を実現できます。
一方で、インフォーマルサービスは公的な機関ではなく、民間の団体や民間業者が提供するため、料金が介護保険サービスより高くなる場合があります。
ケアプランに取り入れる際は、利用者が無理なく利用できるように配慮しましょう。
インフォーマルサービスの重要性
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けるためには、介護保険サービスだけでなく、インフォーマルサービスの活用が不可欠です。
その重要性は、以下の3点に集約されます。
| 生活の質の向上 | インフォーマルサービスは、趣味活動や交流の機会を提供し、利用者の精神的な健康や生きがいを支えます。閉じこもりを防止し、社会とのつながりを保つことで、生活の質を向上させることが期待できます。 |
| 介護予防・重症化予防 | 地域住民との交流や、軽度な生活支援を通じて、心身機能の維持・向上につながります。これにより、介護が必要な状態になることを防ぎ、重症化を予防する効果が期待できます。 |
| 地域包括ケアシステムの構築 | インフォーマルサービスは、地域住民が主体的に介護に関わることを促進し、地域全体の支え合いの輪を広げます。これにより、介護保険サービスだけでは対応しきれないニーズに対応し、地域包括ケアシステムの構築に貢献します。 |
また、令和3年度の介護報酬改定以降、厚生労働省は「多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)」を特定事業所加算の算定要件に加えました。
そのため、居宅介護支援事業所にとっても、インフォーマルサービスの提供は重要な課題です。
ケアマネジャーは、利用者の状況やニーズを的確に把握し、介護保険サービスとインフォーマルサービスをバランス良く組み合わせた、最適なケアプランを作成することが求められます。
参照:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
インフォーマルサービスの種類

インフォーマルサービスの種類には、以下のようなものがあります。
- 生活支援サービス
- 交流・コミュニティ支援サービス
- 移動支援サービス
- その他地域独自のサービス
インフォーマルサービスは、介護保険サービスでは対応が難しい、多様なニーズに応えるための地域資源です。
利用者の意向を踏まえ、適切なサービスを選びましょう。
生活支援サービス
生活支援サービスは、日常生活におけるさまざまな困りごとをサポートするサービスです。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
| 家事援助 | 掃除・洗濯・買い物・調理など、日常生活に必要な家事のサポート |
| 配食サービス | 栄養バランスの取れた食事を自宅まで届けてくれるサービス |
| 見守りサービス | 定期的な訪問・電話による安否確認・緊急時の対応など |
インフォーマルサービスにおける生活支援サービスは、電球の交換や庭の手入れなど、介護保険サービスでは対応できない軽作業や家事を代行できる点が特徴です。
加えて、配食サービスによる栄養面のサポートや、見守りサービスによる緊急時の対応強化なども、利用者がより安心できる生活を送るうえで役立ちます。
上記のサービスは、高齢者が自立した生活を維持するために役立つものです。
また、家族の介護負担を軽減する効果も期待できます。
交流・コミュニティ支援サービス
交流・コミュニティ支援サービスは、地域社会とのつながりを促進し、高齢者の孤立感を解消するためのサービスです。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
| サロン活動 | 地域住民が集まり、趣味活動やレクリエーションなどを楽しむ場 |
| ふれあい教室 | 健康増進や介護予防を目的とした教室 |
| ボランティア団体による交流会 | ボランティア団体が主催する、地域住民同士の交流を深めるためのイベント |
上記のサービスは、高齢者の社会参加を促進し、生きがいを見つけるためのきっかけとなります。
移動支援サービス
移動支援サービスは、外出が困難な利用者の移動をサポートするサービスです。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
| 福祉有償運送 | NPOや社会福祉法人などが提供する、通院や買い物などのための移動サービス |
| ボランティアによる送迎サービス | ボランティアが提供する、地域内の移動をサポートするサービス |
| 公共交通機関の利用支援 | バスや電車などの公共交通機関の利用をサポートするサービス |
高齢者が自由に外出し、社会参加の機会を広げるうえでも、上記のサービスは重要です。
外出する手段を提供することにより、高齢者の自発的な活動を促進できます。
その他地域独自のサービス
上記以外にも、各地域には独自のインフォーマルサービスが存在します。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
| 生活支援体制整備事業 | 地域包括ケアシステムの一環として、地域住民が主体となって生活支援サービスを提供する取り組み |
| 地域ポイント制度 | ボランティア活動や介護支援活動に参加した地域住民にポイントを付与し、地域内の商店などで利用できる制度 |
| 子育て支援との連携 | 高齢者と子育て世代が交流するイベントや、高齢者が子育てを支援する活動 |
いずれのサービスも、地域の実情に合わせて柔軟に提供され、地域全体の活性化にも貢献するものです。
なお、株式会社ワイズマンではすでに介護ソフトを導入しているが、介護ソフトの入れ替えを検討している方に向けて、「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。ダウンロードしてご活用ください。
ケアプランへのインフォーマルサービスの書き方

インフォーマルサービスをケアプランに記載することで、利用者の生活をより豊かにし、自立支援を促進できます。
本章では、ケアプランにインフォーマルサービスを記載する際のポイントを解説します。
ニーズの明確化と目標設定
インフォーマルサービスをケアプランに記載するうえで、もっとも重要なのは利用者のニーズを明確に把握することです。
利用者が抱える課題や希望を丁寧に聞き取り、どのような支援が必要なのかを具体的に理解する必要があります。
ニーズを明確化したら、それに基づいて具体的な目標を設定します。
目標は、利用者がインフォーマルサービスを活用することで、どのような状態を目指すのかを示すものです。
可能な限り具体的で、測定可能なものにしましょう。
例えば、以下のような記載が考えられます。
| ニーズ | 目標 |
| 閉じこもりがちで、 外出する機会が少ない。 | 週に1回、地域のサロンに参加し、他の住民と交流する。 |
| 買い物に行くのが困難。 | 週に2回、民生委員の買い物支援サービスを利用し、必要なものを購入する。 |
| 庭の手入れができず困っている。 | 月に1回、シルバー人材センターの庭の手入れサービスを利用し、庭をきれいな状態に保つ。 |
具体的なサービス内容の記載例
ケアプランには、利用者のニーズと目標に基づいて、具体的なインフォーマルサービスの内容を記載します。
サービスの内容は、「誰が」「いつ」「どこで」「何を」するのかを、明確に記述することが重要です。
また、サービスの利用頻度や時間、費用なども記載すると、よりわかりやすくなります。
以下に、ケアプランへの具体的な記載例を示します。
| サービスの種類 | サービス内容 | 頻度 | 時間 | 費用 | 備考 |
| 生活支援サービス | 民生委員による買い物支援 | 週2回 | 1時間 | 無料 | 購入するものは事前にリストを渡す。 |
| 交流・コミュニティ支援サービス | 地域サロン「ふれあいサロン〇〇」 | 週1回 | 2時間 | 1回300円 | サロンの活動内容: 俳句の指導・作成など |
| 移動支援サービス | ボランティア団体による通院支援サービス | 月2回 | 往復2時間 | 1回500円 | 病院への通院時に利用。 |
ケアプランにインフォーマルサービスを記載する際には、以下の点にも注意しましょう。
- サービスの提供主体(団体名、担当者名など)を明記する。
- サービスの利用にあたっての注意点や制約事項があれば記載する。
- サービス利用開始時期や期間などを記載する。
- インフォーマルサービスの効果を定期的に評価し、必要に応じてケアプランを見直す。
上記の例を参考に、利用者の状況やニーズに合わせたインフォーマルサービスをケアプランに記載し、より質の高いケアプランを作成しましょう。
また、ケアプランは利用者の体調や状況の変化に合わせて見直すことも重要です。
新たに必要と判断された際は、別のインフォーマルサービスの利用も考慮しましょう。
ケアプランにインフォーマルサービスを加えない場合
ケアプランにインフォーマルサービスを加えない場合、基本的には介護保険サービスのみを「サービスの種類」欄に記載します。
その場合、インフォーマルサービスを加えなかった理由を記載する必要があります。
例えば「家族による見守りが毎日行われており、安否確認ができている」「近隣住民による声かけがあり、孤立を防ぐことができている」など、簡潔に状況を記述します。
また、サービス担当者会議などで、家族や地域住民などによるインフォーマルな支援状況について話し合われた際は、ケアプランの「特記事項」欄などに簡単な記録を残しましょう。
ただし、インフォーマルサービスをケアプランに含めない場合、詳細な計画や目標などを記載する必要はありません。
あくまで情報共有の一環として、支援状況を把握している旨を記録する程度に留めましょう。
インフォーマルサービスを扱う際の3つの注意点

インフォーマルサービスは、利用者の方の生活を豊かにする可能性を秘めていますが、活用する際には以下のような注意点があります。
- 利用者の意向を尊重する
- 介護保険サービスとバランス良く組み合わせる
- 関係機関と上手く連携する
インフォーマルサービスを適切に活用し、利用者に最適なケアを提供するためにも、それぞれの注意点を正確に把握しましょう。
利用者の意向を尊重する
インフォーマルサービスは、フォーマルサービスと異なり、提供者との関係性やサービス内容が柔軟であるため、利用者の意向を最大限に尊重することが重要です。
例えば、以下のような点に注意しましょう。
| サービスの選択肢を提示する | どのようなインフォーマルサービスがあるのか、それぞれのサービス内容や費用などを丁寧に説明し、利用者が自分で選択できるようにサポートします。 |
| サービスの利用を強制しない | インフォーマルサービスの利用は、あくまで利用者の自由意志に基づいている必要があります。無理に勧めたり、利用を強制したりすることは避けましょう。 |
| 利用後の満足度を確認する | サービス利用後には、必ず利用者に満足度を確認し、改善点があればサービス提供者と連携して対応します。 |
利用者の意向を尊重することで、インフォーマルサービスはより効果的に機能し、利用者のQOL(生活の質)向上に貢献できます。
不必要なインフォーマルサービスは、利用者に過度の負担を強いる結果になるので注意してください。
介護保険サービスとバランス良く組み合わせる
インフォーマルサービスは、介護保険サービスでは対応しきれないニーズを補完する役割を担います。
そのため、両者をバランス良く組み合わせることが、より質の高いケアプランを作成するうえで重要です。
例えば、以下のような連携が考えられます。
| 状況 | 介護保険サービスの例 | インフォーマルサービスの例 |
| 日中の見守りが必要 | デイサービス | 地域のボランティア団体による見守り |
| 買い物に行けない | 訪問介護(生活援助) | 近隣住民のNPO団体による買い物代行 |
| 話し相手が欲しい | 訪問介護(自立支援) | 地域のサロンや交流会への参加 |
介護保険サービスとインフォーマルサービスを組み合わせることで、利用者の多様なニーズに対応でき、より包括的な支援の提供が可能です。
また、利用者の経済的な負担を抑えられるため、より長期的な支援にもつながります。
関係機関と上手く連携する
インフォーマルサービスは、地域に根ざした活動であるため、さまざまな関係機関との連携が不可欠です。
具体的には、以下のような機関との連携が考えられます。
| 地域包括支援センター | 地域の高齢者に関する総合的な相談窓口であり、インフォーマルサービスに関する情報提供や連携支援を行っています。 |
| 社会福祉協議会 | 地域福祉の推進を目的とした団体であり、ボランティアの育成やインフォーマルサービスのコーディネートなどを行っています。 |
| NPO法人・ボランティア団体 | 地域でさまざまな活動を行っており、インフォーマルサービスの担い手として重要な役割を果たしています。 |
これらの関係機関と連携することで、インフォーマルサービスに関する情報を共有したり、利用者のニーズに合ったサービスを紹介したりできます。
また、サービス提供者同士が連携することで、より効果的な支援の提供も可能です。
関係機関との連携を密にすることで、インフォーマルサービスは地域全体で支え合う、より持続可能なシステムとして機能します。
そもそもケアマネジャーは多職種と連携し、利用者に最適なケアプランを作成する役割を担います。
介護保険サービス・インフォーマルサービスを問わず、適切なケアプランを作成するためにも、関係機関との連携を緊密にしましょう。

ケアプランにインフォーマルサービスを記載する際には、以下の点に留意が必要です。まず、利用者のニーズを適切に把握し、利用者にも理解可能な具体的な目標を設定することが大切です。次に、具体的なサービス内容(誰が、何を)を明確に記述し、利用頻度、時間、費用等も具体的に記載する必要があります。サービス利用にあたっては、利用者の意向を最大限に尊重し、どのようなサービスがあるか丁寧に説明し、利用を強制しないことが不可欠です。インフォーマルサービスは介護保険サービスを補完するため、両者をバランス良く組み合わせることで質の高い支援が可能になります。関係機関との連携を密にすることも重要であり、サービス効果を定期的に評価し、必要に応じてケアプランを見直します。これにより、利用者の生活の質向上に貢献するケアプランが実現します。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護ソフト選びガイドブック」を無料で配布中です。
すでに介護ソフトを導入していている方も、介護ソフトの入れ替えを検討している方も、自身に最適なプロダクトを選ぶために重要な4つのポイントを解説していますので是非ご活用ください。
インフォーマルサービスを活用すればより良いケアプランが実現する

インフォーマルサービスは、ケアプランの質をさらに高めるだけでなく、利用者の生活の質を向上させるための重要な要素です。
インフォーマルサービスは、フォーマルサービスと連携することで、より効果を発揮します。
また、ケアプランにインフォーマルサービスを位置付けることは、利用者やその家族、友人との信頼関係を築くことにもつながります。
介護事業者は、インフォーマルサービスの斡旋を通じて、利用者や家族のニーズを深く理解し、よりパーソナルなケアの提供が可能です。
インフォーマルサービスを積極的に活用し、より質の高いケアプランを作成しましょう。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。