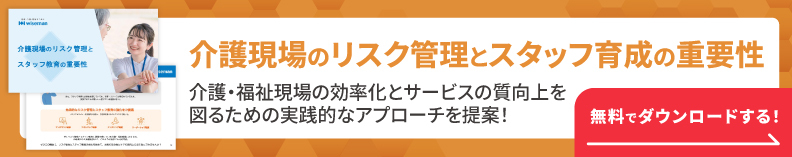ケアプランの押印は不要?|押印廃止に伴う課題などを解説
2025.05.25

2021年以降、 介護保険関連書類の押印が順次廃止されていますが、 ケアプランもその対象です。
押印廃止は書類作成をスムーズにする一方、注意すべきポイントもあります。
本記事では、 ケアプランの押印廃止の背景・具体的な変更点・現場への影響などについて詳しく解説します。
押印廃止によって業務効率化が期待される一方で、 新たな課題も生まれています。
本記事を参考に、 押印廃止後のケアプラン作成・変更業務をスムーズに行うためのヒントを得ましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは、介護現場でのリスク管理やスタッフの教育について課題を感じている方に向けて「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場の効率化とサービスの質向上を図るための実践的なアプローチを提案しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
ケアプランの押印廃止とは

2021年の介護報酬改定以降、介護現場における業務効率化の一環として、さまざまな介護保険関連書類の押印が順次廃止されています。
それに伴い、ケアプランも押印廃止の対象となりました。
本章では、ケアプランの押印が不要となった背景などについて解説します。
ケアプランの押印が廃止された背景
ケアプランの押印廃止は、介護業界のデジタル化推進・行政手続きの簡素化を目指すための取り組みです。
ケアプランをはじめとする各種書類への押印・署名は義務ではないものの、利用者や家族の同意を得た証として慣習的に行われてきました。
しかし、押印が必ずしも本人の意思確認の有効な手段とは言えないことや、押印のために時間や手間がかかることが課題でした。
その結果、厚生労働省は2021年の介護報酬改定に際し、ケアプランを含む介護保険関連書類について、原則として押印を不要とする方針を決定しています。
この変更により、書類作成や手続きにかかる時間やコストの削減・ペーパーレス化の促進が期待されています。
また、押印に代わる本人確認の方法を確立することで、より確実な同意確認の実現も期待されています。
押印廃止の施行日
ケアプランの押印廃止は、2021年4月1日より施行されました。
以降、ケアプランに利用者の押印がなくても、原則として書類は有効とみなされます。
なお、押印や署名の廃止はあくまでそれら以外の手段での本人確認の方法が認められたことを意味するものです。
押印や署名が不要となったとはいえ、本人確認は適切に実施する必要があります。
押印廃止となる介護保険関連書類一覧
ケアプランの押印廃止と合わせて、以下の介護保険関連書類についても押印が原則不要となりました。
- ケアプラン(居宅サービス計画書・施設サービス計画書など)
- 重要事項説明書
- サービス担当者会議の記録
- 訪問介護計画書
- 通所介護計画書
- 福祉用具貸与計画書
上記以外にも、各事業所で使用しているさまざまな記録や報告書において、押印が不要となる場合があります。
厚生労働省からの通知や自治体からの情報を確認し、自事業所で使用している書類が押印廃止の対象であるか確認しましょう。
押印廃止によるケアプラン作成への影響

ケアプランの押印廃止は、介護現場にさまざまな影響を与えています。
様式の変更から現場での運用、確認すべき通知まで、具体的な内容をチェックしましょう。
ケアプラン様式の変更点
押印廃止に伴い、ケアプランの様式から押印欄が削除されました。
従来の様式に慣れている場合は、変更点を確認し、新しい様式に沿ったケアプランを作成する必要があります。
具体的な変更点としては、以下のようなものが挙げられます。
- 押印欄の削除
- 必要に応じて署名欄が追加
- 本人確認に関する記述欄の追加
厚生労働省の通知や各自治体の情報を確認し、最新の様式を使用するようにしましょう。
電子署名や電子印鑑などを利用する際も同様です。
介護現場への影響
ケアプランの押印廃止は、介護現場に以下のような影響を与えています。
| 影響 | 詳細 |
| 業務効率化 | 押印作業が不要になることで、ケアプラン作成にかかる時間や手間が削減されます。 |
| コスト削減 | 印鑑や印鑑証明書などのコストが削減されます。 |
| 書類管理の簡素化 | 押印された書類の保管や管理が不要になるため、書類管理が簡素化されます。 |
| 署名に関する新たな運用ルールの必要性 | 署名が必要なケースでは、誰が、いつ、どのように署名するかなど、具体的な運用ルールを定める必要があります。 |
| 利用者・家族への説明 | 押印廃止の背景や目的、手続きの変更点などを、利用者や家族に丁寧に説明する必要があります。 |
押印廃止は、業務効率化やコスト削減につながる一方で、署名に関する運用ルールの整備や、利用者・家族への丁寧な説明が求められます。
自事業所の対応に問題がないか、必ず確認しましょう。
事業所が確認すべき関連通知・事務連絡
ケアプランの押印廃止に関する情報は、厚生労働省や各自治体からさまざまな通知や事務連絡として発信されています。
事業所は、これらの情報を常に把握し、適切に対応する必要があります。
確認すべき主な通知・事務連絡は、以下のとおりです。
- 厚生労働省からの介護保険関連書類の押印不要に関する通知
- 各自治体からのケアプラン様式変更に関する通知
- 署名に関する運用ルールに関する通知
上記の通知・事務連絡は、厚生労働省のホームページや各自治体の介護保険関連情報を掲載しているページで確認できます。
また、介護保険に関する情報提供サービスや、介護事業者向けの研修会なども活用し、常に最新の情報を入手するように心がけましょう。
ケアプラン作成・変更時の注意点

ケアプランの押印廃止は、業務効率化につながる一方で、作成・変更時の注意点も存在します。
本章では以下の注意点について解説します。
- 署名が必要となるケースがある
- 本人確認と記録が不可欠
それぞれの注意点について解説するので、ぜひ参考にしてください。
署名が必要となるケースがある
押印が廃止されたからといって、すべての手続きで署名が不要になったわけではありません。
以下のケースでは署名が必要です。
| 利用者の同意を得る場合 | ケアプランの内容について、利用者または家族に説明し、同意を得たことを示すために署名が必要となる場合があります。 |
| 重要事項説明書など署名を求めることが定められている書類 | 介護保険サービスを利用するにあたって、重要事項説明書など署名を求めることが定められている書類については、引き続き署名が必要です。 |
これらのケースでは、署名欄を設けるか、または電子印鑑・電子署名など、署名に代わる適切な記録を残す必要があります。
事業所内で統一したルールを設けて、混乱を防ぎましょう。
本人確認と記録が不可欠
押印廃止後、より重要になるのが本人確認と記録です。
ケアプラン作成・変更時には、以下の点に注意しましょう。
| 利用者または家族への丁寧な説明 | ケアプランの内容を十分に説明し、理解を得ることが重要です。 |
| 同意の確認 | 口頭での同意だけでなく、同意を得た日時、方法、担当者などを記録に残しましょう。 |
| 記録の保管 | 作成されたケアプラン、同意の記録、その他関連書類は、適切に保管しましょう。 |
これらの記録は、後々のトラブルを避けるためにも重要です。
記録方法については、書面だけでなく、電子的な記録も検討しましょう。
電子署名やタイムスタンプの活用も有効です。
記録の徹底は事実確認を円滑にするだけでなく、利用者との信頼関係を維持し、質の高い介護サービスを提供するうえでも重要です。
なお、介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方に向けて、「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
ケアプランの押印廃止に伴う課題

ケアプランの押印廃止は、業務効率化の面で大きな期待が寄せられていますが、同時に以下のような課題も浮き彫りにしました。
- 押印廃止に伴う変更点の再確認
- 署名に関する運用ルールの整備
- 職員への周知徹底と研修の実施
- 電子化への対応
円滑な移行のためには、上記の課題に適切に対応していく必要があります。
押印廃止に伴う変更点の再確認
押印廃止は、介護保険関連書類全般に適用されていますが、具体的な対象書類や変更点について、事業所内であらためて確認を徹底しましょう。
厚生労働省からの通知や事務連絡を精査し、誤解や認識のずれがないようにすることが重要です。
また、押印廃止に際して新たに電子署名や電子印鑑などを導入する際は、既存の書式に利用できるか必ずチェックしましょう。
署名に関する運用ルールの整備
押印が不要になった代わりに、署名が必要となるケースがあります。
署名の要否・署名者の範囲・署名方法などについて、明確な運用ルールを整備しましょう。
例えば、ケアプランや各サービスの計画書、重要事項説明書などの同意を利用者・家族から得る際に、どのような形で本人確認の手続きを行うかルールを明確にする必要があります。
また、利用者本人の署名が難しい場合の対応についても、事前の検討が不可欠です。
書字が不可能、もしくは判断が困難な場合を除き、本人の選択を尊重しつつ、家族に同意を得ることも検討しましょう。
職員への周知徹底と研修の実施
押印廃止に関する変更点や運用ルールについて、全職員への周知徹底が欠かせません。
研修などを実施し、ケアプランの作成などに関するルールへの理解度を高めましょう。
特に、ケアプラン作成に関わるケアマネジャーは、変更点を正確に理解し、利用者や家族に適切に説明できるようにする必要があります。
利用者・家族への丁寧な説明
押印廃止の背景や目的、変更点について、利用者や家族に丁寧に説明することが重要です。
特に、これまで押印をすることで安心感を得ていた利用者や家族にとっては、署名のみとなることに不安を感じる可能性があります。
事前に十分な説明を行い、理解と協力を得られるように努めましょう。
電子化への対応
押印廃止は、介護現場における書類の電子化を推進する良い機会です。
電子署名の導入や、ケアプラン作成システムの活用など、電子化に対応することにより、業務効率をさらに向上できます。
なお、利用者へのケアの質を確認するためにその記録などを確認する場合は、特に必要と判断される場合を除き、原則として3名以内とすることが推奨されています。
ただし、電子化にあたっては、セキュリティ対策や個人情報保護に関する規定を遵守することが不可欠です。
また、電子機器の操作に不慣れな職員へのサポート体制も整備する必要があります。
参照:介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について|厚生労働省

ケアプランの押印は、介護業界のデジタル化・行政手続きの簡素化を目指し、2021年4月1日から原則不要となりました。これにより、ケアプラン様式から押印欄が削除され、書類作成の効率化やコスト削減が期待されます。しかし、押印廃止後も注意点があります。利用者や家族の同意を得た証として慣習的に行われてきましたが、同意を得たことの証として署名が必要となるケースがあります。重要事項説明書など署名が定められている書類も対象です。押印が廃止されても、本人確認と記録は不可欠であり、同意を得た日時や方法などを正確に記録することが後々のトラブル回避にも重要です。事業所では、押印廃止に伴う変更点の再確認、署名に関する運用ルールの整備、職員や利用者・家族への周知・説明などが課題となっています。電子化対応も推進されています。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
ケアプランの押印廃止に応じて業務プロセスを見直そう

ケアプランの押印廃止は、介護現場における業務効率化の大きなチャンスです。
しかし、単に押印をなくすだけでなく、業務プロセス全体を見直し、最適化することで、その効果を最大限に引き出せます。
この機会を活かして、業務効率化を図り、より質の高い介護サービスを提供できるよう、積極的に取り組んでいきましょう。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。