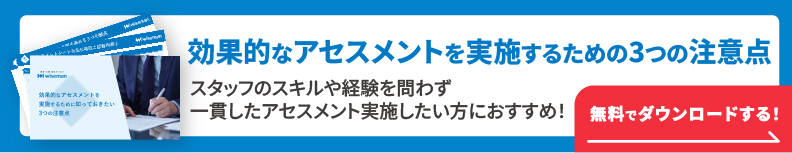ケアプランの長期目標・短期目標の文例16選|作成のポイントも解説
2025.09.25

ケアマネジャーにとって、アセスメントで引き出した利用者の要望を、ケアプランに落とし込む作業は簡単な作業ではありません。
提供するケアを決定するだけでなく、関係者・利用者・利用者の家族などに伝わるように適切な文章表現で記載する必要があるためです。
利用者本位のプランを作りたい気持ちが強くても、適切な表現が見つからず、作業が進まないケースは珍しくありません。
特に長期目標・短期目標は利用者を支援する方針を定める重要な項目です。
適切に記載できなければ、安定的なサービスの提供に影響を及ぼすリスクが生じます。
本記事では、すぐに使えるケアプランの長期目標・短期目標の文例をニーズ別に紹介します。
また、利用者に合わせて応用できる目標設定の考え方についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
アセスメントシートを記載する上で知っておきたい3つの観点を記載しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
ケアプランにおける長期目標・短期目標の基本

ケアプランを作成するうえで、長期目標と短期目標は利用者支援の指針となる非常に重要な要素です。
まずは、それぞれの定義や役割、関係性といった基本を確認しましょう。
長期目標・短期目標の基本を理解すれば、後述する文例を理解しやすくなります。
長期目標とは
ケアプランにおける長期目標とは、利用者と家族が「最終的に目指す姿」や「実現したい生活」を具体的に示したものです。
利用者や家族が持つ漠然とした希望を、誰にでもわかる明確なゴールとして設定する役割があります。
長期目標は主に以下の項目で構成されます。
| 項目 | 説明 |
| 目的 | ケアプラン全体の最終的なゴール(総合的な援助の目標)を定める |
| 期間の目安 | おおむね 6カ月〜1年程度(状態によってはさらに長期の場合もある) |
| 視点 | 利用者や家族が「こうなりたい」と望む生活像・QOL(生活の質)の向上 |
| ポイント | 利用者の尊厳を保ち、意欲を引き出すような希望の持てる内容にする |
長期目標は、支援に関わるすべてのスタッフが同じゴールを共有し、一貫したサービスを提供するうえで不可欠なものです。
短期目標とは
短期目標は長期目標を達成するために、現実的に越えていくべき小さなステップを具体的に示したものです。
つまり、長期目標を達成するうえでクリアすべきマイルストーンと捉えられます。
短期目標を構成する項目は以下のとおりです。
| 項目 | 説明 |
| 目的 | 長期目標達成に向けた、具体的で測定可能な小さな目標を定める |
| 期間の目安 | おおむね 1カ月〜3カ月程度 |
| 視点 | 利用者が「これができるようになった」と実感できる具体的な行動や状態の変化 |
| ポイント | 頑張れば達成できる現実的な内容にし、達成度を客観的に評価できるようにする |
短期目標をそれぞれクリアしていくことで、利用者本人が達成感を得られるので、モチベーション維持につながります。
長期目標と短期目標の関係性・違い
長期目標と短期目標の関係性は、「複数の短期目標を達成した先に、長期目標の達成がある」と捉えられます。
両者の違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | 長期目標 | 短期目標 |
| 位置づけ | 最終ゴール | 中間ステップ |
| 期間 | 6カ月〜1年程度 | 1カ月〜3カ月程度 |
| 具体性 | 包括的・概念的(生活像) | 行動レベルで具体的・測定可能 |
| 役割 | 方向性を示す | 進捗を管理する |
| 例 | 「自宅で安心して生活を継続できる」 | 「手すりを使ってトイレまで一人で移動できる」 |
それぞれの関係性を理解し、長期目標から逆算して短期目標を設定することが、質の高いケアプラン作成の鍵です。
なお、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて、「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
ADL(日常生活動作)の維持・向上に関する文例

ADLとは、食事・排泄・入浴など、日常生活を送る上で基本となる動作のことです。
本章ではADLに関する以下のカテゴリーの長期目標・短期目標の文例を解説します。
- 移動・移乗
- 食事
- 入浴・清潔保持
- 排泄
安全を確保しつつ、利用者本人の「できること」を最大限に引き出す視点で目標を設定しましょう。
移動・移乗
移動・移乗に関する目標設定は、利用者の身体能力や持病などに配慮する必要があります。
利用者の状態によっては、福祉用具の導入も検討しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 転倒への不安があり、室内移動に介助が必要。 | 転倒の不安なく、日中はポータブルトイレまで自力で移動できる。 | ・立ち上がり練習を1日5回行い、下肢筋力の維持を図る。 ・3カ月以内に、手すりを使い、安定して5メートル歩行できるようになる。 |
| ベッドから車いすへの移乗に全介助が必要。 | 介助者の負担が少なく、安全に車いすへ移乗できる。 | ・スライディングボードを導入し、安全な移乗方法を確立する。 ・1カ月後、介助者が声かけと最小限の支えで移乗できるようになる。 |
食事
利用者にとって、食事は栄養状態を左右する重要な要素です。
嚥下機能や口腔ケアを理解して目標を設定しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 食事中にむせることが多く、誤嚥のリスクがある。 | むせることなく、安全に経口摂取を継続し、食事を楽しめるようにする。 | ・食事前に嚥下体操を行い、嚥下機能を維持する。 ・訪問歯科衛生士による口腔ケアを週1回受け、口腔内を清潔に保つ。 ・食形態を刻み食に変更し、食事摂取の様子を観察する。 |
| 食欲が低下しており、低栄養状態が心配される。 | バランスの取れた食事を1日3食摂取し、体重減少を防ぐ。 | ・栄養補助食品を活用し、1日の必要カロリーを摂取する。 ・1カ月後、常食を半分量食べられる日を週3日作る。 |
入浴・清潔保持
入浴や清潔保持に関するケアは、利用者の身体能力に配慮して目標を設定しましょう。
ただし、自立心を養うためにも、衣服の着脱などは可能な限り利用者自身でやってもらうことも重要です。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 自宅での入浴が困難で、身体の清潔が保てていない。 | 週に2回、デイサービスを利用し、安全に入浴して心身ともにリフレッシュする。 | ・デイサービスの見学・体験利用を行い、安心して通える場所を見つける。 ・3カ月以内に、デイサービスの入浴を楽しみにできるような関係性を築く。 |
| 更衣動作に時間がかかり、介助が必要。 | 介助者の見守りのもと、自分で上着の着脱ができるようになる。 | ・前開きの衣類を用意し、更衣しやすい環境を整える。 ・訪問リハビリで、腕の可動域訓練を週1回行う。 |
排泄
利用者によっては、身体機能の問題で単独での排泄が困難なケースは珍しくありません。
利用者の自立心を尊重しつつ、適切なケアを提供しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 夜間のトイレ移動が不安で、おむつを使用している。 | 夜間もおむつに頼らず、ポータブルトイレで排泄できる。 | ・ベッドサイドにポータブルトイレと人感センサーライトを設置する。 ・2カ月以内に、夜間の失禁回数を週2回以下にする。 |
| 便秘傾向があり、腹部膨満感や不快感を訴える。 | 緩下剤に頼らず、自然な排便リズムを取り戻す。 | ・1日に1.5リットルの水分摂取を目標にする。 ・腹部マッサージの方法をヘルパーと家族が習得し、毎日実施する。 |
IADL(手段的日常生活動作)と住環境に関する文例

IADLとは、ADLよりも複雑で高次な動作を指し、自立した在宅生活を継続するうえで重要な役割を果たします。
調理・買い物・服薬管理などを通じて、利用者が社会的な役割や自信を取り戻せるような目標設定が不可欠です。
本章で紹介する長期目標・短期目標の文例は以下のとおりです。
- 調理・買い物
- 服薬管理
- 住環境整備
IADLに関する目標は利用者本人だけでなく、周辺の環境や家族の対応を踏まえた設定が求められます。
調理・買い物
調理・買い物は利用者の生活を改善するだけでなく、精神的な豊かさを維持するうえでも欠かせないものです。
利用者の身体機能やニーズを把握してから、目標を設定しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 簡単な調理もできなくなり、食事の支度に意欲がわかない。 | 週に2回、訪問ヘルパーと一緒に昼食を作り、料理をする楽しみを再確認する。 | ・ヘルパーと一緒に献立を考え、買い物リストを作成する。 ・1カ月後、野菜の皮むきや盛り付けなど、調理の一部を担える。 |
| 外出が困難で、日用品の買い物ができない。 | ネットスーパーの利用方法を覚え、自分で必要なものを注文できるようになる。 | ・家族と一緒にタブレットの操作練習を週1回行う。 ・2カ月後、ヘルパーの見守りのもと、ネットスーパーで3品以上の注文ができる。 |
服薬管理
服薬管理は、利用者の健康管理において非常に重要なサポートです。
利用者が自力で適切な服薬ができるように支援しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 薬の種類が多く、飲み忘れや飲み間違いが頻発している。 | 飲み忘れなく、正しく服薬管理ができ、病状を安定させる。 | ・訪問看護師に依頼し、1週間分のお薬カレンダーへのセットをしてもらう。 ・薬剤師に相談し、一包化調剤に変更してもらう。 |
住環境整備
住環境整備は、住宅の改修や福祉用具の導入によって利用者が快適に生活できる環境を整える取り組みです。
目標によっては、リフォームやリノベーションのような大規模な工事を実施するケースがあります。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 自宅内の段差や滑りやすい床が原因で、転倒リスクが高い。 | 住宅改修と福祉用具の活用により、自宅内を安全に移動できる環境を整える。 | ・福祉用具専門相談員に依頼し、手すりの設置場所や段差解消の方法を検討する。 ・3カ月以内に、介護保険を利用した住宅改修を完了させる。 |
社会参加・生きがいに関する文例

利用者のQOL(生活の質)を考える上で、社会とのつながりや楽しみ・生きがいは欠かせない要素です。
本人の興味・関心事を丁寧に引き出し、生活に彩りや張り合いが生まれるような目標を設定しましょう。
他者との交流・コミュニケーション
他者との交流・コミュニケーションは孤立を防ぎ、人間関係を維持するうえで重要です。
利用者の意向に沿いつつ、気兼ねなく他者と交流できるようなサポートを検討しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 日中独りで過ごすことが多く、会話の機会が減り、孤立感を感じている。 | デイサービスに通い、気の合う仲間と会話やレクリエーションを楽しみ、笑顔で過ごせる時間を持つ。 | ・趣味活動が豊富なデイサービスを2カ所見学し、本人に合う場所を選ぶ。 ・1カ月後、デイサービスのスタッフや他の利用者と挨拶を交わせるようになる。 |
趣味活動・役割の再獲得
趣味活動・役割の再獲得は、利用者の自尊心を維持し、メンタルを安定させるうえで有効です。
利用者の活力を取り戻すきっかけにもなります。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 手先の震えが原因で、長年の趣味だった書道をやめてしまった。 | 持ちやすい筆記用具を工夫し、再び書道を楽しみ、作品を部屋に飾る。 | ・作業療法士に相談し、本人に合った補助具付きの筆を選定する。 ・まずは週に1回、好きな文字を1文字書くことから始めてみる。 |
外出機会の確保
外出機会の確保は利用者の孤立化を防ぎ、社会生活を守るために必要です。
利用者に無理をさせない範囲で外出する機会を設けましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 外出への意欲はあるが、移動手段がなく、閉じこもりがちになっている。 | 月に1回、介護タクシーを利用して、なじみの喫茶店へ行き、気分転換を図る。 | ・地域の社会福祉協議会で、外出支援サービスに関する情報を収集する。 ・2カ月後、まずは近所の公園までヘルパーと散歩に出かける。 |
認知症・精神症状の安定に関する文例

認知症ケアの目標設定では、進行を緩やかにし、BPSD(行動・心理症状)を軽減することで、本人と家族が穏やかに過ごせることを目指します。
利用者のできないことだけに着目するのではなく、本人の残存能力を活かし、安心できる環境を整える視点が大切です。
認知機能の維持・進行緩和
利用者が自立した生活を送れるようにするためにも、認知機能の維持・進行緩和は積極的に取り組む必要があります。
利用者のペースに配慮しつつ、適切なケアを実践しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 物忘れが進行し、日課をこなすことに混乱が見られる。 | なじみの環境で、役割を持って過ごすことで、現在の認知機能を維持し、穏やかに生活する。 | ・1日のスケジュールを絵や写真でわかりやすく提示する。 ・ヘルパーと一緒に洗濯物をたたむなど、簡単な役割を担ってもらう。 |
BPSDの軽減
BPSDは利用者のメンタルに配慮しつつ、本人に合った対処方法を講じることが重要です。
利用者の訴えを否定せず、相手の気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 夕方になると落ち着かず、帰宅願望が強く現れる。 | 不安な気持ちが軽減され、自宅で安心して過ごせる時間が増える。 | ・本人の訴えを否定せず、共感的に耳を傾ける時間を作る。 ・日中の活動量を増やし、生活リズムを整える。 ・なじみの音楽を聴くなど、本人が落ち着ける方法を見つける。 |
医療連携・疾患管理に関する文例

利用者の健康状態を維持し、万が一の事態に対応するためにも、医療連携・疾患管理は最善を尽くす必要があります。
高齢者の多くは、何らかの慢性疾患を抱えているものです。
かかりつけ医や訪問看護師などと密に連携し、病状を適切に管理することで、重症化を防ぎ、安定した在宅生活を支えます。
疾患の管理
疾患の管理は利用者の持病や健康状態に合わせて適切な対応を取りましょう。
疾患によっては、日常生活のささいな習慣が悪影響をおよぼすケースもあるため、多角的な視点からのサポートが不可欠です。
医療関係者と連携し、適切な対策を実施しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 高血圧があり、服薬や食事管理が不十分である。 | 血圧を安定させ、脳血管疾患などの重篤な合併症を予防する。 | ・訪問看護師が週1回訪問し、血圧測定と服薬状況の確認、体調管理の指導を行う。 ・配食サービスを利用し、減塩食を週3回摂取する。 |
褥瘡(床ずれ)の予防・改善
寝たきりの利用者の場合、褥瘡予防が欠かせません。
必要な際は、体圧分散機能のあるマットレスのような福祉用具の導入も検討しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 寝たきりの時間が長く、仙骨部に褥瘡発生のリスクが高い。 | 適切な体圧分散とスキンケアにより、褥瘡を発生させずに安楽な療養生活を送る。 | ・体圧分散性能のあるマットレスをレンタル導入する。 ・2時間ごとの体位交換を徹底し、皮膚の状態を毎日観察・記録する。 |
家族(介護者)の負担軽減に関する文例

利用者本人だけでなく、介護を担う家族に目を向けることもケアマネジャーの重要な役割です。
介護者や、その家族が心身ともに健康でなければ、在宅生活は成り立ちません。
レスパイトケア(休息)の視点を取り入れ、包括的なサポートを実践しましょう。
介護負担の軽減
在宅での介護の場合、利用者の家族に多大な負担がかかるケースは珍しくありません。
利用者の家族の介護負担を軽減する際は、介護施設の活用を検討しましょう。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 24時間の介護により、主介護者である妻が心身ともに疲弊している。 | 介護サービスを適切に利用し、介護者が自分の時間を取り戻し、精神的な余裕を持って介護にあたれる。 | ・週2回のデイサービスに加え、月4日間のショートステイを導入する。 ・地域の介護者交流会への参加を促し、悩みを共有できる場を提供する。 |
介護知識・技術の習得
利用者の家族が適切な介護知識・技術を習得すれば、より最適なケアが可能です。
ただし、利用者の家族に過剰な負担がかからないように配慮する必要があります。
| ニーズ・課題 | 長期目標 | 短期目標 |
| 誤った移乗介助により、介護者が腰痛を抱えている。 | 安全な介助技術を習得し、腰痛を悪化させることなく、安心して介助できるようになる。 | ・訪問リハビリの際に、理学療法士から介助者へ介助指導を月1回実施する。 ・福祉用具を活用した負担の少ない介助方法を検討・導入する。 |
長期目標・短期目標を作成する際のポイント

ケアプランの長期目標・短期目標を作成する際は、以下の5つの視点を意識しましょう。
- 主語は常に利用者にする
- ポジティブな言葉を選ぶ
- 多職種連携で視点を広げる
- 阻害要因を予測・対策を盛り込む
- モニタリングと見直しを前提とする
上記のポイントを意識すれば、より良いケアプランを作成できます。
主語は常に利用者にする
ケアプランの主体はサービス提供者ではなく、あくまで利用者本人です。
目標を設定する際は、主語が「誰」になっているか常に確認しましょう。
| 良い例(主語が利用者) | 悪い例(主語が事業者) |
| ヘルパーの見守りのもと、自分で体を洗える。 | ヘルパーに入浴介助をしてもらう。 |
| 自分でお薬カレンダーを確認し、薬を飲める。 | 訪問看護師に服薬管理をしてもらう。 |
主語を利用者にすることで、本人の「~したい」「~できるようになりたい」といった主体性を引き出すプランになります。
ポジティブな言葉を選ぶ
目標は、利用者にとっての重要な指針であるため、「~しない」といった否定的な表現は避け、「~できる」「~になる」といった肯定的で前向きな言葉を選びましょう。
| ポジティブな表現 | ネガティブな表現 |
| 転倒することなく、安全に歩ける。 | 転倒しない。 |
| むせることなく、食事を楽しめる。 | 誤嚥しない。 |
ポジティブな言葉で表現された目標は、利用者や家族のモチベーションを高める効果があります。
逆に、ネガティブな表現はモチベーションを低下させるリスクが高いため、長期目標・短期目標の文章表現には注意を払いましょう。
多職種連携で視点を広げる
多職種連携で視点を広げることは、ケアプランを作成するうえで重要です。
医師・看護師・理学療法士・サービス提供事業者など、それぞれの専門職が持つ知識や視点を集約することで、プランはより実効性の高いものになります。
例えば、それぞれの専門職からは以下のような知見が期待できます。
| 専門職 | 役割 |
| 医師・看護師 | 疾患管理・医療的ケアの観点からの助言 |
| リハビリ専門職 | 身体機能評価・具体的なリハビリ内容の提案 |
| サービス提供事業者 | 現場での利用者の様子・サービス提供上の工夫 |
サービス担当者会議などを積極的に活用し、チームで利用者を支える意識を持つことが重要です。
また、利用者に万が一の事態が発生した際に備え、スピーディーに連携できる体制を整える必要があります。
阻害要因を予測・対策を盛り込む
目標達成を妨げる可能性のある「阻害要因」をあらかじめ予測し、その対策をプランに盛り込んでおくことで、問題が発生した際に迅速に対応できます。
阻害要因を予測する際は、以下のように実施しましょう。
| 目標 | 阻害要因の予測 | プランに盛り込む対策 |
| デイサービスに通い、他者と交流する。 | ・集団行動への抵抗感 ・疲労感 | ・まずは短時間の利用から開始する ・静かに過ごせるスペースを確保してもらう |
| 筋力トレーニングを継続する。 | ・膝の痛み ・意欲の低下 | ・運動前に湿布を貼る ・達成度をカレンダーに記録し可視化する |
リスクマネジメントの視点を持つことで、ケアプランの信頼性が高まります。
また、対策をあらかじめ設定しておくことで、トラブルが発生した際の利用者への影響を最小化できます。
モニタリングと見直しを前提とする
ケアプランは一度作成したら完成するものではなく、モニタリングと見直しによるブラッシュアップを前提としたものです。
定期的な訪問(モニタリング)でプランに沿ってサービスが提供しているかを必ず確認しましょう。
目標の達成度が低かったり、新たなニーズが発生したりした際は、速やかにかつ柔軟にプランを修正する必要があります。
利用者本人はもちろん、その家族やサービスの提供に関わっている専門職から最新の情報を確認し、いつでもプランを調整できるようにしておきましょう。

本記事は、ケアプラン作成における長期目標・短期目標の重要性を丁寧に整理し、実務に即した文例を多数提示している点が非常に有用です。目標設定は「利用者の生活の質(QOL)をいかに高めるか」という視点が核であり、ケアマネジャーが多職種と共有しやすい表現にすることが求められます。特に、長期目標は生活像や希望を明確化する「方向性の指針」となり、短期目標はそれを達成する「具体的ステップ」として設定することで、進捗の可視化・達成感の醸成が可能となります。記事内の事例は、ADLやIADL、認知症ケア、家族支援など多面的に網羅しており、現場で応用しやすい内容です。ただし実際のケアプランでは、利用者の身体・心理状態、家族状況、環境要因を総合的に評価し、画一的な文例ではなく個別性を反映させることが不可欠です。本記事はその「基本形」を理解し、柔軟に応用するための良質な参考資料といえるでしょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
長期目標・短期目標の文例を参考に理想的なケアプランを作成しよう

長期目標・短期目標の文例は、プラン作成の時間を短縮するための便利なものです。
しかし、もっとも大切なのは、ただ文例を利用するのではなく、利用者にふさわしい言葉を選び取り、調整していくことです。
本記事で紹介した考え方やポイントを意識すれば、適切なケアプランを作成できる可能性が高まります。
介護ソフトのようなICTツールも賢く活用し、業務負担を軽減しながら、専門職として利用者と向き合う時間を大切にしてください。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。