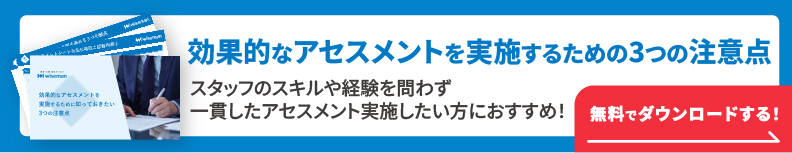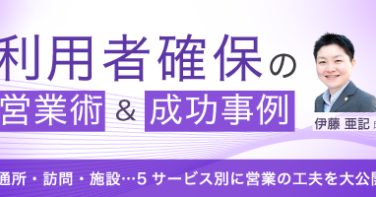看取りケアプランの書き方|不安を自信に変える具体的ステップと専門職の役割
2025.09.25

医師から看取りの方針が示されたとき、ケアマネジャーとして「穏やかな最期を支えたい」という強い責任感が生まれる方は多いのではないでしょうか。それと同時に、ケアプラン作成への不安を感じる方は少なくありません。
「目標設定は適切か」
「サービス内容は具体的にどう書けば良いのか」
このように悩んでしまうこともあるはずです。本記事は、看取りケアプラン作成の教科書として具体的な文例を紹介します。利用者が安心して終末期を過ごせるように、専門職としての役割を全うしましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
アセスメントシートを記載する上で知っておきたい3つの観点を記載しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
看取りケアとは

看取りケアとは、人生の最期を迎える方が穏やかにその人らしく過ごせるようにサポートすることです。身体的な介護だけでなく、精神的なケアや家族への支援も含まれる、包括的なアプローチを指します。
看取りの期間に明確な定義はありませんが、一般的には医師が医学的知見に基づき「回復の見込みがない」と判断した時点から始まります。この判断を受けて、本人や家族へ説明が行われ、同意を得た上で看取りケアへと移行するのが一般的です。
ケアプラン上では、この同意を得た日を基点に看取りに対応したプランへと変更します。
看取りにおけるケアマネジャーの3つの役割

看取りのプロセスにおいて、ケアマネジャーは非常に重要な役割を担います。その役割は多岐にわたりますが、特に意識すべきは以下の3つの側面です。
ケアマネジャーの役割を理解することで日々の業務に軸が生まれ、迷いなく行動できるようになるでしょう。
役割1:本人の代弁者
終末期には、本人が直接意思を伝えることが難しくなる場面が増えます。ケアマネジャーは、これまでの関わりやアセスメントで得た情報に基づき、本人の声にならない想いを汲み取る「代弁者」としての役割を担っています。
本人の価値観や人生観を深く理解し、それを多職種チームや家族に的確に伝えることが重要な仕事のひとつです。
役割2:多職種チームの調整役
看取りケアは医師や看護師、介護職員、薬剤師など、多くの専門職が関わるチームアプローチが不可欠です。
ケアマネジャーは、そのチームの中心に立つ「調整役」としての役割を担います。各専門職が持つ情報を集約・共有し、ケアの方向性がぶれないように舵取りをすることが重要です。
役割3:家族の精神的サポーター
大切な人の最期が近づく中で、家族は身体的にも精神的にも大きな負担を抱えています。ケアマネジャーは利用者だけでなく、その家族にとっても「精神的なサポーター」でなければいけません。
家族の不安や葛藤に耳を傾け、必要な情報を提供し、社会資源につなぐといった伴走者として寄り添う姿勢が大切です。
【完全ガイド】明日から使える看取りケアプランの作成手順

ここからは、看取りケアプランの具体的な作成手順を5つのステップで解説します。各ステップのポイントと文例を参考に、自信を持ってケアプラン作成を進めていきましょう。
ステップ1:アセスメント ・本人と家族の想いを深く理解する
質の高いケアプランは、質の高いアセスメントから生まれます。特に看取り期のアセスメントでは身体状況だけでなく、本人が何を大切にし、どのように最期を迎えたいのか、その価値観や人生観を深く理解することが不可欠です。
身体的・精神的苦痛に関するアセスメント項目
終末期に現れやすい苦痛を的確に把握するための視点です。本人からの訴えだけでなく、表情や言動、バイタルサインなど客観的な情報も重要な指標です。
| アセスメント領域 | 確認すべき具体的な項目例 |
| 疼痛(痛み) | ・痛みの場所、強さ(数値化)、種類(ズキズキ、チクチクなど)はどうか ・痛みが強くなる時間帯や状況はあるか ・現在の痛み止めは効果があるか ・副作用はないか |
| 呼吸状態 | ・呼吸困難感、咳、痰の有無と程度はどうか ・安楽な呼吸ができる体位はあるか ・酸素吸入は必要か |
| 消化器症状 | ・吐き気、嘔吐、便秘、下痢の有無と程度はどうか ・食欲はどうか ・食事の形態や量は適切か |
| 精神状態 | ・不安、恐怖、孤独感、抑うつ、いらだちなどの訴えはないか ・せん妄(意識の混濁、幻覚など)の兆候はないか ・睡眠はとれているか |
| 全身状態 | ・倦怠感、浮腫(むくみ)、皮膚の乾燥、褥瘡のリスクはどうか |
QOL(生活の質)と価値観のアセスメント項目
「その人らしさ」を支えるための情報を集めます。本人だけでなく、家族からもこれまでの人生の様子を伺うとヒントを得られます。
| アセスメント領域 | 確認すべき具体的な項目例 |
| 価値観・人生観 | ・これまでの人生で何を大切にしてこられたか ・最期の時間をどのように過ごしたいと望んでいるか ・宗教や信仰など、心の支えになっているものはあるか |
| 意思決定 | ・延命治療についてどう考えているか ・最期を迎えたい場所はどこか ・誰に意思決定を委ねたいか |
| 趣味・楽しみ | ・好きなこと、楽しいと感じることは何か ・五感で心地良いと感じるものは何か |
| 人間関係 | ・最期のときに誰にそばにいてほしいか ・会いたい人、話したい人はいるか ・伝えたい想いや言葉はあるか |
家族の介護力とサポート体制のアセスメント項目
家族を支え、持続可能なケア体制を築くための視点です。主たる介護者だけでなく、他の家族の意向も確認することが重要です。
| アセスメント領域 | 確認すべき具体的な項目例 |
| 家族の意向 | ・本人の看取りについて、家族としてどのように考えているか ・どのような最期を迎えさせてあげたいと願っているか ・医療的な選択について、家族間で意見の相違はないか |
| 介護力・負担 | ・主たる介護者は誰か ・介護者の健康状態や年齢はどうか ・介護による身体的、精神的、経済的な負担はどの程度か ・介護をサポートしてくれる親族や友人はいるか |
| 理解度・不安 | ・病状や今後の見通しについて、どの程度理解しているか ・介護の方法や緊急時の対応について、不安に感じていることはないか ・死別後の生活について、心配なことはないか |
ステップ2:課題分析(ニーズの抽出)・第1表の書き方
アセスメントで得た情報を整理し、ケアプランの核となるニーズと課題を導き出します。ここでは、ケアプラン第1表の「本人及び家族の生活に対する意向」と「総合的な援助の方針」の書き方を見ていきましょう。
「生活に対する意向」を的確に捉えるポイント
本人や家族から聴取した希望を、そのまま記載するだけでなく、その背景にある想いを汲み取ってまとめることが大切です。具体的な文例は以下のとおりです。
| ポイント | 悪い例 | 良い例 |
| 具体的でポジティブな表現 | 痛いのは嫌だ | 痛みがなく、安楽に過ごしたい |
| 本人の言葉を活かす | 延命治療は不要 | 「機械につながれて生きるのは嫌だ。自然な形で最期を迎えたい」との本人の言葉を尊重する |
| 家族の想いも記載 | 家族は家で看たい | 「父が一番落ち着く家で、家族みんなで静かに見送ってあげたい」と家族は希望している |
ケアマネジメント上の課題を明確にする方法
アセスメント結果と意向を踏まえ、専門職として支援すべき課題を明確にします。「~できない」という視点ではなく、「~できるように支援する」という視点で課題を捉えることが重要です。
以下の文例を参考に、最適なケアプランを作成してみてください。
| アセスメント情報 | 課題分析の文例 |
| がん末期で強い疼痛がある。「痛みがなければもっと話せるのに」との本人の発言 | 疼痛によりQOLが著しく低下しているため、医療と連携し適切な疼痛コントロールを行いながら、穏やかな時間を過ごせるよう支援する必要がある |
| 独居の妻が一人で介護。「夜中に何かあったらと思うと眠れない」と不安を吐露 | 介護者である妻の介護負担・精神的負担が大きく、レスパイトと緊急時対応体制の確保が急務である |
| 延命治療について、長男と長女で意見が異なる | 本人の意思が確認できない中、家族間で延命治療に関する意向が異なっている。意思決定支援と家族間の合意形成に向けた働きかけが必要である |
ステップ3:目標設定(長期・短期)・第2表の書き方【文例付】
課題分析で明確になったニーズを、具体的な目標に落とし込みます。目標は本人・家族だけでなく、関わるすべてのスタッフがケアの目的を共有できる言葉で設定することが理想です。
利用者の尊厳を守る長期目標の立て方と文例
長期目標は、その人らしい最期を実現するためのケア全体のゴールを示します。抽象的になりすぎず、その人ならではの具体的な状態を目指すことがポイントです。
| ニーズ(意向) | 長期目標の文例 |
| 痛みに悩まされず、穏やかに過ごしたい | 身体的苦痛が緩和され、心穏やかに安楽な日々を送ることができる |
| 住み慣れた自宅で、家族に見守られながら最期を迎えたい | 家族の支援と適切な在宅サービスの利用により、最期まで自宅での生活を継続できる |
| 好きな音楽を聴きながら、静かに過ごしたい | 本人の嗜好に合わせた環境が整えられ、尊厳が保たれた中でその人らしい最期を迎えることができる |
具体的な行動につながる短期目標の立て方と文例
短期目標は、長期目標を達成するための具体的なステップです。誰が見ても評価できるように「いつまでに」「どのような状態になる」かを明確に記述します。
| 長期目標 | 短期目標の文例 |
| 身体的苦痛が緩和され、心穏やかに安楽な日々を送ることができる | ・1カ月後、疼痛コントロールが図れ「痛みが楽になった」と笑顔が見られる ・2週間後、呼吸困難感が緩和され、夜間安眠できる日が増える |
| 最期まで自宅での生活を継続できる | ・1カ月後、緊急時の連絡体制と対応方法を家族が理解し、不安なく在宅介護ができる ・退院後1週間以内に、介護ベッドが導入され安楽な療養環境が整う |
| その人らしい最期を迎えることができる | ・1週間後、本人が望む音楽や香りが準備され、リラックスできる時間を持てる ・面会に来た孫と、穏やかな表情でコミュニケーションが図れる |
ステップ4:サービス具体化 ・第2表の援助内容【文例集】
設定した短期目標を達成するために「誰が」「何を」「どのように」行うのかを具体的に記述します。ここでは、ケアの場面ごとにそのまま使える文例を紹介します。
| カテゴリ | サービス内容の具体例 | 留意点・頻度など |
| 精神的ケア・意思決定支援 | ・本人の意思を尊重したケアが行われるよう、多職種と情報共有・調整を行う ・意思決定に関する家族の葛藤を受け止め、精神的に支援する | 週〇回訪問随時電話連絡 |
| 食事・栄養 | ・口腔内の保湿、清潔ケア ・嚥下状態の観察、誤嚥予防の指導 | 週〇回 |
| 排泄ケア | ・便秘や下痢に対する処置(摘便、浣腸など医師の指示に基づく) ・尿量や便の性状を観察し、医療職へ報告 | 週〇回 |
| 家族支援 | ・家族の介護負担や精神的状況を把握し、傾聴と助言を行う ・レスパイトケア(ショートステイなど)の利用を提案・調整する | 週〇回訪問随時電話連絡 |
| 情報提供 | ・家族に対し、症状変化時の対応方法や介護技術について指導する ・死別後のグリーフケアに関する情報提供を行う | 毎訪問時 |
ステップ5:サービス担当者会議とプランの共有・同意
作成したケアプラン原案をもとに、本人・家族および関係者を集め、内容を確認・共有します。この会議は、単なる手続きではありません。全員が同じ目標に向かって進むための「チーム結成式」と捉え、ケアマネジャーは進行役として以下の点を意識しましょう。
| ポイント | 説明 |
| 主役は本人・家族 | 最初に本人・家族から想いや希望を話してもらう場を作る |
| 専門職への翻訳 | 本人・家族の想いを専門職が理解できる言葉に置き換えて伝える |
| 役割の明確化 | 各サービス事業所が担う役割を具体的に確認し、連携事項を整理する |
| 合意形成 | プラン内容について全員が納得し、同意を得る。異論が出た場合は代替案を提示し、再度検討する |
なお、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて、「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
【場所別】看取りケアプラン作成のポイント

看取りを行う場所によって、プラン作成で重視すべき点や活用できる資源が異なります。ここでは、看取りケアプラン作成時のポイントを「在宅」と「施設」に分けて解説します。
在宅(居宅)で穏やかな最期を迎えるためのプランニング
住み慣れた自宅での看取りは、多くの利用者が望む一方で、家族の負担や緊急時への不安が伴います。そのため、ケアマネジャーは24時間365日支える体制を構築することが大切です。
| 対策 | 詳細 |
| 医療連携の強化 | 24時間対応可能な訪問診療医や訪問看護ステーションとの密な連携は必須。緊急時の連絡方法や対応手順を事前に明確にし、家族と共有する |
| 介護サービスの組み合わせ | 日中の訪問介護に加え、夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、時間帯に応じたサービスを組み合わせ、介護の空白時間を作らない工夫が必要である |
| 家族のレスパイト確保 | ショートステイや訪問入浴などを計画的に利用し、介護者である家族が休息を取れる時間を意図的に作る |
| 福祉用具・住宅改修の活用 | 介護ベッドやエアマットレス、ポータブルトイレの導入はもちろん、必要に応じて手すりの設置なども検討し、安全で安楽な療養環境を整える |
施設(特養・グループホーム)でのチームケアを活かしたプランニング
介護・看護職員が常駐する施設では、その強みを活かしたチームケアが可能です。ケアマネジャーは施設内の多職種が円滑に連携し、一貫したケアを提供できるよう調整役を担います。
| 項目 | 内容 |
| 施設内での共通理解 | 施設の看取りに関する指針を職員全員が共有し、ケアの方向性を統一する。医師や看護職員、介護職員、相談員などが参加するカンファレンスを定期的に開催し、本人の状態変化やケア内容を協議する |
| 個別のケア計画への落とし込み | ケアプランの目標や援助内容を、各職員が日々実践する「個別援助計画」に具体的に落とし込む。食事の形態や安楽な体位、声かけの方法など、細かいレベルでの情報共有がケアの質を高める |
| 家族との関係構築 | 家族がいつでも気軽に面会や宿泊ができるような環境を整え、日々の様子をこまめに報告することで信頼関係を築く。家族もチームの一員として捉え、ケアに参加してもらうことも有効である |
| 他の入居者への配慮 | 他の入居者が不安にならないよう配慮し、亡くなられた後は親交のあった方々とお別れの会を開くなど、グリーフケアの視点も重視する |
看取り関連加算の要件とケアプラン上の注意点

質の高い看取りケアを提供することは、介護報酬上の加算にもつながります。ここでは代表的な加算の算定要件と、そのためにケアプランや記録に何を記載すべきかを解説します。
【施設】看取り介護加算の算定要件と記録のポイント
特別養護老人ホームなどで算定できる加算です。算定するには医師や看護職員、介護職員、ケアマネジャーなどが連携し、計画的にケアを行う必要があります。
| 主な算定要件 | ケアプラン・記録への記載ポイント(文例) |
| 医師による看取り期の判断 | 【支援経過記録】 〇月〇日、〇〇医師より「医学的知見に基づき回復の見込みがない」との診断あり |
| 本人・家族への説明と同意 | 【第1表:意向】 本人・家族へ看取り介護指針を説明し、当施設での看取りを希望され、同意書に署名をいただく 【支援経過記録】 〇月〇日、本人・家族同席のもと、〇〇医師、看護師〇〇より病状説明。看取り介護計画について説明し、同意を得る |
| 多職種連携による計画作成 | 【第2表:援助内容】 (ケアプランのサービス内容を具体的に記載) 【支援経過記録】 〇月〇日、看取り介護カンファレンス実施。医師、看護師、介護職員、ケアマネジャー、栄養士が参加し、疼痛緩和と安楽な環境整備について協議 |
| 本人・家族との定期的な協議 | 【支援経過記録】 〇月〇日、家族と面談。本人の状態を報告し、今後のケアについて意向を確認。「痛みがないようで安心している」との言葉あり |
【居宅】ターミナルケアマネジメント加算の算定要件と動き方
在宅での看取りを支援した居宅介護支援事業所が、利用者の死亡月に算定できる加算です。算定するには死亡日および死亡日前14日以内に、以下の要件を満たす必要があります。
| 主な算定要件 | ケアマネジャーの動きと記録のポイント(文例) |
| 24時間連絡できる体制の確保 | 【第1表:総合的な援助の方針】 利用者・家族に事業所の連絡先を渡し、24時間連絡可能な体制であることを説明する 【支援経過記録】 〇月〇日、緊急連絡先と24時間対応について説明。家族は「何かあればすぐに連絡します」と理解 |
| 死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の訪問 | 【支援経過記録】 ・〇月〇日(死亡〇日前):自宅訪問。バイタル安定。家族の介護負担について傾聴 ・〇月〇日(死亡〇日前):自宅訪問。呼吸状態の変化あり。訪問看護師と情報共有 |
| 訪問診療医・訪問看護師との連携 | 【支援経過記録】 ・〇月〇日:〇〇クリニック(訪問診療医)へ電話。症状変化について報告し、指示を仰ぐ ・〇月〇日:〇〇訪問看護ステーションの〇〇看護師と電話。明日の訪問時の観察ポイントについて協議 |
| 看取りに係るアセスメントと同意 | 【支援経過記録】 〇月〇日、自宅にて本人・家族と面談。今後の療養場所や医療に関する意向を最終確認。在宅での看取りを強く希望される |

看取りケアプランは苦手、あるいはやったことがないというケアマネジャーも多いと思います。そのようなケアマネジャーにとって、本記事は看取りケアプランの骨子を実務レベルで整理しており有用です。特に「代弁者/調整役/家族支援」というケアマネの役割定義は現場に落とし込みやすい一方で実装時は①ACP(人生会議)の継続的実施と意思更新の記録、DNAR等の方針・急変時手順・24時間連絡体制の明文化、②苦痛の見える化(NRS・ESAS-r等)とせん妄評価、③家族負担の客観評価(睡眠・役割分担等)とレスパイト導入、④宗教的・文化的配慮および死別後のグリーフケアまでの支援動線をプランに組み込むことが肝要です。またひとりで抱え込まず、多職種連携を意識し、医師・看護師・介護職・ケアマネ・薬剤師・地域包括支援センターなどが一体となって支援しましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
まとめ:最適な看取りケアプランを作成して利用者をサポートしよう

看取りケアプランの作成は、決して簡単な業務ではありません。しかし、一人の人間の尊い人生の最終章に深く関わる、非常にやりがいのある専門的な仕事です。
また、本記事で解説したステップと文例は、ケアプラン作成の一例にすぎません。もっとも大切なのは、目の前の利用者一人一人と真摯に向き合い「その人にとっての最善は何か」を常に問い続ける姿勢です。
作成したケアプランが利用者の穏やかな最期につながったとき、ケアマネジャーとしての大きな喜びと誇りを感じられるでしょう。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。