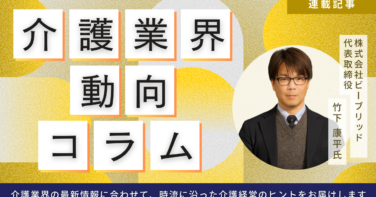【介護業界動向コラム】第15回 導入したのに、なぜか使われなくなるICT
2025.09.30
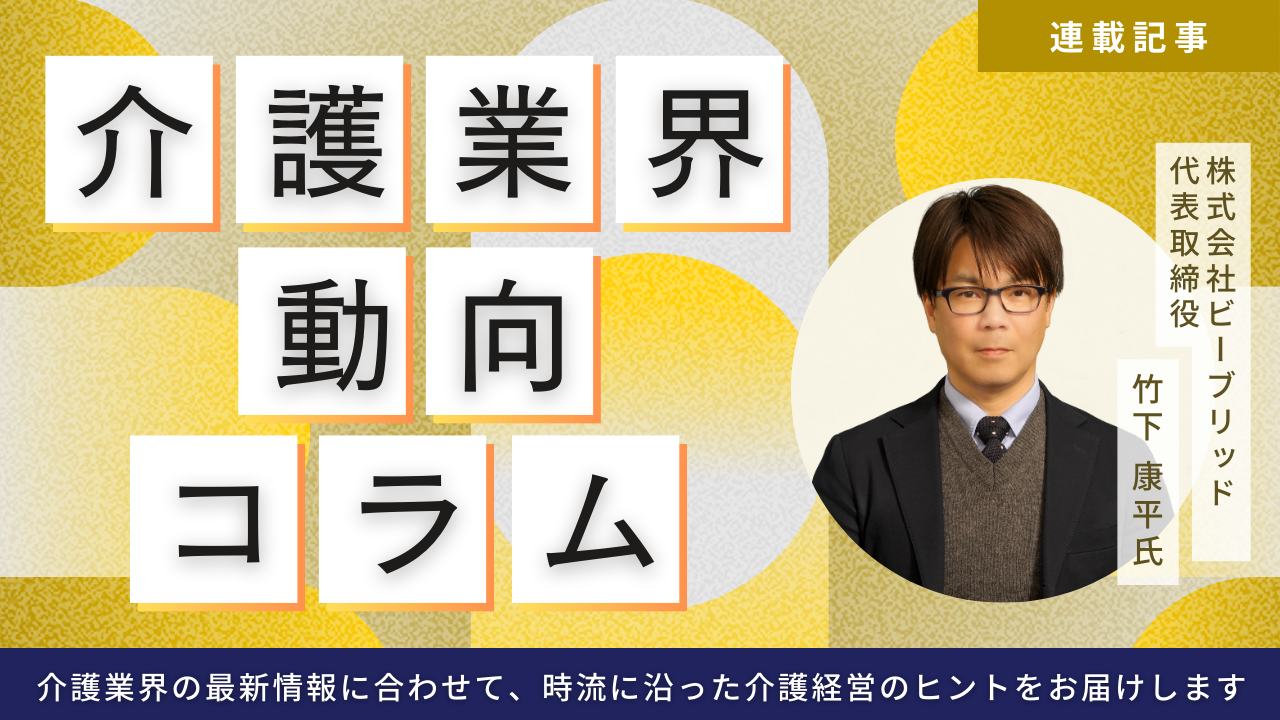
第13回では、なぜICTが使われなくなるのか、その理由を掘り下げました。第14回では、停滞した状況を立て直すために現場でできることを紹介しましたね。しかし、本当に大切なのはその先です。どうやって改善を継続していくか。今回はその点についてお話しします。
改善が止まってしまう瞬間
現場でよく聞くのは、こんな声です。
- 「最初はみんな頑張って使っていたけど、日々の業務に追われるうちに、いつの間にか形だけに…」
- 「担当者が異動してから、全然進まなくなってしまった」
そう、ICT導入や業務改善は“点”の取り組みになりがちです。最初の熱が冷め、担当者がいなくなると、取り組みそのものが止まってしまう。これはどの事業所でも起こり得ることです。
継続するための鍵は「人」と「仕組み」
だからこそ必要なのが、1人の担当者に頼らない「チーム」と、継続を支える「仕組み」です。
まず、介護職だけでなく、看護やリハビリ、事務職など、さまざまな職種が関わる委員会形式で進めましょう。「自分たちの仕事がどう良くなるのか」という目的意識を共有できれば、改善の火は消えません。
さらに、定期的に振り返る場を設けることが重要です。これは厚生労働省が報酬改定で求める「生産性向上委員会」の考え方にも通じます。人が入れ替わっても取り組みが続くのは、こうした仕組みがあるからです。
「見える化」が文化をつくる
改善を続ける上で欠かせないのが「見える化」です。
例えば、夜勤の巡視回数やヒヤリハットの件数を委員会で共有する――これは多くの事業所で実践されています。ところが、そこから改善が根付く組織と、形だけで終わる組織があります。
その違いは「数字をどう扱うか」にあります。
単に「件数を報告する場」になってしまえば、やがて形骸化してしまう。
一方で、改善が根付く組織では、数字をきっかけに「なぜそうなったのか?」を前向きに語り合う場に変えています。
- 数字を“評価”の道具にせず、「学び」のきっかけにする
- 課題を“誰かのせい”にせず、「改善のヒント」として扱う
- 職員の意見を引き出し、「次に試す行動」を具体的に決めて終える
この姿勢の違いが、結果として「改善が文化として定着するかどうか」を分けるのです。
つまり「見える化」は単なる数字の提示ではなく、組織がどんな文化で数字を受け止めるかにこそ価値があります。
小さな改善を積み重ねる仕掛けづくり
ICTは導入して終わりではなく、立て直して終わりでもありません。大切なのは「続けられる仕組み」をつくれるかどうかです。
チームで取り組み、仕組みで支え、成果と課題を“見える化”し続ける。この一連のプロセスそのものが、改善を止めない前向きな「文化」を育むのです。
その積み重ねこそが、利用者に向き合える時間を増やし、介護現場をより良く変えていきます。この“文化としての改善力”こそが、補助金や制度の枠を超え、これからの介護事業経営に不可欠なものだと私は考えます。
ぜひ皆さまの現場でも、「チーム」「仕組み」「見える化」を意識した改善のサイクルを回してみましょう。その一歩が、職員の働きやすさと利用者の安心を同時に高める力になるはずです。

竹下 康平(たけした こうへい)氏
株式会社ビーブリッド 代表取締役
2007 年より介護事業における ICT 戦略立案・遂行業務に従事。2010 年株式会社ビーブリッドを創業。介護・福祉事業者向け DX 支援サービス『ほむさぽ』を軸に、介護現場での ICT 利活用と DX 普及促進に幅広く努めている。行政や事業者団体、学校等での講演活動および多くのメディアでの寄稿等の情報発信を通じ、ケアテックの普及推進中。