短期入所療養介護とは?サービス内容や人員配置基準を徹底解説
2025.02.25

短期入所療養介護は、医療と介護の専門職が連携し、医療的ケアが必要な利用者を支援するサービスです。
医師や看護師が常駐し、点滴や床ずれ処置など、専門的な医療ケアと介護サービスを組み合わせて提供できます。
しかし、人員配置基準やサービス内容について、十分な情報が得られずに悩む方も少なくありません。
本記事では、短期入所療養介護の基本的な仕組みから人員配置基準まで、詳しく解説します。サービスの特徴や基準を体系的に理解し、適切なサービス選択や提供に活かせるでしょう。
目次
短期入所療養介護とは

医療と介護を組み合わせた支援が特徴的なサービスが、短期入所療養介護です。老人保健施設や医療機関に一時的に入所し、看護師による医療的ケアとリハビリ専門職による機能訓練を利用できます。
例えば、退院直後で医療的な管理が必要な方や、定期的な点滴が必要な方など、医療ニーズの高い利用者も安心して滞在できます。
利用者の医療ニーズに応え、家族の介護負担も軽減する短期入所療養介護は、在宅生活の継続を支える有効な選択肢です。
提供される医療ケアと介護サービスの内容
短期入所療養介護では、医療・介護・リハビリの各専門職が緊密に連携し、利用者の心身状態に応じた専門的なケアを提供します。利用者の24時間の生活リズムに合わせて、以下のような専門的なケアを組み合わせます。
| サービス区分 | 専門職の役割と具体例 |
| 医療ケア | 朝夕の定期的な血圧・体温測定 床ずれの予防と処置 服薬時間の管理と副作用の観察 夜間の緊急時対応 |
| 介護ケア | 利用者の好みに配慮した食事介助 安全な入浴介助と皮膚観察 排せつパターンに合わせた介助 夜間の体位変換と安眠支援 |
| 専門的リハビリ | 自宅環境を想定した動作練習 食事動作の改善訓練 歩行の安定性向上 筋力維持のための個別運動 |
| 生活支援 | 趣味を活かした余暇活動 季節の行事参加 在宅復帰に向けた環境調整 家族との情報共有を行う |
利用者の体調や生活習慣に合わせて、それぞれの専門的なケアを柔軟に組み合わせます。例えば、午前中のリハビリ後は十分な休憩時間を設け、午後からレクリエーションに参加するなど、無理のないプログラムを計画します。
短期入所療養介護と短期入所生活介護の違い
短期入所療養介護と短期入所生活介護は、一時的な施設入所である点では同じですが、提供される内容や設置施設に違いがあります。
| サービスの特徴 | 短期入所療養介護 | 短期入所生活介護 |
| 設置施設 | ・医療機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | ・特別養護老人ホーム ・老人短期入所施設 |
| 医療体制 | 医師・看護師が常駐し、24時間の医療管理体制あり | 基本的に医療体制はなし(配置医による対応) |
| 主な対象者 | 医療的ケアやリハビリが必要な方 | 身体介護や生活支援が必要な方 |
| 提供サービス | 医療管理・看護・リハビリ・介護・生活支援 | 食事・入浴・排せつなどの生活支援が中心 |
特に短期入所療養介護は、医療的なケアが必要な方の受け入れに対応できる点が特徴です。例えば、点滴や床ずれ処置が必要な方、退院直後で医療的な管理が必要な方などが、安心して利用できます。
一方、短期入所生活介護は、身体介護や生活支援が中心となり、より家庭的な雰囲気の中でサービスを受けられます。利用者の状態や必要なケアの内容に応じて、適切なサービスを選択しましょう。
短期入所療養介護の主な目的
短期入所療養介護の利用目的は、利用者と家族のニーズによって4つに分かれます。
| 家族の休息と生活支援 | 夜間の介護で疲労が蓄積した家族の休養 結婚式や法事への参列、旅行などの外出機会の確保 仕事と介護の両立をサポート |
| 医療ケアとリハビリの充実 | 理学療法士などによる歩行訓練や筋力アップ 看護師による点滴や傷の処置 正しい服薬タイミングの管理と指導 |
| 在宅生活へのスムーズな移行 | 入院から在宅への段階的な準備期間として活用 福祉用具の選定や住環境の評価 介護施設への入所を検討する際の体験利用 |
| 急な事態への対応 | 介護者の体調不良や入院時の緊急受け入れ 台風や地震などの災害時の一時避難 かかりつけ医からの依頼による医療管理 |
特に、医療ニーズの高い利用者の場合、医師の指示のもと看護師が24時間体制で健康状態を見守ります。例えば、定期的な痛み止めの投与が必要な方や血糖値の管理が欠かせない方でも、専門スタッフが適切に対応できるのが短期入所療養介護の強みです。
短期入所療養介護を運営するメリット・デメリット
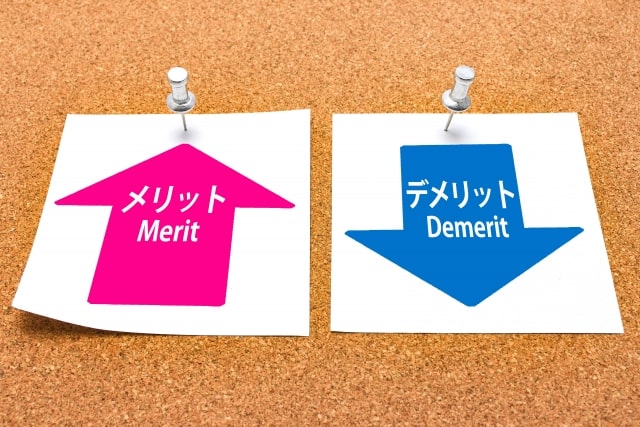
短期入所療養介護を運営する際は、メリットだけではなくデメリットも理解しなければなりません。
短期入所療養介護運営によるメリット
短期入所療養介護事業を運営する上でのメリットは多岐にわたり、施設側と利用者側の双方に利点があります。メリットを理解し、事業運営に活かすことが大切です。
具体的なメリットは、以下のとおりです。
- 安定した収益確保
- 在宅介護の負担軽減に貢献
- 専門性の高い人材育成
- 多様なニーズへの対応
- 他の介護サービスとの連携強化
短期入所療養介護の運営は、安定した収益確保だけではなく、地域社会への貢献や人材育成にもつながります。
多様なニーズに応え、他サービスとの連携を強化すれば、利用者とその家族も、安心して利用できるでしょう。
短期入所療養介護運営によるデメリット
短期入所療養介護事業の運営には、メリットだけではなく、デメリットも存在します。デメリットを事前に把握し、適切な対策を講じることが、運営をする上では大切です。
具体的なデメリットは、以下のとおりです。
- 人材確保の困難さ
- 医療機器の導入や維持管理、専門スタッフへの人件費などの運営コスト
- 医療事故リスク
- 複雑な手続きと規制
短期入所療養介護の運営には、人材確保の難しさやコストの高さなど、多くの課題が存在します。上記の課題に適切に対応しながら、質の高いサービスを提供していく必要があります。
短期入所療養介護の具体的な利用条件とルール

短期入所療養介護の利用には、一定の条件とルールがあります。
利用を検討する際は、事前に確認しておきましょう。
利用対象者と適用条件
短期入所療養介護は、要介護1~5の認定を受けた方が利用できるサービスです。ただし、要介護認定だけでは利用できません。
利用には、次の条件を満たす必要があります。
- 医療ニーズが高い
- 一時的な入所が必要
- 介護保険の適用を受けている
上記以外にも、施設ごとに利用条件が異なる場合があります。
短期入所療養介護の予約・利用の流れ
短期入所療養介護の予約から利用開始までの流れは、以下のとおりです。円滑な運営のため、以下の手順を把握しておきましょう。
| ケアマネジャーとの連携 | ケアマネジャーから、利用希望者の情報提供を受ける 利用目的や期間などを確認し、受け入れ可否を判断 |
| 利用申し込みの受付 | ケアマネジャーから利用申し込みを受け付ける 利用者の介護・医療情報を確認し、居室の空き状況や受け入れ体制を調整 |
| ケアプランの作成 | ケアマネジャーと連携し、利用者の状態に合わせたケアプランを作成 予算や他のサービスとの調整も行い、施設でのサービス提供体制を整える |
| 契約とサービス開始 | ケアプランに沿って、利用者と契約を締結 利用者の状態を注意深く観察し、適切なケアを提供 |
上記の流れを参考に、施設での受け入れ体制を整備しましょう。
計画書作成時の要件と注意事項
短期入所療養介護では、利用開始前に「短期入所療養介護計画書」を作成する必要があります。計画書は、利用者が適切なサービスを受けるために欠かせないものです。
計画書作成時の要件と注意点を以下にまとめました。
| 利用者の状態を正確に把握 | 利用者の病歴や現在の健康状態、介護状況などを正確に把握し記載する |
| 必要なサービスを明確に | 医療的ケアや介護、リハビリテーションなど、利用者が必要とするサービスを明確に記載 |
| 目標と期間を設定 | 短期入所療養介護で達成したい目標(例:症状の安定、体力回復など)を設定し、そのために必要な期間を決定 |
| 関係機関と連携 | 主治医やケアマネジャー、ご家族など、関係機関と連携を図りながら計画書を作成 |
| 加算要件を考慮 | 看護体制加算、医療連携強化加算などの加算を算定する場合は、ケアプランの内容に含める必要がある |
計画書は、利用開始前に施設と利用者、ご家族で内容を確認し、合意の上で決定します。計画書の内容は、利用期間中に変更となる場合もあるため、定期的な見直しも大切です。
具体的なケアプラン作成のポイントや注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。
「ケアプランはショートステイの際に必要?作成手順やポイントを解説」
利用者負担や費用の概要
短期入所療養介護の費用は、要介護度やサービス内容、滞在日数などによって変動します。
利用者負担は、介護保険制度に基づき、原則1割または2割の自己負担です。
施設側は、残りの費用を介護保険から受け取ります。医療費や食事代などは、利用者様からの別途徴収となる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
運営側は、これらの費用体系を把握しておかなければなりません。
短期入所療養介護と他の介護サービスの併用ルール
短期入所療養介護は、他の介護サービスと併用できる場合があります。例えば、在宅での訪問介護やデイサービスとの併用も可能です。
ただし、併用できるサービスや範囲は、利用者の状況や施設の状況によって異なります。
併用を希望する場合は、事前にケアマネジャーや施設へ相談し、利用計画を作成する必要があります。
短期入所療養介護の必要な基準
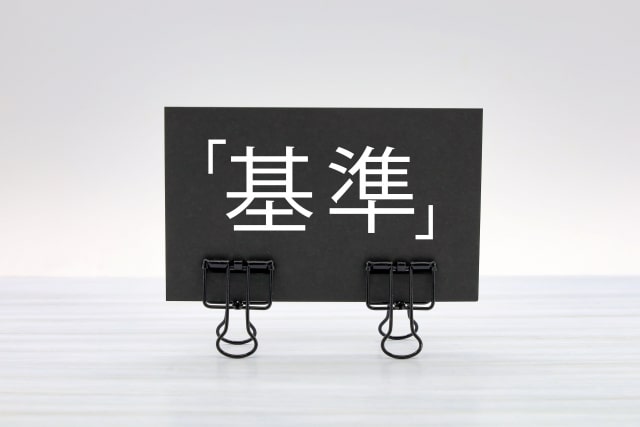
短期入所療養介護を提供するにあたり、施設の種類や人員配置には、満たすべき基準があります。基準を理解し、円滑な施設運営を目指しましょう。
サービス提供施設の種類
短期入所療養介護を提供できる施設は、以下のとおりです。
必要な人員や設備は、原則として施設ごとに満たすべき基準が定められています。
- 介護老人保健施設
- 療養病床を有する病院、または診療所
- 診療所(療養病床を有するものを除く)
- 介護医療院
診療所(療養病床を有するものを除く)は、以下の要件を満たす必要があります。
- 床面積は、利用者1人につき6.4㎡以上
- 浴室がある
- 機能訓練を行うための場所がある
上記の施設基準を踏まえ、自施設でのサービス提供を検討しましょう。
人員配置に必要な基準と職種別要件
短期入所療養介護の人員配置基準は、厚生労働省令で定められています。具体的な基準は、施設の規模や利用者の状況によって異なります。
人員配置の基準と職種別の主な要件は、以下のとおりです。
| 職種 | 配置基準の例(目安) |
| 医師 | 1名以上 |
| 看護師または准看護師 | 利用者3名につき1名以上(常勤換算) |
| 介護職員 | 利用者3名につき1名以上(常勤換算) |
| 生活相談員 | 利用者100名につき1名以上(常勤換算) |
| その他(必要に応じて) | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士など |
上記は人員配置の目安です。実際の配置基準は、各施設で異なるため必ず詳細を確認してください。
短期入所療養介護の課題

短期入所療養介護は、利用者の在宅生活を支える上で重要な役割を担っていますが、運営する際には以下のような課題があります。
- 急な体調変化や緊急事態への対応が難しい
- 人員不足や多職種間の連携不足
- 認知症や医療依存度の高い方など多様なニーズへの対応
- サービス認知度が低く、情報提供が不足
上記の課題を解決するためには、関係機関との連携強化や人員確保、サービス内容の充実、情報提供の強化など、多角的な取り組みが必要です。

介護サービス従事者でも、短期療養生活介護と短期入所生活介護の違いを説明できる方はなかなかいないのではないでしょうか。そもそも両サービスはショートステイという言葉で包括されてしまっている感もあります。提供サービス事業体の母数でわかりやすく説明すると、老人保健施設が提供するのが『短期療養生活介護』で、特別養護老人ホームを中心に提供するのが『短期入所生活介護』となります。短期療養生活介護は、老人保健施設がメインの提供母体なので、手厚いリハビリを受けられる!と期待される方もおられるかもしれませんが、残念ながら実態は大差ないサービスとなってしまっています。目の肥えた団塊の世代がメインの顧客となりつつある今、短期療養生活介護・短期療養生活介護共にわかりやすい特色を打ち出せないと事業運営は厳しいでしょう。
まとめ|短期入所療養介護の導入要件を理解し適切に運営しよう!
短期入所療養介護は、医療的なケアが必要な利用者への支援と、介護する家族の負担軽減を両立できるサービスです。
サービス提供には医師の常駐や看護体制の整備など、一定の基準を満たす必要がありますが、地域の医療・介護ニーズに応える役割を果たせるでしょう。
運営にあたっては、人材確保やコスト管理などの課題もありますが、多職種連携の強化や効率的な体制づくりで克服できます。利用者一人一人の状態に合わせた質の高いケアを提供し、安定した運営を実現していきましょう。
今後、導入を検討される場合は、まずは人員配置基準や設備要件を確認し、地域のニーズ分析から始めることをおすすめします。丁寧な準備と計画的な運営で、地域に必要とされる施設が運営できるでしょう。

監修:伊谷 俊宜
介護経営コンサルタント
千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。











