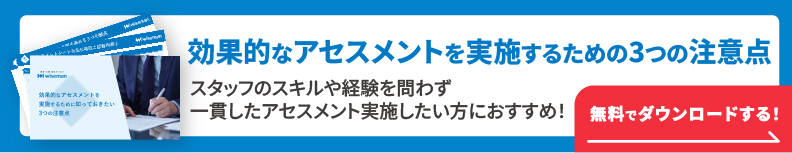【記入例あり】アセスメントシートの書き方とは?必須項目や作成時のポイントを紹介
2023.05.18

アセスメントシートは、介護保険サービスの利用者のためにケアプランを作成する際に必要となる重要な書類です。主にケアマネジャーが作成しますが、アセスメントシートには用途に応じてさまざまな種類があります。
この記事では、アセスメントシートの書き方や必須項目、作成する際の注意点などについて、記入例を交えながら解説します。
なお、株式会社ワイズマンでは、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
アセスメントシートを記載する上で知っておきたい3つの観点を記載しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
アセスメントシートとは?【支援内容の明確化】

アセスメントシートは、介護サービスの利用者を支援するために必要な内容や、サービスを受けるに至った背景などの情報をまとめた書類です。利用者のケアプランを作成するために、ケアマネジャーが利用者や家族に対してアセスメントを行う際に作成します。
アセスメントシートの役割
アセスメントシートを作成すると、利用者に関する以下のような内容を関係者間で共有できます。
- 生活環境や心身の状態
- 生活するうえでの問題点や課題
- どのようなサービスを希望しているか
アセスメントシートはケアプランの作成に欠かせないものであり、利用者の目標の設定や、提供する介護支援の方針を決定するのに役立ちます。アセスメントシートの作成で手を抜くと、利用者や家族に対して適切なサービス提供ができなくなる恐れがあります。
アセスメントシートが使われる施設
アセスメントシートは、ケアプラン作成の土台となる書類です。居宅介護支援事業所や、以下のような介護施設・医療施設でケアプラン作成時に使われます。
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護
アセスメントシートの作成に携わるのは、主にケアマネジャーです。
要支援1または要支援2と認定された方、基本チェックリストで事業対象者の認定を受けた方の場合は、地域包括支援センターの保健師などがケアプランを作成します。そのため、アセスメントシートも保健師などが作成することが一般的です。
フェイスシートとの違い
アセスメントシートと似たものに「フェイスシート」があります。フェイスシートとは、以下のような利用者の基本情報が記載されている書類です。
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 要介護度
- 住所
- 電話番号
- 家族構成
- 既往歴
- 職歴
- 服薬歴
フェイスシートもアセスメントシートも、利用者の基本情報であることに変わりはありません。しかし、フェイスシートは利用者がどういう人物であるかといったプロフィールであるのに対して、アセスメントシートは利用者の抱えている課題を分析するものという違いがあります。
アセスメントシートで利用者の状況や課題をより詳細に調べ、ケアプラン作成に役立てます。
なお、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて、「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
アセスメントシートの7つの種類
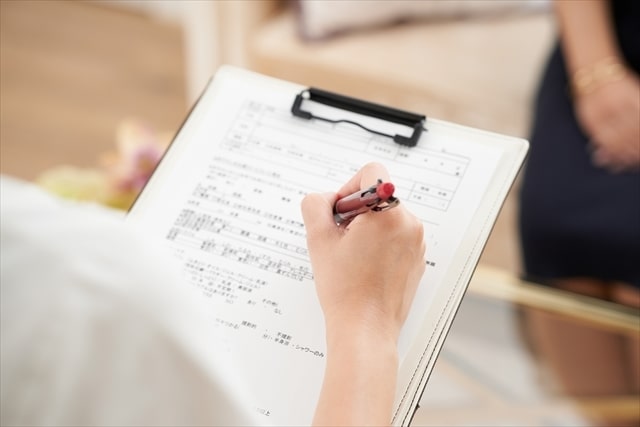
アセスメントシートには、以下のように7つの種類があります。
- 全老健版ケアマネジメント方式R4システム
- ケアマネジメント実践記録方式
- 日本介護福祉会方式
- 日本訪問介護振興財団版方式
- 包括的自立支援プログラム
- 居宅サービス計画ガイドライン
- MDS-HC方式
アセスメントシートの書類によって特徴が異なるため、必要に応じたシートを選びましょう。ここでは、具体的な特徴を紹介します。
全老健版ケアマネジメント方式R4システム
全老健版ケアマネジメント方式R4システム(以下「R4」という)は、介護老人保健施設(老健)での支援を目的に、公益社団法人全国老人保健施設協会(全老健)が作成した様式です。R4では全老健が保有している老健の情報を分析し、国際分類であるICFを利用して5段階の絶対評価を行います。
概要は以下のとおりです。
- 入所後のアセスメントを4段階で行う
- ケアマネジメントを4段階で行う
- モニタリングを4つの視点で行う
上記のように「4つ」という括りが多いことからR4と命名されました。これらの議論やアセスメントを経て完成したケアプランは正確でわかりやすく、情報共有しやすいです。
なお、R4システムの概要や導入するメリットは、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方は、併せて参考にしてください。
ケアマネジメント実践記録方式
ケアマネジメント実践記録方式は、別名「日本社会福祉会方式」とも呼ばれます。日本社会福祉会が在宅介護支援センターの事例を中心に情報を収集、作成した様式です。
利用者や家族の意見・ニーズだけでなく、アセスメント担当者が考える課題についても記入します。在宅介護だけでなく介護保険施設でも使用が可能で、基本調査の82項目を取り入れたアセスメントが可能ですが、記入内容が多いためアセスメントに時間がかかります。
日本介護福祉会方式
日本介護福祉会方式は、訪問看護の実績により開発されたものです。利用者の生活全体を「衣食住」「心や体の健康」「家族関係」「社会関係」の領域に分類して、生活における障がいを把握します。これらの領域をさらに46項目に細分化し、利用者が抱える問題を整理します。
利用者の意見を重視し、これまでどおりの生活リズムを尊重するため、利用者の意欲や可能性を引き出すことが可能です。記述が多いぶん利用者にとっては具体的でわかりやすく、利用者自身もケアプランの作成に参加しやすい方式です。
日本訪問介護振興財団版方式
日本訪問介護振興財団版方式は、日本介護福祉会方式と同様に訪問介護の実績をベースとして開発された様式です。利用者の衣食住、体や心の健康、家族関係、社会関係などの幅広い領域で課題を分析します。複数回にわたって記入できる方式を採用しているため、利用者のこれまでの経緯を確認できます。
一方、調査項目が細かいため、アセスメントには時間がかかります。対象者は在宅介護の方が中心ですが、介護施設でも使用できます。また、高齢者に限定せずに使用できるのも特徴です。
包括的自立支援プログラム
包括的自立支援プログラムは、アセスメントと要介護認定に使用される認定調査票を連動させ、すでに作成したケアプランの再構築を図るものです。全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設協会、介護力強化病院連絡協議会の3つの団体によって開発されました。
主に介護施設用のケアプラン作成に用いられますが、在宅復帰のためのケアプランも作成可能で、利用者の入居から退去後までの一貫したプラン作成ができます。
居宅サービス計画ガイドライン
居宅サービス計画ガイドラインは、介護保険制度が2000年に創設されるにあたって、全国社会福祉協議会(全社協)がケアプラン作成のためのアセスメント手法を確立すべく開発したものです。
利用者の持つ強みを理解してケアプラン作成に落とし込み、利用者が自分の能力によって課題を解決したり、自信をもてるよう力をつけたりする「エンパワメント支援」の考え方を採用しています。主に全国各地の居宅介護支援事業所で使用されています。
MDS-HC方式
MDS-HC方式は、在宅介護と介護施設の両方を利用する人の情報を収集して分析する際の基準として活用されているものです。機能面、精神面、感覚面、健康問題、ケア管理、失禁管理の領域を包括的に把握できます。
もともとは、アメリカで開発された「MDS RAPs」の導入に携わった各国の研究者や国際的な研究組織であるinterRAI(インターライ)などによって、在宅介護版として開発されたものです。
利用者の状況を記号でこまかくチェックできるようになっており、事前の情報整理や効率的に利用するための技術が求められますが、使いこなすことで精度の高いアセスメントが可能です。
アセスメントシートの書き方

アセスメントシートは、基本情報に関する9項目と課題分析に関する14項目の計23項目を必ず記載しなければいけません。ここからは、各項目の詳細と記入例を紹介します。
アセスメントシートの必須項目
まずは、アセスメントシートに書くべき必須項目について解説します。
【基本情報に関する項目】
基本情報に関する項目は、以下の9項目です。
| No. | 標準項目名 | 概要 |
| 1 | 基本情報 | ・利用者の個人情報、氏名、年齢、住所、緊急連絡先、身分証のコピーなど |
| 2 | 生活状況 | ・生活状況や生活歴、家族構成、日常生活、住環境、趣味など利用者の普段の様子がわかるようにまとめておく |
| 3 | 利用者の被保険者情報 | ・介護保険をはじめとする保険の概要を記載 |
| 4 | 現在利用しているサービスの状況 | ・利用者が利用している介護サービスの状況をまとめる→ほかのサービスとの連携がスムーズになる |
| 5 | 障がい老人の日常生活自立度 | ・利用者の身体能力や自立度を評価する |
| 6 | 認知症である老人の日常生活自立度 | ・認知の程度や自立度を評価する |
| 7 | 主訴 | ・利用者やその家族の悩みをまとめる |
| 8 | 認定情報 | ・要介護認定の等級、有効期限を記載する |
| 9 | 課題分析(アセスメント)理由 | ・利用者の課題やその理由をまとめる |
これらの「基本情報に関する項目」のうち、生活状況とは以下のような項目を指します。
- 利用者の生活環境
- 就労状況
- これまでの病歴
- 介護の必要性
これらを時系列に沿って書くことで、利用者の状況を正確に把握できます。また、主訴とは利用者が希望している主要なものを指し、アセスメントの中でも特に重要です。アセスメントシートは利用者や家族の要望をもとに作成していくため、主訴が明確でないと利用者にあった適切なケアプランが作成できない恐れがあります。
【課題分析に関する項目】
課題分析に関する項目は、以下の14項目です。
| No. | 標準項目名 | 概要 |
| 10 | 健康状態 | ・利用者の健康状態や持病、服薬を記録する |
| 11 | ADL | ・日常生活における自立度を評価する。例えば、着衣や起き上がり、寝返りなど |
| 12 | IADL | ・やや複雑な日常生活の行動をどの程度行えるかを評価する ・電話の利用・買い物・掃除・食事の準備・服薬管理など |
| 13 | 認知 | ・認知状態を詳細に記録する |
| 14 | コミュニケーション能力 | ・言語理解や表現能力を評価する |
| 15 | 社会との関わり | ・社会生活への参加度合いや人間関係を記録する |
| 16 | 排尿・排便 | ・排泄の状態をまとめる ・トイレの自立度を評価する |
| 17 | じょく瘡・皮膚の問題 | ・皮膚の状態を把握する ・じょく瘡の有無や状態を記録する |
| 18 | 口腔衛生 | ・歯や口腔内の状態を記録する |
| 19 | 食事摂取 | ・食事の状態を記録する ・栄養管理をまとめる |
| 20 | 問題行動 | ・問題行動の有無や頻度などを記録する |
| 21 | 介護力 | ・家族の介護状態を記録する ・家族以外の介護者がいる場合は、その旨も管理する |
| 22 | 居住環境 | ・住宅環境を調査して管理する ・バリアフリー化が進んでいるかなどの安全性も考慮する |
| 23 | 特別な状況 | ・特別な医療の必要性を記載する |
「課題分析に関する項目」の中のADLとは、Activities of Daily Livingの略語で、日常生活を送るのに最低限必要な動作のことです。起き上がりや移乗、移動、入浴、食事、排泄、更衣などの動作を指します。
一方、IADLはInstrumental Activities of Daily Livingの略語で、ADLよりも複雑で判断を伴う日常動作を言います。例えば、掃除や洗濯、買い物、電車の乗降、電話応対といった動作です。
アセスメントシートの記入例
訪問介護のケースでアセスメントシートの記入例をみてみましょう。
作成日:令和○年□月△日
作成者:□△ ○○
| 利用者名 | ○△ □○(女) |
| 生年月日 | 昭和○年□月□日 |
| 住所 | ○○県△市■■番地の× |
| 電話番号 | ○○○-○○○○-○○○○ |
| 障がい者の日常生活自立度 | A |
| 認知症高齢者の日常生活自立度 | 該当なし |
| 認定情報 | 要介護度:3認定年月日:令和△年○月□日認定期間:令和○年□月○日〜令和○年△月✖️日 |
| 被保険者情報 | 介護保険:被保険者番号 2223334440医療保険:後期高齢者身体障害者手帳:身体障害2級 |
| 家族構成 | 夫:死別娘(長女):同居娘婿:同居孫2人:同居 |
| 生活概要 | 家族同居 |
| 介護者情報 | 娘(長女):○○ □△自宅にいる際は日常的にトイレ付き添い、食事の準備などのサポートをしている |
| 趣味、嗜好 | ・読書(小説)・音楽鑑賞(演歌)・テレビ(時代劇) |
| 生活暦 | 60歳の定年まで、メーカーで経理の仕事に従事してきた。退職後しばらくしてから脳梗塞で倒れ手術を受ける。退院後は歩行が困難となり車椅子の生活を続けているが、訪問リハビリを週に3回受けている。娘の介助を受けているが、仕事が忙しくなりこれまでどおりのサポートが難しくなっている。 |
| 利用している介護サービス | 訪問リハビリ:週3回事業所名:介護老人保健施設○○ |
| 訪問介護に関する意向 | (本人)現在は歩行が困難であるが、リハビリを通じて少しでも自分の足で歩けるようになりたい。娘の負担を軽減するために、身の回りの介助をヘルパーさんにお願いしたい。 (家族)現在は仕事が忙しく、母親の介助が思うようにできない。介護離職をすると生活が成り立たなくなるので、ヘルパーさんの手を借りたい。自分ができることはこれまでどおりやっていきたい。 |
アセスメントシート作成時のポイント

ここでは、アセスメントシートを作成する際の3つのポイントについて見ていきます。
利用者本人からの情報を記載する
アセスメントシートを作成する際、利用者以外からの情報をもとに作成してしまうと、事実とは異なる部分が出てくる可能性があります。
適切なケアプラン作成のためには、ご家族などから得た情報ではなく、利用者本人からのヒアリングで得た情報をもとに作成しましょう。
ケアプランについては以下のページで詳しく解説しています。
関連記事:「ケアプランとは?役割や作り方、サ高住のケアプラン点検についても解説」
誰が見てもわかるような内容にする
アセスメントシートは、誰が見てもわかる内容にする必要があります。主観ではなく、客観的かつ具体的な内容で記載することが大切です。
また、文章の主語を明確にし「5W1H」を意識することで理解しやすい文章に仕上がります。そうすることで他職種との連携もスムーズになるでしょう。
必須項目以外の情報も記載する
アセスメントシートには必須項目以外の情報も記載するようにしましょう。例えば利用者の趣味や習慣については、定型シートであれば記載する欄がないこともありますが、聞き取れた場合は書き留めておくようにしましょう。
利用者の趣味や習慣を知っておくことで、コミュニケーションのきっかけとなったり、緊急時の対応に役立ったりすることもあります。

アセスメントシートは、介護保険サービスを利用する方のケアプランを作成する際に欠かせない重要な書類です。アセスメントシート作成の際には、利用者本人の意見を重視し、誰が見ても分かりやすい記載を心掛けることが重要です。ただ、ケアマネジャーの業務は多岐にわたり、日々の業務負担は非常に大きいものです。
このような状況の中で、アセスメントシート作成を効率化するためには、介護ソフトなどのシステムを活用することが有効です。システムを導入することで、過去のデータを参照しながらスムーズに記入できるほか、自動入力やチェック機能を活用することで記入ミスを防ぐことが可能になります。
忙しいケアマネジャーの皆さんが、限られた時間の中でより良いケアを提供できるよう、積極的にシステムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、株式会社ワイズマンでは「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
アセスメントシートの書き方をマスターしてより良い支援を提供しよう

アセスメントシートは、利用者のケアプランを作成する過程のアセスメントで大変重要な書類です。ただし、アセスメントシートにはさまざまな様式があり、施設によって使用される種類が異なるため注意が必要です。
また、記載すべき項目は多岐にわたるため、アセスメントシートを作成するのに時間を要することもあるでしょう。アセスメントシート作成の業務効率を上げるためには、介護ソフトの導入がおすすめです。
例えばワイズマンの「施設ケアマネジメント支援システムSP」や「在宅ケアマネジメント支援システムSP」を使用すると、簡単に計画書を作成できたり、文例を登録することで業務の簡素化できたり、書類作成の進捗状況の把握が簡単にできたりします。
適切なケアプランを作成し、質の高いサービスを提供するためにも、介護ソフトの導入をご検討ください。ワイズマンの介護ソフトの資料請求は、こちらから簡単にお問い合わせいただけます。
>>「介護・福祉向け製品カタログ(無料ダウンロード)フォーム」

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。