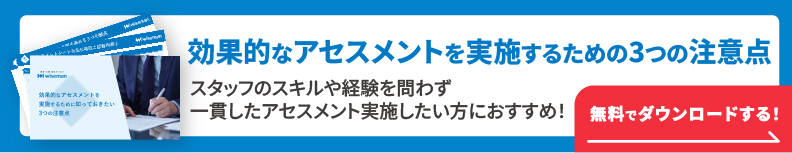【文例付】定期巡回・随時対応型訪問介護看護のケアプラン作成ガイド
2025.09.25

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提案したいけれど、ケアプランの書き方がよくわからない」
「具体的な文例を探しているけど、なかなか見つからない」
このような悩みを抱えるケアマネジャーは多いのではないでしょうか。定期巡回サービスは利用者の在宅生活を24時間支える強力なサービスですが、その特殊な仕組みからケアプラン作成に戸惑う方も少なくありません。
この記事では、上記のようなお悩みを持つケアマネジャーに向けて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のケアプラン作成方法を、具体的な文例を交えながら徹底的に解説します。本記事を読めばサービスの基本から費用、実務上の注意点まで網羅的に理解でき、自信を持って質の高いケアプランを作成できるようになるはずです。
なお、株式会社ワイズマンでは、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
アセスメントシートを記載する上で知っておきたい3つの観点を記載しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、要介護状態の利用者が住み慣れた自宅で24時間365日、安心して生活を続けられるように支援することを目的とした、地域密着型サービスです。
まずは、ケアプランを作成する前提知識として、定期巡回・随時対応型訪問介護看護がどのようなサービスなのか、基本をしっかり押さえておきましょう。
サービスの3つの構成要素
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、以下の3つのサービスで構成されています。それぞれの役割を理解することが、適切なケアプラン作成の第一歩です。
| サービス名 | 内容 |
| 定期巡回サービス | 1日複数回、決まった時間に訪問し、安否確認や身体介護を行う |
| 随時対応・訪問サービス | 利用者や家族からの通報(コール)を受け、相談援助や必要に応じた訪問を行う |
| 訪問看護サービス | 看護師が訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う。ただし、主治医の指示が必要である |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、これらのサービスが連携し、利用者の日々の生活と健康を包括的にサポートする仕組みです。
従来の訪問介護との違い
従来の訪問介護と大きく異なるのは、サービスの提供方法と料金体系です。その違いを理解することで、なぜこの利用者に定期巡回サービスが必要なのかを明確に説明できます。
| 比較ポイント | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 従来の訪問介護 |
| 1.料金体系 | 月額定額制(包括報酬) 要介護度に応じて料金が一定 | 出来高制 サービスの時間や内容に応じて料金が加算される |
| 2.訪問回数・時間 | 制限なし 利用者の状態に応じて、1日数回の短時間訪問など柔軟に対応可能 | 制限あり ケアプランで定められた回数・時間のみの訪問が原則 |
| 3.計画変更の柔軟性 | 柔軟に変更可能状態の変化に応じて、即座に訪問回数や内容の見直しが可能 | 変更には手続きが必要ケアプランの変更やサービス担当者会議が必要な場合がある |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは、状態が変化しやすい方や日中に複数回のケアが必要な方にとって、より柔軟できめ細かい対応が可能なサービスと言えるでしょう。
「一体型」と「連携型」の違い
事業所の運営形態には「一体型」と「連携型」の2種類があります。これは、訪問看護サービスを自前の事業所で提供するか、他の訪問看護事業所と連携して提供するかの違いです。
| 項目 | 一体型 | 連携型 |
| 運営形態 | 1つの事業所が訪問介護と訪問看護を一体的に提供する | 訪問介護を行う事業所が、別の訪問看護事業所と連携してサービスを提供する |
| 特徴 | 情報共有がスムーズで、迅速な対応がしやすい | 地域の医療資源を有効活用できる |
| 注意点 | – | 連携する訪問看護事業所との密な情報共有と役割分担が不可欠である |
ケアプランを作成する際は、利用する事業所がどちらのタイプなのかを把握し、情報共有体制を計画に盛り込むことが重要です。
【メリット・デメリット】定期巡回サービス導入で変わること

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの導入を検討する際は、良い面だけでなく注意すべき点も把握し、利用者や家族に丁寧に説明することが重要です。ここでは、利用者とケアマネジャーそれぞれの視点からメリットとデメリットを解説します。
利用者・家族にとってのメリットと注意点
利用者やその家族にとって、24時間体制の支援は大きな安心につながります。その一方で、費用面などでの注意も必要です。
| メリット | デメリット(注意点) |
| 24時間365日の安心感 夜間や早朝でも、体調不良時や緊急時にすぐ対応してもらえる | 月額定額制の費用 費用が一定のため、サービスの利用が少ない月は割高に感じる可能性がある |
| 状態変化への迅速な対応 退院直後など、状態が不安定な時期でも柔軟に訪問回数を増やせる | 多様なスタッフの関与 多くのスタッフが入れ替わりで訪問するため、人間関係の構築に時間がかかる場合がある |
| 在宅生活の継続 重度になっても医療と介護の連携により、住み慣れた家での生活を続けやすい | サービス提供エリアが限定的 地域密着型サービスのため、利用できる事業所が限られる |
ケアマネジャー・事業所にとってのメリットと注意点
ケアマネジャーにとってもサービスの選択肢が増える一方で、連携業務の重要性が増します。
| メリット | デメリット(注意点) |
| 重度者への対応力強化 医療ニーズの高いケースやターミナルケアにも対応しやすくなる | 計画作成責任者との密な連携 日々のサービス計画は事業所が担うため、密な情報共有が不可欠である |
| 柔軟なプランニング 利用者の状態に合わせて、サービス内容を調整できる | 情報共有の複雑化 関わる職種やスタッフが増えるため、情報共有のルールを明確にする必要がある |
| 利用者の在宅生活を支えるやりがい 利用者の在宅生活を支援することで、専門職としての満足度が高まる | 制度理解の必要性 包括報酬や減算ルールなど、独自の制度を正確に理解しておく必要がある |
【文例】定期巡回サービスにおけるケアプランの具体的な書き方

ここからは、ケアプランについて具体的な文例を交えながら書き方のポイントを解説します。文例を参考に、ケアプランを作成してみてください。
第1表「総合的な援助の方針」の書き方と文例
第1表では、このケアプラン全体の方向性を示します。定期巡回サービスの特性を活かし、24時間体制で利用者を支えるという視点を盛り込むことがポイントです。
【文例】
24時間365日の訪問介護・看護体制を構築し、日中の安否確認と服薬支援、および夜間の排泄介助を行うことで、〇〇様が麻痺による身体的な不安や独居による精神的な孤独感を感じずに、住み慣れたご自宅で安全かつ安心して生活を継続できるよう支援します。状態変化にも迅速に対応できる体制を整え、ご家族の介護負担軽減も図ります。
第2表「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」の書き方と文例
第2表はケアプランの心臓部です。利用者のニーズ(課題)に対し、長期・短期の目標を設定し、その目標を達成するための具体的なサービス内容を記載します。ここでは、よくある4つのケース別に文例を紹介します。
ケース1:日中の服薬管理と安否確認が必要なケース
| 項目 | 記載例 |
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 認知機能の低下により、薬の飲み忘れや飲み間違いがあり、血圧が不安定になることがある。日中独居のため、安否が心配である |
| 長期目標 | 服薬を適切に管理し、体調を維持することで、自宅での生活を安全に継続できる |
| 短期目標 | 3カ月以内に介護職員の見守り・声かけのもと、毎日決まった時間に服薬できる習慣を身につける |
| 援助内容(サービス内容) | 【定期巡回】 ・1日3回(朝・昼・夕)訪問し、服薬の声かけと確認を行う ・バイタルサイン(血圧・脈拍)を測定し、記録する ・日中の様子や体調に変化がないか確認する 【訪問看護】 ・週1回訪問し、健康状態の確認と服薬状況の評価、療養上の相談を行う |
ケース2:夜間の排泄介助と体位交換が必要なケース
| 項目 | 記載例 |
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 夜間に複数回のトイレ介助が必要だが、家族の負担が大きい。寝返りが困難で、褥瘡のリスクがある |
| 長期目標 | 適切な排泄ケアと体位交換により、皮膚トラブルなく、夜間も快適に過ごすことができる |
| 短期目標 | 1カ月以内に夜間帯の訪問により、オムツ交換のタイミングが適切になり、失禁による不快感を軽減する |
| 援助内容(サービス内容) | 【定期巡回】 ・1日5回(日中3回、夜間2回)訪問し、排泄介助(オムツ交換)を行う ・2時間おきを目安に体位交換を行い、褥瘡発生を予防する ・夜間の睡眠状況や様子を確認する 【訪問看護】 ・週1回訪問し、皮膚の状態を観察し、必要に応じて処置を行う |
ケース3:退院直後で状態が不安定なケース
| 項目 | 記載例 |
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 大腿骨骨折の手術後、退院したが、ADLが低下し、自宅での生活に不安がある。疼痛管理やリハビリが必要 |
| 長期目標 | 身体機能の回復を図り、再び自宅で安定した生活を送る |
| 短期目標 | 2週間以内に自宅環境での動作に慣れ、疼痛なく離床して過ごす時間が増える |
| 援助内容(サービス内容) | 【定期巡回】 ・1日数回訪問し、更衣、整容、食事、排泄などの身の回りの介助を行う ・転倒リスクを評価し、安全な移動介助を行う 【訪問看護】 ・毎日訪問し、創部の処置、疼痛コントロール、全身状態の管理を行う ・主治医やリハビリ専門職と連携し、居宅でのリハビリテーションを支援する |
ケース4:認知症があり日中の見守りが必要なケース
| 項目 | 記載例 |
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 認知症の周辺症状(BPSD)として、日中に落ち着きなく歩き回り、目的なく外出しようとすることがある |
| 長期目標 | 穏やかに過ごせる時間を増やし、住み慣れた自宅で安心して生活を継続できる |
| 短期目標 | 1カ月以内に日中の訪問回数を増やすことで、不安や混乱を軽減し、落ち着いて過ごせるようにする |
| 援助内容(サービス内容) | 【定期巡回】 ・1日4回程度訪問し、話し相手になったり、簡単な作業を一緒に行ったりすることで、不安を傾聴し、精神的な安定を図る ・水分補給を促し、脱水を予防する 【随時対応】 ・興奮状態になった際に通報(コール)があれば、オペレーターが傾聴し、必要に応じて随時訪問を行い、クールダウンを支援する |
第3表「週間サービス計画表」の書き方と注意点
第3表は、1週間のサービス提供の予定を記載するものです。従来の訪問介護のように「月曜日 9:00~9:30 身体介護」と細かく記載するのではなく、サービスの柔軟性を担保するため、包括的な書き方をします。
また、訪問看護など、状態に応じて提供されるサービスについては「週1回程度」「適宜」といった表記を用います。
なお、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて、「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
質の高いケアプランを作成するための3つの重要ポイント

次に、質の高いケアプランを作成するための土台となる3つの重要なポイントを押さえておきましょう。これらの視点を持つことで、単なる作業としての計画作成ではなく、利用者の生活を真に支えるプランニングが実現します。
ポイント1:正確なアセスメントで潜在ニーズを掘り起こす
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの強みは、利用者の細かなニーズに対応できる点です。表面的な課題だけでなく、利用者が言葉にしない不安や希望といった「潜在ニーズ」を掘り起こすアセスメントが不可欠です。
ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)といった基本情報に加え、以下のような視点でアセスメントを行います。
| 項目 | 内容 |
| 生活歴・価値観 | これまでどのような人生を送り、何を大切にしてきたか |
| 1日の生活リズム | 特に、日中独居の時間帯や夜間の過ごし方 |
| 不安に感じること | 「夜中に一人でトイレに行くのが怖い」「薬の飲み忘れが心配」など |
| 続けたいこと・希望 | 「庭の草むしりを続けたい」「近所の人と話したい」など |
| 家族の意向と介護力 | 家族は介護にどの程度関われるか、どのような支援を望んでいるか |
ポイント2:訪問看護との連携と役割分担を明確にする
定期巡回サービスでは、介護と医療の連携がサービスの質を左右します。特に、訪問看護がどのように関わるのかなど、ケアプラン上で役割分担を明確にすることが重要です。
そのためにも、ケアプランには以下のような内容を具体的に記載し、関係者全員が共通認識を持てるようにしましょう。
| 担当 | 業務内容 |
| 医療的ケア | 褥瘡の処置、インスリン注射、バイタルチェックなど、看護師が行う業務を明記する |
| 日常的なケア | 排泄介助、食事介助、服薬確認など、介護職員が行う業務を明記する |
| 状態変化時の連絡体制 | 介護職員が利用者の異常を発見した場合、誰に、どのように連絡・相談するかのフローを定める |
| 情報共有 | 連絡ノートの活用、定期的なカンファレンスの開催など、具体的な情報共有のルールを決める |
ポイント3:利用者・家族の同意と目標共有を行う
サービスをスムーズに導入・継続していくためには、利用者と家族の十分な理解と納得が欠かせません。特に、月額定額制の費用や多くのスタッフが関わる点については事前に説明し、同意を得ておく必要があります。
なお、説明の際はサービス内容だけでなく「このサービスを利用することで、どのような生活を実現できるか」という目標を共有しましょう。
例えば、「夜間のトイレの不安を解消し、朝までぐっすり眠れるようにしましょう」といった具体的な目標を一緒に設定することで、利用者のモチベーションを引き出し、より良い関係性を築けます。
ケアマネジャーが知っておくべき単位数・費用と注意点

ケアプランを作成するケアマネジャーは、利用者や家族に対して費用を正確に説明する責任があります。また、不適切なプランニングによる減算などを避けるためにも、報酬体系とルールを正しく理解しておくことが重要です。
介護報酬(単位数)の仕組みと自己負担額の計算例
定期巡回サービスの介護報酬は、要介護度別に定められた月額定額(包括)報酬です。訪問回数や時間に関わらず、費用は一定とされています。
| 要介護度 | 訪問看護を利用しない場合 | 訪問看護を利用する場合 |
| 要介護1 | 5,680単位 | 8,287単位 |
| 要介護2 | 10,138単位 | 12,946単位 |
| 要介護3 | 16,833単位 | 19,762単位 |
| 要介護4 | 21,293単位 | 24,361単位 |
| 要介護5 | 25,752単位 | 29,512単位 |
なお、単位数は事業所のタイプや改定により変動します。最新の情報は必ず公的資料でご確認ください。
【自己負担額の計算例】
- 条件:要介護3の方が訪問看護を利用し、自己負担1割の場合(地域区分1単位=10円と仮定)
- 計算式:19,762単位 × 10円/単位 × 0.1(1割負担) = 19,762円/月
※この他に、各種加算や食費などの実費負担がかかる場合があります。
減算対象にならないための注意点とコンプライアンス
定期巡回サービスでは、適切なサービスが提供されない場合、減算となる可能性があります。ケアマネジャーとして介護報酬のルールを理解し、減算を未然に防ぐことが重要です。
【主な減算と注意点】
| 減算の種類 | 内容 | 注意すべきポイント |
| 連携体制減算 | 事業所の計画作成責任者とケアマネジャーの連携が不十分な場合に適用される | ・最低でも月に1回はカンファレンスなどで情報共有を行う ・アセスメントやモニタリングの結果を文書で共有し、記録を残す |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束の適正化に関する検討委員会を設置していないか、もしくは指針を整備していない場合に適用される | ケアマネジャーは、事業所が身体拘束廃止に向けた取り組みを適切に行っているか確認する責務がある |
これらの減算を避けるためには、サービスを提供する事業所との密なコミュニケーションが不可欠です。定期的なカンファレンスを設定し、議事録を作成するなど、連携の証拠をきちんと記録に残しておくことが、コンプライアンス遵守とリスク管理につながります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は2012年(平成24年)4月の介護保険法改正で新設されました。本記事は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護という複雑な仕組みを、ケアマネジャーがプラン化する視点から整理している点が大変有益です。特に第1表~第3表の文例は、サービスの特性(24時間体制・包括報酬・計画変更の柔軟性)を踏まえた書き方の参考になります。一方実務では①計画作成責任者・訪問看護・介護職の役割分担と連絡フローを明確にし、記録・情報共有を習慣化すること、②状態変化時の緊急対応手順と随時対応の判断基準をプランに反映すること、③利用者・家族への費用説明や多職種訪問の顔ぶれ・連絡窓口を事前に伝え同意を得ることが重要です。「誰が・いつまでに・どの指標で」を明確にする目標設定と、定期的なモニタリング・見直しをセットにすることで、本サービスの柔軟性と安心感を最大限に活かせます。
なお、株式会社ワイズマンでは「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
まとめ:文例を参考に定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスのケアプランを作成しよう

本記事では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のケアプラン作成について、サービスの基本から具体的な文例、費用や注意点まで詳しく解説しました。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者の「最期まで自宅で暮らしたい」という願いを叶えられる、非常に価値のあるサービスです。そのポテンシャルを最大限に引き出す鍵は、ケアマネジャーのプランニングにかかっています。
この記事で紹介した文例やポイントを参考に、ぜひ自信を持って利用者一人一人に寄り添ったケアプランの作成に取り組んでください。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。