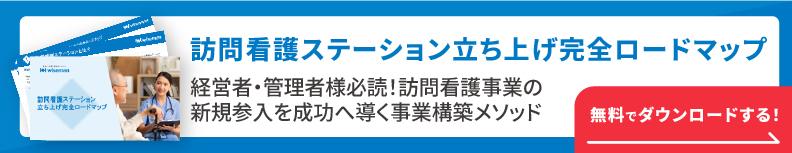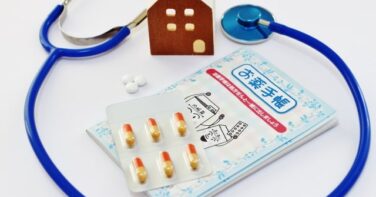訪問看護の目標設定完全ガイド|具体例やフィードバックのコツを徹底解説
2025.07.20

「自分の立てた目標は何を基準に立てるべき?」
「部下の目標設定に対するフィードバックは必要?」
訪問看護の現場で働く看護師の方や、これから実習に臨む看護学生にとって、目標設定は避けて通れないテーマです。しかし、日々の業務に追われる中で、じっくりと目標を考える時間を確保するのは簡単ではありません。
本記事では、訪問看護における目標設定のコツや必要な理由を徹底解説します。
経験年数や立場に応じた具体的な目標の立て方から、目標達成を後押しするフィードバックのコツまで網羅しています。
訪問看護の目標設定で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
訪問看護で目標設定が必要な理由

そもそも、なぜ訪問看護で目標を設定する必要があるのか、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
単なる業務や評価のためだけでなく、目標設定には日々の看護をより豊かにする理由があります。
目標を持てば、日々の業務に明確な目的意識が生まれ、質の高いケアの提供につながります。訪問看護で目標設定が必要な理由は、主に下記のとおりです。
- 目的や課題を可視化できる
- モチベーション維持につながる
- 成果を数値で評価できる
目標設定は、利用者様へのケアの質を高めるだけでなく、看護師の専門職としての成長を支える重要なプロセスです。
目的や課題を可視化できる
訪問看護において目標設定を行うメリットは、患者さんや利用者の目的・課題を具体的に可視化できることです。
訪問看護は生活の場で行う医療ケアであり、病院とは異なり利用者一人一人の生活背景や疾患の状況、家族の支援体制などが大きく異なります。そのため、画一的なケアではなく、個別性を重視した看護計画が求められます。
目標設定を行えば、「ADL(日常生活動作)の維持・向上」「服薬管理の自立」「褥瘡(じょくそう)予防」など具体的な支援内容を明確にできるのです。
課題が可視化されると、看護師・理学療法士・家族など関わる全員が共通認識を持ち、連携もスムーズに進みます。また、利用者本人も自身の課題を客観的に理解できるようになるため、積極的にケアに取り組む姿勢が生まれやすいです。
モチベーション維持につながる
目標設定は、利用者本人・家族・訪問看護スタッフのすべてにとって、モチベーション維持に大きく役立ちます。訪問看護は短期間で劇的な成果が出にくい場合も多く、日々の小さな積み重ねが大切です。
「できるようになったこと」を一つずつ確認できる目標は、利用者の自己効力感を高めます。例えば、「毎日自分で車いすへ移乗する」「週に2回散歩できる」といった具体的な目標は、達成するごとに自信となり、次の取り組みへの意欲につながります。
看護スタッフにとっても、目標に向けた進捗を確認することでケアの成果を実感でき、支援の質向上に対するやりがいが生まれるのです。
家族にとっても、漠然とした介護負担感が減り、「ここまで良くなった」という具体的な実感が、安心感をもたらします。
成果を数値で評価できる
訪問看護では客観的な成果評価が重要であり、目標設定を行えばケアの成果を数値や具体的な指標で把握できます。
例えば「週3回の服薬忘れをゼロにする」「歩行距離を10メートルから20メートルに伸ばす」「体重減少を防止しBMIを20以上に維持する」など、数値での設定が可能です。
評価基準があれば、ケアマネジャーや主治医との情報共有もスムーズになり、必要な支援内容の見直しも的確に行えます。行政や保険請求の場面でも、訪問看護計画書や報告書において客観的な成果を示すことは非常に重要です。
数値化された成果は、利用者・家族にとっても努力の結果を実感できる材料となり、今後の生活目標への意欲を高める効果も期待できます。
訪問看護の目標設定に効果的なフレームワーク
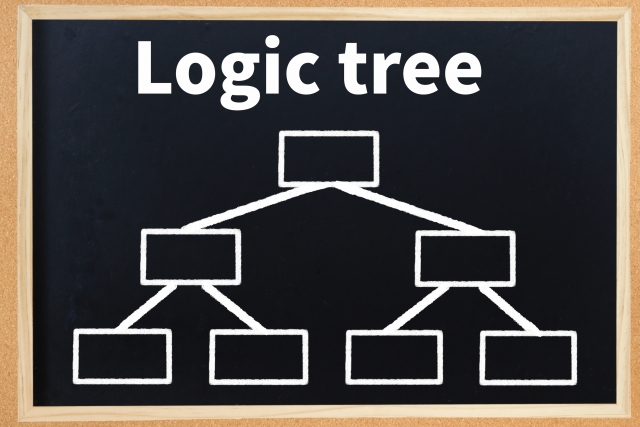
「目標が大切なのは分かったけど、具体的にどうやって立てればいいの?」と感じる方も多いでしょう。
そんなときに役立つのが、目標設定の「フレームワーク」です。
フレームワークとは、目標を論理的かつ具体的に設定するための思考の枠組みです。以下のフレームワークを活用すれば、効果的に訪問看護の目標を設定できます。
- SMARTの法則
- OKR
- 目標管理制度(MBO)
- KPIツリー
SMARTの法則
SMARTの法則は、具体的で達成可能な目標を設定するための、もっとも基本的で有名なフレームワークです。
目標設定に慣れていない新人・若手看護師の方におすすめです。
| 要素 | 意味 | 解説 |
|---|---|---|
| Specific | 具体的か | 誰が読んでも同じように解釈できる、明確な内容か |
| Measurable | 測定可能か | 達成できたかどうかを客観的な数値や状態で判断できるか |
| Achievable | 達成可能か | 現実的に達成できる範囲の目標か、挑戦的すぎないか |
| Relevant | 関連性があるか | 自身の役割や組織の目標と関連しているか |
| Time-bound | 期限が明確か | 「いつまでに」達成するのか、具体的な期限が設定されているか |
SMARTを意識すれば、漠然とした目標が、具体的な行動計画へとつながります。
【SMARTを活用した目標設定の例】
- 悪い例:褥瘡(じょくそう)ケアのスキルを上げる。
- 良い例:3カ月後までに(T)、褥瘡を持つ利用者様3名のケアプランを(S)、先輩の助言なしに一人で立案し(M)、褥瘡の大きさを10%改善させる(R)。(A:経験年数を考慮し設定)
具体的な行動と期限、数値を盛り込むことで、何をすべきかが明確になります。
OKR
OKRは、「Objectives and Key Results(目標と主要な結果)」の略で、挑戦的な目標設定に使われるフレームワークです。
GoogleやFacebookなどの企業で採用されており、個人の成長を促すのに非常に効果的です。
ある程度の経験を積み、次のステップを目指したい中堅看護師の方に適しています。
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|
| Objective(O) | オブジェクティブ | 達成したい、定性的で挑戦的な「目標」(例:チームの認知症ケアの質を向上させる) |
| Key Results(KR) | キーリザルト | 目標の達成度を測る、定量的で具体的な「主要な結果」(例:勉強会を四半期に1回開催する) |
OKRの特徴は、目標(O)を少し高めに設定し、達成度が60〜70%でも成功とみなす点です。現状維持ではなく、常に高みを目指す文化が生まれます。
【OKRを活用した目標設定の例】
- Objective(目標)
- 認知症ケアの専門性を高め、チーム全体のケアの質をリーダーとして牽引する。
- Key Results(主要な結果)
- 認知症ケアに関する外部研修に、次の半期で2回参加する。
- 研修で得た知識をもとに、ステーション内で月1回の勉強会を主催する。
- 担当する認知症利用者のBPSD(行動・心理症状)に関する家族からの緊急相談件数を、3カ月で20%削減するケアプランを立案・実行する。
目標管理制度(MBO)
目標管理制度(MBO)は、個人の目標と組織全体の目標を連動させることで、組織全体の成果を最大化するマネジメント手法です。
豊富な経験を持ち、組織運営にも貢献したいベテラン看護師の方に向いています。
MBOでは、まずステーション全体の目標(売上、利用者数、地域での評判など)を明確にします。その上で、個々人がその大きな目標達成のために、自分に何ができるかを考え、具体的な個人目標を設定しましょう。
【MBOを活用した目標設定の例】
- ステーションの目標:
- 今年度の新規利用者獲得数を前年比10%向上させる。
- ベテラン看護師の個人目標:
- 自身の持つ地域連携のネットワークを活かし、担当エリアの居宅介護支援事業所からの新規紹介件数を、下半期で5件獲得する。
- 具体的な行動計画:
- 地域の主要な居宅介護支援事業所5カ所をリストアップし、月1回以上の定期的な訪問と情報交換を行う。
- ステーションの強みや受け入れ可能な症例をまとめたパンフレットを作成し、訪問時に提供する。
- 連携先からの問い合わせに対し、24時間以内にレスポンスする体制を構築する。
KPIツリー
KPIツリーは、最終的な目標(KGI)を達成するために、どのような中間指標(KPI)を追いかけるべきかをツリー構造で可視化する手法です。
管理者や経営層が、ステーション全体の目標を達成するための具体的な戦略を立てる際に非常に役立ちます。
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|
| KGI(Key Goal Indicator) | ケイジーアイ | 組織全体の最終的な「重要目標達成指標」(例:年間売上〇〇円達成) |
| KPI(Key Performance Indicator) | ケーピーアイ | KGIを達成するための中間的な「重要業績評価指標」(例:月間訪問件数、新規利用者獲得数) |
例えば、「訪問件数を増やす」というKGIを達成するためには、「新規利用者を増やす」「一人あたりの訪問回数を増やす」「訪問のキャンセル率を下げる」などのKPIを挙げられます。
KPIツリーを使えば、最終目標から逆算して、今何をすべきかが明確になります。
訪問看護の目標設定におけるポイント

フレームワークと合わせて、目標を立てる際に下記のポイントを押さえておきましょう。
- 具体的な数値を取り入れる
- 6W1Hで目標を決める
- 達成可能な難易度にする
- 具体的な行動計画を立てる
- 組織内で目標を共有する
- 目標達成度と人事評価を連動させる
上記のポイントを押さえれば、さらに質の高い目標を設定できます。
具体的な数値を取り入れる
目標は、誰が見ても達成度がわかるように、具体的な数値で示すことが大切です。
- 悪い例:利用者とのコミュニケーションを密にする。
- 良い例:担当利用者全員と、週に1回は5分以上の時間を確保し、療養生活以外の世間話をする機会を作る。
数値を設定することで、目標達成に向けた行動が具体的になり、振り返りもしやすいです。
6W1Hで目標を決める
目標を具体化するために、「6W1H」の視点で考えてみましょう。
| 6W1H | 視点 |
|---|---|
| When | いつ(期限、頻度) |
| Where | どこで |
| Who | 誰が、誰に |
| What | 何を |
| Why | なぜ(目的) |
| How | どのように(手段) |
| How much | いくら(数値目標) |
6W1Hの要素を目標に盛り込むことで、何をすべきかが一目瞭然となり、実践するべき行動が明確になりやすいです。
達成可能な難易度にする
目標は高すぎても低すぎてもいけません。簡単すぎると成長につながりませんし、現実離れした目標はモチベーションの低下を招きます。
自分の現在のスキルや状況を客観的に分析し、「少し頑張れば達成できる」くらいの、現実的かつ挑戦的なレベルに設定することが大切です。
具体的な行動計画を立てる
目標を立てただけで満足してはいけません。その目標を達成するために、「具体的に何を、いつまでに行うのか」という行動計画まで落とし込みましょう。
- 目標:3カ月で終末期ケアに関する知識を深める。
- 行動計画:
- 関連書籍を月に2冊読む。
- 終末期ケアに関する外部研修を1回受講する。
- 学んだことを、週1回のチームカンファレンスで共有する。
組織内で目標を共有する
設定した目標は、上司や同僚と共有しましょう。周囲に公言することで、良い意味でのプレッシャーが生まれ、達成意欲が高まります。
また、周囲からフィードバックやサポートを得やすくなり、目標達成の可能性が大幅に向上します。チーム全体で目標を共有すれば、お互いに協力し合う文化も醸成されるのでおすすめです。
目標達成度と人事評価を連動させる
管理者や経営者は、スタッフの目標達成度を公正に評価し、昇給や賞与などの人事評価に適切に反映させる仕組みを整えることが大切です。
目標達成が正当に評価される環境は、スタッフのモチベーションを大きく向上させます。これにより、個人の成長が組織の成長へとつながる、好循環を生み出せます。
訪問看護の目標に対するフィードバックのコツ
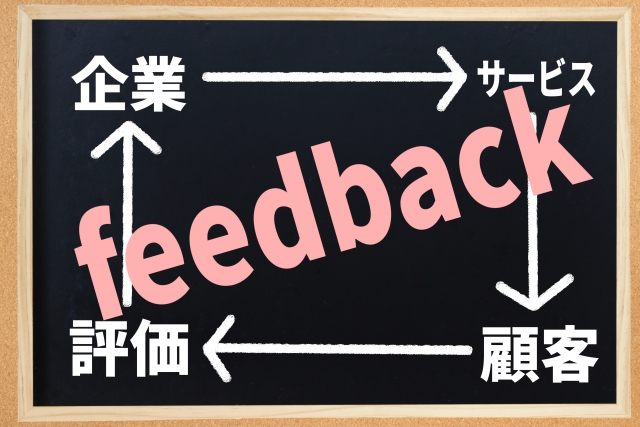
目標は「立てて終わり」では意味がありません。上司や先輩からの適切なフィードバックがあってこそ、目標達成への道筋が明確になり、部下や後輩の成長を力強く後押しできます。
効果的なフィードバックのコツは、下記のとおりです。
- 行動や成果に対して迅速にフィードバックする
- ポジティブな内容を含める
- 具体的な内容を伝える
- 定期面談や評価を実施する
- フィードバックをもとに行動計画を修正する
行動や成果に対して迅速にフィードバックする
フィードバックは、できるだけタイムリーに行うことが大切です。良い行動や成果が見られたら、その場ですぐに褒めることで、相手のモチベーションは大きく向上します。
逆に、改善すべき点がある場合も、時間を置かずにフィードバックすれば、行動を修正しやすいです。
訪問看護の目標設定に対するフィードバックは、スピード感を意識しましょう。
ポジティブな内容を含める
フィードバックは、相手の成長を願って行うものです。そのため、単に欠点を指摘するだけでなく、ポジティブな要素を盛り込みましょう。
相手にとってネガティブな印象を与える改善点は、サンドイッチ型フィードバックを活用することで、フィードバック全体をポジティブな印象に変えられます。
サンドイッチ型フィードバックとは、以下のように「褒め」と「指摘」を繰り返して、ポジティブな印象でフィードバックする手法です。
【サンドイッチ型フィードバックの例】
- (パン)褒める:「〇〇さん、先日の利用者さんへの対応、とても丁寧で素晴らしかったですよ。」
- (具)改善点を伝える:「もし可能であれば、ご家族への説明の際に、専門用語をもう少し簡単な言葉に置き換えると、さらに分かりやすくなるかもしれませんね。」
- (パン)期待を伝えて締める:「〇〇さんの細やかな気配りは大きな強みなので、これからも期待しています。」
このように、肯定的な言葉で挟むことで、相手は前向きにアドバイスを受け入れやすくなります。
具体的な内容を伝える
「もっと頑張って」「良かったよ」といった曖昧な言葉では、相手は何を改善し、何を続ければ良いのか分かりません。
フィードバックは、具体的な行動や事実に基づいて伝えましょう。
- 悪い例:「報告が分かりにくい。」
- 良い例:「先ほどの報告で、利用者さんのバイタルサインの数値が具体的に示されていたので、状況が非常によく理解できました。次回からは、その変化に対するアセスメントも一言添えてもらえると、さらに判断がしやすくなります。」
定期面談や評価を実施する
日々のフィードバックに加えて、定期的な1on1ミーティングや評価面談の場を設けることが重要です。目標の進捗状況を確認し、困っていることや課題がないかを聞き出しましょう。
改まった場で対話することで、部下は安心して悩みを相談でき、上司は個々の状況に合わせたサポートを提供できます。
フィードバックをもとに行動計画を修正する
フィードバックは、次の行動につなげるためのものです。
面談の最後には、フィードバックの内容を踏まえて、目標や行動計画を一緒に見直しましょう。
「では、来週までに〇〇を試してみましょうか」といったように、具体的な次のアクションを一緒に決めることで、部下は迷わずに行動を開始できます。
このPDCAサイクルを回していくことが、確実な成長につながります。

本記事は、訪問看護における目標設定の意義や実践方法を、具体的なフレームワークや例を交えて丁寧に解説しており、現場の看護師だけでなく、学生や管理者にとっても非常に有用な内容です。特に「SMART」「OKR」「MBO」などのビジネス手法を看護に応用する視点は新しく、日常業務に追われがちな訪問看護の現場においても、目標達成への道筋を論理的に捉える手助けとなるでしょう。また、フィードバックの重要性を具体例とともに紹介している点は、後輩育成やチーム内コミュニケーションの質を高めるうえでも参考になります。目標は“立てること”自体が目的ではなく、“日々の行動と成長にどう結びつけるか”が肝心です。その点、本記事は「すぐに実践できる目標設定と支援」の視点から、多くの示唆を与える構成となっており、日々のケアの質向上に直結する内容として評価できます。
訪問看護の目標を設定してやりがいと成長を実感しよう

目標設定は、決して形式的な作業ではありません。
訪問看護の目標設定は、利用者様へより良いケアを届けるための道しるべであり、看護師が専門職として輝き続けるための指標です。
今回ご紹介したフレームワークや例文を参考に、ぜひあなた自身の言葉で、モチベーションとサービスの質を向上させる目標を立ててください。明確な目標を持つことで、日々の業務は新たなやりがいに満ち、看護師としてより豊かで確かなキャリアを形成できます。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。