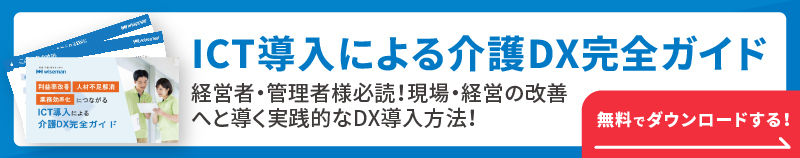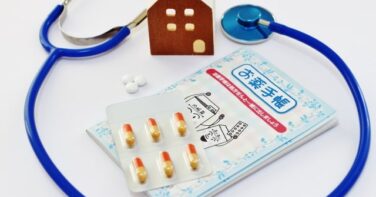【2024年改定対応】訪問看護「20分未満」の算定要件と運用の注意点
2025.07.20

訪問看護の現場では、点滴やインスリン注射など、短時間で完了する処置が増える中「20分未満」の訪問が認められています。
しかし、条件や算定方法について、制度上の理解が不十分なまま運用されてしまうケースも少なくありません。
特に「2時間ルール」との関係や、医療保険・介護保険それぞれの違いを正確に把握しておかないと、思わぬ返戻や減算につながるリスクもあります。
この記事では「20分未満」の訪問看護について、制度上の算定要件・2024年度改定のポイント・医療保険との違い・具体的な請求手順・注意点まで、現場ですぐ使える実務目線でわかりやすく整理しました。
「うちの事業所、この運用で本当に大丈夫?」と感じる場合は、ぜひこの記事を参考に、請求ルールや記録の見直しをしてみてください。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
訪問看護の「20分未満」の算定要件とは?

20分未満の訪問看護は、通常の訪問とは異なり、短時間かつ頻回な医療的処置などが必要な利用者に限定され、単独での算定は認められていません。
20分未満の訪問が認められる要件は、以下のとおりです。
- 週1回以上、看護師など(准看護師は除く)による訪問看護が居宅サービス計画に含まれていること
- 訪問看護ステーションが24時間対応体制を整え、緊急時訪問看護加算を算定していること
- 短時間の医療処置(例:吸引や経管栄養)が頻繁に必要であること
上記の要件は、短時間訪問が制度上も医療的に見て適切なサービスとされるために必要です。
現場で「20分未満の訪問だけで算定しよう」とすると、制度違反や返戻リスクにつながることもあるため、必ずこれらの条件を事前に確認・整備しておきましょう。
「20分未満」の算定時間と算定基準の考え方
訪問看護における「20分未満」の算定は、誰にでも適用できるものではなく、厳密な基準に基づいた運用が求められます。
これはいわゆる「20分ルール」として制度上定義されており、以下の2つの要件を同時に満たしていることが必要です。
「20分未満」算定の前提要件は、以下のとおりです。
- 週1回以上、20分以上の訪問看護がケアプランまたは訪問看護計画に組み込まれていること
- 24時間対応体制を整備し、「緊急時訪問看護加算」を算定していること
2つの要件がそろっていない場合、「20分未満」の訪問を行っても、算定できません。
「20分未満」の訪問は、あくまで計画的な訪問看護の補完として位置づけられます。
「20分未満」の単位数と算定方法
「20分未満」の訪問看護を介護保険で算定する場合、算定要件を満たしていれば1回の訪問につき所定の単位数が算定可能です。
2024年度改定後の単位数(20分未満の場合)は、以下のとおりです。
| 訪問看護ステーションからの提供 | 314単位 |
| 病院・診療所からの提供 | 266単位 |
提供主体によって単位数が異なる点に注意が必要です。
単位数は、「20分未満」の訪問があくまで計画的な訪問の補完として位置づけられていることを踏まえ、慎重に運用しましょう。
2024年度改定のポイント
2024年度の介護報酬改定では、訪問看護の基本報酬が一部見直され、「20分未満」の訪問看護についても単位数が1単位増加しました。
わずかな改定ではあるものの、すべての訪問時間区分と職種での見直しが行われた点が特徴です。
指定訪問看護ステーションにおける改定内容は、以下のとおりです。
| 訪問時間・内容 | 改定前 | 改定後 |
| 20分未満の訪問 | 313単位 | 314単位 |
| 30分未満の訪問 | 470単位 | 471単位 |
| 30分以上~1時間未満の訪問 | 821単位 | 823単位 |
| 1時間以上~1時間30分未満の訪問 | 1,125単位 | 1,128単位 |
| リハビリ職(PT・OT・ST)による訪問 | 293単位 | 294単位 |
報酬改定の背景には、訪問看護の重要性の再評価と、物価高騰・人件費上昇などへの配慮があります。
特に、20分未満の短時間訪問は、医療的処置や急性期の対応など高い専門性が求められる業務でありながら、これまで評価が十分とはいえない面もありました。
単位数はわずかに増えたものの、事業所にとっては収益構造の見直しや報酬の積み上げ方を再検討するきっかけにもなるでしょう。
介護保険と医療保険における20分未満訪問看護|比較早見表

訪問看護における「20分未満」の取り扱いは、介護保険と医療保険で大きく異なります。
制度ごとの算定ルールや考え方を誤解しないよう、基本的な違いを整理しておきましょう。
主な相違点は、以下のとおりです。
| 比較項目 | 介護保険 | 医療保険 |
| 時間区分 | 「20分未満」が明確に定義されている | 明確な時間区分なし(おおむね「30分未満」で判断) |
| 算定要件 | 週1回以上の20分以上の訪問+緊急時訪問看護加算が必須 | 明確な要件なし(主治医の指示に基づく) |
| 認められるケース | 短時間の医療処置、服薬指導、点滴確認など | 医療ニーズが高く頻回な訪問が必要な場合など |
| 利用頻度 | 1日複数回の訪問も可能(条件あり) | 主治医の指示内容に準拠 |
制度によって目的や仕組みが異なるため、混同すると返戻や誤算定の原因になります。
利用者の保険種別に応じて、制度の前提と条件を正しく踏まえた対応が求められます。
訪問看護の「2時間ルール」と20分未満訪問の関係性
訪問看護において「2時間ルール」は、同一利用者に対する複数回の訪問を算定する際の基準です。
ただし、20分未満の訪問については、このルールの例外または対象外として扱われるケースがあります。
介護保険と医療保険では、違いがあり、制度ごとに適用の有無や考え方が異なります。
両制度における2時間ルールと20分未満訪問の関係性を比較してみましょう。
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
| 2時間ルールの適用 | 原則適用(ただし20分未満訪問は例外として算定可能) | 適用なし(制度上2時間間隔の要件は存在しない) |
| 20分未満訪問の算定条件 | ・週1回以上の20分以上の訪問あり ・緊急時訪問看護加算の算定 | ・医師の訪問看護指示書に基づき、医学的必要性に応じて柔軟に訪問 |
| 2時間以内の複数訪問 | 上記要件を満たせば別々に算定可能 | 医学的必要性があれば柔軟に対応可能 |
介護保険では「要件を満たした場合に限り例外的に算定可能」であるのに対し、医療保険ではそもそも2時間ルールの制約がないことが大きな違いです。
制度ごとの特性を理解したうえで、訪問看護の提供体制やスケジュールを柔軟に調整し、誤算定や返戻リスクを回避しましょう。
20分未満訪問が「2時間ルール」の例外適用となるケース
介護保険における「2時間ルール」は、同一利用者に対する同日の複数回訪問について、前回訪問終了から次回訪問開始までの間隔が2時間未満の場合、原則として1回の訪問として合算算定するルールがあります。
しかし、「20分未満」の訪問看護に限っては、この2時間ルールの例外として算定が認められるケースがあります。
以下のような条件をすべて満たす場合、たとえ2時間未満の間隔で複数回訪問しても、それぞれを別々に算定可能です。
| 条件 | 内容 |
| ① 計画的な訪問 | 週1回以上の「20分以上」の訪問看護が、ケアプランまたは訪問看護計画に組み込まれていること |
| ② 緊急時訪問看護加算の算定 | 「緊急時訪問看護加算」を算定している=24時間対応可能な体制が整備されていること |
要件を満たしていれば、以下のような訪問でもそれぞれ個別に算定できます。
| 10:00~10:15(15分)訪問 → 11:30~11:45(15分)再訪問 → 2時間以内だが、上記の条件を満たせば、それぞれ別個に算定可能 |
なお、この取扱いは介護保険での規定です。
医療保険には2時間ルール自体が存在しないため、医師の指示と医学的必要性に応じて、頻回訪問や短時間訪問を柔軟に実施できます。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
「20分未満」を算定する際の注意点

「20分未満」の訪問看護は、特定の条件下でのみ算定が認められる“例外的な対応”です。
制度上は可能でも、運用方法や記録の仕方を誤ると、返戻や減算の対象になるリスクがあります。
特に注意したいのは、緊急対応や再訪問時に本当に算定が可能なのかどうか、複数回訪問した際の時間の合算ルールなど、現場で判断が分かれやすいケースです。
ここでは、「やっていいこと」「ダメなこと」を明確にしながら、制度上の注意点をあらかじめ押さえておきましょう。
緊急対応や再訪問時の「20分未満」の算定可否
20分未満の訪問は、短時間で医療的処置が完了する場合に限定されており、算定には厳密なルールが設けられています。
特に緊急対応や再訪問では、通常以上に慎重な判断と記録が必要です。
以下のようなケースは、20分未満での算定が認められる可能性があります。
- 利用者の急な体調変化や転倒により、即時対応が必要になった場合
- 計画された処置を補完するため、短時間で再訪問したケース
- 週1回以上の20分以上の定期訪問があり、かつ緊急時訪問看護加算を算定している場合
これらの場面では、制度に沿っていることを記録で示すことが必要です。
訪問看護記録書Ⅱなどには以下の情報をしっかりと記載しておきましょう。
- 開始・終了の時刻(分単位)
- 実施した処置の具体的な内容(例:点滴抜去、インスリン注射など)
- 利用者の状態やバイタルサイン、前回との変化
- 20分未満で終了した理由(例:「ケア内容が早期に完了したため」など)
短時間訪問であっても、なぜ必要だったのか、なぜ短時間で終えたのかを、客観的かつ具体的に記録しなければなりません。
1日に複数回訪問看護を受ける場合、料金はどうなる?
1日あたりに複数回の訪問看護を実施する場面では、「それぞれの訪問を個別に算定できるのか、それとも合算する必要があるのか」が判断ポイントです。
これは主に、訪問の間隔と制度の違いによって決まります。
介護保険制度では、同じ利用者に対し同一職種が2時間未満の間隔で訪問を行った場合、基本的には2回分の訪問時間を合算して1回として算定します。
ただし、以下のような場合はそれぞれの訪問を別々に算定可能です。
- 緊急訪問として対応し、緊急時訪問看護加算を算定している場合
- 訪問時間が20分未満で、かつ所定の要件を満たしている場合
- 看護師とリハ職など、職種が異なる場合に行われた訪問
一方、医療保険制度では、介護保険のような「2時間ルール」は存在しません。
医師の指示に基づき、医学的に必要であれば、1日に複数回の訪問が可能であり、それぞれ個別に算定できます。
1日複数回の訪問に関する算定は、「保険制度」「訪問間隔」「訪問の内容・目的」などを総合的に見て判断する必要があります。
現場で迷わないためにも、制度ごとの算定ルールを事前に整理しておくことが、返戻や減算を防ぐポイントです。
訪問看護の20分未満訪問の請求手順

20分未満の訪問看護を正しく算定・請求するには、制度上の条件を満たすだけではなく、記録やコード選択などの運用面でも慎重な対応が求められます。
特に、短時間の訪問は返戻や減算の対象になりやすいため、各ステップでの確認が必要です。
以下の4つのステップに沿って「制度に準拠した算定かどうか」「記録や摘要に不備がないか」を丁寧に確認していきましょう。
- STEP1|20分未満訪問の算定可否判断
- STEP2|訪問看護計画書への適切な記載とサービス提供記録の確認
- STEP3|20分未満訪問の請求コード選択と摘要欄記載のポイント
- STEP4|返戻・減算を防ぐための最終チェック
手順を習慣化し、制度に沿った適正な請求と現場の負担軽減の両立を実施していきましょう。
STEP1|20分未満訪問の算定可否判断
20分未満の訪問看護を提供する前に、その訪問が制度上、算定可能かどうかの判断が最初のステップです。
以下の項目をチェックし、制度要件を満たしているかを確認しましょう。
| ケアプラン・訪問看護計画の内容 | ・週1回以上の「20分以上の訪問看護」が計画に含まれているか |
| 緊急時訪問看護加算の算定状況 | ・事業所が「緊急時訪問看護加算」を届け出済みか(=24時間対応体制の整備) |
| 2時間ルールとの関係 | ・直前の訪問から2時間以上空いているか ・2時間未満の場合は、例外(緊急対応・20分未満の特例など)に該当するか |
上記3点すべてに該当していれば、20分未満訪問の算定は可能です。
見落としによる返戻や減算を防ぐためにも、「算定できるかどうか」は訪問実施前に必ずチェックしましょう。
STEP2|訪問看護計画書への適切な記載とサービス提供記録の確認
20分未満の訪問看護を正しく算定するには「なぜ短時間訪問が必要なのか」を計画書に明記し、サービス提供後も適切な記録を残すことが大切です。
これらの書類は、実地指導や監査時に算定の正当性を証明する根拠となります。
主なチェックポイントは、以下のとおりです。
| 訪問看護計画書の記載内容 | ・訪問の目的・内容・所要時間の目安を明確に書く |
| サービス提供記録の記載事項 | ・訪問の開始・終了時刻(分単位) ・実施したケアの具体的な内容(例:点滴交換、褥瘡処置など) ・20分未満で終了した理由(例:利用者の希望、計画上の処置完了など) |
上記記載は「本当に必要な短時間訪問であったか?」を客観的に示す重要な証拠です。
日々の記録精度が、正確な請求と安心した運営につながります。
特に短時間訪問=不正請求と誤解されやすい項目のため、丁寧な書類管理を心がけましょう。
STEP3|20分未満訪問の請求コード選択と摘要欄記載のポイント
20分未満訪問の請求では、サービスコードの誤選択や摘要欄の記載漏れが、返戻・減算の原因になりやすい項目です。
以下のポイントを確認しましょう。
| 対象サービスコードの選択 | ・利用者の保険種別(要介護・要支援) ・訪問する職種(看護師・療法士など) ・ソフトや請求システム内での正しいコード選択 |
| 摘要欄に記載すべき内容 | ・訪問日時・緊急対応の経緯など、算定根拠が明確な情報 ・例:「〇月〇日〇時〇分、利用者急変により緊急訪問対応」 |
記載は、実地指導やレセプト審査の場面で「請求の妥当性」を示す重要なエビデンスとなります。
請求の裏付けとして、記録と整合性が取れているかを必ず見直しておきましょう。
STEP4|返戻・減算を防ぐための最終チェック
訪問看護の「20分未満」訪問を適正に請求するには、最後のチェック工程が欠かせません。
返戻や減算を防ぐためには、書類や請求内容の整合性を丁寧に確認する必要があります。
具体的には、以下の項目を確認しましょう。
| 計画書と記録の整合性 | ケアプラン・訪問看護計画書・サービス提供記録・レセプト内容に齟齬がないか確認 |
| 利用者情報・保険者情報の確認 | 被保険者番号や保険者名、要介護度など、入力ミスがないかチェック |
| ダブルチェック体制の実施 | 可能であれば、作成者とは別の職員が最終確認を行い、人的ミスを防ぐ体制を構築 |
最終チェックを怠ると、レセプト審査で返戻・減算の対象になるリスクがあります。
適正な請求と信頼性のある運営体制を保つためにも「提出前のダブルチェック」はルーチンとして定着させていきましょう。

短時間訪問が増加するなかで、訪問看護「20分未満」の正確な理解と適切な運用は、事業所の安定運営と質の高いサービス提供に直結します。特に介護保険制度における「週1回以上の20分以上訪問」や「緊急時訪問看護加算」の要件、そして「2時間ルール」の例外規定などは、実務で誤解や運用ミスが生じやすい部分です。本記事は、制度の基本から2024年度報酬改定の影響、介護保険と医療保険の違い、さらには請求や記録の実務ポイントまでを体系的に解説しており、日々現場で業務にあたる看護職や管理者にとって非常に実用的な内容となっています。法令に準拠した適切なサービス提供と返戻・減算の回避には、制度と記録の正確な理解が不可欠です。現場での運用に不安がある場合は、ぜひ本記事を確認し、あらためて事業所の対応状況を見直してみてください。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
まとめ|20分未満訪問を正しく活用し、質の高いケアと安定経営を実現
20分未満の訪問看護は、利用者の多様なニーズに応じた、柔軟できめ細やかなケアを可能にする重要なサービスです。
その一方で、算定要件は複雑であり、特に「2時間ルール」との関係性を正しく理解していなければ、意図せず不適切な請求をしてしまうリスクも伴います。
本記事で解説したポイントを改めて確認しましょう。
| 介護保険での算定要件 | 「週1回以上の20分以上の訪問」が計画にあり、「緊急時訪問看護加算」を算定していることが必須 |
| 医療保険との違い | 医療保険には「20分未満」の明確な区分や「2時間ルール」は存在しないため、医療ニーズに応じて判断される |
| 記録の重要性 | なぜその訪問が20分未満で完了したのか、客観的な事実の正確な記録が、請求の正当性を担保する |
制度は常に変化するため、厚生労働省の通知など公的な最新情報を定期的に確認し、法令を遵守した上で柔軟なサービス提供を心がける必要があります。
20分未満訪問を正しく理解し活用すれば、質の高いケア提供と訪問看護ステーションの健全な経営、そしてスタッフの負担軽減にも繋がります。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。