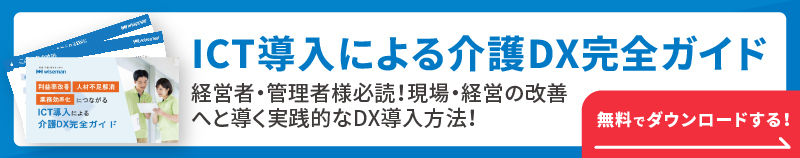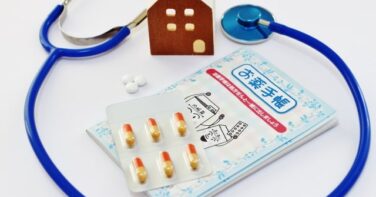訪問看護の「2時間ルール」とは?運用ミスを防ぐためのポイントも解説
2025.07.20

訪問看護の現場で、「2時間ルール」の解釈に迷ったことはありませんか。
日々の訪問計画やレセプト請求で、このルールがどう影響するのか不安に感じる方も少なくないでしょう。
訪問看護の2時間ルールは、医療保険と介護保険で扱いが異なり、例外規定も存在するため、正しく理解するのは簡単ではありません。
もしルールを誤って解釈してしまうと、サービスの不適切な提供や、意図せず不正請求とみなされるリスクにも繋がります。
この記事では、訪問看護の「2時間ルール」について、その定義から医療・介護保険での違い、具体的な例外ケースまでを解説します。
訪問看護における「2時間ルール」制度の再確認や現場での運用方法を見直したいと感じている方は、ぜひ参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
訪問看護における2時間ルール

訪問看護の現場では、制度に基づいた適切な算定が求められます。
なかでも「2時間ルール」は、複数回訪問時の報酬請求に深く関わる重要なルールです。誤って運用してしまうと、返戻や減算の原因となるため、正確な理解が欠かせません。
ここでは、以下の4点を順番に解説していきます。
- 2時間ルールとは
- 2時間ルールが定められた理由
- 介護保険・医療保険それぞれでの適用範囲
- 2時間ルールが適用されない例外ケース
制度の背景や保険別の違い、例外的な取り扱いまで整理し、現場で迷わず判断できるようにしておきましょう。
2時間ルールとは
訪問看護には、「2時間ルール」という制度上の決まりがあります。
これは、同じ職種が同じ利用者に複数回訪問する場合、2時間以上の間隔を空ける必要があるとするものです。
このルールは、短時間訪問を不自然に分割して、報酬を多く算定してしまうことを防ぐために定められています。
訪問看護の報酬単価は、訪問時間によって異なり、時間が短いほど、1分あたりの単価は高くなります。
以下は、要介護者に対する訪問看護の例です。
| 20分未満 | 314単位(約15.7単位/分) |
| 30〜60分未満 | 823単位(約13.7単位/分) |
| 60〜90分未満 | 1128単位(約12.5単位/分) |
2時間未満の間隔で同じ職種が訪問した場合は、時間を合算して1回分として算定するルールが定められています。
正しい理解と運用が、制度に沿った適正なケアの提供につながります。
2時間ルールが定められた理由
2時間ルールは、不適切な算定を防ぎ、適正なケア提供を守るために定められました。
報酬制度の不公平を防ぎ、利用者にとって無理のないスケジュールを確保する目的があります。
訪問看護の報酬は、訪問時間が短いほど1分あたりの単価が高くなる仕組みです。
制度を悪用すれば、長時間の訪問を分けて請求すれば、実際より多くの報酬を得ることができてしまいます。
そのような事態を防ぐために、以下のような制度的意図が設定されています。
- 短時間訪問の繰り返しによる過剰な請求を防ぐ
- 利用者の生活リズムに配慮したケア間隔を確保
- 報酬請求の公平性と妥当性を担保
例えば、45分の訪問を2回に分けて請求すれば、90分の1回分よりも高額になります。
本来のサービス提供と実際の請求にズレが生じれば、制度の信頼性を損なう結果につながります。
こうした背景を踏まえ、2時間以上の間隔をあけることが、制度運用の基準として設けられました。
介護保険・医療保険それぞれでの適用範囲
2時間ルールは、適用される保険制度によって運用の基準が異なります。
現場での混乱を防ぐためにも、それぞれの制度の考え方を正確に把握する必要があります。
医療保険では、訪問看護は原則として1日1回で、複数回訪問が必要な場合は、医師の判断に基づく「特別訪問看護指示書」が必要です。
一方で、介護保険では、ケアプランに基づいた訪問が可能です。
プランに明記されていれば、同じ日に複数回の訪問を行うことも認められます。
ただし、それぞれの訪問の間隔を2時間以上空けることが原則です。
制度ごとの特徴をまとめると、以下のとおりです。
| 医療保険 | ・医療保険には「20分未満」の明確な区分や「2時間ルール」は存在しない ・医療ニーズに応じて判断される |
| 介護保険 | ・ケアプラン次第で1日複数回も可能 ・ただし2時間以上の間隔が必要 |
医療保険では回数制限が基本であり、介護保険ではケアプランに基づく柔軟な対応が可能です。
それぞれの制度に応じて、正しく判断できる体制づくりを目指しましょう。
2時間ルールが適用されない例外ケース
訪問看護の2時間ルールには、「例外」と「対象外」の2つのパターンがあります。
どちらも2時間以内の訪問が認められるケースですが、その意味合いが異なります。
以下のようなケースでは、2時間未満の訪問でも合算せずに個別算定が可能です。
| 緊急訪問(利用者の急変・転倒など) | ・24時間対応体制が整っていれば、2時間以内の訪問でも算定可能 ・緊急時訪問看護加算・緊急訪問看護加算の対象 |
| 予定より訪問が前倒しになった場合 | ・点滴が早く終わったなど、計画上は2時間空けていたが実際は前倒しになった場合、理由が明確であれば例外として認められる |
そもそも2時間ルールの枠組みに当てはまらないケースには、以下のようなものがあります。
| 所要時間が20分未満の訪問 | ・吸引や経管栄養など、短時間の医療処置が必要な場合 →一定の要件を満たせば、2時間未満でも複数回算定可能 |
| 異なる職種による連続訪問 | ・「看護師→理学療法士」など、職種が異なる場合はそれぞれ別算定 →2時間ルールの対象外 |
2時間ルールの「例外」と「対象外」を分けて理解しておくことで、制度を正しく運用しやすくなります。
現場の判断力を高め、誤算定のリスクを防ぐためにも、スタッフ全員で共有しておきましょう。
2時間ルール違反による算定リスク

2時間ルールを正しく運用できていない場合、請求や記録の面で重大なリスクを招くことがあります。
制度上の違反が繰り返されると、事業所の信頼性にも影響しかねません。
特に注意が必要なリスクは、以下のとおりです。
- 誤算定による返戻・減算が発生する
- 訪問記録と実際の請求データに時間ズレが生じている
- 職種や時間ルールの誤認が不正請求とみなされる可能性がある
上記のようなリスクは、単なるミスとして処理できないケースもあります。
それぞれのリスク内容を確認していきましょう。
誤算定による返戻・減算が発生する
2時間ルールを正しく理解せずに運用していると、算定ミスが起こりやすくなります。
中でも多いのが、訪問間隔が2時間未満であるにもかかわらず、2回分の加算として請求してしまうケースです。
誤算定が発生すると、審査の段階で返戻や減算の対象となり、以下のような影響が出てしまいます。
- 請求金額が減り、収益に直接的な打撃を受ける
- 修正対応に人手と時間がかかり、事務作業の負担が増える
- 複数回の返戻が重なると、事業所全体の信用が損なわれる
特に「ルールを把握していなかった」「2回訪問したから加算できると思った」といった曖昧な運用は要注意です。
継続的にミスが発生すれば、指導や監査対象になる可能性も出てきます。
現場での誤解や記録ミスを減らすためにも、2時間ルールの基本的な運用方法を明文化し、日常的に確認できる仕組みを整えておきましょう。
訪問記録と実際の請求データに時間ズレが生じている
訪問看護における記録と請求は、常に一致していなければなりません。
わずかな時間のズレでも、請求の正当性が疑われる原因につながります。
特に注意が必要なのは、以下のような場面です。
- 記録上は2時間以上の間隔があるが、実際は2時間未満だった
- 記録とレセプトに記載された訪問時間が一致していない
- 訪問時間の開始・終了が曖昧で、記録根拠が不明瞭になっている
上記のような状態では、後から修正対応が必要になるだけではなく、監査の際に「制度の不正運用」と見なされるおそれもあります。
訪問時間の入力は、実績と請求の根拠になる情報です。
現場スタッフ任せにせず、システムやルールで管理できる環境を整えることが欠かせません。
職種や時間ルールの誤認が不正請求とみなされる可能性がある
2時間ルールは、看護師だけではなく理学療法士や作業療法士などの訪問にも適用されます。
制度を正しく理解していないと、知らず知らずのうちに不適切な請求を行ってしまうおそれがあります。
特に注意したいポイントは、以下のとおりです。
- 「職種が違えば別算定できる」と誤って解釈してしまう
- 「概ね2時間」といった表現を広くとらえ、1時間半などで訪問を繰り返してしまう
- 職員ごとに判断が異なり、運用にばらつきが出ている
上記のような状況が続くと、事業所全体の請求内容に疑義が生じるだけではなく、結果的に不正請求と判断される可能性もあります。
制度を守るためには、一人ひとりが正確な理解を持ち、組織としてルールを統一する必要があります。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
2時間ルールの判断基準

2時間ルールは単なる時間の目安ではなく、請求の正当性を左右する明確な算定基準です。
現場での判断ミスを防ぐためにも、基本的な考え方を共有しておくことが欠かせません。
特に意識すべき判断ポイントは、以下の3つです。
- 同日訪問の算定可否は“2時間以上の間隔”を基本とする
- 同職種か異職種かによって扱いが変わる
- 特別指示書がある場合の例外対応を明確にする
正しく理解しておくことで、不要な返戻や誤算定のリスクを避けられます。
ここでは、それぞれの判断基準を具体的に確認していきましょう。
同日訪問の算定可否は“2時間以上の間隔”を基本とする
同一利用者に対して同じ日に複数回訪問する場合、訪問間隔が「2時間以上空いているかどうか」が判断基準となります。
これは、訪問時間の不適切な重複請求を防ぎ、制度上の公平性を保つために定められたルールです。
「2時間の訪問間隔」の定義は、1回目の訪問におけるサービス提供が終了した時刻から、2回目の訪問でサービスを開始した時刻までの時間で判断します。
| 計算対象となる時間 | ・利用者宅でのケア提供時間・ケア提供に必要な準備・片付けの時間 |
| 計算対象とならない時間(含めないもの) | ・事業所への移動時間・事業所内での記録作成や申し送り時間 |
訪問スケジュールを立てる際には、これらの定義を正しく理解し、2時間以上の間隔が確保されているかどうかを事前に確認する必要があります。
現場での混乱を避けるためにも、明確な時間管理と記録が求められます。
同職種か異職種かによって扱いが変わる
2時間ルールは、訪問する職種によって扱いが異なります。
特に注意したいのが、「異なる職種が続けて訪問するケース」です。
同じ職種による訪問の場合、2時間以上の間隔がなければ訪問時間は合算され、1回の訪問とみなされます。
一方で、異なる職種による訪問であれば、2時間ルールの適用対象外となり、個別に算定できます。
| 看護師 → 看護師(同職種) | 訪問の間隔が2時間未満なら、時間を合算して1回分として算定 |
| 看護師 → 理学療法士(異職種) | それぞれの職種ごとに、別々に算定が可能 |
| 理学療法士 → 作業療法士(異職種) | 職種が異なるため、合算の必要はなく個別に算定できる |
異職種であれば合算しなくてよい点は制度上明確ですが、実施にあたっては注意も必要です。
1人の利用者に対して、短時間に連続で訪問が必要だった理由や、訪問の順序が妥当であったかは、ケアマネジメントに基づいた判断が前提となります。
サービスの提供根拠や連携意図は、記録や計画書にきちんと残しておきましょう。
特別指示書がある場合の例外対応を明確にする
特別訪問看護指示書とは、病状の急変や終末期、退院直後など、通常よりも頻回な訪問看護が必要な場合に、主治医が交付する医療保険上の指示書です。
指示書が交付されると、最長14日間、医療保険で毎日の訪問看護が可能になります。
対象となるのは、以下のように集中的な支援が求められるケースです。
- 急性増悪や症状不安定による頻回なモニタリングが必要な状態
- 家族支援や処置の継続が不可欠な退院直後
- 看取り期や在宅ターミナルケアへの対応が求められる状況
ただし、特別訪問看護指示書があるからといって、2時間ルールがすべて免除されるわけではありません。
訪問間隔が2時間未満になる場合も、医学的な必要性が明確に示されており、ケアプランや訪問看護計画書にもその理由が記載されていることが前提です。
「指示書さえ出ていれば自由に訪問できる」と誤解されることもありますが、制度上はあくまでも例外対応です。
訪問理由の妥当性と記録の整合性を重視し、チーム全体での共通理解を共有しておきましょう。
訪問看護の2時間ルールを現場で正しく運用するポイント

制度の理解だけではなく、現場での実践につなげるには「判断の統一」と「継続的な運用体制」が欠かせません。
2時間ルールを正しく守りながら、効率的なケア提供と請求処理を行うために、組織として取り組むべきポイントは以下のとおりです。
- 2時間ルールの判断基準を明文化し全員で共有する
- スタッフ研修に制度の具体例を取り入れて浸透させる
- 2時間ルール対応機能を備えたシステムを導入する
それぞれの取り組みが連携すれば、制度と現場のギャップを最小限に抑え、誤算定やミスを未然に防ぐ体制が整います。
2時間ルールの判断基準を明文化し全員で共有する
2時間ルールを現場で正しく運用するうえで、最も重要なのが「判断基準の明文化」です。
担当者ごとの解釈に頼っていては、誤算定や対応のバラつきが生じるリスクがあるからです。
まずは、ステーション独自の運用マニュアルを整備しましょう。
マニュアル化すれば、制度への対応を属人化させず、誰が見ても同じ判断ができる状態をつくることができます。
マニュアルに盛り込むべき主な内容は、以下のとおりです。
- 2時間ルールの基本的な考え方
- 医療保険と介護保険それぞれでの適用の違い
- 緊急時や20分未満訪問など、例外が認められる具体的なケースと記録の書き方
- 職種の違いによる算定ルールの注意点
- 判断に迷った際の相談フローやエスカレーションの手順
マニュアルは作成して終わりではなく、全スタッフがいつでも見られる状態にする必要があります。
制度改定や現場からの声を踏まえて、定期的な見直しを行うことで、制度と現場のズレを最小限に抑えることができます。
スタッフ研修に制度の具体例を取り入れて浸透させる
ルールを正しく運用するには、マニュアルの整備だけではなく、スタッフ一人ひとりの理解と判断力を高めることが欠かせません。
そのためには、定期的な研修を通じて、制度知識を現場感覚に落とし込んでいく必要があります。
効果的な研修にするためには、以下のようなケーススタディを活用しましょう。
- 「利用者Aさんは転倒し、痛みを訴えている。1時間前に訪問を終えたばかりだが、緊急訪問として対応して良いか?」
- 「利用者Bさんのケアプランで、午前中に看護師による入浴介助、午後に理学療法士によるリハビリが組まれている。訪問間隔は1時間半だが、算定は可能か?」
上記のような場面をチームで考えることで、制度の理解が「知識」から「行動」へとつながりやすくなります。
新人・ベテランを問わず、全員が同じ基準で判断できるようにすれば、誤算定を防ぐ体制が整えられるでしょう。
2時間ルール対応機能を備えたシステムを導入する
訪問の間隔をすべて手動で管理しながら、2時間ルールを正確に運用し続けるのは、現場にとって大きな負担です。
特に多忙な業務の中では、制度を意識し続けるだけでも相当な労力がかかります。
上記のような状況に対して、訪問看護専用の業務支援システムの導入は有効な手段となります。
近年のシステムには、訪問スケジュール作成時に2時間ルールに抵触しそうなケースを自動でアラート表示するなど、制度遵守をサポートする機能が備わっています。
主な導入メリットは以下のとおりです。
- 訪問スケジュール作成時のミスや確認漏れを防げる
- 訪問記録と請求データが一元管理され、整合性のある運用ができる
- 制度確認にかかる時間や心理的な負担を軽減し、本来のケア業務に集中できる
人の判断に頼らず、ルール順守をシステムで支援すれば、属人化のリスクを抑えると同時に、組織としての制度運用を安定化させる仕組みが構築できます。
それが結果的に、利用者へのサービスの質向上にもつながっていきます。

訪問看護における「2時間ルール」は、制度の公正な運用と不適切な算定の防止を目的とした極めて重要な基準です。本記事では、医療保険と介護保険それぞれの制度的背景や、例外的な取扱いに関する具体例まで丁寧に整理されており、現場で混乱しやすいポイントが網羅的に解説されています。看護師のみならず、理学療法士や作業療法士を含む多職種に共通するルールである点や、記録と実績の整合性の重要性についても触れられており、訪問看護ステーションの運営者としても実務に即した内容と評価できます。制度の正確な理解に加え、現場での判断力向上や仕組み化の重要性が強調されており、新人から管理者まで参考になる内容です。ルールを「知っている」だけでなく「使いこなせる」体制づくりの一助となる有益な記事であり、継続的な教育と運用体制の整備にもつながるでしょう。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
まとめ|訪問看護の2時間ルールを再確認し制度に沿った運営体制を整えよう
訪問看護における2時間ルールは、利用者への適切なサービス提供と、公正な報酬請求を両立させるための制度です。
しかし、医療保険と介護保険での扱いの違いや、緊急時・異職種による訪問などの例外規定があることで、現場では判断に迷う場面も少なくありません。
誤算定や運用ミスを防ぐためには、制度を正しく理解したうえで、判断基準を明文化し、スタッフ全員で共通認識を持つことが必要です。
具体的な事例を用いた研修や、2時間ルールに対応したシステムの導入など、仕組みとして支える体制を整えることが、安定した運営につながります。
制度への対応を「誰かの判断」に委ねるのではなく、組織として仕組みで支える視点を持つことが、現場の安心とサービスの質向上に直結していくはずです。
2時間ルールの目的と運用を見直し、制度に沿った実践を積み重ねていきましょう。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。