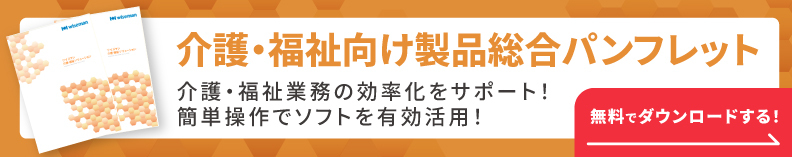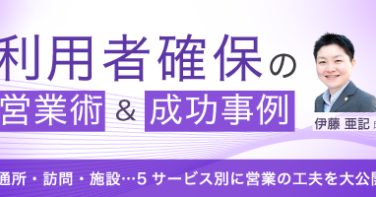ケアプラン点検とは?実施すべき準備や指摘されやすいポイントなどを解説
2025.11.27

ケアマネジャーにとって、常に利用者の自立支援を実現するケアプランの作成は目指すべき目標です。
一方で、より良いケアプランを実現するためにも、行政によるケアプランの点検に対応する必要があります。
しかし、ケアプラン点検は正しく理解し、ポイントを押さえて準備すれば、むしろ自身のスキルを見つめ直し、ケアの質を向上させる絶好の機会です。
本記事では、ケアプラン点検の目的・具体的な準備・指摘されやすいポイントなどを解説します。
点検への対応だけでなく、より良いケアプランを作成する際の参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。
目次
ケアプラン点検の概要

まずは、ケアプラン点検がどのようなものなのか、その目的や位置づけを正しく理解することから始めましょう。
全体像を把握することで、落ち着いて準備に取り組めます。
ケアプラン点検とは
ケアプラン点検とは、ケアプランが利用者の自立支援につながる適切な内容であるかを、保険者(市区町村など)とケアマネジャーが共同で検証・確認するプロセスです。
これは、介護保険法に基づく「介護給付適正化事業」の一環として実施されます。
ケアプラン点検の主な目的は、単に書類の不備をチェックすることではありません。
主な目的は以下のとおりです。
ケアプラン点検においては、ケアマネジメントのプロセスを踏まえ利用者の「尊厳の保持」、「自立支援」に資する適切なケアマネジメントとなっているかを、基本となる事項を介護支援専門員とともに検証確認しながら、介護支援専門員及び保険者両者の「気づき」を促し「学び」につなげるとともに「自立支援に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、「利用者の尊厳」を確保することが重要です。
引用:ケアプラン点検について|厚生労働省
ケアプラン点検は厚生労働省が作成したケアプラン点検項目に基づいて実施されます。
点検を受ける際は、事前にチェックしましょう。
ケアプラン点検を通じて、ケアマネジャー自身に業務を振り返る「気づき」を促し、ケアマネジメントの質を高めることが重要視されています。
最終的には、すべての利用者が質の高いサービスを受け、自分らしい生活を送れるように支援することが目指されています。
ケアプラン点検と実地指導の違い
ケアプラン点検と混同されがちなものに実地指導があります。
どちらも行政が事業所に対して行うものですが、それぞれ以下のように目的・対象・根拠法が異なります。
| 項目 | ケアプラン点検 | 実地指導 |
| 目的 | ケアマネジメントの質の向上・給付の適正化 | 事業所運営の適正化・運営基準の遵守状況の確認 |
| 主な対象 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)個人が作成したケアプラン | 居宅介護支援事業所全体 |
| 主な視点 | ケアプランの内容・プロセス・自立支援への貢献度 | 人員基準・設備基準・運営基準の遵守状況 |
| 雰囲気 | 対話的・協働的・気づきを促す | 指導的・監査的・是正を求める |
ケアプラン点検はケアマネジャー個人のプランに着目し、質の向上を目指す対話的なプロセスです。
対して、介護保険法等に基づく実地指導は、事業所全体の運営基準遵守を確認する監査的な意味合いが強い取り組みです。
参照:ケアプラン点検の基礎知識
ケアプラン点検の事前準備
本章では、ケアプラン点検の通知を受け取ってから点検当日までに行うべき準備を、以下のステップに沿って解説します。
- 全体像の把握
- 必要書類の準備
- 自己点検で最終チェック
上記の流れに沿って進めれば、不備なく、効率的に準備を整えられます。
全体像の把握
まずは、ケアプラン点検がどのような流れで進むのか、全体像を把握しましょう。
自治体によって細部は異なりますが、一般的には以下のステップで進行します。
| ステップ | 主な内容 |
| ケアプラン点検の目的の設定 | 自治体における現状と課題を踏まえ、ケアプラン点検の目的(ケアプラン点検を通じて何を達成するか)を明確化します。 |
| 事業所選定・ケアプラン抽出 | ケアプラン点検の目的や保険者の課題意識に応じて事業所の選定、ケアプランを抽出します。 |
| 点検書類提出の依頼(通知) | 点検する書類(アセスメントシートおよび第1表~第5表などを想定)の提出を事業所に依頼します。 点検書類の提出を依頼する際、保険者からケアプラン点検の目的を伝えるようにしましょう。 |
| 書類の受領 | 点検書類を受領します。 受領する書類は紙媒体ではなく、電子データの場合も考えられます。 |
| 書類の確認・面談の準備 | 受領した書類を確認し、面談の際に何を確認するか等について検討します。 点検項目によってケアプランを確認した後は、その結果を元に、面談時にどのようなことを介護支援専門員に確認するのかを検討します。 なお、点検の観点に偏りが生じないよう、専門職を含む2人1組で実施することが望ましいです(面談も同様)。 |
| 面談 | 事前に準備した確認事項等に基づき、介護支援専門員と面談を実施します。 面談時は、点検項目やケアプラン点検支援ツールを活用して得られた結果を介護支援専門員に示すなど、点検結果の根拠を示すことで、点検を受ける介護支援専門員の気づきが促されることが期待されます。 介護支援専門員との面談の際、当該介護支援専門員が属する居宅介護支援事業所の管理者にも同席を求めることも考えられるので留意しましょう。 また、ケアプラン点検後は、必要に応じて、ケアプランの修正を依頼することも考えられます。 |
| 点検結果の分析 | 面談まで終えたケースの結果を分析することで、介護支援専門員がつまづいていたポイントや、得られた気づきなどを把握できます。 |
各ステップを理解するだけでなく、厚生労働省が提示しているケアプラン点検のマニュアルや、点検項目も事前にチェックしておきましょう。
必要書類の準備
次に、点検で提出を求められる書類を揃えましょう。
必要書類は自治体によって異なりますが、例えば世田谷区の場合、以下の書類が必要となります。
- 居宅サービス計画書(第1表〜第7表)
- アセスメントシート
- 基本情報シート
- 訪問介護計画書(居宅サービス計画書に該当する場合は除く)
また、準備の基本となる各種マニュアルは、厚生労働省や各自治体のWebサイトで公開されています。
必ず最新版に目を通し、点検の基準や視点を把握しておきましょう。
自己点検で最終チェック
書類が揃ったら、提出前に必ず自己点検を行いましょう。
第三者の視点で自分の作成したプランを見直すことで、客観的な課題や改善点が見えてきます。
以下のチェックリストを参考に、特に指摘されやすいポイントを確認し、万全の状態で提出できるようにしましょう。
| チェック項目 | 確認の視点 |
| 1. アセスメント | ・課題分析標準項目の23項目はすべて網羅されているか? ・利用者の生活歴や価値観など、個別性が反映されているか? |
| 2. 課題の明確化 | アセスメントの結果から、利用者の生活上の課題が具体的に抽出されているか? |
| 3. 目標設定 | ・長期目標と短期目標は、利用者の意向を踏まえた具体的で測定可能な内容か? ・「自立支援」に資する目標になっているか?(例:おむつ交換→トイレでの排泄) |
| 4. サービス内容 | ・設定した目標を達成するために、そのサービスが必要な理由が明確か? ・アセスメントや課題、目標、サービス内容に一貫性があるか? |
| 5. 多職種連携 | ・サービス担当者会議の記録に、具体的な検討内容や各専門職の意見が記載されているか? ・日常的な情報共有の記録は残っているか? |
| 6. 利用者の意向 | ・プラン作成の各段階で、利用者や家族の意向を確認し、記録しているか? ・意思決定のプロセスが分かるように記載されているか? |
| 7. モニタリング | ・定期的にモニタリングを実施し、目標の達成度や状況の変化を記録しているか? ・モニタリングの結果に基づき、プランの変更が適切に行われているか? |
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。
ケアプラン点検で指摘されやすいポイント

本章では、実際の点検で特に厳しくチェックされる以下のポイントを解説します。
- アセスメントの網羅性と個別性
- 「自立支援」につながる目標設定とサービス内容の整合性
- 多職種連携の証跡
- 利用者・家族の意向の反映
- 面談で効果的に伝えるための準備と心構え
上記のポイントを事前に理解し、自身のケアプランに反映させることで、指摘を受けるリスクを大幅に減らせます。
面談時に自信を持ってプランの意図を説明するための準備にもつながるので、ぜひ参考にしてください。
アセスメントの網羅性と個別性
アセスメントは、質の高いケアプランを作成するための土台となるもっとも重要なプロセスです。
点検では、まず厚生労働省が示す課題分析標準23項目が網羅されているかどうかが確認されます。
しかし、単に項目を埋めているだけの形骸化したアセスメントは厳しく指摘されます。
重要なのは、収集した情報から利用者の生活背景・価値観・強み(できること)を読み解き、ケアプランに反映させる個別性です。
例えば、「転倒歴あり」といった事実だけでなく、「なぜ転倒したのか」「本人は外出をどう思っているのか」といった背景まで深掘りし、記録することが求められます。
「自立支援」につながる目標設定とサービス内容の整合性
ケアプランの目標は、利用者の「自立支援」に資するものでなければなりません。
単に身体機能の維持・向上を目指すだけでなく、利用者が主体的に生活に関わり、役割を持って暮らせることを支援する視点です。
目標は「〜できる」「〜に参加する」といった、具体的で測定可能な言葉で設定することが重要です。
加えて、その目標を達成するために、なぜそのサービスが必要なのか、論理的な一貫性(整合性)が求められます。
多職種連携の証跡
ケアマネジャーは、多職種チームの要として連携を調整する役割を担う立場です。
点検では、チームケアが適切に機能しているかどうかが、記録を通して確認されます。
特にサービス担当者会議の議事録は重要な証跡です。
単に参加者の署名があるだけでなく、「誰がどのような意見を述べたか」「どのような検討を経てプランに合意したか」など議事の内容が具体的に記載されている必要があります。
日々のモニタリング記録においても、サービス事業所から得た情報や、ケアマネジャーとしての評価・対応を記録しておくことが、連携の証となります。
利用者・家族の意向の反映
ケアプランは、利用者と家族が主体となって作成されるべきものです。
専門職の視点だけで作られたプランは、利用者本位ではありません。
点検では、プラン作成のあらゆるプロセスにおいて、利用者や家族の意向が適切に聴取され、反映されているかが確認されます。
ケアプラン(第2表)の利用者や家族の意向の欄はもちろん、アセスメント記録やサービス担当者会議の議事録など、随所に意向を確認したプロセスを記録することが重要です。
「〜という希望があったため、サービスAを導入することにした」のように、意思決定の過程がわかるように記載することが、利用者本位のケアマネジメントの証明になります。
面談で効果的に伝えるための準備と心構え
書類提出後に行われる面談は、ケアプラン点検の核心部分です。
面談では、書類だけでは伝わらないプランの背景やケアマネジャーの専門的判断を、自身の言葉で説明することが求められます。
過度に緊張せず、対話を通じて学びを得る場と捉えるためにも、以下のポイントを意識しましょう。
| 準備・心構えのポイント | 具体的なアクション |
| 1. 根拠の説明準備 | 提出したケアプラン一式をあらためて読み込み、「なぜこの課題なのか」「なぜこの目標なのか」「なぜこのサービスなのか」をすべて説明できるように、頭の中を整理しておく。 |
| 2. 想定問答集の作成 | 指摘されやすいポイントに基づき、「もしこう聞かれたら、こう答えよう」といった問答集を簡単に作成しておくと、当日落ち着いて対応できる。 |
| 3. ポジティブな姿勢 | 面談を評価される場ではなく、「専門職として意見交換し、学びを得る場」と捉える。指摘や助言は、今後のスキルアップのための貴重なフィードバックと前向きに受け止める。 |
| 4. 誠実な対話 | わからないことや不確かなことは、正直に伝える。威圧的に感じても感情的にならず、質問の意図を確認しながら冷静かつ誠実に対話する姿勢を心がける。 |
| 5. チームで臨む意識 | 一人で抱え込まず、事前に事業所内の他のケアマネジャーや管理者に相談し、模擬面談などを行う。当日は「事業所の代表」として臨む意識を持つことも大切にする。 |
ケアプラン点検後に実施すべきこと

本章では、点検を「やりっぱなし」にせず、自己成長と事業所全体の質向上につなげるための具体的なアクションについて解説します。
ケアプラン点検は、面談が終わればすべて完了ではありません。
むしろ、点検で得たフィードバックを次にどう活かすかがもっとも重要です。
点検結果を精査する
点検結果には、今後のケアマネジメント業務に役立つヒントがつまっています。
まずは、記載されている指摘事項や助言を真摯に受け止め、その内容を正確に理解しましょう。
指摘事項に対し、なぜそうなってしまったのか原因を分析し、具体的な改善策を盛り込んだ改善計画書を作成しましょう。
例えば、「目標設定が抽象的」と指摘された場合を想定しましょう。
その場合は、「今後はSMART(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)の原則を用いて目標を設定する」といった具体的な行動計画に落とし込むことが重要です。
事業所内での情報共有とスキルアップ
点検で得た学びや気づきは、個人の経験だけに留めるものではありません。
事業所内で報告会を開き、どのような指摘を受けたか、どのような点が評価されたかをほかのケアマネジャーと共有しましょう。
特定のケアマネジャーが受けた指摘は、事業所全体の共通課題である可能性も少なくありません。
共有された事例をもとに勉強会や事例検討会を開催することで、事業所全体のケアマネジメントの質を標準化し、レベルアップを図れます。
これにより、次に誰が点検の対象になっても、組織として対応できる体制が整います。

本稿にもあるように、ケアプラン点検は、作成された居宅サービス計画が「利用者の自立支援」に的確につながっているかを検証する重要な仕組みです。保険者(市区町村など)が中心となり、ケアマネジャーと協働で内容を確認することで、計画の妥当性や根拠を可視化し、支援の質向上を図ります。これは介護保険法に基づく「介護給付適正化事業」の一環として実施されるものであり、単なる書類点検ではなく、支援経過や目標設定を振り返り、専門職としての視点を再確認するプロセスでもあります。点検では、アセスメントから課題分析、サービス目標の整合性、モニタリング結果までの一連の流れを丁寧に見直すことが重要です。指摘事項を「指導」ではなく「学び」として活かし、チームで共有・改善する姿勢が、地域全体のケアマネジメント力を高めます。ケアプラン点検は、介護現場の質と信頼を支える“振り返りの文化”です。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。
ケアプラン点検を乗り越えて信頼を得よう

ケアプラン点検は、決してケアマネジャーを追い詰めるためのものではなく、むしろ専門性を高めるための協働的なプロセスです。
点検で指摘された事項は、ケアマネジャーの成長の糧となります。
また、点検を通じてプランを見直すのは、最終的に利用者へのより良いサービス提供につながります。
本記事を参考に、自信を持ってケアプラン点検に臨んでください。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。