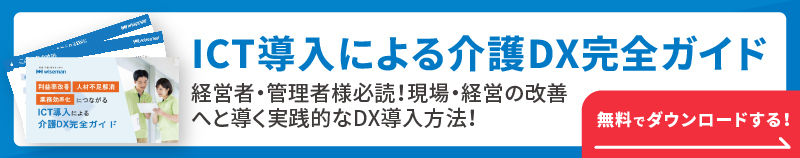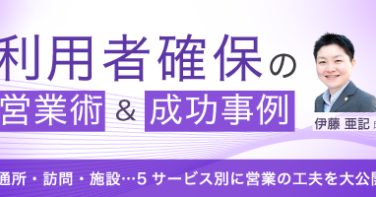【2025年度版】介護のDXカオスマップ|成功させるポイントも解説
2025.09.25

昨今、介護DXに取り組む介護事業所が増加しています。
業務の効率化・サービスの質向上・介護スタッフの負担の軽減など、さまざまな課題を解決するうえで、介護DXが有効な戦略となるためです。
しかし、介護DXを推進するには、多くのポイントを押さえておく必要があります。
そこで役立つのが、業界の全体像を一枚の地図のように可視化した「介護DXカオスマップ」です。
本記事では、2025年度の最新版カオスマップを基に、介護DXの全体像から具体的なツールの選び方・導入を成功させるためのポイントを解説します。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
介護DXとは

介護DXとは、単にITツールを導入することではありません。
AI・IoT・ロボットといったデジタル技術を活用して、業務プロセスや働き方を根本から変革し、サービスの質を向上させる取り組み全体を指します。
介護DXが推進される背景には、避けては通れない以下の課題があります。
| 課題 | 内容 |
| 2025年問題と人手不足 | 団塊の世代が75歳以上となり、介護需要が急増する一方、生産年齢人口は減少傾向にあります。その結果、介護人材が需要に対して不足している状況です。 |
| アナログ業務の限界 | 手書きの介護記録・紙ベースでの情報共有・請求業務など、非効率なアナログ業務が現場を圧迫しています。本来のケア業務にかける時間を削っているなど、サービスの質にも影響を与えています。 |
| LIFEへの対応 | 科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出が求められ、データに基づいた質の高いケアの実践が求められるようになりました。 |
上記の課題解決に向け、国も補助金などでDXを強力に後押ししており、介護DXは今や事業継続に不可欠な経営戦略となりました。
カオスマップとは

カオスマップとは、特定の業界や市場に存在する企業・サービス・製品などをカテゴリ別に分類し、一枚の図にまとめた「業界地図」のことです。
混沌(カオス)とした市場の状況を、地図のように俯瞰できることからこの名がついています。
介護DXの分野でも、昨今は数多くの企業がさまざまなサービスを提供しており、まさにカオスな状態です。
介護DXカオスマップを活用することで、以下のようなメリットがあります。
| 業界の全体像を把握できる | どのような種類のサービスが存在するのかを一目で理解できます。 |
| 自社の立ち位置を確認できる | 現在利用しているサービスがどのカテゴリに属するのかを客観的に把握できます。 |
| 新たなツール選定の指針になる | 自施設の課題解決に必要なサービスを効率的に探し出すための羅針盤となります。 |
| 最新トレンドを把握できる | 毎年更新されるカオスマップを見ることで、業界の新しい動きや注目されている技術を把握できます。 |
介護DXを推進するのにあたり、最初に着手する施策を検討する際に、カオスマップは有用です。
【2025年度版】介護DXカオスマップ

本章では、最新の介護DXカオスマップについて解説します。
以下の画像が、2025年度の介護業界における主要なサービスや企業を網羅したカオスマップです。

出典:つながる介護さっぽろ
上記のカオスマップには、日々の記録業務を効率化するツールから、利用者の安全を見守る最新技術まで、多種多様なソリューションが詰め込まれています。
業界全体のサービスや技術トレンドを一目で把握できるため、自社の立ち位置や注力すべき分野を客観的に判断できます。
また、多数の選択肢から最適なソリューションを見つけやすく、導入検討の効率化につながる点も魅力です。
加えて、競合他社の動向を把握し、差別化戦略を練る際にも役立ちます。
カオスマップは、介護DX推進における羅針盤として、戦略策定から具体的なソリューション選定まで、幅広い場面で有効活用できるものです。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
カオスマップの主な分類

介護DXカオスマップは、多岐にわたるサービスを機能や目的別に分類しています。
代表的な分類は以下のとおりです。
- 介護システム・介護ソフト
- コミュニケーションツール
- 見守りシステム
- リハビリの支援サービス
- 直接的な介護サービスに関連するシステム
- バックオフィスの支援システム
本章では、主な分類とそれぞれの役割について解説します。
介護システム・介護ソフト
介護システムや介護ソフトは、介護記録・ケアプラン作成・保険請求・職員の勤怠管理など、介護事業所の基幹となる業務を一元管理するソフトウェアです。
日々の業務の中核を担い、ペーパーレス化と業務効率化を大きく推進します。
| 主な機能 | 解決できる課題 |
| 介護記録(音声入力・スマホ入力) | 記録業務にかかる時間と手間を削減 |
| 保険請求業務 | 煩雑な請求計算を自動化し、ミスを防止 |
| ケアプラン作成支援 | アセスメントから計画作成までをサポート |
| 職員の勤怠管理・シフト作成 | 複雑なシフト作成業務を効率化 |
介護システムや介護ソフトは、紙媒体によるアナログな作業を削減し、業務を効率化するうえで有用なツールです。
また、蓄積されたデータをサービスのブラッシュアップや、経営戦略の策定に活用できるなど、介護事業所の運営において大きく貢献します。
コミュニケーションツール
職員間の情報共有や、多職種(医師・看護師・ケアマネジャーなど)との連携を円滑にするためのツールです。
リアルタイムな情報伝達を可能にし、チームケアの質を向上させます。
| ツールの種類 | 特徴 |
| ビジネスチャット | スタッフ間の申し送りや緊急連絡を迅速化 |
| 医療介護連携SNS | 地域の医療機関や薬局と安全に情報共有 |
インカムを利用したり、スマートフォンやタブレット端末と連携したりすれば、外出先の職員との情報共有がスムーズになります。
緊急事態への対応もしやすくなるなど、利用者へのサービスの質の向上も期待できるツールです。
見守りシステム
見守りシステムとは、ベッドや居室に設置したセンサー・カメラ・AIを活用して、利用者の状態(睡眠・離床・バイタルサインなど)をリアルタイムで把握するツールです。
夜間の巡回業務の負担を軽減しつつ、利用者の安全確保とプライバシー保護を両立させます。
| 主な機能 | 解決できる課題 |
| 睡眠・覚醒状態の把握 | 睡眠の質をデータで評価し、ケアに活用 |
| 離床・転倒検知 | ヒヤリハットを早期に検知し、事故を予防 |
| バイタルサイン測定 | 非接触で心拍数や呼吸数を測定 |
見守りシステムは職員の負担を減らすだけでなく、見守りの精度を向上させ、利用者の微細な変化を把握しやすくします。
また、システムを通じて得たデータを介護記録ソフトと連携させることで、より客観的なデータに基づいたケアプランの作成が可能です。
リハビリの支援サービス
昨今は、リハビリロボットやVR(仮想現実)技術などを活用し、利用者の機能訓練をサポートするサービスが登場しています。
ゲーム感覚で楽しく取り組めるプログラムも多く、利用者のリハビリ意欲の向上につながります。
| 主な技術 | 特徴 |
| 装着型ロボット | 身体の動きをアシストし、歩行訓練などを支援 |
| VR/AR技術 | 仮想空間でのリハビリ体験を提供 |
高齢の利用者にとって、身体機能の維持は健やかな生活を続けるうえで不可欠な取り組みです。
介護DXは、より効果的なリハビリを実現する効果も期待できます。
直接的な介護サービスに関連するシステム
介護職員の身体的負担が大きい移乗・入浴・排泄といった業務を直接的に支援するツールを含めた分野です。
これらのロボットや機器は、職員の腰痛予防や身体的な負担軽減に大きく貢献し、結果として人材の定着促進にもつながります。
例えば、移乗をサポートするロボットは、職員が抱え上げる必要性を減らし、腰への負担を軽減します。
入浴支援ロボットは、利用者の安全な入浴をサポートしつつ、職員の負担を減らすうえで有用です。
また、排泄支援ロボットは、排泄介助の頻度を減らし、職員の精神的な負担も軽減します。
直接的な介護サービスに関連するシステムは、介護現場における労働環境改善に不可欠であり、介護職員がより質の高いケアを提供できる環境作りを支援します。
バックオフィスの支援システム
事業所運営を円滑に進めるためのシステムは、介護現場における直接的な業務をサポートするだけでなく、バックオフィス業務全般の効率化に不可欠です。
人事労務管理システムは、従業員の採用から退職までの情報を一元管理し、給与計算や社会保険手続きなどを自動化します。
財務会計システムは、日々の経理処理を効率化し、経営状況をリアルタイムでの把握が可能です。
人材採用・育成システムは、最適な人材の確保と育成を支援し、組織全体のスキルアップを図ります。
さらに、経営分析システムは、事業所のデータを分析し、経営戦略の策定に役立つ情報を提供します。
また、経営状況の可視化により、迅速な意思決定を支援し、安定的な事業運営を実現するうえでも有用です。
介護DXを成功させるポイント

本章では、介護DXを成功に導くための以下のポイントを解説します。
- 自施設の課題を洗い出す
- スモールスタートを心がける
- 職員向けの研修を必ず実施する
- 費用対効果を計測する
カオスマップの活用に合わせて、上記のポイントを押さえれば、よりスムーズに介護DXを推進できます。
自施設の課題を洗い出す
もっとも重要なのは「何のためにDXを行うのか」といった目的を明確にすることです。
ツールを導入することが目的になると、本来の効果を得られなくなります。
まずは、現場のスタッフを交えて、現状の課題を具体的に洗い出しましょう。
| 課題の例 | 目的 | 検討すべきツールのカテゴリ |
| 介護記録に毎日2時間かかっている | 記録時間を30分に短縮し、利用者と話す時間を増やしたい | 介護ソフト(音声入力・スマホ入力) |
| 夜間の巡回で職員が疲弊している | 職員の負担を減らしつつ、利用者の睡眠を妨げないようにしたい | 見守りシステム |
| 職員間の申し送りに漏れがある | リアルタイムで正確な情報共有ができるようにしたい | コミュニケーションツール |
スモールスタートを心がける
介護DXはスモールスタートを心がけましょう。
最初から大規模なシステムを全施設・全部署に一斉導入するのは、現場の混乱を招きやすく、計画の遅延やコストの超過だけでなく、最終的には失敗のリスクを高める可能性があります。
そのため、まずは特定の部署や、業務範囲を限定した小規模な範囲に絞って試験的に導入するスモールスタートがおすすめです。
スモールスタートを意識すれば、初期投資を抑えつつ、システムの有効性や課題を早期に発見し、改善しやすくなります。
また、小さな成功体験を積み重ねることは、職員の新しいツールへの抵抗感を和らげ、システム導入に対するポジティブな意識を醸成し、結果として事業所全体の改善につながります。
職員向けの研修を必ず実施する
新しいツールの導入を成功させるには、現場職員の協力が不可欠です。
特に、IT機器の操作に不慣れな職員もいるため、導入前の丁寧な研修や勉強会を必ず実施しましょう。
研修では、基本的な操作方法だけでなく、よくある質問への対応、トラブルシューティングなども含めることが望ましいです。さらに、新しいツールを導入することで、業務効率がどのように向上するのか、残業時間が削減されるのかなど、具体的なメリットを丁寧に説明することで、職員のモチベーション向上につながります。
費用対効果を計測する
介護DXは導入後の効果測定が不可欠です。
定期的な計測・評価によって、導入効果を数値で可視化し、改善点を明確にできます。
可視化されたデータは、次なるDX戦略を策定するうえで貴重な情報源となり、より効果的な介護サービスの提供につながるものです。
また、万が一導入したシステムやツールの定着率が低い場合でも、早期の段階で改善できるため、介護DXの効果を最大化できます。

2025年問題や人手不足、アナログ業務の限界に直面する介護業界にとって、DXは事業継続に不可欠な経営戦略です。介護DXは、単なるITツール導入ではなく、AI・IoTなどのデジタル技術で業務プロセスや働き方を根本から変革し、サービスの質向上を目指す取り組み全体を指します。本記事の「介護DXカオスマップ」は、多種多様なサービスから自施設の課題解決に最適なツールを見つける羅針盤となり、業界全体像の把握と戦略的な導入を支援します。DX成功の鍵は、まず「何のためにDXを行うのか」という目的の明確化と課題洗い出しです。さらに、スモールスタートでの導入、丁寧な職員研修、そして導入後の費用対効果の計測と改善が不可欠です。これらのポイントを押さえ、介護DX効果を最大化することで、質の高いケア提供と持続可能な事業運営を実現できると確信しております。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
カオスマップは介護DXの指針になる

本記事では、2025年度版の介護DXカオスマップをもとに、介護業界のDXの全体像と、導入を成功させるためのポイントを解説しました。
人手不足や業務負担の増大といった深刻な課題を抱える介護業界にとって、DXはもはや避けては通れない道です。
しかし、やみくもにツールを導入しても、期待した効果は得られません。
まずはカオスマップを羅針盤として活用し、業界全体の動向を把握することから始めましょう。
加えて、介護DXを成功させるうえで重要なポイントを押さえることも不可欠です。
自施設の課題を明確にし、目的意識を持ってツールを選定することが成功への第一歩です。
また、スモールスタートで小さな成功体験を重ねながら、費用対効果を正確に計測すれば、介護DXの効果をより高められます。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。