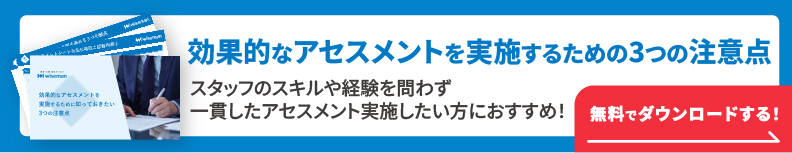通所介護の個別機能訓練加算とは?算定要件や注意点などを解説
2025.02.25

介護報酬の改定に伴い、通所介護事業所において、利用者の状態に応じた個別機能訓練の提供がますます重要になりました。
個別機能訓練加算を介護報酬に設けるなど、厚生労働省も個別機能訓練の提供を後押ししています。
しかし、個別機能訓練加算は種類や算定要件などが複雑で、導入に二の足を踏んでいる事業所も多いのではないでしょうか。
本記事では、通所介護における「個別機能訓練加算」について、概要・種類・算定要件・注意点までをわかりやすく解説します。
なお、株式会社ワイズマンでは、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
アセスメントシートを記載する上で知っておきたい3つの観点を記載しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
個別機能訓練加算とは

個別機能訓練加算とは、通所介護事業所において、利用者一人一人の状態や目標に合わせた個別的な機能訓練を実施した場合に算定できる加算です。
そもそも個別機能訓練は、高齢者の心身機能の維持・向上・自立支援を促進することを目的としています。
従来の集団訓練に加え、個別的なニーズに対応することで、より効果的な機能訓練を提供し、利用者のQOL向上につなげられる取り組みです。
具体的には、利用者の状態を詳細に把握し、最適な訓練計画を作成・実施することで、より効果的なリハビリテーションを提供することを目指しています。
個別機能訓練は利用者の身体機能を維持し、より健やかな生活を継続するうえで欠かせません。
個別機能訓練加算は、利用者のニーズに応え、通所介護事業所が個別機能訓練に関するサービスを積極的に提供できるよう後押しするために設けられました。
個別機能訓練加算の3つの種類と違い

通所介護における個別機能訓練加算は、大きく分けて3種類あります。
それぞれ、提供するサービス内容や算定要件が異なるので注意しましょう。
それぞれの加算の種類と違いは以下のとおりです。
| 加算の種類 | 機能訓練指導員の配置要件 | 単位数 | 主な違い |
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 専従1名以上配置(配置時間の定めなし) | Ⅰイ:56単位/日 | ・もっとも高度な機能訓練を提供することが目的・配置要件が厳しく、単位数も多い |
| 個別機能訓練加算Ⅰロ | ・個別機能訓練加算(Ⅰ)イの配置要件に加え、合計で2名以上の機能訓練指導員を配置 ・2名以降の配置時間についても定めはない。 | Ⅰロ:76単位/日 | Ⅰイよりも配置要件は緩和されているが、個別機能訓練の対象者・実施者はより厳しく設定されている |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 専従1名以上配置 (配置時間の定めなし) | 20単位/月 | 加算Ⅰの要件を満たしているうえに、LIFEへの情報提出やフィードバックを実施する必要がある |
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について(検討の方向性)|厚生労働省
令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
介護保険最新情報Vol.1225|厚生労働省
個別機能訓練加算は、2024年度の介護報酬改定によって一部要件が変更されました。
なお、Ⅰのイとロは併算定ができません。
いずれかのみの算定になるので、介護報酬を請求する際は注意しましょう。
個別機能訓練加算の算定要件

個別機能訓練加算は、通所介護事業所が利用者一人一人に合わせた個別的な機能訓練を提供する場合に算定できる加算です。
前述の表でも解説しましたが、個別機能訓練加算は以下の3種類があります。
- 個別機能訓練加算Ⅰイ
- 個別機能訓練加算Ⅰロ
- 個別機能訓練加算Ⅱ
本章では、それぞれの加算の算定要件を詳しく解説します。
個別機能訓練加算Ⅰイの算定要件
個別機能訓練加算Ⅰイの算定要件は以下のとおりです。
| ニーズ把握・情報収集 | 通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認 |
| 機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上配置(配置時間の定めなし) |
| 計画作成 | 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成 |
| 機能訓練項目 | ・利用者の心身の状況に応じて、身体機能および生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定 ・訓練項目は複数種類を準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する |
| 訓練の対象者 | 人数制限なし |
| 訓練の実施者 | 制限なし(機能訓練指導員の管理の下に別の従事者が実施した場合でも算定可能) |
| 進捗状況の評価 | 上記の過程を3カ月に1回以上実施し、個別機能訓練計画の進捗状況等に応じ、訓練内容の見直し等を行う |
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について(検討の方向性)|厚生労働省
令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
介護保険最新情報Vol.1225|厚生労働省
2024年度の介護報酬改定において、個別機能訓練加算Ⅰイの算定要件に変更はありませんでした。
個別機能訓練加算Ⅰロの算定要件
個別機能訓練加算Ⅰロの算定要件は以下のとおりです。
| ニーズ把握・情報収集 | 通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認 |
| 機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上配置(配置時間の定めなし)※個別機能訓練加算(Ⅰ)イの配置(専従1名以上配置(配置時間の定めなし))に加え、合計で2名以上の機能訓練指導員を配置している時間帯において算定が可能 |
| 計画作成 | 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成 |
| 機能訓練項目 | 利用者の心身の状況に応じて、身体機能および生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定訓練項目は複数種類を準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する |
| 訓練の対象者 | 5人程度以下の小集団または個別 |
| 訓練の実施者 | 機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない) |
| 進捗状況の評価 | 上記の過程を3カ月に1回以上実施し、個別機能訓練計画の進捗状況等に応じ、訓練内容の見直し等を行う |
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について(検討の方向性)|厚生労働省
令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
介護保険最新情報Vol.1225|厚生労働省
個別機能訓練加算Ⅰロは、機能訓練指導員の配置要件に加え、訓練の対象者・実施者が異なります。
2021年度の介護報酬改定時は、2名以降の機能訓練指導員の配置時間はサービスの提供時間と定められていましたが、2024年度に配置時間の定めが撤廃されました。
そのため、以前より要件を満たしやすくなっています。
一方、先述したように個別機能訓練加算Ⅰイとロは併算定ができません。
介護報酬を請求する際は、いずれかを選択する必要があります。
個別機能訓練加算Ⅱの算定要件
個別機能訓練加算Ⅱは、個別機能訓練加算Ⅰの算定要件に加え、科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出とフィードバックの活用が求められます。
| 要件 | 説明 |
| 個別機能訓練加算Ⅰの算定 | 個別機能訓練加算Ⅰ(イまたはロ)の算定が必須。 |
| 科学的介護情報システム(LIFE)の活用 | LIFEへのデータ提出と、フィードバックに基づいた機能訓練計画の見直し・改善を行う。 |
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について(検討の方向性)|厚生労働省
令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
介護保険最新情報Vol.1225|厚生労働省
なお、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて、「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
個別機能訓練加算の算定における注意点

個別機能訓練加算を算定する際には、いくつかの注意点があります。
本章では以下の注意点について解説します。
- Ⅰ・Ⅱを併用するなら人員配置に注意する
- 利用者やその家族との連携を重視する
Ⅰ・Ⅱを併用するなら人員配置に注意する
個別機能訓練加算ⅠとⅡを併用する場合、人員配置に関する規定を厳守しましょう。
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱは訓練内容が異なるため、対応すべき人員の数や提供するサービスの内容が異なります。
そのため、それぞれの目標を立てたうえで訓練を実施できるように人員配置を考慮する必要があります。
人員配置が不適切な場合、加算の算定が認められないだけでなく、サービス提供の質にも影響を与えかねません。
そのため、事前に人員配置計画を綿密に立て、必要に応じて人員の増員や配置換えなどを検討することが重要です。
加算ⅠとⅡの併用を検討する際には、それぞれの算定要件を詳細に確認し、自施設の人員配置状況と照らし合わせましょう。
問題なく算定できるかどうかを事前に確認すれば、要件を満たせる可能性が高まります。
利用者やその家族との連携を重視する
個別機能訓練加算は、利用者一人一人の状態に合わせた個別的な機能訓練を提供することを目的としています。
効果的な機能訓練を行うためには、利用者やその家族との綿密な連携が不可欠です。
個別機能訓練計画書の作成段階から、利用者の希望・目標・現在の状態などを丁寧にヒアリングし、計画に反映させましょう。
また、訓練実施後には、その効果や課題などを共有し、必要に応じて計画の見直しを行うなど、継続的なコミュニケーションを心がけましょう。
利用者や家族との良好な関係を築くことで、信頼関係を構築し、より効果的な機能訓練を提供できます。

デイサービスはもともと『レスパイト(同居家族の休息)』として位置づけられているサービスです。ひと昔前までは「日中のお預かり」だけで問題なかったのですが、社会保障費抑制の御旗のもと、デイサービスに求められる機能も変遷しています。簡単に説明すると、ただ「お預かり」するのではなく、「お預かりして元気にする(ADLの維持・改善等)」ことが求められています。この部分を具体化しているのが、個別機能訓練加算です。ⅠとⅡに関しては、個別機能訓練加算Ⅰ(イもしくはロ)で実施した内容をⅡでLIFEに提出するという関係性となっています。実施した機能訓練の情報をLIFEへ提出し、フィードバックを受け、更なる利用者の能力向上に繋げる必要があります。デイサービスも具体的な成果が求められる時代となっているのです。
なお、株式会社ワイズマンでは「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
個別機能訓練加算を理解して通所介護事業所の運営に活用しよう

個別機能訓練加算は、単なる加算ではなく、利用者一人一人の状態に合わせた個別的な機能訓練を提供するための重要な制度です。
そのため、単に算定要件を満たすだけでなく、利用者のニーズを的確に把握し、効果的な訓練計画を立案・実施することが不可欠です。
その過程で、機能訓練指導員の専門性を活かし、利用者や、その家族との丁寧なコミュニケーションを図れば、加算算定だけでなく、事業所の信頼度の向上にもつながります。
個別機能訓練加算は、通所介護事業所のサービスの質を高め、利用者の生活の質向上に貢献するうえで欠かせません。
本記事で解説した内容を踏まえ、事業所の状況に合わせて適切に活用することで、利用者により良いサービスを提供しましょう。

監修:伊谷 俊宜
介護経営コンサルタント
千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機 に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。これまで、数々の特別養護老人ホーム、 グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。現在は、“現場第一主義!”を旗印とし、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施 設づくり」を積極的にサポートしている。