【介護業界動向コラム】第16回 介護情報基盤がもたらす業務変革 ~これからの介護事業に求められること~
2025.10.29
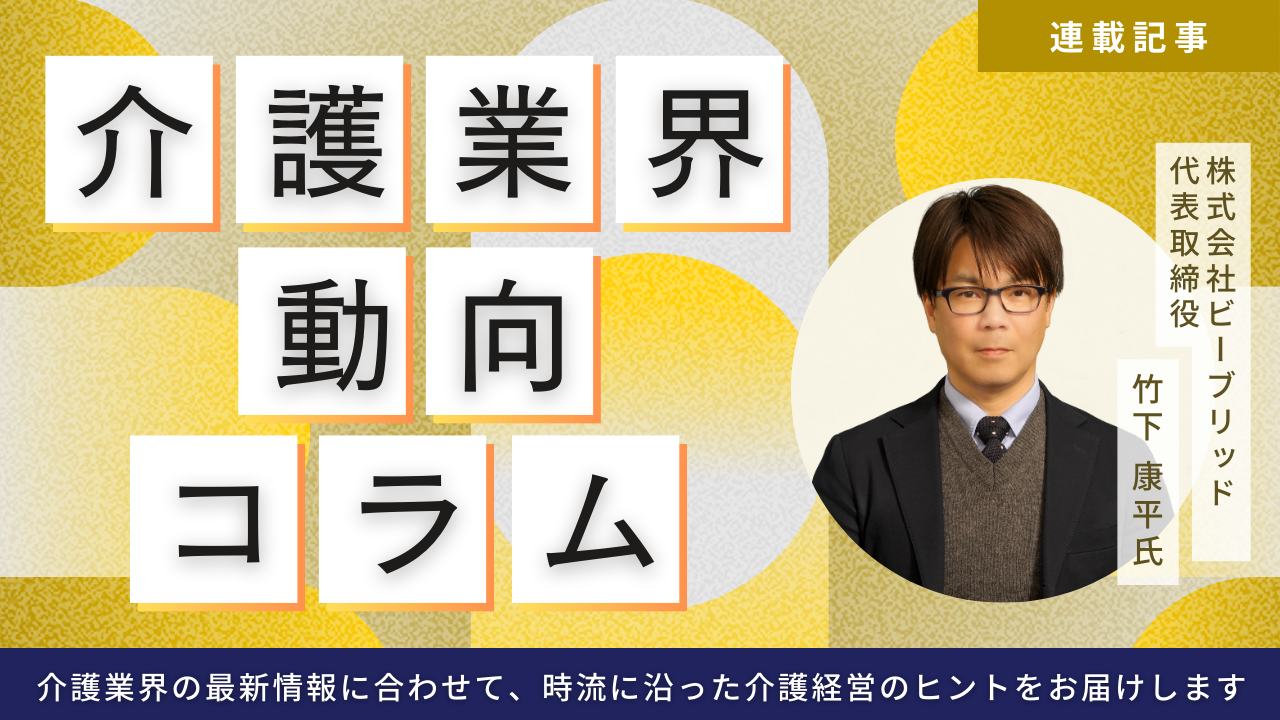
2026年度から本格的に稼働する「介護情報基盤」。これまで市町村、医療機関、介護事業所がそれぞれの仕組みで行っていた情報のやり取りが、全国共通のオンライン基盤の上でつながるようになります。
介護情報基盤は、各種の介護・医療情報システムを支える共通の基盤として整備が進められています。 ケアプランのデータ連携だけでなく、介護保険資格確認、要介護認定情報、LIFE、医療機関との情報共有など、 多様な情報がこの基盤を通じてつながり、介護と医療のデータが一体的に活用できる仕組みが目指されています。
介護情報基盤は、市町村(保険者)・医療・介護が共通の環境で公的情報を安全に共有するための仕組みです。いわば、介護の行政情報と現場情報をつなぐ“共通基盤”です。
一見すると「行政システムの話」に思われるかもしれませんが、実はこれは介護現場の働き方そのものを変える仕組みです。
国保中央会の資料では、介護情報基盤によって「これまでの紙・電話・FAX中心のやり取りがオンラインで完結する」と明確に示されています。
では、この仕組みが始まると、介護事業所の業務はどう変わるのでしょうか。
■ 資格確認からケアマネ連携まで、日常業務が変わる
これまで介護事業所では、利用者の負担割合証や限度額認定証を利用者や家族に持参してもらい、内容を確認していました。
また、証書の更新時期には毎回利用者宅を訪問して確認するなど、時間と手間がかかっていたのが現実です。
しかし今後は、「介護保険資格確認等WEBサービス」を通じて、利用者情報を即座にオンラインで確認できるようになります。
ケアマネジャーはケアプラン作成時に、認定調査票や主治医意見書を自治体から取り寄せる必要がなくなり、介護WEBサービス上で確認・ダウンロードが可能になります。
また、住宅改修費や福祉用具購入費の利用状況も、自治体へ電話して確認するのではなく、自事業所でオンライン照会できます。
居宅サービス計画の届出も、本人確認のうえでオンライン提出が可能となり、FAXや郵送での提出が不要に。
認定結果の共有もリアルタイムで行えるため、「結果が届くまで動けない」状況が減ります。
つまり、これまで1件の手続きを完了させるのに「紙を準備 → 郵送 → 電話確認 → 修正 → 再送」という流れだったものが、一度の操作で完結する時代がやってくるのです。
■ “事務の効率化”が、“ケアの質向上”につながる
国保中央会は、介護情報基盤の導入による変化を次の3点に整理しています。
1. いつでも情報を確認できる
2. やりとりの負担を軽減できる
3. 質の高いケアを実現できる
これらは単なる事務改善ではなく、「時間の再配分」です。
紙の確認や窓口対応に使っていた時間が減ることで、ケアマネはより多くの時間を利用者や家族との面談、プランの見直し、他職種連携に充てることができるようになります。
また、認定結果がリアルタイムで共有されれば、「結果待ち」による業務停滞も解消され、
サービス開始までの時間短縮にもつながります。介護情報基盤は、「情報がつながること」で現場の判断と支援のスピードを変えていく仕組みなのです。
■ 「つながる介護」を現実にするために
介護情報基盤は、単なるICTシステムの導入ではなく、「介護の仕組みを再設計する国家的プロジェクト」です。
紙や電話に頼る慣れた業務フローを変えるのは簡単ではありません。
しかし、だからこそ今、先んじて取り組む法人が地域のモデルになります。
ICT化は“目的”ではなく、“手段”です。
最終的に目指すのは、「情報が早く正確に届くことで、より良い介護を提供できる現場」。
そのための基盤づくりが、まさに今始まろうとしています。
次回では、この介護情報基盤を導入するために活用できる助成金制度と、
実際に事業所がどのような準備を進めるべきかについて詳しく解説します。

竹下 康平(たけした こうへい)氏
株式会社ビーブリッド 代表取締役
2007 年より介護事業における ICT 戦略立案・遂行業務に従事。2010 年株式会社ビーブリッドを創業。介護・福祉事業者向け DX 支援サービス『ほむさぽ』を軸に、介護現場での ICT 利活用と DX 普及促進に幅広く努めている。行政や事業者団体、学校等での講演活動および多くのメディアでの寄稿等の情報発信を通じ、ケアテックの普及推進中。






