【介護業界動向コラム】第14回 導入したのに使われないICT ―現場を立て直すために、今すぐできること―
2025.09.02
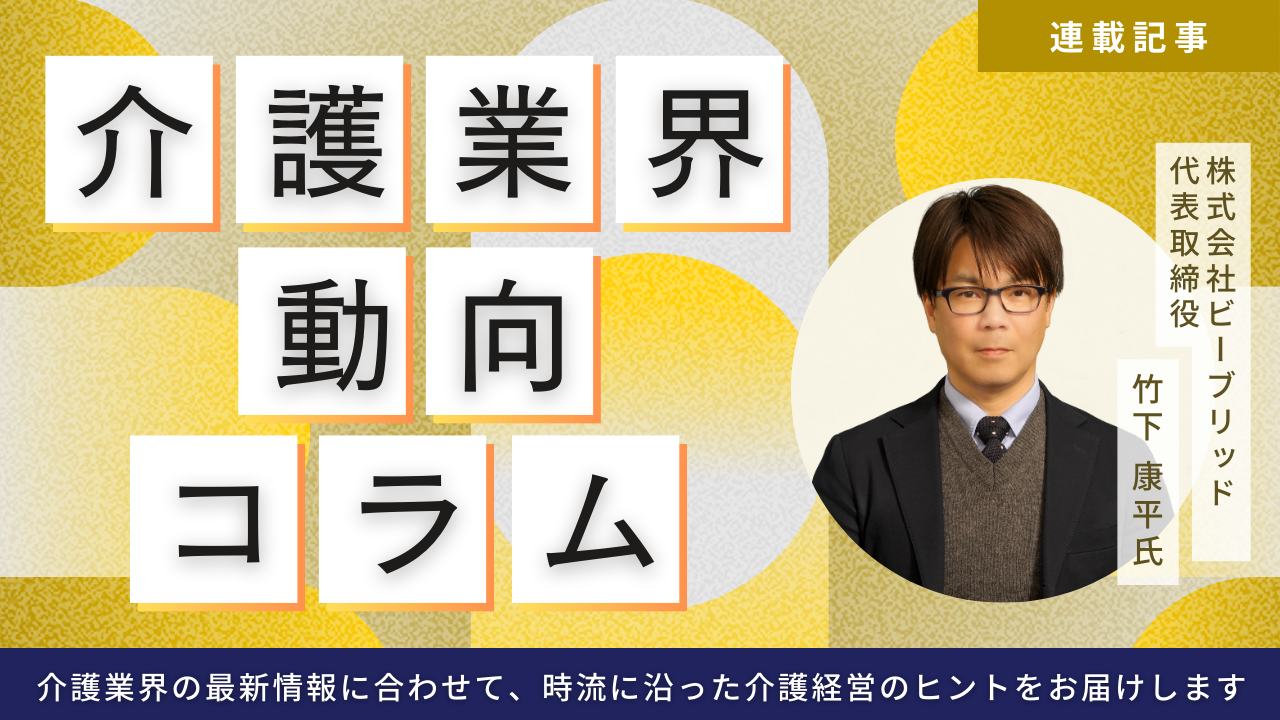
目次
導入したのに使われないICT
― 現場を立て直すために、今すぐできること ―
昨年、補助金を活用して見守り支援機器や記録ソフトを導入したものの、「結局あまり使われていない」「手書きに戻っている」といった声を、私たちは現場で数多く耳にしてきました。導入時には「これで効率化できる」「記録の時間が減る」と期待されていたはずのICT。しかし、1年経って振り返ると、期待と現実のギャップに直面している事業所も少なくありません。
※なぜICTは使われなくなるのか?については、前回のコラム(第13回)で詳しく解説しています。今回はそこから一歩踏み込み、「使われていないICTをどう立て直すか?」という視点で掘り下げていきます。
成功している現場がやっている3つのこと
使われていないICTを“使われる仕組み”に変えるには、単なる操作研修だけでは不十分です。
私たちが支援してきた中で、実際にICT定着に成功している現場には、共通する3つの取り組みが見られました。
① 「なぜそれを導入するのか」を徹底的に言語化した
「記録時間を短縮したい」「転倒リスクを早期発見したい」「夜勤者の心理的負担を軽減したい」――。
成功している現場では、“何をどう良くしたいか”という目的が、具体的かつ現場にとってリアルでした。
そして、その目的は現場職員にも明確に共有されています。
「新しいICT機器を使うことで、自分たちの仕事がどう変わるのか」が腹落ちしていれば、苦手意識のある職員も前向きになれます。
逆に、「なんとなく導入された」「上から言われた」という受け止め方がされてしまうと、使う意義を感じられず、形だけの運用になってしまいます。
② 試用・小規模導入で“失敗する余白”を設けた
いきなり全職員に一斉展開するのではなく、まずは1〜2ユニット・一部職員に試してもらう“試用期間”を設けていた事業所も多くありました。
この段階では、目的達成のために「何がうまくいって」「何が使いにくいか」を把握することが主な狙いです。
「慣れるまで時間がかかるのは当然」「失敗していい期間をあえて設ける」と最初から伝えることで、職員もリラックスして操作に向き合えます。
そしてこの試用期間で得た“使用者の声”をもとにマニュアルを簡素化したり、トラブル対応フローを整備したりすることで、本格展開後のスムーズな運用につながります。
③ “ICT担当者”に孤独を背負わせない仕組みをつくった
ICT導入時、多くの現場では「得意な人」が担当を任されがちです。
しかし、その人が自分の本来業務を抱えたまま、操作説明やトラブル対応まで丸ごと背負ってしまうと、時間的にも心理的にも負担が大きくなります。
成功している現場では、以下のような「孤立させない工夫」がされていました:
- 役割の明確化:ICT推進担当者を任命するときに、「業務調整込み」で行う
- チーム体制:1人にせず2〜3人で“担当グループ”を作る
- 運用資料:質問対応の負担を減らす簡易マニュアルやQ&A集の整備
- 相談しやすい空気づくり:使いこなせていない職員を責めない文化
「人」が変わっても継続できる運用体制を作ることこそ、真の“定着”だといえるでしょう。
立て直すなら、今がチャンス
「今さら」ではなく、
「今だから」やる意味がある
ICTがうまく使われていないことを恥じる必要はありません。
むしろ、現場に合わせて“再設計”する姿勢こそ、ICT活用の本質です。
なぜなら、現場は日々変化していくからです。
職員は成長し、ICTへの理解やスキルも変化します。
一方で、入退職や異動によって体制が入れ替わることもあります。
利用者様の状態もまた日々変わり、求められるケアや業務の重点が変化するのは当然のことです。
それにともない、ICTに求めたい機能や使い方も、時間とともに変わっていきます。
だからこそ大切なのは、「何のためにこのICTを使うのか」という目的を明確に保ち続けること、そして、その目的に沿って“今、うまく使えているのか?”を定期的にチェックすることです。
さらに忘れてはならないのが、ICT機器そのものも進化するということ。
ソフトウェアの更新によって新たな機能が追加されたり、以前は取得できなかったデータが見られるようになったりするケースもあります。
せっかく持っている機器を最大限活かすためにも、メーカーやコンサルタントから最新情報を定期的に収集することをおすすめします。特に、生産性向上委員会などの場で、担当者が直接ヒアリングする仕組みを設けておくと、情報が現場全体に共有されやすくなります。
1年前の計画が今とズレていても構いません。
気づいたときに軌道修正すること、それ自体が“活用している証”です。
この夏は、「ICTの立て直し」を始める絶好のタイミングです。

竹下 康平(たけした こうへい)氏
株式会社ビーブリッド 代表取締役
2007 年より介護事業における ICT 戦略立案・遂行業務に従事。2010 年株式会社ビーブリッドを創業。介護・福祉事業者向け DX 支援サービス『ほむさぽ』を軸に、介護現場での ICT 利活用と DX 普及促進に幅広く努めている。行政や事業者団体、学校等での講演活動および多くのメディアでの寄稿等の情報発信を通じ、ケアテックの普及推進中。






