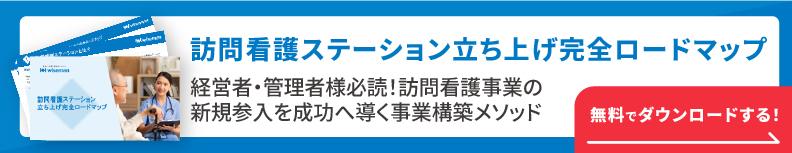【2025年版】訪問看護、医療保険で1日2回訪問できる条件とは?料金・算定要件を解説
2025.09.04

在宅医療の現場では、病状が不安定な利用者への対応として、訪問看護を医療保険で1日2回訪問するケースも珍しくありません。
しかし、医療保険制度では原則「1日1回」が基本ルールとされており、2回以上訪問する場合には特定の条件を満たす必要があります。
制度の理解が不十分なまま実施してしまうと、返戻や減収といったリスクに直結しかねません。
本記事では、訪問看護を医療保険で1日に2回行う場合の制度上の例外条件や算定要件、加算・減算に関する注意点をわかりやすく解説します。
医療保険での訪問看護における「正しい運用」と「安心できる請求体制」を整えるために、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
目次
医療保険での訪問看護は「1日1回」が基本

医療保険における訪問看護は、原則として「1人の利用者につき1日1回まで」とされています。制度上の基本ルールとして、必要最小限の訪問で適切な医療ケアが提供されることを前提としているからです。
この原則は、医療保険による訪問看護の「回数と頻度」に関して、以下のようにまとめられます。
| 項目 | 原則 | 例外(医師の指示等がある場合) |
| 1日の訪問回数 | 1回 | 病状によって2回以上も可 |
| 週の訪問回数 | 週3回まで | 特別管理加算対象者等は増回可能 |
| 1回の訪問時間 | 30〜90分程度 | 状況に応じて柔軟な対応が可能 |
ただし、病状の悪化や特別管理が必要と判断されたケースでは、1日2回以上の訪問が例外的に認められることがあります。上記のような場合には、主治医による訪問看護指示書が必要となり、レセプト摘要欄に明記した上で算定しなければなりません。
訪問スケジュールの作成や請求判断を行う際は、まずこの「1日1回」の原則を踏まえた上で、例外に該当するかどうかを冷静に確認しましょう。
1日2回以上の訪問が可能になるケース
医療保険で1日に2回以上の訪問が認められるのは、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つは、厚生労働大臣が定める特定の疾病等に該当するケースです。
もう1つは、主治医が「頻回な訪問が必要」と判断し、特別な指示書を発行した場合です。
| 対象となるケース | 概要 |
| 厚生労働大臣が定める疾病等 | 国が指定した特定の難病や状態にある利用者様 |
| 特別訪問看護指示書 | 主治医が一時的に頻回な訪問が必要と判断した場合に交付される指示書 |
それぞれのケースを確認していきましょう。
■厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)
以下に示す疾病や状態に該当する方は、週4回以上、あるいは1日複数回の訪問が医療保険上で認められています。
これらは、国が「特に手厚いケアが必要」と定めている対象です。
| 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七) |
| 末期の悪性腫瘍 / 多発性硬化症 / 重症筋無力症 / スモン / 筋萎縮性側索硬化症(ALS) / 脊髄小脳変性症 / ハンチントン病 / 進行性筋ジストロフィー症 / パーキンソン病関連疾患 / 多系統萎縮症 / プリオン病 / 亜急性硬化性全脳炎 / ライソゾーム病 / 副腎白質ジストロフィー / 脊髄性筋萎縮症 / 球脊髄性筋萎縮症 / 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 / 後天性免疫不全症候群(AIDS) / 頸髄損傷 / 人工呼吸器を使用している状態 |
これらの疾病や状態に該当する利用者様は、医療保険のルールにより、通常の訪問看護よりも頻回の訪問が認められています。
■特別訪問看護指示書が交付された利用者
一方、病状の急性増悪や退院直後などで、利用者様の状態が一時的に不安定になった場合、主治医が「頻回な訪問が必要」と判断し、特別訪問看護指示書を交付します。
この指示書があれば、最長14日間にわたり、週4日以上かつ1日複数回の訪問が可能です。
| 特別訪問看護指示書が交付される主なケース |
| 急性感染症などによる急な症状の悪化末期がん以外の終末期退院直後で集中的なケアが必要な場合気管カニューレを使用している状態真皮を超える褥瘡(床ずれ)がある状態 |
上記条件に当てはまる場合に限り、医療保険で1日2回以上の訪問看護が認められています。
訪問計画を立てる際や請求手続きを行う際には、該当要件をしっかり確認し、適切に対応する必要があります。
1日複数回訪問の実務|記録と請求のポイント
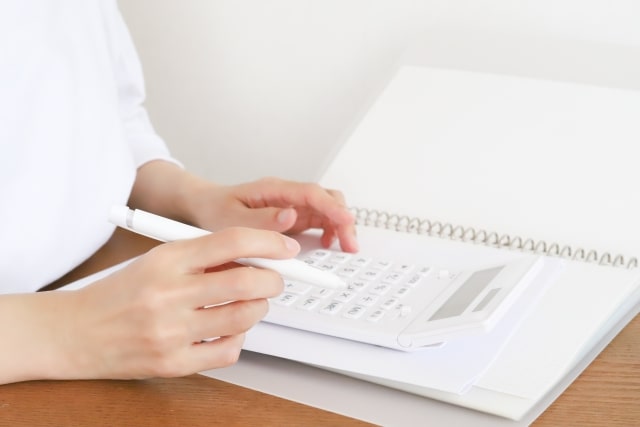
訪問看護において、1日に複数回の訪問が必要となるケースは限られていますが、適切な記録と請求手続きを行う必要があります。
特に、医療保険を利用して1日2回以上の訪問を行う場合は、指示書の内容や訪問の状況を正確に記録し、算定漏れや誤請求を防ぐための細かな対応が求められます。
レセプト返戻などのトラブルを避けるためにも、以下の点を徹底しましょう。
医師からの明確な指示を指示書に記載する
訪問看護で1日に複数回訪問する場合は、医師の指示内容を訪問看護指示書に正確かつ具体的に記載する必要があります。
これがないと、医療保険での適正な請求やサービス提供が認められません。
| 訪問頻度 | 1日に何回訪問するか(例:1日2回、1日3回)を具体的に示す |
| 訪問理由 | なぜ複数回の訪問が必要なのか、病状や医療的必要性を明記する |
| 訪問時間帯 | 訪問の時間帯や開始終了時刻の目安を記載する |
| 特別訪問看護指示書の有無 | 特別訪問看護指示書が必要な場合は、その旨を明確に示す |
指示書の有効期間は通常1ヶ月から6ヶ月であり、期間内に指示内容が有効であることを確認しなければなりません。
主治医の変更があった場合は新たな指示書の取得が求められます。
医師からの明確で具体的な指示が訪問看護指示書に記載されていることが、正確な記録管理と適切な請求事務の基礎となります。
訪問看護記録書へ理由とケア内容を記載する
1日に複数回の訪問看護を行う場合は、訪問ごとに理由と具体的なケア内容を訪問看護記録書に詳細に記載する必要があります。
これにより、サービスの質を保ちつつ、適正な保険請求が可能になります。
| 記載すべき主な内容 | ・訪問日時(各訪問の具体的な時間(例:10:00、14:00)を正確に記録) ・訪問理由(複数回の訪問が必要となった具体的な理由を記載) ・ケア内容(各訪問で実施した具体的なケアの内容を詳細に記録) ・状態の変化(訪問時の利用者の状態やケア前後の変化も記録) ・その他特記事項(家族への指導内容や利用者の意向など、ケアに関わる重要事項を忘れずに記録) |
| 請求時のポイント | ・訪問回数(介護保険・医療保険それぞれのルールに沿って適切に訪問回数を算定) ・加算の算定(複数回訪問加算やその他必要な加算を正確に計算し請求) ・レセプトの作成(訪問看護記録書の内容と請求内容が一致していることを確認し、正確なレセプトを作成) |
訪問看護記録書への正確かつ具体的な情報の記載は、利用者様の安全なケアと事業所の適正な運営に欠かせません。
日々の記録を丁寧に行い、訪問看護の質の維持と確実な請求処理を実現しましょう。
レセプト摘要欄への具体的な書き方
返戻を防ぐために、レセプトの摘要欄には訪問回数だけでなく、2回目以降の訪問時間や訪問理由など、必要な情報を具体的に記載する必要があります。
正確な情報を記載すれば、審査担当者が訪問の必要性を理解しやすくなり、返戻や査定のリスクを減らせます。
摘要欄に記載すべき内容の具体例は、以下のとおりです。
- 1日2回訪問の場合、2回目の訪問時間(例:午後14時)を明記する
- 訪問理由を簡潔に示す(例:疼痛管理のための臨時訪問、褥瘡処置の継続)
- 特別訪問看護指示書がある場合はその旨を記載する
- 複数回訪問加算や特別管理加算など、算定している加算も適切に反映する
例えば「1日2回訪問:午前10時は褥瘡処置、午後2時は疼痛管理の訪問実施。特別訪問看護指示書あり複数回訪問加算算定」などの具体的な記載が推奨されます。
請求時は訪問看護記録書や医師の指示書と内容を照合し、記載漏れや誤りがないか必ず確認しましょう。
医療保険には「2時間空けるルール」がない
医療保険の訪問看護には、介護保険で定められている「2時間空けるルール」が存在しません。
これは、医療保険の訪問看護が利用者の病状や医師の指示に基づき柔軟に対応できる仕組みだからです。
介護保険では、同一利用者に同日に複数回訪問する場合、訪問間隔をおよそ2時間以上空ける必要があります。
しかし医療保険では、このような時間間隔の制限がなく、必要に応じて1日に2回以上の訪問が可能です。
例えば、医師が頻回の訪問を指示し、特別訪問看護指示書が発行されている場合は、間隔を空けずに複数回の訪問を行い、適切に保険請求が行えます。
医療保険の訪問看護では、2時間ルールに縛られず、利用者の状況に応じた柔軟な訪問計画が可能であることを理解しておきましょう。
【料金・加算】1日2回訪問した場合の訪問看護療養費の計算方法

訪問看護療養費の請求において、1日に複数回訪問したケースは加算の対象となり、正確な計算が求められます。
特に1日2回訪問した場合には、基本療養費に加えて難病等複数回訪問加算が適用されるため、訪問回数や利用者の状況に応じた正確な算定が必要です。
ここでは、厚生労働省の規定に基づき、1日2回訪問時の訪問看護療養費の計算方法と加算のポイントについて詳しく解説します。
基本療養費と算定できる各種加算一覧
訪問看護における報酬は、「基本療養費」と、それに上乗せして算定される「各種加算」で構成されています。
これらを正しく理解し、適切に算定すれば、質の高いケア提供と事業所の経営安定の両立が可能になります。
なかでも加算は、利用者の状態や訪問の頻度、訪問時間帯などに応じて細かく設定されており、1日2回以上の訪問時や緊急対応、24時間体制の整備など、さまざまな場面に応じた評価がされます。
例えば以下のような費用が主な加算です。
| 訪問看護基本療養費 | 1回あたりの基本報酬(例:5,550円~) |
| 難病等複数回訪問加算 | 1日2回訪問で4,500円/日、3回以上で8,000円/日 |
| 夜間・早朝加算/深夜加算 | 時間帯に応じて2,100円または4,200円/回 |
| 緊急訪問看護加算 | 緊急対応を評価(例:月2,650円) |
| 特別管理加算 | 気管カニューレ・点滴管理など(2,500円/5,000円/月) |
| 24時間対応体制加算 | 月6,800円(条件により異なる) |
上記のような加算には、算定回数の制限(1日1回、月1回など)や、届出や記録の要件があるため、ルールを把握しておく必要があります。
複数の訪問看護ステーションを併用している場合には、一部の加算が算定できないこともあるため、事前確認も徹底しましょう。
注意すべき「同一建物居住者減算」とは?
訪問看護では、たとえ別々の利用者を訪問する場合でも、同じ建物内に複数の利用者が住んでいると、報酬が自動的に減額されることがあります。
この仕組みが「同一建物居住者減算」です。
制度上は、訪問先が近距離であれば移動の負担が少ないとされ、看護の内容や時間にかかわらず一律で報酬が調整されるため、現場の実感とズレを感じやすい部分でもあります。
特に、1日に複数回の訪問を行う際や、集合住宅・サービス付き高齢者住宅などを訪れる場合には要注意です。
減算の対象になる主な条件は、以下のとおりです。
- 同一の建物内に住む利用者が3人以上いる場合(医療保険・介護保険共通)
- 訪問時間や看護の内容に関係なく、建物単位で一括して判断される
- 午前と午後で違う利用者を訪問しても、同一建物とみなされ減算される可能性がある
例えば、午前中に101号室のAさん、午後に202号室のBさんを訪問した場合、どちらも「同一建物内の訪問」としてまとめられ、基本療養費が通常よりも少なくなるケースがあります。
現場での労力は変わらないのに、報酬だけが軽く扱われる場合もあるため、請求前に利用者の住居状況を確認しておく必要があります。
減算ルールを正しく理解しておかないと、思わぬ減収や返戻リスクに直結するため、訪問の組み方や記録内容にも意識を向けましょう。
複雑な算定業務を効率化させるポイント

訪問看護の算定業務では、加算・減算ルールや請求制度の複雑さから、人為的ミスや記録のズレによる返戻・減算が起こりやすくなっています。
事業所を複数展開している法人では、現場ごとの算定状況をリアルタイムで把握できていないことで、経営全体に影響するロスも発生しがちです。
そこでここでは、算定ミスの防止や業務の効率化を実現するための実践的なポイントとして、
- 請求と記録を一元管理する重要性
- 複数事業所の訪問状況を可視化する体制の整備
の2つの視点から解説します。
算定ミスを防ぎ、請求と記録を一元管理する
訪問看護の現場では、手作業での請求処理や記録管理が、重大な算定ミスや返戻につながる原因になります。
これは、職員の経験や記憶に頼る業務フローの中で、「訪問件数の誤入力」「加算条件の見落とし」「同じ情報の二重入力」などが起こりやすいからです。
特に、保険請求業務ではほんの小さなミスでもレセプトの差し戻しや減収を招くことがあるため、事業所の収益と信頼性の両面で影響が出かねません。
よくあるミスの例には、以下のようなものが挙げられます。
- 訪問時間の記録漏れや入力誤り
- 同一利用者に対して、加算の重複請求
- 訪問回数や日数のズレによる返戻
- 同じ内容を、記録と請求にそれぞれ別で転記しミスが発生
リスクを回避するには、記録と請求を分離せず、一元管理できる環境が必要です。
日々の業務でのヒューマンエラーを最小限に抑え、正確かつ効率的な運営体制を築くことが、継続的な運用にもつながります。
複数事業所の情報をリアルタイムで把握する
訪問看護を複数拠点で運営している場合、各事業所の請求状況や訪問実績をタイムリーに把握できるかどうかが、経営管理の質につながります。
手作業や個別ファイルで情報を管理していると、集計や確認に時間がかかるだけではなく、「加算の取り漏れ」「訪問件数の把握漏れ」「記録の抜け」など、見落としによる損失が生じるリスクがあります。
リアルタイムで把握できると、以下のようなメリットがあります。
- 各拠点の訪問件数・訪問時間・加算の状況がすぐに確認できる
- 訪問漏れや未入力の記録を早期に発見・対応できる
- 月末にあわてて集計する必要がなくなり、請求ミスや返戻を減らせる
- 担当者が不在でも、他の職員が状況を把握しやすい
情報を集約し、全体の動きを「見える化」すれば、経営判断のスピードも正確さも格段に上がります。
特に複数拠点の運営では、属人化を避け、チーム全体で状況を共有できる体制が必要です。

訪問看護における夜間加算は、スタッフの時間外勤務に対する正当な評価を目的とした重要な仕組みです。特に「夜間・早朝加算」と「深夜加算」は、提供時間帯に応じた加算が設定されており、介護保険・医療保険それぞれに異なるルールがあります。本記事では、夜間加算と緊急加算との違いや、算定条件、計画的訪問の重要性、時間帯をまたぐ訪問の判断基準など、現場で混同しやすいポイントを非常に丁寧に解説しています。加算の取りこぼしや返戻を防ぐには、制度の理解に加え、記録・計画・訪問実績の整合性が不可欠です。また、ICTや介護ソフトを活用した業務効率化も、加算の適正算定や職員負担の軽減に直結します。制度を正しく理解し、現場に即した運用を行うことで、利用者への安心と、スタッフの働きやすさ、経営の安定化を両立することができます。
まとめ|訪問看護医療保険1日2回訪問のルールと対応方法を正しく理解しよう
訪問看護を医療保険で1日に2回行う場合、制度上のルールに基づいた対応が求められます。
「難病等複数回訪問加算」のような算定要件には、医師の明確な指示や利用者の状態の根拠を記録として残すことが必須です。
同一建物内で複数の利用者を訪問する場合、「同一建物居住者減算」の対象となることがあり、時間帯や訪問内容にかかわらず報酬が減額されるケースもあります。
これらの制度は少し複雑に感じるかもしれませんが、あいまいな理解のまま運用してしまうと、返戻や減収といったリスクが生じます。
だからこそ、記録と請求の整合性を保ち、訪問前に利用者の状況や適用ルールを正しく確認しましょう。
制度の意図を正確に捉え、現場で実践できる知識として備えておくことが、安定した運営のためには必要です。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。