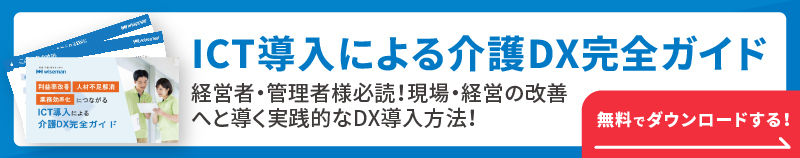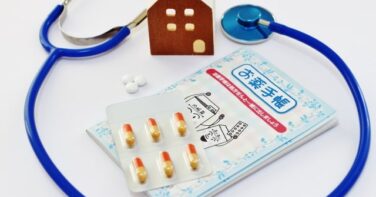訪問看護の人員基準とは|計算方法や違反リスクなどについて解説
2025.08.23

訪問看護ステーションを運営するうえで、人員基準は無視できない法令です。
法令遵守は訪問看護事業の根幹であり、基準を満たせていなければ、行政処分の対象になる恐れがあります。
本記事では、訪問看護ステーションの人員基準について解説します。
また、正確な常勤換算の計算方法や、違反した場合の重大なリスクなど、訪問看護ステーションの運営に不可欠な知識についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
訪問看護の人員基準とは

訪問看護の人員基準とは、利用者に安全で質の高いサービスを提供するために、介護保険法や健康保険法にもとづいて国が定めた、職員の数や資格に関する最低限のルールのことです。
人員基準は、単に法律を守るためだけに存在するわけではありません。
適切な数の専門職を配置することで、すべての利用者に行き届いたケアを提供し、サービスの質を担保する目的があります。
コンプライアンスを遵守することは、行政からの指導やペナルティを回避するだけでなく、利用者やその家族、さらには地域からの信頼を得て、事業を安定的に継続させるための土台です。
参照:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準|厚生労働省
【職種別】訪問看護ステーションの人員基準

訪問看護ステーションを運営するために定められている以下の職種について、それぞれの基準を詳しく見ていきましょう。
- 看護職員
- 管理者
- 理学療法士等(PT/OT/ST)
人員基準は訪問看護ステーションの運営を円滑にするだけでなく、利用者に最適なサービスを提供するうえでも無視できない要素です。
各職種の役割を把握することで、人員基準の意義を理解しやすくなります。
看護職員
人員基準のもっとも中核となるのが、看護サービスの担い手である看護職員の配置です。
看護職員の人員基準は以下のとおりです。
| 職種 | 人員基準 | 備考 |
| 保健師・看護師・准看護師 | 常勤換算で2.5人 以上 | うち1名は常勤であること事業の実情に応じて配置 |
具体的には、保健師や看護師、または准看護師を「常勤換算で2.5人以上」配置することが義務付けられています。
この数字は、事業所に所属する看護職員全員の総労働時間を、常勤職員1人分の労働時間で割って算出します。
このため、常勤職員が1名しかいない場合など、組み合わせによっては最低でも3名以上の看護職員が必要になる点に注意が必要です。
職員の急な退職や長期の休職によって一時的に基準を下回った場合は、速やかにその旨を行政に報告し、人員補充に努めなければなりません。
管理者
管理者は、ステーション全体の運営を統括し、サービスの質を担保する重要な役割を担います。
管理者は原則として、常勤かつ専従の保健師または看護師でなければなりません。
ただし、ステーションの管理業務に支障がない場合に限り、同一法人内の他の事業所の職務との兼務が認められています。
令和6年度の介護報酬改定において、兼務に関する要件が変更されました。詳細については、厚生労働省の関連資料をご確認ください。
介護報酬の改定により、ICTツールなどを活用して適切に管理業務が行えるのであれば、離れた場所にある事業所との兼務も可能になりました。
理学療法士等(PT/OT/ST)
理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)といったリハビリテーションの専門職については、看護職員のように具体的な人数は定められていません。
事業所の実情に応じて「適当数を配置できる」とされています。
しかし、注意が必要なのが、令和6年度の介護報酬改定で導入された減算ルールです。
ステーションからの訪問のうち、看護職員による訪問よりもリハビリ専門職による訪問の割合が著しく高い場合、報酬が減算される可能性があります。
そのため、看護とリハビリのバランスの取れたサービス提供と人員配置が、よりいっそう重要になりました。
常勤換算の計算方法

人員基準を遵守するうえで、常勤換算の計算方法を把握することは重要です。本章では「常勤換算」について、具体的な計算方法をステップごとに解説します。
常勤換算の基本式と計算のポイント
常勤換算は、以下の計算式で算出します。
常勤換算数 = 事業所の全職員の合計勤務時間 ÷ 事業所が定める常勤職員の勤務時間
上記の計算を正確に行うためには、以下の2つのポイントを正しく理解しておくことが重要です。
| 常勤職員の勤務時間を明確にする | まず、自施設の就業規則で「常勤職員が勤務すべき時間数(所定労働時間)」が週に何時間かを明確に定めます(例:週40時間)。これが計算の分母となります。 |
| 全職員の勤務時間を合計する | 常勤職員、非常勤職員(パートタイマー)を問わず、全看護職員の1週間の労働時間を合計します。これが計算の分子です。 |
常勤職員・非常勤職員などといった職員区分は、計算上以下のように扱われます。
| 職員区分 | 計算上の扱い |
| 常勤職員 | 1人としてカウントします。 |
| 非常勤職員 | 「その職員の週の勤務時間 ÷ 常勤職員の週の勤務時間」で計算します。 (例:週20時間勤務の非常勤職員 ÷ 常勤が週40時間 = 0.5人) |
| 育児・介護休業法の時短勤務者 | 勤務時間が短縮されていても、本人が希望すれば「常勤」として扱う特例があります。この場合、1人として計算可能です。 |
【モデルケース別】計算シミュレーション
本章では、具体的なモデルケースを用いて計算方法を見ていきましょう。
なお、本記事の事例では常勤職員の週の勤務時間を「40時間」と仮定します。
ケース1:新規開設のステーション(非常勤中心)
| 職員 | 区分 | 週の勤務時間 |
| スタッフA | 常勤 | 40時間 |
| スタッフB | 非常勤 | 20時間 |
| スタッフC | 非常勤 | 15時間 |
| スタッフD | 非常勤 | 10時間 |
| 合計 | 85時間 |
計算式:(常勤職員の勤務時間) + (非常勤職員の勤務時間合計) ÷ (常勤の勤務時間)
40時間 + (20時間 + 15時間 + 10時間) = 85時間
85時間 ÷ 40時間 = 2.125人
結果:このケースでは常勤換算数が2.125人となり、基準の2.5人を満たしていません。
ケース2:バランスの取れたステーション
| 職員 | 区分 | 週の勤務時間 |
| スタッフA | 常勤 | 40時間 |
| スタッフB | 常勤 | 40時間 |
| スタッフC | 非常勤 | 20時間 |
| スタッフD | 非常勤 | 10時間 |
| 合計 | 110時間 |
計算式:110時間 ÷ 40時間 = 2.75人
結果:常勤換算数は2.75人となり、基準の2.5人を満たしています。
ケース3:パートタイマーが多いステーション
| 職員 | 区分 | 週の勤務時間 |
| スタッフA | 常勤 | 40時間 |
| スタッフB | 非常勤 | 20時間 |
| スタッフC | 非常勤 | 20時間 |
| スタッフD | 非常勤 | 20時間 |
| 合計 | 100時間 |
計算式:100時間 ÷ 40時間 = 2.5人
結果:常勤換算数は2.5人となり、基準をちょうど満たしています。
ただし、誰か一人が急に休んだり退職すると、即座に基準違反となるリスクの高い状態といえます。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
訪問看護における人員基準違反のリスク

人員基準違反は、単なる手続き上のミスでは済まされません。
違反した場合、以下のようなリスクが想定されます。
- 人員基準欠如減算
- 行政指導・指定取り消し
発覚した場合、ステーションの経営に影響する重大なペナルティが科せられます。
本章では、報酬面と行政処分の両面から、その具体的なリスクを解説します。
人員基準欠如減算
人員基準を満たせない状態でサービスを提供し続けると、介護報酬が大幅に減額される人員基準欠如減算が適用されるため注意が必要です。
減算は、人員基準に満たないことが判明した月から、その状態が解消される月まで継続されます。
看護職員の数が基準を下回った場合、人員基準欠如減算が適用され、介護報酬が減額されます。減算率については、最新の介護報酬に関する情報を参照してください。
減算が科せられると、ステーションの収益に直接的な大打撃を与え、経営を著しく圧迫する事態になりかねません。
行政指導・指定取り消し
人員基準違反に対する行政からの対応は、その悪質性や改善状況に応じて段階的に厳しくなります。
以下の表をご覧ください。
| 処分段階 | 内容 |
| ① 指導 | 口頭または書面で改善を促されます。多くの場合は、まずこの段階で改善計画書の提出を求められます。 |
| ② 勧告 | 指導に従わない場合、期限を定めて改善するよう勧告されます。この内容は公表される可能性があります。 |
| ③ 命令 | 勧告にも従わない場合、業務改善命令や人員増強命令が出されます。命令違反には罰則が伴います。 |
| ④ 指定の効力停止 | 悪質な違反や命令無視が続くと、一定期間、介護保険事業を行うことができなくなります。事実上の営業停止です。 |
| ⑤ 指定取り消し | もっとも重い処分です。虚偽の報告など悪質性が極めて高いと判断された場合、訪問看護ステーションとしての指定そのものが取り消され、事業を廃止せざるを得なくなります。 |
特に、過去には人員基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の勤務表を作成して不正に報酬を請求するような行為は、指定取り消し処分を受けるリスクが高まります。
人員基準違反の隠蔽によって一度失った信頼を回復するのは極めて困難です。
最悪の場合、事業の継続が不可能になることに留意しましょう。
人員基準を遵守する際のポイント

人員基準を遵守する際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 人材の定着率を高める
- 採用の方法を工夫する
- ICT化を推進する
本章では、人員基準の遵守だけでなく、訪問看護ステーションの人材確保の観点からも解説します。
人材の定着率を高める
看護師不足は業界全体の課題ですが、工夫次第で人材を確保し、定着率を高められます。
人材の定着率を高めるためには、以下の施策を実践することが効果的です。
| 柔軟な働き方の実現 | 非常勤・短時間勤務・オンコール体制の工夫など、多様な働き方を可能にすることで、子育て世代や経験豊富なベテラン層など、幅広い人材を惹きつけます。 |
| チームワークの重視 | スタッフ間の連携を強化し、互いにサポートし合える温かい職場環境を構築します。定期的なミーティングや研修、懇親会などを実施し、コミュニケーションを促進しましょう。 |
| キャリアパスの提示 | 経験に応じた昇進制度や研修制度を設け、キャリアアップを支援することで、長期的な定着を促します。認定看護師や専門看護師の資格取得支援も有効です。 |
| 継続的な人材育成 | 新人の訪問看護師に対しては、経験豊富な看護師による丁寧なOJTを実施し、訪問看護の基礎知識やスキルを習得させます。 |
| 外部研修の活用 | 地域の研修機関や学会などが主催する研修に積極的に参加させ、最新の知識や技術を習得する機会を提供します。 |
| メンター制度の導入 | 新人看護師に対して、メンターとなる先輩看護師を配置し、精神的なサポートを行うことで、不安を軽減し、早期離職を防ぎます。 |
上記のポイントを踏まえ、訪問看護ステーションの規模や地域特性に合わせた体制を整えることが重要です。
給与や福利厚生の充実を図り、キャリアアップ支援制度を設けることで、優秀な人材を引きつけられます。
また、都市部では柔軟な働き方を支援する制度(時短勤務・テレワークなど)を導入し、地方では住宅手当や通勤手当を充実させるなど、地域特性に合わせた待遇改善も有効です。
採用の方法を工夫する
訪問看護ステーションの人材採用を工夫することも、人員基準を遵守するうえで不可欠な要素です。
人材の採用は、以下のポイントを意識しましょう。
| ステップ | 内容 |
| 求める人物像の明確化 | ステーションの理念やビジョン、提供するサービス内容を考慮し、どのようなスキル・経験・価値観を持つ人材を求めているのか明確にする必要があります。必要な資格(看護師・理学療法士など)・臨床経験・コミュニケーション能力・運転免許の有無などを定義しましょう。特に訪問看護は利用者宅での個別ケアとなるため、自律性・判断力・問題解決能力が重要となります。 |
| 効果的な求人活動 | 求人媒体の選定は、ターゲット層に合わせたものが重要です。看護師専門の求人サイト・地域の医療機関との連携・ハローワーク・人材紹介会社などを活用しましょう。求人広告には、ステーションの魅力(働きがい・キャリアパス・福利厚生など)を具体的に記載し、応募者の興味を引くように工夫します。また、SNSを活用した情報発信も有効です。 |
| 面接・選考の徹底 | 面接では、応募者のスキルや経験だけでなく、人柄や価値観も重視します。訪問看護における倫理観や責任感、利用者への共感力などを確認するため、具体的な事例に基づいた質問をすると効果的です。必要に応じて、適性検査や実技試験を実施し、客観的な評価を行います。採用決定前に、必ずリファレンスチェックを行い、応募者の過去の勤務状況を確認しましょう。 |
| 入職後のサポート体制 | 採用した人材が長く活躍できるよう、入職後のサポート体制を充実させることが重要です。OJTによる丁寧な指導や研修制度、定期的な面談などを実施し、スキルアップやキャリア形成を支援します。また、チームワークを重視し、相談しやすい雰囲気づくりを心がけることで、離職率の低下につながります。 |
| 労働条件の明確化 | 給与・勤務時間・休日・福利厚生などの労働条件を明確に提示し、誤解がないようにします。訪問看護は移動時間が長くなるため、移動手当や車両の使用に関する規定も明確にしておきましょう。働きやすい環境を提供することで、優秀な人材の確保・定着につながります。 |
ICT化を推進する
ICT化の推進は人員基準の遵守につながる施策です。
日々の業務に追われる中で、人員配置の最適化や書類作成に多くの時間を費やしている事業所は少なくありません。
訪問看護の業務に役立つシステムを導入することは、こうした課題を解決し、間接的に人員基準の遵守を支える強力な一手となります。
ただし、ICT化は闇雲に実施しても効果がありません。
ICT化を進める際は、以下のように取り組みましょう。
| 導入前の課題 | ICT導入による解決策 | 導入後の効果 |
| 訪問後の記録作成に時間がかかる | タブレットで訪問先で記録を完結 | 事務所での残業時間が大幅に削減 |
| スタッフ間の情報共有が不足 | クラウド上でリアルタイムに情報共有 | 緊急時も迅速・的確な対応が可能に |
| シフト作成や人員配置が煩雑 | 勤務状況をデータで可視化・分析 | 常勤換算の計算が容易になり、人員不足を未然に防止 |
上記の取り組みを通じて創出された時間は、新たな訪問件数の確保・職員の研修・利用者と向き合う時間の増加にあてられます。
ICT化は、単なる業務効率化ツールではなく、職員の負担を軽減し定着率を高め、結果として質の高いサービス提供と安定した経営を実現するための戦略的な投資です。

この記事では、訪問看護ステーションの人員基準が、単なる法令遵守を超え、質の高いサービス提供と事業の安定継続に不可欠な基盤であることが明確に解説されています。特に、看護職員の常勤換算2.5人以上という中核基準に加え、管理者配置や理学療法士等とのバランスの重要性も示されており、経営の要諦を突いています。基準違反がもたらす介護報酬の減算や指定取り消しといった重大なリスクについても詳細に触れられており、その影響の大きさを再認識させられます。こうしたリスクを回避し、持続的な事業運営を実現するためには、人材の定着率向上や採用方法の工夫、そしてICT化推進による業務効率化が不可欠であるという提言は、非常に示唆に富んでいます。本記事を参考に、貴ステーションの安定運営と利用者様への質の高いケア提供に向けた体制強化を推進されることを期待いたします。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
訪問看護ステーションの運営には人員基準の遵守が不可欠

人員基準は、事業運営における単なるルールではなく、利用者に安全で質の高いケアを届け、地域からの信頼を得るための基盤です。
法令を正しく理解し、常に遵守することは、訪問看護ステーションの経営者や管理者のもっとも重要な責務です。
人材定着への取り組みやICT化の推進など、先を見据えた対策を講じることで、安定して基準を遵守できます。
職場環境の整備や業務プロセスの見直しを行い、人員基準を遵守できる体制を整えましょう。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。