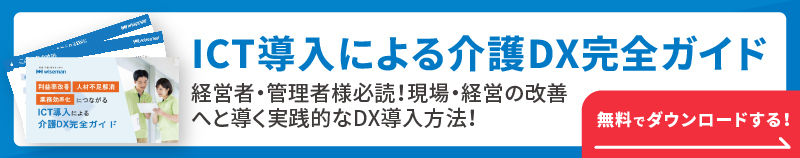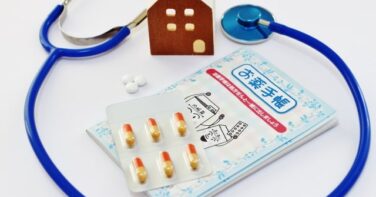訪問看護とケアマネが連携する重要性|役割の違いなどを解説
2025.08.11

訪問看護とケアマネージャーの連携は、より良いサービスを提供するうえで不可欠な取り組みです。
しかし、訪問看護とケアマネージャーの連携はさまざまな点に配慮して実施する必要があります。
本記事では、訪問看護師とケアマネの役割の違いを明確にし、日々の業務を円滑に進めるための具体的な連携方法を解説します。
さらに、信頼関係を築き、ステーションの発展にもつながる営業のポイントを伝えるので、ぜひ参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
訪問看護とケアマネージャーの連携が重要な理由

在宅医療の現場において、訪問看護師とケアマネージャーの連携は、質の高いケアを提供するうえで非常に重要な要素です。
両者が持つ専門性を活かし、利用者の情報を密に共有することで、変化に迅速に対応し、最適なサービスを途切れることなく提供できます。
両者の連携が円滑に行われることで、利用者は心身ともに安定した在宅療養生活を送れます。
また、専門職にとっても、業務の効率化や精神的な負担の軽減につながるなど、多くのメリットが生まれるのです。
訪問看護とケアマネージャーの役割とは

訪問看護師とケアマネージャーは、どちらも在宅で療養する利用者を支える専門職ですが、その役割と専門性は異なるものです。
連携を深める第一歩は、お互いの役割を正確に理解することから始まります。
本章では、それぞれの役割と、両者がどのように協働関係を築くべきかを解説します。
訪問看護師の役割
訪問看護師は、医師の指示に基づき、利用者の自宅で専門的な医療ケアを提供する役割を担います。
主な業務内容は以下のとおりです。
- 病状の観察と管理(バイタルチェック・症状のアセスメントなど)
- 医師の指示に基づく医療処置(点滴・インスリン注射・創傷処置など)
- 服薬管理と指導
- 身体の清拭や入浴介助などの清潔ケア
- リハビリテーションの実施と指導
- ターミナルケア(看取り)
- 利用者や家族からの相談対応・精神的なサポート
訪問看護師は、ケアマネージャーが作成したケアプランに基づきながら、医療の専門家として利用者の日々の健康を守り、療養生活を直接的に支える存在です。
ケアマネージャーの役割
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険サービスを利用する際の総合的な窓口となり、ケアプランを作成・管理する専門職です。
利用者が自立した日常生活を送れるよう、多角的な視点から支援を設計します。
主な役割は以下のとおりです。
- 利用者や家族との面談(インテーク)
- アセスメント(課題分析)とニーズの把握
- ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成
- サービス担当者会議の開催
- 訪問看護を含む各サービス事業者との連絡・調整
- モニタリング(サービスの実施状況や効果の評価)とプランの見直し
- 給付管理(サービス費用の計算)
ケアマネージャーは、利用者の生活全体を見渡し、必要なサービスを組み合わせる「司令塔」のような役割を担っています。
医療と介護をつなぐ「協働関係」の重要性
訪問看護師とケアマネージャーは、決して上下関係ではありません。
それぞれの専門性を持ち寄り、利用者を支える対等なパートナー、つまり「協働関係」にあります。
この関係性が、質の高い在宅ケアの基盤となります。
両者の役割はそれぞれ以下のとおりです。
| 視点 | 訪問看護師 | ケアマネージャー |
| 主な役割 | 医療的ケアの提供・健康管理 | ケアプランの作成・サービス調整 |
| 専門性 | 看護・医療 | 介護保険制度・福祉・多職種連携 |
| 関わりの中心 | 利用者の「療養」生活 | 利用者の「地域での暮らし」全体 |
| 法的根拠 | 医師の指示書 | ケアプラン |
上記のように、異なる専門性を持つ両者が情報を共有し、同じ目標に向かって協力することで、利用者に最適なケアが実現します。
訪問看護とケアマネージャーが連携するメリット

訪問看護とケアマネが円滑に連携すれば、利用者・訪問看護ステーション・ケアマネージャーに以下のメリットが期待できます。
- サービスの充実
- 利用者の確保
- 利用者満足度の向上
- 多職種連携の強化
良好な関係は、単に業務がスムーズになるだけでなく、質の高いサービスの提供や事業所の成長にも直結するものです。
サービスの充実
訪問看護ステーションとケアマネージャーの連携はサービスの充実に貢献します。
訪問看護師からの専門的な医療情報や、日々の細かな変化の報告は、ケアマネージャーがケアプランを最適化するうえで極めて重要な情報源です。
これらの情報に基づき、利用者の状態やニーズの変化に迅速かつ適切に対応したケアプランの見直しが可能となります。
例えば、服薬状況の変化・創傷の状態・精神的な落ち込みなど、訪問看護師ならではの視点から得られる情報はケアマネージャーが利用者全体の状態を把握し、多角的な視点からケアプランを検討するうえで不可欠です。
適切な情報共有を行えば、利用者の状態に即した、より個別化された質の高いサービス提供が実現します。
その結果、利用者のADL(日常生活動作)の維持・向上を促すだけでなく、合併症の予防も可能です。
結果として、利用者のQOL(生活の質)向上に直接つながり、より豊かな生活を送るサポートになります。
利用者の確保
ケアマネージャーによる利用者の確保は、訪問看護ステーションの経営安定化に不可欠な要素です。
なぜなら、ケアマネージャーは利用者が利用する訪問看護ステーションを決定するうえで非常に重要な立場にあるからです。
したがって、日ごろからケアマネージャーとの密な連携を心がけ、強固な信頼関係を築くことが重要となります。
具体的には、「あのステーションは報告が迅速で丁寧だ」「難しいケースでも親身に相談に乗ってくれる」といった評価を得られるよう、質の高いサービス提供を徹底することが求められます。
質の高いサービスと迅速な情報共有は、ケアマネージャーからの信頼獲得につながり、結果として新たな利用者の紹介へとつながる可能性を高める取り組みです。
また、定期的な情報交換会や勉強会などを開催し、ケアマネージャーとのコミュニケーションを深めることも有効です。
積極的に情報発信を行い、自ステーションの強みや特徴を理解してもらうことで、よりスムーズな連携体制を構築し、利用者の紹介を促進することが期待できます。
利用者の満足度向上
訪問看護ステーションとケアマネージャーの緊密な連携は、利用者とその家族の満足度を大きく左右する重要な要素です。
医療と介護の専門家が互いに協力し、シームレスな連携体制を構築することで、利用者様は一貫性のある、質の高いサービスを享受できます。
訪問看護ステーションは利用者の状態に関する情報をケアマネージャーに共有し、互いの専門知識を生かして最適なケアプランを作成することが重要です。
例えば、訪問看護師が医療的な視点から助言を行い、ケアマネージャーが生活全般のニーズを考慮することで、より包括的なサポートが実現します。
両者の連携により、利用者は「自分のことをしっかり見てもらえている」と感じるうえに、情報共有の漏れや手続きの遅延といったトラブルも未然に防止できます。
取り組みが成功すれば、サービス全体への満足度が向上し、口コミによる良い評判へとつながります。
良い評判は新たな利用者を獲得し、訪問看護ステーションの事業を拡大するうえで不可欠な要素です。
訪問看護ステーションは、ケアマネージャーとの連携を積極的に推進し、利用者にとってより質の高いサービスを提供できるよう努めましょう。
多職種連携の強化
多職種連携の強化は、訪問看護とケアマネージャーの連携における重要なメリットです。
訪問看護師とケアマネージャーの連携は、単に両者の情報共有に留まらず、医師・リハビリ専門職・薬剤師・ヘルパーなど、多岐にわたる専門職との連携を促進するハブとしての役割を果たします。
訪問看護師は、利用者の状態を詳細に観察し、ケアマネージャーは、利用者のニーズを総合的に把握します。
両者が緊密に連携することで、それぞれの専門分野からの見識を組み合わせられるため、より質の高いケアプランの作成が可能です。
例えば、訪問看護師が利用者の服薬状況や体調の変化をケアマネージャーに迅速に伝えることで、ケアマネージャーは医師への相談や、必要に応じて薬剤師との連携をスムーズに実行できます。
また、リハビリ専門職からの情報も共有することで、より効果的なリハビリテーション計画の立案につながります。
さらにヘルパーからの生活状況に関する情報も加えることで、より包括的な支援体制の構築が可能です。
このように、訪問看護師とケアマネージャーが中心となって情報を整理・共有することで、チーム全体での支援体制が強化され、より包括的で、きめ細やかなケアが実現します。
結果として、利用者のQOL(生活の質)向上に大きく貢献することが期待できます。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
訪問看護とケアマネージャーの連携を強化する際のポイント

訪問看護とケアマネージャーの連携強化のポイントは以下のとおりです。
- 情報共有を徹底する
- コミュニケーションのタイミングを意識する
- 顔合わせの機会を設ける
上記のような工夫と配慮を重ねることが、ケアマネとの強い信頼関係につながります。
情報共有を徹底する
質の高い連携の基本は、正確かつタイムリーな情報共有です。
ケアマネージャーは、訪問看護師からの客観的な情報をもとにケアプランの評価や見直しを行います。
以下のような情報は、特に重要視されます。
| 情報 | 詳細 |
| 利用者の状態変化 | 病状・ADL(日常生活動作)・認知機能・食事や水分の摂取量・排泄状況など |
| 家族の状況・意向の変化 | 介護者の健康状態・介護負担感・サービスに対する要望など |
| 医療的な情報 | 医師からの指示変更・処方薬の変更・検査データなど |
| インフォーマルな情報 | 利用者の発言・表情・生活上の小さな変化など |
上記の情報を、電話や報告書を通じて具体的かつわかりやすく伝えることが、信頼関係構築の第一歩です。
コミュニケーションのタイミングを意識する
ケアマネージャーとのコミュニケーションのタイミングも意識しましょう。
ケアマネージャーは多くの利用者を担当しており、多忙を極めています。
連絡する際は、相手の状況を考慮したタイミングと方法を選ぶ配慮が重要です。
ケアマネージャーへの連絡方法には以下のようなものがあります。
| 連絡方法 | 最適な利用シーン |
| 電話 | 利用者の状態急変時・緊急の相談や確認 |
| FAX/メール | 定期報告・サービス担当者会議の日程調整 |
| 連絡ノート | ヘルパーなど他職種との情報共有 |
| ICTツール | 日々の細かな情報共有・写真や動画の共有 |
上記の方法でも、ケアマネージャーへ電話をする際は時間帯に注意しましょう。
「午前中の早い時間帯や夕方は避ける」「要点をまとめて手短に話す」といった配慮が、良好な関係を築くうえで効果的です。
顔合わせの機会を設ける
日々の連絡は電話や書面が中心になりがちですが、直接顔を合わせる機会は非常に重要です。
サービス担当者会議や退院時カンファレンスなどは、お互いの人柄や考え方を知る絶好の機会となります。
定期的にステーションに訪問して情報提供を行うなど、意識的に「顔の見える関係」を作る努力が、いざという時のスムーズな連携につながります。
雑談の過程で、ケアマネージャーが抱える悩みやニーズが聞けることも少なくありません。
訪問看護ステーションがケアマネを営業する際のポイント

本章では、訪問看護ステーションがケアマネを営業する際のポイントを解説します。
重要なポイントは以下のとおりです。
- 利用者に寄り添ったアプローチを行う
- 提供するサービスの付加価値を考慮する
- 現場との信頼関係を構築する
- 継続的な連携を心がける
- フォローアップやフィードバックを欠かさない
訪問看護ステーションがケアマネを営業する場合、単にパンフレットを配るだけでは効果は期待できません。
本章で紹介するポイントを理解し、適切な営業を実践しましょう。
利用者に寄り添ったアプローチを行う
ケアマネを営業するうえで、もっとも重視すべきポイントは利用者に寄り添ったアプローチを行うことです。
営業の際は、訪問看護ステーションの実績や規模をアピールするだけでなく、利用者にどのように寄り添い、どのようなケアを提供したいのかを理解してもらう必要があります。
利用者やその家族の相談に親身に乗るなど、パートナーとしての姿勢を示しましょう。
提供するサービスの付加価値を考慮する
ケアプランの作成を通じて自ステーションを利用者に選んでもらうためには、サービスの付加価値を明確に伝える必要があります。
例えば、以下のような点が強みになります。
| 特徴 | 詳細 |
| 対応領域の専門性 | 精神科・小児・難病・ターミナルケアなど |
| 専門職の在籍 | 認定看護師・専門看護師・リハビリ専門職(PT/OT/ST)など |
| 24時間対応体制 | 緊急時の迅速な対応力 |
| 他機関との連携力 | 近隣の医療機関や施設との密な関係 |
| 独自の取り組み | 家族会や勉強会の開催、最新のICT機器導入など |
上記のような強みを分かりやすくまとめた資料を用意し、ケアマネのニーズに合わせて的確にアピールしましょう。
現場との信頼関係を構築する
営業担当者だけでなく、実際に訪問する看護師の対応が、ステーション全体の評価につながります。
日々の利用者への丁寧なケアはもちろん、迅速で誠実な報告・連絡・相談が訪問看護ステーションの信頼を維持する最大の営業活動です。
現場の看護師と営業担当者が連携し、ステーション全体で現場との信頼関係を築く意識を持つことが大切です。
継続的な連携を心がける
訪問看護ステーションとケアマネージャーは継続的な連携を維持する必要があります。
ケアマネージャーと常に連携し、情報を共有できる体制を構築することで、利用者のサービスを常に最適化できます。
定期的に訪問して情報交換を行ったり、ステーションの空き状況を共有したりと、継続的な情報交換を行うことが重要です。
継続的な連携を維持することで、利用者の容体の急変やニーズの変化にも対応しやすくなります。
フォローアップやフィードバックを欠かさない
利用者へのフォローアップやフィードバックは不可欠な取り組みです。
ケアの状況や利用者の変化を定期的にケアマネージャーにフォローアップすることで、安心感と信頼感を与えられます。
また、「私たちの連携について何か改善すべき点はありますか?」と謙虚にフィードバックを求める姿勢も、訪問看護ステーションの評価を向上するうえで重要です。

この記事は、在宅医療を支える両者の不可欠な協働関係を深く掘り下げ、役割の明確化から具体的な連携手法、そして事業運営上の多大なメリットまで、すべて解説されています。特に、訪問看護師からの専門的な医療情報や日々の細かな変化の報告が、ケアマネージャーによるケアプランの最適化にいかに貢献するか、またその連携が利用者のQOL向上、ひいては訪問看護ステーションの信頼獲得と利用者確保に直結する点が丁寧に述べられています。
情報共有の徹底、適切なコミュニケーションのタイミング、顔の見える関係構築といった実践的なポイントは、現場の専門職の皆様にとってすぐに役立つと思われます。さらに、多職種連携のハブとしての役割や、利用者に寄り添ったアプローチ、サービスの付加価値を明確にする営業戦略、継続的な連携の重要性も言及されており、皆様の質の高い在宅ケア実現に大いに参考にして頂けると思います。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
質の高い在宅ケアは訪問看護とケアマネの強い信頼関係から生まれる

本記事では、訪問看護師とケアマネージャーの役割の違いや、日々の連携を強化する具体的なポイントなどについて解説しました。
両者の連携は役割の相互理解・効果的なコミュニケーション・継続的な協働関係によって成立します。
訪問看護師とケアマネージャーが強い信頼関係で結ばれるとき、単なる業務の円滑化に留まりません。
医療と介護が真に一体となり、利用者に寄り添った最高品質の在宅ケアが実現します。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。