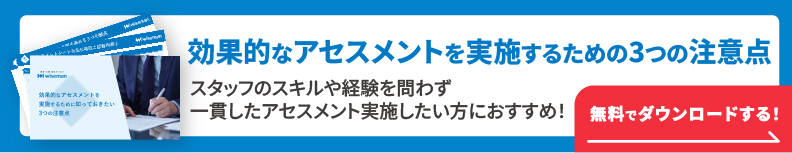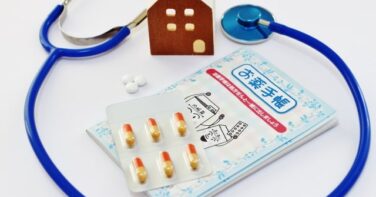訪問看護におけるケアプラン|文例や作成のポイントなどを解説
2025.08.11

初めて訪問看護を導入するケアプランを作成する際、書き方に悩む方は少なくありません。
訪問看護のケアプランは医療的な視点が必要になるため、訪問介護のプランとは異なる難しさがあります。
本記事では、訪問看護のケアプランの基礎知識・作成手順・そのまま使える文例までを解説します。
利用者にとって最適なケアプランを作成するうえでもぜひ参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
アセスメントシートを記載する上で知っておきたい3つの観点を記載しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
訪問看護とケアプランの関係性

在宅療養を支えるうえで、訪問看護とケアプランは密接な関係にあります。
まず、それぞれの役割と関係性を正しく理解しましょう。
訪問看護におけるケアプランとは
訪問看護におけるケアプランとは、正式には「介護サービス計画書」のことを指します。
これはケアマネジャーが作成するもので、利用者が在宅で自立した生活を送るために必要な介護サービス全体を計画する、いわば「在宅療養の設計図」です。
訪問看護は、この設計図に位置づけられる重要なサービスの一種です。
訪問看護のケアプランの構成
ケアプランは主に3つの様式で構成されています。
それぞれの役割を理解しておきましょう。
| 様式 | 名称 | 主な内容 |
| 第1表 | 居宅サービス計画書(1) | 利用者や家族の意向、総合的な援助の方針など、プラン全体の基本方針を記載します。 |
| 第2表 | 居宅サービス計画書(2) | 生活全般の解決すべき課題(ニーズ)・長期目標・短期目標・具体的なサービス内容と種別を記載する、ケアプランの中心部分です。 |
| 第3表 | 週間サービス計画表 | 第2表で計画したサービスを、1週間のどの曜日・時間帯に利用するかを具体的に示したスケジュール表です。 |
なお、本記事では特に訪問看護の具体的な内容を記述する「第2表」の書き方を中心に解説していきます。
ケアプランと訪問看護計画書の違い
ケアプランと混同されやすいものに「訪問看護計画書」があります。
それぞれ作成者も目的も異なるため、違いを明確に理解しておくことが重要です。
ケアプランと訪問看護計画書の違いは以下のとおりです。
| 項目 | ケアプラン(居宅サービス計画書) | 訪問看護計画書 |
| 作成者 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー | 訪問看護ステーションの看護師 |
| 目的 | 利用者の生活全体の課題解決と自立支援 | 医師の指示に基づく具体的な看護の実践 |
| 法的根拠 | 介護保険法 | 介護保険法・健康保険法 |
| 主な内容 | 生活全体のニーズ・目標・利用するサービスの種類や頻度など、包括的な計画 | 病状観察・医療処置・リハビリなど、専門的な看護ケアの詳細な計画 |
まず、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、訪問看護の必要性が判断されます。
その後、作成したケアプランの内容を受けて、訪問看護師がより専門的で具体的な訪問看護計画書を作成する流れです。
両者はサービス担当者会議などを通じて密に連携し、利用者の状態変化に柔軟に対応していくことが求められます。
訪問看護の保険適用ルール
訪問看護は介護保険と医療保険のいずれかを利用できますが、どちらが適用されるかは利用者の状況によって決まります。
ケアマネジャーとして、このルールを正確に理解しておくことは非常に重要です。
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
| 対象者 | ・年齢制限なし ・厚生労働大臣が定める疾病等の該当者 ・要介護や要支援でも、急性増悪期や退院直後など、特別な指示期間にある方 | ・65歳以上の要介護や要支援(第1号被保険者) ・40~64歳で特定疾病により要介護や要支援の認定を受けた方(第2号被保険者) |
| 指示書 | 主治医からの「訪問看護指示書」が必須 | ケアプランに基づき、主治医が「訪問看護指示書」を発行 |
| 利用の流れ | 主治医・訪問看護ステーションに相談 → 契約 → 開始 | 要介護認定申請 → ケアプラン作成 → 契約 → 開始 |
| 費用負担 | 1~3割(年齢や所得による) | 1~3割(所得による) |
| 利用制限 | 原則週3回まで(病状により例外あり) | ケアプランの支給限度額内での利用 |
| 特徴 | 医療的ケアの必要性が高い場合に利用 | 生活支援と医療的ケアの両面からサポート |
原則として、要介護・要支援認定を受けている利用者は介護保険が優先されます。
しかし、がん末期や難病などの厚生労働大臣が定める疾病などに該当する場合や、病状が急激に悪化した場合は、医療保険での訪問看護が適用されることがあります。
判断に迷う場合は、主治医や訪問看護ステーションに確認しましょう。
訪問看護のケアプラン第2表の作成手順

ここからは、実際に訪問看護を位置づけるケアプラン第2表を作成する手順を以下のフェーズに分けて解説します。
- アセスメント
- 課題分析(ニーズの把握)
- 目標設定
- サービス内容の検討
- モニタリングと再評価
上記の流れに沿って進めることで、質の高いケアプランを作成できます。
アセスメント
質の高いケアプランは、質の高いアセスメントから始まります。
訪問看護の導入を検討する場合、特に医療的な視点での情報収集が不可欠です。
アセスメントの際は、以下の作業を実施しましょう。
| 情報源 | 詳細 |
| 主治医からの情報収集 | 診療情報提供書や訪問看護指示書から、病名・病状・治療内容・今後の見通しを正確に把握します。特に、禁忌事項や緊急時の対応方針は必ず確認しましょう。 |
| 本人・家族からのヒアリング | 現在の症状(痛み・息苦しさ・だるさなど)や生活での困りごとを具体的に聴き取ります。服薬状況、食事・排泄の状況、睡眠パターンなども重要な情報です。「今後どのように暮らしたいか」など本人の意向や価値観を丁寧に確認します。 |
| 多職種からの情報収集 | すでにほかのサービスを利用している場合、訪問介護員やデイサービスのスタッフからの情報も参考にします。 |
課題分析(ニーズの把握)
アセスメントで収集した情報を整理し、利用者が抱える「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を明確にします。
課題を「ADL/IADLに関する課題」と「医療的な管理・処置に関する課題」に分けて考えると整理しやすくなります。
| 課題の分類 | 具体例 |
| ADL/IADLに関する課題 | ・一人での入浴に転倒のリスクがある ・食事の準備が困難になってきた ・薬の飲み忘れが多い |
| 医療的な管理・処置に関する課題 | ・血圧や血糖値が不安定で、専門的な管理が必要・褥瘡(床ずれ)が悪化しないよう処置が必要 ・点滴やカテーテルの管理が必要 |
課題をリストアップしたら、利用者や家族の希望を踏まえ、優先順位をつけてケアプランに反映させましょう。
目標設定
課題が明確になったら、解決するための目標を設定します。
目標は、利用者の意欲を引き出す具体的で達成可能なものであることが重要です。
| 目標の種類 | 説明 | 例 |
| 長期目標 | 最終的に目指す状態を、利用者がイメージしやすい言葉で設定します。 | 「自宅で安心して穏やかに生活を実現する」 |
| 短期目標 | 長期目標を達成するための、数ヵ月単位で達成可能な具体的なステップを設定します。 | 「血圧が安定し、体調変化に自分で気づけるようになる」「転倒することなく、安全に入浴ができるようになる」 |
サービス内容の検討
設定した短期目標を達成するために、訪問看護師にどのようなサービスを提供してもらうかを具体的に記述します。
「誰が」「何を」「どのように」行うのかが明確にわかるように書きましょう。
- 良い例:「安定した血圧を維持するため、週2回看護師が訪問し、血圧測定と体調確認を行い、異常があれば主治医へ報告する。」
- 悪い例:「健康管理」
訪問看護で依頼できること・できないことを正しく理解し、適切なサービス内容を記載することが、訪問看護師とのスムーズな連携につながります。
モニタリングと再評価
ケアプランは一度作成したら終わりではありません。
定期的に利用者の自宅を訪問(モニタリング)し、計画に沿ってサービスが提供されているか、目標の達成状況はどうかなどを確認します。
訪問看護師から提出される「訪問看護報告書」は、利用者の状態を知るための重要な情報源です。
報告書の内容をよく確認し、ケアマネジャー自身のモニタリング結果と合わせて評価を行い、必要に応じてプランの見直し(再評価)を行いましょう。
このPDCAサイクルを回すことが、ケアの質の向上につながります。
なお、新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方に向けて、「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
訪問看護ケアプラン第2表の文例集

ここでは、ケアマネジャーが現場でよく直面するニーズ・目的別に、ケアプラン第2表の文例を紹介します。
「ニーズ」「長期目標」「短期目標」「サービス内容」をセットで記載しているので、ぜひ参考にしてください。
全身状態の観察・健康管理
| 項目 | 文例 |
| ニーズ | 高血圧があり、脳梗塞の再発が心配。体調の変化に早く気づき、安心して自宅で生活を続けたい。 |
| 長期目標 | 病状が悪化することなく、安定した在宅生活を継続できる。 |
| 短期目標 | 自身の血圧の正常値を理解し、体調変化のサインに気づける。(3ヵ月) |
| サービス内容 | 看護師が週1回訪問し、血圧・脈拍・体温等の測定と全身状態の観察を行う。測定値や体調の変化を記録し、本人・家族に説明するとともに、異常時は速やかに主治医へ報告する。 |
測定した数値を本人と一緒に確認したり、どのような時に連絡すべきかを具体的に伝えたりするなど、利用者のセルフケアの意識を高めることが重要です。
医療処置・カテーテル管理
| 項目 | 文例 |
| ニーズ | 仙骨部に褥瘡(床ずれ)があり、悪化させずに治したい。家族だけでは処置の方法が分からず不安。 |
| 長期目標 | 褥瘡が治癒し、皮膚トラブルなく過ごすことができる。 |
| 短期目標 | 褥瘡が悪化することなく、感染兆候が見られない。 |
| サービス内容 | 看護師が週2回訪問し、主治医の指示に基づき褥瘡部の洗浄・薬剤塗布・ドレッシング交換を行う。また、皮膚の状態を観察し、体圧分散の工夫(体位交換、クッションの使用)について家族へ助言する。 |
上記の例の場合、処置だけでなく、栄養状態の改善や体圧分散も重要です。
必要に応じて、管理栄養士による栄養指導(居宅療養管理指導)や、福祉用具(エアマットレスなど)の導入も併せて検討しましょう。
日常生活動作(ADL)の維持・向上
| 項目 | 文例 |
| ニーズ | 脳梗塞後遺症による右片麻痺があり、リハビリをして少しでも歩けるようになりたい。安全にトイレに行けるようになりたい。 |
| 長期目標 | 自宅内での生活範囲が広がり、意欲的に毎日を過ごせる。 |
| 短期目標 | 杖と手すりを使って、日中はポータブルトイレまで安全に移動できる。(3ヵ月) |
| サービス内容 | 看護師または理学療法士が週2回訪問し、主治医の指示とケアプランに基づき、関節可動域訓練や筋力トレーニング、歩行訓練等のリハビリテーションを行う。また、安全な移乗動作や福祉用具の活用方法について本人・家族に指導する。 |
リハビリの目標は、利用者の「できるようになりたいこと」に焦点を当てることが大切です。
訪問リハビリの専門職と連携し、具体的な動作目標を設定すると、評価がしやすくなります。
認知症・精神面のケア
| 項目 | 文例 |
| ニーズ | 認知症があり、夕方になると不安が強くなり落ち着かなくなる。薬の管理も自分でできず、家族が困っている。 |
| 長期目標 | 不安な気持ちが軽減され、自宅で穏やかに過ごせる時間が増える。 |
| 短期目標 | 夕方の不安な時間帯に、興奮することなく落ち着いて過ごすことができる。 |
| サービス内容 | 看護師が週3回、特に不安が強くなる夕方に訪問し、穏やかに傾聴することで精神的な安定を図る。また、主治医の指示に基づき服薬の管理・支援を行うとともに、家族の介護負担に関する相談に応じ、適切な対応方法を助言する。 |
認知症の利用者へのケアでは、本人の言動の背景にある思いを理解しようとする姿勢が重要です。
看護師には傾聴や回想法など、専門的なコミュニケーション技術を用いた関わりを依頼します。
家族の介護負担軽減のため、デイサービスやショートステイの利用も検討しましょう。
終末期ケア(ターミナルケア)
| 項目 | 文例 |
| ニーズ | がん末期であり、住み慣れた自宅で、家族と穏やかな最期の時間を過ごしたい。痛みなどの苦痛はできるだけ和らげてほしい。 |
| 長期目標 | 身体的・精神的苦痛が緩和され、安楽に最期まで自分らしく過ごすことができる。 |
| 短期目標 | 痛みを感じることなく、夜間に安眠できる。 |
| サービス内容 | 24時間対応体制の訪問看護ステーションと連携し、看護師が必要に応じて訪問する。主治医の指示に基づき、疼痛コントロール(麻薬の管理等)・全身状態の観察・安楽な体位の工夫・身体の清拭などを行う。本人・家族の不安や思いに寄り添い、精神的な支援を行う。 |
ターミナルケアでは、利用者と家族の意思決定を最大限に尊重します。
主治医・訪問看護師と密に連携を取り、病状の変化に迅速に対応できる体制を整えることが不可欠です。
看取りの体制について、事前に本人・家族と話し合い、その意向を関係者全員で共有しておきましょう。
家族支援・介護指導
| 項目 | 文例 |
| ニーズ | 医療的ケア(痰の吸引)が必要な夫を在宅で介護しているが、吸引手技に自信がなく、いつ何があるかと思うと夜も眠れない。 |
| 長期目標 | 介護者である妻が、自信と安心感を持って介護を継続できる。 |
| 短期目標 | 妻が一人で安全に痰の吸引を実施できるようになる。 |
| サービス内容 | 看護師が週2回訪問し、妻が安全・安楽に痰の吸引を行えるよう、具体的な手技の指導・確認を行う。また、介護に関する悩みや不安を傾聴し、精神的なサポートを行うとともに、緊急時の連絡体制について再確認する。 |
在宅療養は、介護者である家族の存在なくしては成り立ちません。
介護者の身体的・精神的負担を評価し、支援することもケアマネジャーの重要な役割です。
レスパイト目的のショートステイの利用や、介護者自身の相談窓口を紹介することも検討しましょう。
訪問看護のケアプラン作成のポイント

訪問看護のケアプランを作成する際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 情報共有でミスコミュニケーションを防ぐ
- サービス担当者会議を有効活用する
- 利用者の立場に寄り添う
訪問看護師と円滑に連携し、チームとして利用者を支えることで、初めてプランは生きたものになります。
本章では、より質の高いケアプランを作成するうえで重要なポイントを紹介します。
情報共有でミスコミュニケーションを防ぐ
訪問看護ステーションとの情報共有の際に、ミスコミュニケーションを防ぐことは重要です。
訪問看護師にケアプランを渡す際は、第1表・第2表だけでなく、アセスメントで得た利用者や家族の背景情報も併せて伝えましょう。
生活歴・価値観・キーパーソンとの関係性といった情報が加わることで、訪問看護師はより利用者に寄り添ったケアを提供できます。
また、電話やFAXだけでなく、ICTツールを活用することで、より迅速かつ正確な情報共有が可能です。
サービス担当者会議を有効活用する
サービス担当者会議は、単なる情報共有の場ではありません。
チームとしての目標を確認し、各専門職の役割分担を明確にするための重要な機会です。
ケアマネジャーは会議の進行役として、訪問看護師から専門的な意見や提案を積極的に引き出すことを意識しましょう。
利用者の立場に寄り添う
ケアプランを作成する際は、必ず利用者の立場に寄り添いましょう。
利用者にとって、どの訪問看護ステーションを選ぶかは、在宅療養の質を大きく左右します。
ケアマネジャーは、利用者の代理人として、質の高いサービスを安定して提供できるステーションを見極める視点を持つことが大切です。
訪問看護ステーションが提供するサービスの内容はもちろん、利用者が安心して訪問看護を受けられる体制が整っているかを見定めることもケアマネジャーの重要な役割です。
また、管理者や訪問看護師と日ごろから良好な関係を築き、何でも相談できるパートナーシップを育むことが、結果的に利用者の安心につながります。

この記事は、訪問看護におけるケアプラン、特に「介護サービス計画書」の作成に関して、基礎知識から具体的な手順、実用的な文例まで網羅的に解説され、専門職の皆様にとって大変有益な内容です。訪問介護のプランとは異なる医療的視点の重要性が強調されている点は、質の高い計画立案において深く認識すべき要素です。
ケアプランと訪問看護計画書の違い、医療保険・介護保険の適用ルールに関する解説は、制度理解を深め、実務判断に不可欠な情報です。アセスメントから課題分析、目標設定、モニタリングと再評価に至るPDCAサイクルの重要性が示されている点は、ケアの質向上に直結します。情報共有の徹底やサービス担当者会議の有効活用、利用者本位の視点といった実践的な作成ポイントは、多職種連携を円滑にし、質の高い訪問看護の鍵となります。貴事業所での利用者様への最適なケアプラン作成に、本記事が大きく貢献することを期待いたします。
なお、株式会社ワイズマンでは「効果的なアセスメントを実施するための資料」を無料で配布中です。
新しいスタッフによるアセスメントの運用に課題を感じている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
適切なケアプランはより良い訪問看護を実現する

訪問看護をケアプランに位置づけることは、医療ニーズのある利用者が住み慣れた自宅で安心して暮らすために不可欠です。
利用者の症状を把握し、訪問看護師など多職種からの見解を参考にしながらケアプランを作成しましょう。
また、ケアプランの作成は利用者に寄り添うことも不可欠です。
利用者や家族のニーズを正確に把握すれば、自然と質の高いケアプランが実現します。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。