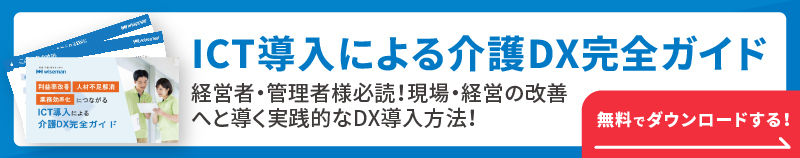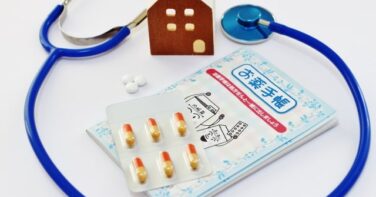【令和6年度改定】訪問看護の専門管理加算とは?算定要件から届出、Q&Aまで徹底解説
2025.08.11

「専門管理加算の算定要件が複雑で、事業所で算定できるのかわからない」
「令和6年度の報酬改定で新設されたけど、具体的に何をすればいいのかわからない」
「算定漏れで収益機会を逃したくないし、誤請求で指摘されるのも避けたい」
訪問看護ステーションの管理者や請求担当者のなかには、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
専門管理加算は、在宅で高度な医療ケアを必要とする利用者に質の高いサービス提供を評価するうえで非常に重要な加算です。しかし、その算定要件は複雑で正確に理解するのは難しいと感じる方もいるでしょう。
この記事では、訪問看護における専門管理加算について、算定要件から届出方法、実務上の注意点、経営への活用法を専門外の方にもわかりやすく徹底的に解説します。この記事を最後まで読めば、専門管理加算に関するあらゆる疑問が解消され、明日からの業務に自信を持って取り組めるでしょう。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
訪問看護の専門管理加算とは

訪問看護における専門管理加算は、在宅で過ごす利用者の医療ニーズがますます高度化・複雑化している現状に対応するために、令和6年度の介護報酬改定で新設された制度です。
専門的な知識や技術を持つ看護師が、特定の状態にある利用者に対して計画的な管理を行うことを評価します。これにより、質の高い訪問看護サービスの提供を促進し、利用者が安心して在宅療養を続けられる体制を構築できます。
医療ニーズの高度化に応えるための新設加算
専門管理加算が新設された背景には、国の医療政策が大きく関与しています。入院期間の短縮化や地域包括ケアシステムの推進により、以前は病院でケアを受けていたような医療依存度の高い方が、在宅で療養するケースが増加しています。
特に、緩和ケアや重度の褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱の管理などは、高度な専門知識と技術が不可欠です。専門管理加算はこうした専門的なケアを提供する訪問看護ステーションを正当に評価し、事業所が質の高いサービスを継続的に提供できる基盤を整えるために導入されました。
特別管理加算との違い
専門管理加算と名称が似ているため混同されやすいのが「特別管理加算」です。この2つの加算は目的や対象者が異なるため、正しく理解しておく必要があります。
大きな違いは、専門管理加算が「専門研修を修了した看護師による計画的な管理」を評価するのに対し、特別管理加算は「特定の医療処置が必要な状態」そのものを評価する点にあります。
以下の表で違いを確認しましょう。
| 項目 | 専門管理加算 | 特別管理加算 (Ⅰ・Ⅱ) |
| 目的 | 専門性の高い看護師による計画的な管理を評価 | 在宅での特別な医療管理が必要な状態を評価 |
| 対象者 | ・緩和ケアが必要な悪性腫瘍の利用者 ・真皮を越える褥瘡がある利用者 ・人工肛門 ・人工膀胱を造設している利用者 | ・在宅悪性腫瘍等指導管理を受けている状態 ・気管カニューレを使用している状態 ・留置カテーテルを使用している状態 など |
| 看護師の要件 | 指定された専門研修を修了していること | 特になし |
| 単位数 | 250単位/月 | Ⅰ:500単位/月 Ⅱ:250単位/月 |
| 併算定 | 特別管理加算との併算定は可能 | 専門管理加算との併算定は可能 |
特に重要なのは、両加算はそれぞれの算定要件を満たせば併算定が可能であるという点です。例えば、緩和ケアが必要な末期がんの利用者(専門管理加算の対象)が、同時に留置カテーテルを使用している場合(特別管理加算の対象)、両方の加算を算定できます。
【完全ガイド】訪問看護における専門管理加算の算定要件

ここからは、専門管理加算を算定するための具体的な要件を詳しく解説します。専門管理加算は、介護保険と医療保険でそれぞれルールが定められています。
算定要件は複雑に見えますが、ポイントを押さえれば正しく理解することが可能です。事業所がどの要件に該当するのか、一つひとつ確認していきましょう。
専門管理加算(イ)の要件・単位数と対象者
まず、主に介護保険の訪問看護で用いられることが多い「専門管理加算(イ)」の要件です。専門管理加算(イ)は、特定の専門研修を修了した看護師による管理を評価するものです。
| 項目 | 内容 |
| 単位数 | 250単位/月 |
| 対象者 | 以下のいずれかに該当する利用者 ・悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を行っている ・真皮を越える褥瘡の状態にある ・人工肛門や人工膀胱周囲の皮膚にびらんなどの皮膚障害が持続的もしくは反復して発生している ・人工肛門または人工膀胱の他の合併症を有する |
| 実施内容 | 訪問看護計画に基づき、上記の看護師が利用者に対して計画的な管理を行う |
専門管理加算(ロ)の要件・単位数と対象者
次に「専門管理加算(ロ)」です。こちらも先ほどと同様に、特定行為研修を修了した看護師による管理を評価するものです。
| 項目 | 内容 |
| 単位数 | 250単位/月 |
| 対象者 | 以下のいずれかに該当する行為 ・気管カニューレの交換 ・胃ろうカテーテルもしくは腸ろうカテーテルまたは胃ろうボタンの交換 ・膀胱ろうカテーテルの交換 ・褥瘡もしくは慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ・創傷に対する陰圧閉鎖療法 ・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 ・脱水症状に対する輸液による補正 |
| 実施者 | 特定行為研修を修了した看護師 |
| 実施内容 | 医師が交付した手順書に基づき、上記の看護師が利用者に対して計画的な管理を行う |
訪問看護計画書の記載ポイント
専門管理加算を算定するうえで、訪問看護計画書への適切な記載は極めて重要です。監査の際にも、この計画書に基づいて「計画的な管理」が行われているかがチェックされます。
以下のポイントを盛り込み、誰が見ても専門的な管理内容がわかるようにしましょう。
- 専門性の高い看護師が関わる具体的なケア内容
- 例:「緩和ケア認定看護師による週1回の疼痛アセスメントと、レスキュー薬使用状況の評価」
- 多職種との連携計画
- 例:「毎週水曜日の医師・ケアマネジャーとの合同カンファレンスで状態を共有し、ケアプランを調整」
- ケアの具体的な目標設定(評価可能な指標を用いる)
- 例:「1ヶ月以内にNRS(疼痛スケール)を5から3へ軽減させる」
- 例:「2ヶ月以内に褥瘡のDESIGN-R®スコアをd3からd2へ改善させる」
専門管理加算の要件となる「専門性の高い研修」とは

算定の鍵となるのが、看護師が「専門性の高い研修」を修了しているかどうかです。具体的にどのような研修が該当するのか、加算(イ)と(ロ)に分けて解説します。
1.緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・膀胱ケアに係る専門研修
専門管理加算(イ)の算定には、以下のいずれかの研修を修了した看護師が必要です。
- 緩和ケア
- 褥瘡ケア
- 人工肛門・人工膀胱ケア
事業所の看護師が過去に受講した研修が該当するか不明な場合は、研修の主催団体や都道府県の担当窓口に確認することをおすすめします。
2.特定行為研修
専門管理加算(ロ)の算定には、厚生労働省が指定する研修機関で「特定行為研修」を修了した看護師が必要です。
特定行為とは医師の判断を待たずに、手順書に基づき看護師が実施できる診療の補助行為のことです。訪問看護の現場で関連が深い特定行為には、以下のようなものがあります。
- 気管カニューレの交換
- 胃ろうカテーテルもしくは腸ろうカテーテルまたは胃ろうボタンの交換
- 褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去(デブリードマン)
- 創傷に対する陰圧閉鎖療法
これらの行為を手順書に基づき実施できる看護師がいることは、事業所の大きな強みです。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
訪問看護における専門管理加算の算定に向けた4つのステップ

算定要件を理解したら、次はいよいよ算定に向けた準備です。ここでは、実際に加算を算定するまでの流れを4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:事業所の体制を確認する
まず、事業所が専門管理加算を算定できる体制にあるかを確認します。以下のチェックリストを活用してください。
- 専門管理加算の対象となる研修を修了した看護師が在籍しているか
- 24時間対応体制加算を届け出ており、実際に24時間連絡・対応できる体制が整っているか
- 専門的な管理内容を記載できる訪問看護計画書の様式が準備できているか
- 多職種と連携するためのカンファレンスや情報共有の仕組みがあるか
これらの体制が整っていない場合は、算定開始までに整備を進める必要があります。
ステップ2:行政に届出書を提出する
算定体制が整ったら、管轄の地方厚生局や都道府県の担当窓口に届出書を提出します。主に必要な書類は以下のとおりです。
- 専門管理加算に係る届出書
- 専門の研修を修了したことが確認できる書類
これらの書類に、専門管理加算を算定する旨を記載して提出します。自治体によって様式や提出方法が異なる場合があるため、事前にホームページなどで確認しましょう。
ステップ3:利用者への説明・同意を得る
実際に加算を算定する利用者が決まったら本人または家族、担当のケアマネジャーに説明し、同意を得る必要があります。説明の際は、以下の点を丁寧に伝えましょう。
- なぜ専門管理加算が必要なのか
- 具体的にどのようなケアが行われるのか
- 加算に伴う自己負担額の変更について
一方的な説明ではなく、質問の時間も十分に設け、納得いただいたうえで同意書などに署名してもらうことが重要です。
ステップ4:適切な記録とレセプト請求を行う
ケアを開始したら、日々の記録と毎月のレセプト請求を行います。
- 訪問看護記録:訪問看護計画書に沿って、専門的な管理・ケアを実施した内容を具体的に記録する
- レセプト請求:介護給付費明細書や訪問看護療養費明細書の「加算」の欄に、専門管理加算の単位数または金額を忘れずに記載する
算定漏れや返戻を防ぐため、記録と請求のダブルチェック体制を整えることが望ましいです。
【経営視点で考える】専門管理加算のメリットと業務効率化

専門管理加算は単なる報酬アップだけでなく、ステーションの経営に多くのメリットをもたらします。ここでは、経営者の視点から加算の活用法とそれに伴う課題への対策を考えます。
ステーションの収益向上と専門性強化
専門管理加算は、1件あたり月額2,500円(250単位)の収益増につながります。具体的な収益向上シミュレーションは以下のとおりです。
| 算定人数 | 1カ月あたりの収益増 | 1年あたりの収益増 |
| 5名 | 12,500円 | 150,000円 |
| 10名 | 25,000円 | 300,000円 |
| 20名 | 50,000円 | 600,000円 |
また、収益面だけでなく、専門性の高いケアを提供できる事業所として、地域の医療機関やケアマネジャーからの信頼が高まります。これにより、新規利用者の紹介が増えるといった効果も期待できるでしょう。
これはスタッフの専門職としての誇りやモチベーション向上にもつながり、ひいては組織全体の質の向上という好循環を生み出します。
算定における課題と対策
専門管理加算はメリットがある一方、算定を進めるうえではいくつかの課題も考えられます。あらかじめ対策を講じておくことが重要です。
| 課題 | 対策例 |
| 専門研修を修了した看護師がいない・足りない | ・研修参加費用の助成制度を設ける ・資格取得支援制度(手当支給など)を導入する ・eラーニングなどを活用し、働きながら学べる環境を整える |
| 多職種との連携がうまくいかない | ・定期的な合同カンファレンスを仕組み化する ・ICTツールを導入し、リアルタイムな情報共有を行う |
| 計画書作成や記録の業務負担が増える | ・計画書や記録のテンプレートを整備・標準化する ・訪問看護専用の電子カルテシステムを導入し、記録業務を効率化する |
訪問看護の専門管理加算に関するQ&A

最後に、訪問看護における専門管理加算に関するよくある質問とその回答をまとめました。制度を利用するうえで重要なポイントともなるため、それぞれの疑問点についての理解を深めておきましょう。
Q1. 専門性の高い看護師1名で複数名の利用者を担当できるか
A1. 可能です。
ただし、一人ひとりの利用者に対して、訪問看護計画書に基づいた計画的な管理を実施しなければいけません。一人の看護師が担当できる人数に上限はありませんが、ケアの質が担保できる範囲で担当するようにしましょう。
Q2. 月の途中で対象となった場合の算定はどうなるか
A2. 月の途中で対象となった場合でも、1ヶ月分の単位数を算定します。
専門管理加算は月単位の算定であり、日割り計算は行いません。その月の最初の訪問看護を提供した日に、所定の単位数を算定するのが原則です。
Q3. 研修修了予定でも算定できるか
A3. 算定できません。
算定要件は、あくまで「研修を修了した看護師」が計画的な管理を行うことです。そのため、研修を受講中もしくは修了予定の段階では算定対象とはなりません。修了証が発行された時点から算定が可能です。

この記事は、令和6年度介護報酬改定で新設された本加算について、概要から算定要件、届出、実務上の注意点、経営的活用法まで網羅的に解説され、専門職の皆様にとって大変有益な指針です。在宅医療ニーズ高度化に対応する本加算の意義、既存の特別管理加算との明確な違い、両加算の併算定が可能である点は、実務理解に不可欠です。専門管理加算(イ)と(ロ)の対象者・実施内容、鍵となる「専門性の高い研修」の具体的内容、特定行為研修修了看護師の強みが明示されており、算定可否の指針となります。訪問看護計画書の記載ポイント、算定に向けた4ステップは実践的であり、Q&Aも現場の疑問を解消します。収益向上に加え、専門性強化や地域からの信頼向上、スタッフのモチベーション向上にも繋がるという経営的視点、そして課題と対策まで言及され、質の高いケア提供と安定運営の参考にして頂けそうです。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
まとめ:訪問看護の専門管理加算を正しく理解して質の高いケアを提供しよう

今回は、令和6年度の報酬改定で新設された専門管理加算について概要から算定要件、実務上の流れまでを詳しく解説しました。
専門管理加算を正しく理解し活用することは、医療ニーズの高い利用者へ質の高いケアを届けることに直結します。また、訪問看護ステーションの安定した経営基盤を築くうえでも大きな力となるでしょう。まずは事業所の体制を確認し、専門管理加算の算定に向けた第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。