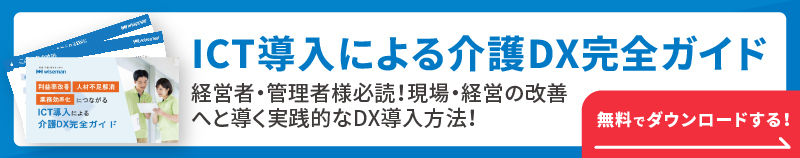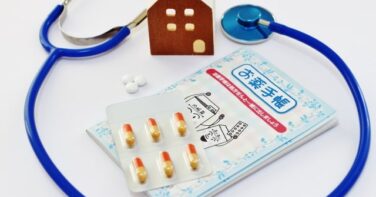【2024年度改定対応】訪問看護の減算とは?算定要件と経営改善につながる対策を一覧で徹底解説
2025.08.11

訪問看護ステーションの運営において「このケースは減算対象にならないだろうか」「2024年度の改定でルールはどう変わったのか」といった不安は尽きません。
特に、報酬改定のたびに複雑化する減算のルールは、管理者や請求事務担当者にとって大きな悩みの種です。算定ミスは事業所の収益に直結するため、絶対に避けたいと考えるのは当然のことでしょう。
この記事では、訪問看護における減算の全体像から2024年度介護報酬改定の最新情報、また収益を守るための具体的な対策までを網羅的に解説します。正しい知識を身につけて算定ミスを防ぎ、安心して事業所を運営するための一助となれば幸いです。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
訪問看護の減算とは

訪問看護における「減算」とは、国が定めるサービスの基準やルール(算定要件)を満たせなかった場合に、本来得られるはずの介護報酬から一定の単位数が差し引かれる仕組みのことです。質の高いサービスや手厚い体制を評価して報酬が上乗せされる「加算」とは対照的な位置づけにあります。
減算はサービスの質を担保し、制度の公平性を保つための重要なルールです。そのため、減算の対象となる項目や条件を正確に理解して日々の業務で遵守することが、コンプライアンスの観点や事業所の安定経営のために極めて重要です。
なお、減算を避けるためには定期的な研修や情報共有を通じて、スタッフ全員が最新の制度内容を把握し、適切なサービス提供を心がける必要があります。また、記録の正確性も重要であり、監査に備えて日頃から適切な記録管理体制を構築しておくことが求められます。
【2024年度改定】訪問看護における3つの重要減算

2024年度の介護報酬改定では、訪問看護の現場に大きな影響を与える重要な減算が新設・変更されました。これらはサービスの提供体制や質をよりいっそう問い直すものであり、すべての事業所で正しい理解と対応が求められます。
ここでは、特に押さえておくべき3つの減算について詳しく見ていきましょう。
1.リハビリ専門職(PT・OT・ST)の訪問回数超過減算
看護の視点に基づいたサービス提供を重視する観点から、リハビリ専門職による訪問が過度に多くなることを是正するための減算が新設されました。
前年度の理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)による訪問の合計回数が、看護職員の訪問回数を超過した場合に適用されます。この減算は、訪問1回につき「マイナス8単位」です 。
訪問看護はあくまで看護が主体であるべきという国の考えが反映された改定であり、看護とリハビリのバランスの取れたサービス提供計画が不可欠です。
2.業務継続計画(BCP)未策定減算
感染症のまん延や自然災害といった不測の事態が発生しても、利用者に必要なサービスを継続できる体制を整えることが今まで以上に重要視されています。この背景から、業務継続計画(BCP)の策定が義務付けられました。
業務継続計画(BCP)とはBusiness Continuity Planの略で、事業所が予期せぬ事態に遭遇した場合でも重要な業務を中断させずに、または中断した場合でも可能な限り迅速に再開できるようにするための計画のことです。
2025年4月1日以降、感染症または災害のいずれか、もしくは両方のBCPが未策定の場合、基本報酬から1%が減算されます。さらに、事業継続計画の策定だけではなく、定期的な研修・訓練の実施も義務付けられています。従業員や利用者を守るために必要な計画となるため、忘れず策定しておきましょう。
3.高齢者虐待防止措置未実施減算
利用者の尊厳を守り、安全なサービス提供を確保するため、高齢者虐待防止に向けた事業所の体制整備が義務化されました。以下の4つの措置がすべて実施されていない場合、基本報酬から1%が減算されます。
- 虐待防止のための委員会の設置
- 虐待防止のための指針の整備
- 虐待防止のための定期的な研修の実施
- 虐待防止対策を検討する担当者の設置
これらの措置は虐待の発生を未然に防ぐだけでなく、発生した際に迅速かつ適切に対応するための基盤となり得ます。形式的な整備だけでなく、実効性のある取り組みとして定着させることが重要です。
【一覧表】訪問看護の主な減算と算定要件

2024年度改定で注目される3つの減算以外にも、訪問看護にはさまざまな減算が存在します。ここでは、特に実務で関わることが多い「同一建物減算」と「准看護師による訪問減算」について、その要件を見ていきましょう。
なお、それぞれの概要は以下のとおりです。
| 減算の種類 | 適用条件 | 計算方法 |
| 同一建物減算 | 事業所と同一の建物、またはそれ以外の同一建物で、1カ月のサービス利用者が20人以上の場合 | 所定単位数 × 0.90(10%減算) |
| 事業所と同一の敷地内にある建物(養護老人ホームなど)で、1カ月のサービス利用者が50人以上の場合 | 所定単位数 × 0.85(15%減算) | |
| 准看護師による訪問減算 | 准看護師が訪問看護を提供した場合 | 所定単位数 × 0.90(10%減算) |
同一建物減算
同一建物減算とは集合住宅や高齢者向け住宅など、一つの建物に複数の利用者が居住している場合に適用される減算です。訪問の効率性を考慮したルールであり、利用者の人数によって減算率が10%または15%と異なります。
ただし「どの範囲までが同一建物と見なされるか」など、判断が難しいケースもあります。請求事務を行う際は利用者の居住形態を正確に把握し、該当するかどうかを慎重に確認しなければいけません。
准看護師による訪問減算
訪問看護を准看護師が行った場合、所定単位数から10%が減算されます。これは、看護師と准看護師の資格や役割の違いを報酬に反映させたものです。事業所の人員配置を検討する際には、この減算ルールを念頭に置き、看護師と准看護師のバランスを適切に管理することが経営上のポイントです。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
訪問看護の減算を避けるための具体的な対策

減算は事業所の収益に直接影響を与えるため、具体的な回避策は経営上の重要課題の一つです。しかし、減算対策は単なるリスク回避にとどまりません。ルールを正しく理解し、適切な対策を講じることは業務プロセスの見直しやサービス品質の向上、またより安定した経営基盤の構築へとつながります。
対策1:リハビリ減算を防ぐ訪問計画と多職種連携
リハビリ専門職の訪問回数超過減算を防ぐには、年間の訪問回数を計画的に管理することが不可欠です。看護職員とリハビリ専門職が密に連携し、利用者の状態や目標を共有する場を定期的に設けましょう。
訪問看護計画書には、看護とリハビリそれぞれの目標と具体的な訪問スケジュールを明記することが推奨されます。これにより、特定の職種に訪問が偏るリスクを低減し、利用者一人ひとりに適したサービス提供体制の構築につながる可能性があります。
さらに、訪問の必要性を定期的に見直し、記録に残すことも重要です。利用者の状態変化や目標達成度に合わせて、柔軟に訪問計画を修正しましょう。多職種連携を強化して情報共有を密に行うことで、より質の高い、効率的な訪問看護サービスを提供でき、結果として減算リスクを回避できます。
対策2:BCP・虐待防止体制の早期構築と届出
BCP未策定減算や高齢者虐待防止措置未実施減算は、体制を整備すれば確実に回避できる項目です。厚生労働省が提供するガイドラインやひな形を参考に、事業所の実情に合ったBCPを速やかに策定しましょう。策定後は定期的な研修や訓練を通じて、全職員に内容を浸透させることが重要です。
BCPは災害や感染症発生時における事業継続計画であり、利用者へのサービス提供を維持するために不可欠です。定期的な見直しと改善も行い、実効性を高めましょう。
同様に、虐待防止措置についても委員会や指針の整備、研修計画の立案などを着実に進める必要があります。これらの体制整備に関する届出の要否は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認してください。
虐待防止は利用者の人権を守り、安全な環境を提供するために不可欠です。職員一人ひとりが高い倫理観を持ち、日々のケアにあたる必要があります。
参考:介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修資料・動画|厚生労働省
対策3:同一建物減算の影響を抑える効率的な訪問スケジュール
同一建物減算は避けられないケースもありますが、その影響を最小限に抑えることは可能です。鍵となるのは、訪問スケジュールの最適化です。
同じ建物内の利用者をまとめて訪問する時間帯を設けるなど、移動時間を短縮する工夫が求められます。スケジュール管理システムなどのツールを活用すれば、ルートの最適化や訪問時間の調整が容易になるため、業務効率と収益性の両立を図れます。
さらに、同一建物内の利用者に対するサービス内容を工夫することも重要です。例えば、短時間で提供できるサービスを組み合わせたり、利用者同士の交流を促進するプログラムを導入したりすることで、満足度を高めながら効率的なサービス提供を目指せます。
また、関係機関との連携を強化して情報共有を密にすれば、より質の高い支援を提供しながら減算の影響を軽減できます。
対策4:記録の徹底と最新情報の収集
すべての減算対策の基礎となるのが、日々の正確な記録と制度に関する最新情報の収集です。訪問看護計画書や報告書にはサービスの根拠となる情報を具体的に記載し、サービスの必要性を誰が見てもわかるようにしておくことが実地指導などへの備えにつながります。
また、介護報酬改定に関する情報は、厚生労働省のWebサイトなどで常に最新のものを確認する習慣をつけましょう。信頼できる情報に基づいた運営が、算定ミスや返戻を防ぐ確実な方法です。
さらに、サービス提供時間や内容、利用者の状態変化などを詳細に記録することが重要です。客観的な事実に基づいた記録は、万が一の疑いが生じた際に強力な証拠として扱われます。
なお、定期的に内部監査を実施し、記録内容の整合性や制度遵守状況を確認すればリスクを未然に防げます。つまり、記録体制の強化と監査の徹底が安定的な運営に不可欠です。
訪問看護の減算に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、訪問看護の減算に関して現場の管理者や請求担当者からよく寄せられる質問にお答えします。日々の業務で生じる疑問の解消にお役立てください。
Q1. リハビリ減算はいつの訪問回数で判断されるのか
リハビリ専門職の訪問回数超過減算は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の看護職員とリハビリ専門職の訪問回数の実績によって判断されます。したがって、年度の途中から回数を調整するのではなく、年間を通じた計画的な訪問スケジュール管理が重要です。
Q2. 同一建物減算で「同一敷地内」とはどこまでを指すか
同一建物減算における「同一敷地内」とは、その建物が所在する土地や隣接する土地のうち、一体的に利用されている土地の範囲を指します。例えば、同じ敷地内に複数のアパートが建っている場合や道路を隔てていても専用の通路などで接続されている場合などが該当します。
最終的な判断は指定権者(都道府県や市町村)が行うため、判断に迷う場合は事前に確認することが推奨されます。
Q3.減算の適用を避けるために必要な届け出や手続きはあるのか
基本的に、減算そのものを回避するための特別な「届出」はありません。減算は、定められた基準を満たしていない場合に自動的に適用されるものです。したがって、各減算の算定要件を正しく理解し、要件を満たせるように日々の事業所運営やサービス提供体制を整備・管理することが重要です。
ただし、高齢者虐待防止措置のように体制を整備したことを運営規程に記載したり、BCPを策定して職員に周知したりといった「実施記録」を残しておくことは、実地指導などで適切に運営していることを示すうえで非常に重要なポイントとなるでしょう。

この記事は、訪問看護における「減算」の概念から、2024年度介護報酬改定で新設・変更された重要事項まで、非常に詳しく解説されており、管理者や実務担当者にとってとても参考になる内容です。特に、リハビリ専門職による訪問回数超過減算、業務継続計画(BCP)未策定減算、高齢者虐待防止措置未実施減算といった新たなルールへの対応の重要性が明確に示されています。
これら減算が単なる収益減に留まらず、サービスの質やコンプライアンスに関わる重大な課題であるという指摘は、事業所の運営において深く認識しておく点です。記事内で提案されている、多職種連携による訪問計画の見直し、BCP・虐待防止体制の早期構築、そして記録の徹底といった具体的な対策は、減算回避のみならず、より質の高いサービス提供と安定した事業経営基盤の構築に直結するものです。本記事を通じて、貴事業所の持続可能な発展と利用者様への安心安全なケア提供が図られることを強く期待いたします。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
まとめ:訪問看護における減算を理解して安定経営を実現しよう

訪問看護の減算ルールは複雑で、特に報酬改定の時期は内容の把握に苦労することも多いでしょう。しかし、減算は単に報酬が減るというネガティブな側面だけではありません。一つひとつのルールにはサービスの質を担保し、利用者を守るという明確な目的があります。
今回解説した減算の種類や算定要件を正確に理解し、計画的な対策を講じることが重要です。さらに、ICTツールなどを活用して業務を効率化すれば、質の高いサービスを提供し続けながら安定した事業所経営を実現できるでしょう。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。