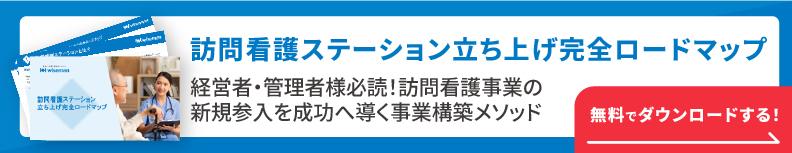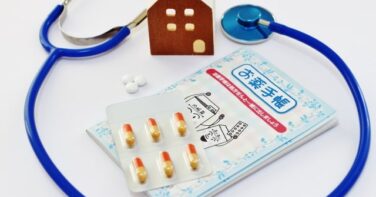訪問看護で准看護師ができること・できないこと|運用ポイントも解説
2025.07.20

訪問看護の現場では、准看護師の役割が年々重要性を増しています。
一方で「正看護師との違いは?」「どこまで任せていいの?」といった不安や疑問を抱えたまま運用されているケースも少なくありません。
准看護師は、制度上「医師または看護師の指示に基づいて業務を行う」ことが定められており、自己判断での対応には明確な制限があります。
誤った運用は、減算・返戻・指導リスクにつながるおそれもあるため、制度に沿った理解と対応が欠かせません。
この記事では、准看護師が訪問看護で担える具体的な業務と、注意が必要な業務、そして制度面での違いや減算リスクを防ぐ運用ポイントまで詳しく解説します。
准看護師の活用に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
訪問看護で准看護師ができる業務と注意が必要な業務

訪問看護における准看護師の業務範囲は、正看護師と完全に同じではなく、制度上の制限や注意点が設けられています。
「どこまで任せてよいのか」「単独で訪問していいのか」といった疑問を抱えたまま運用すると、思わぬ返戻や指導リスクを招く可能性もあります。
ここでは、准看護師が訪問看護で対応できる具体的な業務と、判断や医療行為を伴うために注意が必要な業務について、制度的な背景に沿って整理していきましょう。
准看護師が訪問看護で対応できる業務
訪問看護の現場では、准看護師も正看護師と同様に多くのケアに携わることができます。
しかし、制度上は「医師・看護師の指示を受けて業務を行う」ことが前提であり、独自の判断で対応できる範囲には限りがあります。
日々の業務で「これは任せていいのか」と迷う場面も少なくありません。
そこでここでは、訪問看護において准看護師が対応できる具体的な業務内容を整理しておきましょう。
バイタルサイン測定や状態観察
訪問看護において、バイタルサインの測定や利用者の状態観察は、准看護師が担える基本的な業務の一つです。
正しく対応できていれば、日々の健康管理や異常の早期発見につながります。
例えば、以下のような対応は准看護師でも実施可能です。
- 体温・血圧・脈拍などの測定
- 呼吸状態や皮膚の色などの観察
- 異常がないかの経過記録
ただし注意すべきは、自ら判断してケアの内容を変更したり、医療的判断を下したりはできません。
状態変化が見られた際には、看護師への報告と指示を仰ぐ必要があります。
訪問看護記録には「何を観察し、どうだったか」を正確に記録しなければなりません。
計画書や指示書との整合性を意識し、根拠のある業務として記録を残すことが、制度対応や指導時の備えにもなります。
清拭・更衣介助・褥瘡予防などの基本的ケア
准看護師は、訪問看護の現場で医療的な判断を伴わない日常的ケアを担うことができます。
対応できる主なケア業務は、以下のとおりです。
- 清拭・入浴介助
- 更衣介助
- 体位変換・除圧ケア(褥瘡予防(じょくそうよぼう))
- 整容・爪切り・口腔ケアなどの生活援助
上記業務は医師や看護師の判断を必要としない範囲であれば、准看護師が単独で実施可能です。
ただし、皮膚トラブルや体調の異常に気づいた場合は、自ら判断せず、看護師に報告して指示を仰ぐことが必須です。
判断や対応は看護師が行い、准看護師はその指示に従ってケアを提供すれば、安全で制度に適した対応が可能になります。
看護師の指示に基づく医療処置の補助
准看護師は、看護師や医師の明確な指示のもとであれば、医療処置の一部補助を行うことが可能です。
ただし「補助」であることがポイントであり、自ら判断して処置を行うことは制度上できません。
対応可能な主な補助業務は以下のとおりです。
- 点滴の準備(薬剤や物品の取り揃えなど)
- カテーテル交換に伴う備品の準備
- 医療物品の管理・補充
- 傷の観察や報告(処置そのものは看護師の対応が原則)
上記業務は、必ず「誰の指示で、何の目的で行うか」が明確になっていることが前提です。
医療処置の一部に関わる場合は、訪問看護指示書や記録との整合性も問われるため、「実施記録の正確性」も重要な管理ポイントです。
「正看護師が不在でもできるか」の現場判断を、曖昧にしないことが減算・返戻を防ぐことにつながります。
指示系統を明確に保ち、准看護師が担える範囲を適切に運用していきましょう。
准看護師が単独判断できない、または注意が必要な業務
訪問看護において准看護師が担える業務には一定の範囲が定められており、看護師のように独自の判断で対応できないケースも多く存在します。
特に医療処置や計画の立案、利用者への説明などは、判断や責任が伴うため注意が必要です。
制度上の制約を正しく理解しておかないと、意図せず不適切な対応となり、返戻や指導リスクを招く可能性もあります。
ここでは、准看護師が単独で判断・実施できない、または特に注意が必要な業務について確認していきましょう。
看護師の指示がない医療処置
准看護師が医療処置を行う際は、必ず医師または看護師の明確な指示を受けて実施する必要があります。
指示がない状態での処置は、制度上の要件を満たさず、保険請求の不備や不適切対応として指導対象になるおそれがあります。
看護師の指示がない処置に関する注意点は、以下のとおりです。
| 明示的な指示が必要な処置 | 点滴の管理やカテーテル処置、吸引、注射など、医療的判断を要するケアは指示なしでは実施不可 |
| 口頭・電話指示の曖昧さ | 「言われた気がする」「前回もやったから」などの曖昧な根拠での対応は避け、記録に残る形での指示が必要 |
| 自己判断による応用・変更はNG | 状態の変化に対する対応や処置内容の変更などは、看護師の判断が必要 |
上記のような対応は、あくまで准看護師は“指示を受けて実施する立場”であることを再確認し、現場全体でルールを共有しておくことが大切です。
新たな訪問看護計画の立案やアセスメント
訪問看護において、利用者の状態変化に応じたアセスメントや看護計画の立案は、看護師が担うべき業務とされています。
准看護師はこれらの業務を独自に判断したり実施したりはできません。
准看護師が対応できない主な業務は、以下のとおりです。
| 訪問頻度やケア内容の決定 | ・ 「週3回の訪問を週2回に減らす」などの判断は不可 ・計画変更には看護師の判断が必要 |
| 状態変化への介入方針の判断 | ・バイタル異常や褥瘡悪化などに対するケア内容の見直しや指示出しは、看護師の職責 |
| 計画書・報告書の作成・修正 | ・訪問看護計画書や報告書に関する記載は、看護師または保健師が対応 |
准看護師が現場で得た情報は貴重な視点になりますが、それをもとに判断や計画を立てるのは看護師の役割です。
誤った判断が算定ミスや安全面のリスクにつながる可能性もあるため、対応範囲を正しく把握しておく必要があります。
利用者や家族への病状説明などの判断を伴うコミュニケーション
訪問看護では、利用者や家族とのコミュニケーションも重要な業務ですが、病状説明や予後に関する発言には慎重な対応が求められます。
特に准看護師が判断を伴う説明を単独で行うことは制度上の役割を逸脱する恐れがあります。
准看護師がコミュニケーションを取る際は、以下の点に注意しましょう。
| 病状や診断名に関する説明 | 病気の進行具合や検査結果などの説明は、医師や看護師が対応すべき範囲 |
| 予後・介護方針に関する助言 | 終末期ケアの方向性や施設入所の是非など、判断を伴う相談には答えない |
| 質問対応時の対応フロー | 「このままの状態だとどうなりますか?」などの質問には即答せず、看護師への引き継ぎを徹底 |
コミュニケーションの中で利用者や家族から信頼を寄せられる場面もありますが、制度上の職責を越えて発言しないことが大切です。
不明な点はすぐに看護師に相談し、利用者への説明もチーム全体で適切に対応する体制を整えましょう。
訪問看護における准看護師と正看護師の制度上の違い

訪問看護においては、准看護師と正看護師の違いを正しく理解しておくことが、制度遵守や適切な運営のために欠かせません。
一見、現場での業務内容は似ていても、保有する免許や業務遂行の裁量、請求制度への影響など、法的な位置づけには明確な差があります。
特に准看護師は、医師または看護師の指示のもとでしか業務を行えないと法律に定められており、自己判断によるケアや判断が認められていません。
ここでは、訪問看護の現場で求められる両者の制度的な違いを具体的に確認していきましょう。
教育課程と国家資格上の権限の違い
准看護師と正看護師では、免許の発行主体や教育課程、業務遂行に必要な能力水準に明確な違いがあります。
制度上の立場を把握しておくことは、配置や指導の際の判断材料にもなります。
准看護師と正看護師の主な違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 正看護師 | 准看護師 |
| 免許の発行主体 | 厚生労働大臣 | 都道府県知事 |
| 学歴要件 | 高等学校卒業 | 中学校卒業 |
| 教育課程・履修時間 | 3〜4年課程で3,000時間以上を履修 | 2〜3年課程で1,890時間以上を履修 |
| 資格の法的根拠 | 保健師助産師看護師法 第五条 | 保健師助産師看護師法 第六条 |
| 要求される能力水準 | 科学的根拠に基づき計画的に業務を実施できる能力 | 指示を受けて業務を実施できる能力 |
准看護師は「指示を受けて行動する職種」である点が制度上明確に位置付けられています。
訪問看護においても、この前提をふまえたうえで業務範囲や指導体制を整備していきましょう。
訪問現場における判断・指示の裁量差
訪問看護の現場では、看護師と准看護師の間に、明確な「判断権限」の違いがあります。
一見すると業務内容が似ていても、誰が判断し、誰が指示を出すかで役割は大きく異なります。
判断・指示の裁量差の違いをまとめると、以下のとおりです。
| 項目 | 正看護師 | 准看護師 |
| アセスメント | 自身で実施可 | 原則不可(情報提供のみ) |
| 状況変化への対応判断 | 可(訪問頻度やケア内容の修正など) | 不可(指示があれば実施) |
| 医療処置の可否判断 | 可(注射、カテーテル管理なども含む) | 不可(処置内容によっては対応外) |
| 他職種や家族への対応判断 | 状況に応じて適宜判断・説明が可能 | 判断を要する説明は不可/看護師に引き継ぐ必要あり |
| ケアの指示 | スタッフへ指示可 | 他スタッフへの指示は不可 |
裁量差を理解しておかないと、「准看護師が独自判断で訪問・処置を行ってしまった」といったケースが起こりかねません。
制度違反による減算や指導のリスクにもつながるため、しっかりと把握しておきましょう。
制度・請求面での対応範囲の違い
看護師と准看護師は、制度上の位置づけに違いがあり、請求できる加算や運営基準の適用範囲にも差があります。
制度・請求面での主な違いをまとめると、以下のとおりです。
| 項目 | 正看護師 | 准看護師 |
| 加算の算定要件 | 多くの加算で算定可能 | 一部加算で対象外となることがある |
| 医療保険の請求要件 | 医師の指示書に基づき訪問・請求可能 | 医師の指示がなければ請求不可 |
| 介護保険での単位数 | 所定単位数(100%) | 所定単位数の90%で算定 |
| 看護体制強化加算の基準 | 看護師が6割以上必要な基準達成に寄与 | 多すぎると基準未達となり減算リスクが生じる |
| 管理者要件 | 要件を満たせば管理者として配置可 | 管理者として配置不可 |
准看護師を採用・活用する場合は、制度で定められた訪問・請求の条件を常に確認する必要があります。
特に「医師の指示書の有無」「訪問記録との整合性」「加算の要件充足状況」はチェックを怠らないようにしましょう。
准看護師の訪問で減算や加算不可になるケース

訪問看護において准看護師を活用する際、制度や請求のルールを正しく理解していないと、思わぬ減算や加算不可といったリスクが生じることがあります。
特に、人員基準の未達成や医師・看護師の指示の不備、オンコール体制の構築ミスなどは、指導や返戻につながりかねません。
こうした事態を避けるためには「どのようなケースが制度上のリスクにつながるのか」を事前に把握しておく必要があります。
ここでは、准看護師の訪問で減算や加算不可になる代表的なケースを確認していきましょう。
看護師比率6割の基準を満たしていない
訪問看護ステーションの体制加算を算定するためには、看護職員に占める正看護師の割合が6割以上であることが求められます。
准看護師の採用比率が高まり、全体の看護師比率が6割を下回ると、加算が算定できなくなり、事業所の収益にも影響が出る可能性があります。
そのため、以下のような点を意識した人員配置が必要です。
- 看護職員における正看護師の割合を常に6割以上に保つ
- 24時間対応体制加算など、関連加算の届出内容と整合性をとる
- 特別管理加算の対象者割合など、他要件も含めて確認する
採用や勤務体制の計画段階で、職種構成のバランスを把握しておくことは、体制加算の維持に直結します。
正看護師の割合が要件を満たさない状態が続けば、加算の算定ができなくなるだけではなく、収益の低下や経営計画の見直しにつながるリスクもあります。
そのため、採用方針やシフト配置の段階から、加算要件を踏まえた人員戦略が必要です。
看護師の指示がないまま准看護師が訪問・ケアを実施した
准看護師が正看護師の指示を受けずに業務を行うことは、重大な制度違反であり、不正請求と見なされるリスクがあります。
准看護師は保健師助産師看護師法により、医師または看護師の明確な指示のもとでのみ、業務を行えると定められています。
これに違反する運用は、コンプライアンス上の問題につながりかねません。
現場では以下のようなケースに注意が必要です。
- 指示書や計画書がない状態で、准看護師が単独で訪問した
- 状態変化があったにもかかわらず、正看護師への報告を怠った
- ケア内容を独自に変更し、事後報告すらされていなかった
訪問の前に、必ず正看護師がアセスメントと指示を行い、准看護師はその内容に沿って対応するなどの基本フローを徹底してください。
「記録がない=指示がなかった」と判断される場合もあるため、書類の整備も含めた体制構築が必要です。
現場全体でルールの再確認を行い、組織としてのリスクを防ぎましょう。
准看護師のみでオンコール体制を組んでいる
オンコール体制は、必ず正看護師が中心となって対応すべき業務です。
緊急時には利用者の状態を的確に判断し、必要な医療的対応を即座に決定する能力が求められるため、制度上も准看護師が単独でオンコールを担うことは認められていません。
特に「24時間対応体制加算」を届け出ている訪問看護ステーションでは、オンコール対応者は原則として看護師または保健師である必要があると明記されています。
准看護師単独のオンコール運用によるリスクには、以下のようなものが挙げられます。
- 緊急時の判断や訪問指示を自己判断で行うと、不正請求に該当する可能性がある
- 24時間対応体制加算の算定要件を満たせず、返戻や減算の対象になる
- 制度違反とみなされ、行政指導や監査リスクが高まる
オンコール体制は、正看護師が電話対応・判断を行い、必要に応じて准看護師へ出動を指示するなどの役割分担が基本です。
勤務体制や夜間対応のシフトを組む際は、制度要件を満たす体制かどうかを今一度確認しましょう。
訪問看護で准看護師を配置する際の運用ポイント

准看護師の採用は、看護師不足などの現場の深刻な課題に対する現実的な対策の一つです。
ただし、制度上の制限や算定要件を正しく理解し、適切な運用体制を整えなければ、思わぬ減算リスクや監査の対象となる可能性もあります。
そこでここでは、准看護師を安全かつ効果的に配置するための具体的なポイントをご紹介します。
人員構成・記録体制・オンコール対応といった観点から、制度に即した運用を確認していきましょう。
人員基準を満たす配置計画を事前に組む
准看護師の採用は、人材確保の手段として有効です。
特に採用難が続く地域では、貴重な戦力となり得ます。
しかし、採用の際に人員基準を満たす計画を立てておかないと、減算リスクや加算の未達につながる可能性があります。
採用前の段階で、以下の観点から人員構成と運用体制を確認しておきましょう。
| 人員配置基準の遵守 | 常勤換算で2.5人以上の看護職員を確保できるか確認する |
| 看護師比率の維持 | 「看護体制強化加算」などを目指す場合、正看護師の割合が6割以上を維持できるかを見積もる |
| 准看護師への教育体制 | 未経験者を採用する場合、同行訪問・OJT・マニュアル整備などを事前に準備しておく |
上記のような準備を通じて、制度基準を満たしながら准看護師を有効に活用できる体制づくりを進めていきましょう。
特に、加算要件や人員基準に準拠した計画的な配置は、返戻や減算を防ぐだけではなく、現場の混乱を避けるためにも欠かせません。
職員が安心して働ける環境を整えることで、結果として組織全体の安定運営にもつながっていきます。
訪問記録・指示書の管理で制度要件を担保する
准看護師を訪問看護に配置するうえで、記録と指示書の管理体制を整えることは制度遵守の必須条件です。
適切な管理ができていない場合、返戻や指導の対象となるリスクが高まります。
そのため、以下のポイントを押さえた運用が求められます。
| 指示の明文化 | 正看護師からの業務指示は、口頭だけではなく文書やシステム上に記録し、第三者にも確認できるようにする |
| 報告の記録徹底 | 准看護師によるケアの実施後は、内容や状態変化を正看護師に報告し、電子カルテや記録用紙に正確に反映させる |
| チームでの定期的確認 | 訪問看護計画書や記録を定期的に確認し、ケアの方針や対応内容にずれが生じていないかをチェックする |
| ICTツールの活用 | ICTツールを活用すれば、指示・報告の流れを効率化できる |
准看護師は、制度上の制限がある一方で、現場では重要な担い手です。
だからこそ、指示・報告の管理を「曖昧な運用」で済ませるのではなく、組織的に仕組み化し、誰が見ても整合性が取れている記録を残すことが大切です。
制度に沿った記録の整備は、トラブルや減算を未然に防ぐためにも、自事業所の管理体制を見直してみましょう。
看護師が主導するオンコール・緊急時対応体制を構築する
准看護師を適切に活用するためには、オンコールや緊急時対応において「正看護師が主導する体制」を明確にしておくことが必要です。
緊急時の判断や指示は、制度上も正看護師が担うべきとされています。
准看護師のみで判断・出動すると、不適切な運用とみなされるリスクがあるほか、利用者やご家族に不安を与えてしまうこともあります。
そこで重要なのが、正看護師が中心となって対応方針を定め、必要に応じて准看護師が指示を受けて対応するフローの構築です。
具体的には以下のようなポイントに注意し、運用体制を整えていきましょう。
- オンコールの電話対応は原則として正看護師が実施する
- 出動時のケア内容は事前にマニュアル化し、正看護師の指示が必須であることを周知する
- 利用者やご家族には、事前に対応体制を丁寧に説明する
上記のように、現場での即時対応力を保ちつつ、制度遵守と安心の両立を目指す体制づくりが必要です。
特にオンコール体制は、外部からも注目されやすい領域です。
書面上の届出だけではなく、実態としても整合性のある運用が求められます。
看護師主導の仕組みを整えることで、准看護師が安心して働ける環境と、利用者の信頼を両立させられるでしょう。

訪問看護の現場では、准看護師の活用がますます重要になる一方で、制度上の制限や指示系統の管理を曖昧にすると、思わぬ減算・返戻リスクが生じます。准看護師は医師または看護師の指示を受けて業務を行う職種であり、自己判断による対応は原則として認められていません。本記事では、准看護師が実施できる業務とその制限、制度面での注意点について、非常に実務的かつ分かりやすく解説されています。特に、オンコール対応や医療処置の判断に関する誤解は多く、組織内で明確な指示体制と記録管理を徹底する必要があります。准看護師を安全に活用するには、法令の趣旨を正しく理解したうえで、配置計画や教育、情報共有の仕組みを整えることが欠かせません。訪問看護に関わるすべての管理者・実務者にとって、本記事は現場運営の再点検に大いに役立つ内容といえるでしょう。
まとめ|准看護師の制度を正しく理解し、減算を防ぐ運用を徹底しよう
准看護師は訪問看護の現場において、採用の幅を広げる重要な人材です。
しかし、制度上の位置づけや業務範囲には明確な制限があり、それを誤解したまま運用してしまうと、減算や返戻などの請求トラブルにつながります。
本記事では、准看護師が訪問看護で担える業務とそうでない業務の違い、正看護師との制度的な違い、そして加算要件や人員基準を守るための運用上のポイントを解説しました。
これらを正しく理解し、記録管理や指示体制を整備すれば、制度に沿った適切なサービス提供が可能になります。
准看護師を制度に沿って適切に活用すれば、サービスの質と運営の安定性を両立できます。
現場での混乱や請求リスクを避けるためにも、記事内容を参考に、あらためて体制の見直しや運用ルールの整備を進めていきましょう。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。