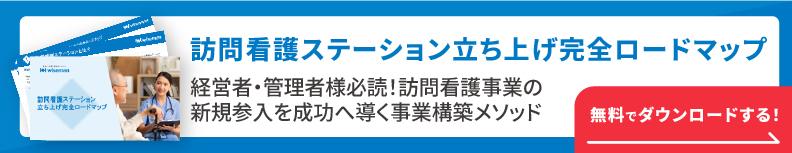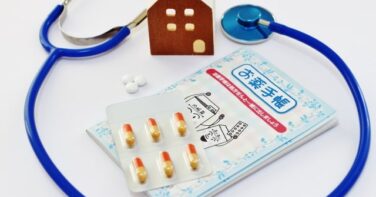訪問看護の必須研修とは?法定研修6種の一覧や計画の立て方を解説
2025.07.20

2024年度の診療報酬改定に伴い、訪問看護における研修の重要性が高まりました。
訪問看護ステーションはスタッフに法定研修を受講させることが必須となっています。
しかし、法定研修は種類が多く、多忙な業務の合間をぬって効率的に受けさせる必要があります。
本記事では、法令で定められた必須研修の全体像から、具体的な年間計画の立て方・費用を抑える方法などについて解説します。
法定研修を通じて、法令遵守はもちろんのこと、研修をスタッフのスキルアップとケアの質向上につなげ、事業所の競争力を高める絶好の機会にしましょう。
訪問看護の法定研修の概要

2024年度の診療報酬改定により、訪問看護ステーションにおける研修の実施がより一層重要視されるようになりました。
まずは、すべての事業所が知っておくべき法定研修の基本的な考え方について解説します。
法定研修とは
訪問看護における法定研修は、質の高い看護サービスを提供するために、医療保険制度および介護保険制度によって義務付けられているものです。
研修内容は、高齢者虐待防止・ハラスメント対策・看護師の資質向上をテーマにした研修など、多岐にわたります。
これらの研修を通じて、利用者のQOL(生活の質)向上に貢献できる知識・技術を習得することが、法定研修の目的です。
法定研修はスタッフの訪問看護に関する能力やスキルを向上させるためだけでなく、利用者の人権尊重や非常時の訪問看護ステーションの対応などをテーマにしたものもあります。
定期的な研修受講は、スタッフの専門性を維持・向上させるうえで不可欠です。
法定研修の対象者
訪問看護ステーションにおける法定研修は、事業運営において不可欠であり、その対象者は、原則としてステーションに勤務するすべての職員におよびます。
これは、看護師や准看護師といった医療資格を持つ者に限定されず、事務職員・リハビリ専門職・介護職など、職種を問わず研修への参加が義務付けられていることを意味します。
法定研修の目的は、訪問看護サービスを提供するうえで必要な知識・技術・倫理観をすべての職員が共有し、サービスの質を向上させることです。
また、感染症対策・個人情報保護・緊急時対応など、安全管理に関する知識の習得も重要な要素です。
すべての職員が研修を通じて、最新の知識やスキルを習得し、共通認識を持つことで、利用者に対してより質の高い、安全な訪問看護サービスを提供できます。
したがって、訪問看護ステーションは、職種に関わらず、すべての職員が法定研修に参加できる体制を整え、質の高いサービス提供を目指す必要があります。
法定研修の頻度
訪問看護の法定研修の頻度について、法律で明確な定めはありません。
しかし、多くの自治体の指導やサービスの質を維持する観点から、年に1回以上の実施が必須とされています。
定期的な研修の実施は、職員の知識・スキルの向上に加え、法令遵守の徹底やサービスの質の維持につながります。
一方で、研修の種類によっては半年や四半期に一度研修の受講が求められる場合があるので注意しましょう。
特に、BCP(事業継続計画)に関する研修は、緊急事態発生時の事業継続を確実にするために、定期的な見直しと訓練が重要です。
BCP研修では、計画の内容理解・役割分担の確認・代替手段の検討などを行い、訓練を通じて実践的な対応能力を養うことが求められます。
研修内容も、法改正や社会情勢の変化に合わせて定期的に見直し、最新の情報を取り入れることが必要です。
法定研修を受けなかった際の罰則
訪問看護ステーションが法定研修を実施しなかった場合、運営基準を満たしていないと見なされ、実地指導での指摘や行政処分を受ける可能性があります。
具体的には、介護報酬の減算や指定の取り消しといった処分が考えられます。
これらの処分はステーションの運営に深刻な影響を及ぼすため、法定研修の実施は経営上の必須事項です。
また、介護報酬が減算されると、ステーションの収入が減少し、経営が圧迫される可能性があります。
さらに、指定が取り消されると、訪問看護サービスを提供できなくなり、事業の継続が不可能となります。
したがって、計画的な研修実施は、法令遵守だけでなく、ステーションの安定的な運営のためにも非常に重要です。
訪問看護で必須の法定研修

2024年度から、すべての訪問看護ステーションで以下の6つの法定研修の実施が義務付けられました。
- 看護師等の資質の向上のための研修
- ハラスメント等防止研修
- 感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修
- 非常災害時の対応に関する研修
- 業務継続計画(BCP)に関する研修
- 高齢者虐待の防止等に関する研修
それぞれの研修がなぜ必要なのか、その目的と内容を具体的に解説します。
看護師等の資質の向上のための研修
この研修は、訪問看護サービスの質の根幹を支えるためのものであり、スタッフの知識や技術を継続的に高めることを目的としたものです。
研修を通じて、最新の医療知識や看護技術を習得し、ケアの質を向上させることを目指します。
フィジカルアセスメント技術の向上・医療機器の安全な操作方法の習得・リスクマネジメント(インシデント事例の共有と対策)・倫理的な課題への対応方法などが研修内容です。
それぞれの研修を受講すれば、スタッフはより質の高い訪問看護サービスを提供できます。
継続的な学習と実践を通じて、専門職としての成長を促進し、変化する医療ニーズに対応できる能力を養います。
倫理的な問題への対応能力を高めることは、利用者の権利擁護にもつながり、信頼関係を構築するうえで不可欠です。
ハラスメント等防止研修
訪問看護におけるハラスメント等防止研修は、スタッフが安心して業務を遂行できる環境を整備し、質の高い看護サービスを提供するために不可欠です。
研修では、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・ジェンダーハラスメント・カスタマーハラスメントといった多様なハラスメントの種類・定義・具体例を学びます。
訪問看護の現場は、患者宅という密室空間での業務が多いため、ハラスメントのリスクが高い側面があります。
研修を通じて、具体的な事例に基づいた対応方法や、万が一被害に遭った際の相談窓口・訪問看護ステーションとしてのサポート体制について理解を深めることが重要です。
管理職向けの研修では、ハラスメントの兆候を早期に発見し、適切な対応を行うための知識やスキルを習得します。
訪問看護事業者は、研修の実施を通じて、従業員の意識向上を図り、ハラスメントのない健全な職場環境を構築することで、離職率の低下やサービス品質の向上につなげることが期待されます。
感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修
在宅療養中の利用者にとって、感染症は非常に深刻なリスクとなるものです。
そのため、スタッフは感染症予防に関する十分な知識を持ち、適切な対策を徹底することが不可欠です。
この研修は、感染症や食中毒の発生を未然に防ぎ、万が一発生した場合でもその拡大を最小限に抑えることを目的としています。
研修内容としては、まず基本となる標準予防策の徹底が挙げられます。
これは感染の有無にかかわらず、すべての利用者・職員・関係者に対して行うべき基本的な感染予防策です。
加えて、感染経路別の予防策として、接触感染・飛沫感染・空気感染といった各経路に応じた具体的な対策に加え、手指衛生の重要性を再認識し、正しい手順とタイミングを習得します。
手指衛生は、感染予防の基本中の基本であり、適切な方法で行うことで感染リスクを大幅に低減できます。
また、個人防護具(手袋・マスクなど)の適切な着脱方法についても学ぶ点も特徴です。
この研修を通して、訪問看護職員は感染症に対する意識を高め、日々の業務の中で適切な感染予防策を実践できるようになることが期待されます。
非常災害時の対応に関する研修
訪問看護における非常災害時対応研修は、地震・水害・火災といった予期せぬ災害発生時において、利用者と職員の生命を守ることを目的としたものです。
研修では、迅速かつ的確な判断と行動ができるよう、具体的な行動計画を確認します。
まず、地域のハザードマップを確認し、災害リスクを把握することが重要です。
これにより、どのような災害が起こりやすいのか、事前に理解を深められます。
加えて、安否確認の方法と緊急連絡網の整備も研修内容です。
災害発生時、迅速に連絡を取り合い、安否を確認できる体制を整えることは、混乱を最小限に抑えるうえで欠かせません。
避難経路と避難場所の確認も重要な要素です。
安全な避難経路を複数把握し、避難場所までの移動手段や注意点を確認することで、いざという時にスムーズな避難行動が可能となります。
さらに、食料・水・医薬品・懐中電灯など、必要な非常用物資を事前に準備し、定期的に点検しましょう。
これらの研修内容を通じて、訪問看護職員は災害に対する意識を高め、具体的な対策を講じることで、利用者と自身の安全を確保し、地域社会への貢献を目指します。
業務継続計画(BCP)に関する研修
業務継続計画(BCP)とは、災害や感染症のまん延といった緊急事態が発生しても、必要なサービスを継続するための計画です。
業務継続計画に関する研修は、2024年度から完全義務化され、特に重要性が高まりました。
この研修は、緊急時でもサービスを継続するための計画を策定し、全職員で共有・訓練することを目的としています。
研修では、BCPの目的と重要性を理解し、優先して継続すべき業務を特定します。
また、職員や物資など限られた資源の配分計画を策定し、BCPに基づいたシミュレーション訓練を実施することで、緊急時における対応能力を高めます。
高齢者虐待の防止等に関する研修
訪問看護における高齢者虐待防止研修は、利用者の尊厳を守り、権利を擁護するために欠かせません。
高齢者虐待防止法に基づき、虐待の未然防止・早期発見・適切な対応を目的とした研修です。
研修では、身体的虐待・心理的虐待・経済的虐待・性的虐待・ネグレクトといった虐待の種類や兆候を理解し、早期発見のための視点を養います。
また、虐待を発見した場合の通報義務や関係機関との連携方法・利用者の権利擁護と倫理についても学びます。
研修コストを抑える方法

法定研修の重要性は理解していても、すべての職員に研修を受けさせるとなると、費用や時間の確保が大きな課題となります。
しかし、国の制度や新しい学習方法をうまく活用することで、コストを抑えながら効果的な研修の実施が可能です。
助成金・補助金の活用
国や自治体は、事業所の人材育成を支援するための助成金・補助金制度を設けています。
以下のものを活用することで、研修費用の負担を大幅に軽減できます。
| 制度名 | 概要 |
| 人材開発支援助成金 | 厚生労働省が提供する制度で、研修費用や研修期間中の賃金の一部が助成されます 。 |
| 地域医療介護総合確保基金 | 都道府県が主体となり、医療・介護従事者の研修を支援する制度です。 |
| 市区町村独自の補助金 | 自治体によっては独自の補助金制度があるため、事業所の所在地の役所に確認してみましょう。 |
eラーニングの活用
eラーニングは、時間や場所を選ばずに学習できるため、多忙な訪問看護スタッフにとって有効な研修方法です。
移動時間や会場費がかからず、コスト削減にもつながります。
昨今は専門性の高い研修もeラーニングで提供されるケースが増えました。
例えば、精神科訪問看護基本療養費を算定するために必須となる研修も、オンラインで受講可能なプログラムがあります 。
訪問看護ステーションの研修計画の立て方

研修を場当たり的に行うのではなく、計画的に実施することが、法令遵守とケアの質向上の両立につながります。
本章では、実用的で無理のない研修計画を立てるための2つのステップを紹介します。
年間研修計画を立てる
まずは、1年間の見通しを立てることから始めましょう。
法定研修を網羅し、「いつ」「何を」「誰を対象に」実施するかを一覧にすることで、計画の抜け漏れを防ぎます。
年間研修計画は以下のように作成しましょう。
| 研修予定月 | 研修テーマ | 主な内容 | 対象者 |
| 4月 | 新年度キックオフ研修 | 今年度の事業方針・ハラスメント防止 | 全職員 |
| 5月 | 感染症対策研修 | 梅雨時期に向けた食中毒予防・最新の感染症情報 | 全職員 |
| 7月 | 医療安全研修① | 転倒や転落の防止・熱中症対策 | 全職員 |
| 9月 | 非常災害時対応研修 | 台風や水害への備え・BCP訓練 | 全職員 |
| 11月 | 虐待防止研修 | 虐待の早期発見・権利擁護 | 全職員 |
| 1月 | 資質の向上に関する研修 | ターミナルケア・看取りについて | 看護職員 |
| 3月 | 医療安全研修② | 年度末の振り返り・ヒヤリハット事例共有 | 全職員 |
研修記録をシステムで効率的に管理する
研修を実施したら、その記録を適切に保管する義務があります。
しかし、職員全員分の記録を紙やExcelで管理するのは非常に煩雑です。
そこでおすすめなのが、研修管理機能を備えたシステムの活用です。
ICTを活用することで、記録業務を効率化し、本来のケア業務に集中する時間を生み出せます。
| システムの種類 | 主な機能 | メリット |
| 訪問看護ステーション向け介護ソフト | ・研修受講履歴の記録 ・管理・職員ごとの受講状況の把握 ・各種帳票との連携 | ・日々の記録業務と一元管理できる ・システムによってはeラーニング機能も搭載 |
| eラーニングシステム | ・オンラインでの研修受講 ・自動での受講履歴管理 ・理解度テストの実施 | ・時間や場所を選ばず受講できる ・集合研修に比べコストを抑えられる |
| 医療介護連携サービス | ・多職種間での情報共有 ・研修資料の共有 | ・地域全体での研修レベル向上に貢献 ・スムーズな連携体制を構築できる |

2024年度の診療報酬改定で義務化された訪問看護の法定研修は、利用者のQOL向上とスタッフの専門性維持に不可欠な重要な取り組みです。高齢者虐待防止、ハラスメント対策、感染症予防、自然災害・感染症BCP、非常災害時対応、看護師等の資質向上など6種類の研修が全職員に必須で、年1回以上の実施が求められます。これらの研修は、利用者への質の高い安全なサービス提供、職員の知識・スキル向上、人権尊重、非常時対応能力の習得を目的としています。未実施の場合、介護報酬の減算や指定取消の罰則規定があり、事業所の安定運営に深刻な影響を及ぼします。助成金やeラーニングを賢く活用しながら、年間計画の策定やICTシステムでの効率的な記録管理を進めることで、コストを抑えつつ法令遵守と質の高いケアを両立させ、利用者から選ばれる事業所の競争力向上に繋げることが可能です。
計画的な研修で法令遵守と質の高い訪問看護ケアを両立しよう

2024年度から義務化された法定研修は、訪問看護ステーションにとって避けては通れない重要な取り組みです。
一見、業務負担が増えるように感じるかと思いますが、法定研修はサービスの質と安全性を高めるだけでなく、利用者や職員を守るための重要な投資でもあります。
今回ご紹介したように、まずは6つの法定研修を盛り込んだ年間計画を立てることから始めてみましょう。
また、助成金やICTシステムを賢く活用することで、コストや手間を抑えながら、効果的な研修の実施が可能です。
計画的な研修を通じて、法令を遵守しながら、利用者から選ばれる訪問看護ステーションを目指していきましょう。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。