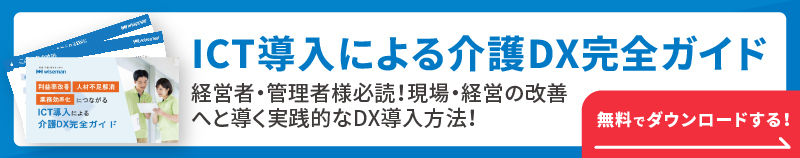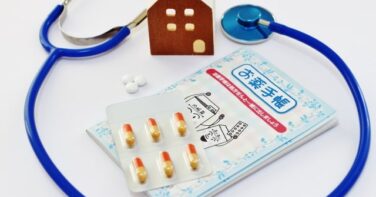訪問看護のオンコールとは?内容や頻度などについて解説
2025.07.20

訪問看護ステーションにおいて、オンコールは重要性が高い業務です。
一方で、オンコールは重い責任を伴ううえに、スタッフに負担がかかりやすい一面があります。
本記事ではオンコールの基本的な概要・具体的な業務内容に加え、スタッフの負担を削減する方法などについて解説します。
オンコール業務の改善は、訪問看護ステーションの利用者にとっても重要です。
ぜひ参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
訪問看護のオンコールとは

まずは、訪問看護におけるオンコールの基本的な役割と制度上の位置づけについて理解を深めましょう。
在宅療養を支えるうえで、オンコールがいかに重要であるかが見えてきます。
オンコールの業務内容
訪問看護のオンコールとは、担当する利用者の緊急時に備えて、勤務時間外でも対応できるように待機する業務のことです。
具体的には、利用者やその家族から事業所の緊急連絡用携帯電話などに連絡があった際に、電話で対応したり、必要に応じて自宅へ訪問したりします。
この体制があることで、利用者や家族は24時間365日、いつでも専門家である看護師に相談できるという安心感を得られます。
オンコールが担う主な役割は以下のとおりです。
- 利用者や家族の急な不安を和らげる
- 容態の変化を早期に発見し、重症化を防ぐ
- 不要な救急搬送や緊急入院を回避する
まさに、オンコールは在宅療養を支えるための重要なセーフティーネットと捉えられます。
訪問看護におけるオンコールの重要性
オンコールは、ただの任意サービスではありません。
介護保険制度や医療保険制度において、質の高い在宅療養支援を提供する証として正式に評価されています。
具体的には、「緊急時訪問看護加算」や「24時間対応体制加算」といった形で診療報酬・介護報酬に反映されます。
実際に、厚生労働省のデータによると、全国の訪問看護ステーションの約86%がこの緊急時訪問看護加算を算定しており、多くの事業所がオンコール体制を整えていることがわかります。
この加算を算定するためには、いつでも連絡が取れる体制や、緊急訪問ができる人員の確保などが求められます。
つまり、オンコールは国からも推奨される、訪問看護の質の高さを担保する重要な機能です。
参照:訪問看護|厚生労働省
訪問看護オンコールの種類

オンコール対応は、大きく分けて「電話による対応」と「緊急訪問による対応」の2種類があります。
かかってくる連絡の多くは電話相談で解決しますが、状況によっては迅速な訪問が求められることもあります。
本章では、それぞれの対応について、あらためて確認しましょう。
電話によるオンコール
電話によるオンコールは、利用者や家族からの電話連絡を受け、状況をヒアリングし、必要なアドバイスを行う対応が基本です。
実際には、ほとんどのケースがこの電話対応で完結するとされています。
相談内容は多岐にわたりますが、主に以下のようなものが挙げられます。
| 相談内容 | 例 |
| 症状に関する相談 | 「熱が出た」「呼吸が苦しそう」「痛みが強い」など |
| 医療機器に関する相談 | 「在宅酸素の機械の調子が悪い」「カテーテルが詰まったかもしれない」など |
| 薬剤に関する相談 | 「薬の飲み方がわからない」「副作用が心配」など |
| 精神的な不安 | 「一人でいると心細い」「眠れない」といった精神的なサポートを求める相談 |
訪問によるオンコールと違って体力的な負担は少ないものの、電話によるオンコールの重要性は低くありません。
電話口で冷静に状況を判断し、的確な助言を行うためには、高度な知識とコミュニケーション能力が求められます。
訪問によるオンコール
電話でのヒアリングの結果、直接的なケアや処置が必要だと判断した場合に行うのが緊急訪問です。
看護師が利用者の自宅へ駆けつけ、必要な対応を行います。
例えば、以下のような状況では緊急訪問が必要と判断されます。
- 転倒してしまい、自力で起き上がれない
- 呼吸困難が続き、SpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)が低下している
- カテーテルなどの医療機器に明らかなトラブルが発生している
- 強い痛みを訴え、電話での指示だけではコントロールが難しい
訪問によるオンコールは深夜や早朝の出動になることもあり、体力的な負担も伴うものです。
しかし、利用者の安全を直接守る重要な役割を担っています。
訪問看護オンコールの頻度

オンコールの頻度は、事業所の体制などによって大きく異なります。
明確な基準はありませんが、一般的にはスタッフの人数に比例して1人あたりの担当回数は少なくなります。
例えば、看護師が10名在籍している事業所の場合、1カ月で100件程度のオンコールが発生すれば、単純計算で1人あたり月におよそ3〜4回程度オンコール当番が回ってくる計算です。
ただし、常勤・非常勤の割合や、子育て中のスタッフへの配慮などによっても変動するので注意しましょう。
訪問看護オンコールの手当

オンコール業務には、その負担に見合った手当を支給する事業所がほとんどです。
手当は大きく分けて「待機手当」と「出動手当」の2種類があります。
待機手当は、いわゆる「オンコール手当」として、1回あたりに定額を支給するのが一般的です。
金額は事業所や地域によって異なりますが、全国訪問看護事業協会のデータによると以下のような相場観があります 。
| 項目 | 平均的な待機手当(1回あたり) |
| 平日 | 1,000円~3,000円 |
| 休日 | 2,000円~5,000円 |
参照:訪問看護ステーションにおける24時間対応体制に関する調査研究事業報告書|一般社団法人全国訪問看護事業協会
一方、出動手当は、実際に緊急訪問を行った場合に、労働基準法に基づき時間外手当(残業代)として支払われます。
こちらは移動時間も含めて労働時間とみなされ、深夜であれば割増賃金が適用されます。
給与体系にオンコール手当がどのように組み込まれているか、評価制度はどうなっているかなども、スタッフの働きがいに関わる重要な要素です。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
オンコールの具体的な対応事例

実際のオンコールで実施する対応は利用者によって異なりますが、本章では以下の事例について解説します。
- 事例①終末期がん患者の疼痛管理
- 事例②独居高齢者の転倒
- 事例③認知症患者による健康相談
それぞれのケーススタディを通して、オンコール対応のリアルな流れを見ていきましょう。
事例①終末期がん患者の疼痛管理
70代男性、在宅で終末期がんの療養中。
夜間に「痛みが強くて眠れない」と家族からオンコールが入った。
| 段階 | 内容 |
| 電話対応 | まずは電話で患者の状態(痛みの強さ・部位・性質など)を詳しくヒアリング。事前に医師から指示されていた鎮痛剤の追加使用を家族に指示した。 |
| 緊急訪問判断 | 電話だけでは痛みが治まらず、患者の不安も強いため、緊急訪問を決定。 |
| 訪問後の対応 | 自宅に到着後、NRSスケール(疼痛評価スケール)を用いて痛みを客観的に評価。バイタルサインも確認し、患者の手を握りながら傾聴し、精神的なサポートを実施。 |
| 結果 | 適切なケアにより痛みが緩和し、患者は無事に睡眠状態に入った。この対応により、夜間の緊急入院を回避でき、住み慣れた自宅での療養の継続を実現した。 |
事例②独居高齢者の転倒
80代女性、一人暮らし。
夜中にトイレに行こうとして転倒し、起き上がれないと本人からか細い声で連絡があった。
| 対応 | 内容 |
| 電話対応 | 意識状態や怪我の有無を確認しようとしますが、電話口では詳細な状況把握が困難。直ちに緊急訪問が必要と判断。 |
| 緊急訪問判断 | 管理者や他のスタッフに状況を報告し、救急要請の可能性も伝えながら自宅へ向かう。 |
| 訪問後の対応 | 現場に到着し、バイタルサインを測定すると血圧が200/100mmHgと高値。意識レベルはJCS(ジャパン・コーマ・スケール)でI-1。脚の変形と強い痛みを認めたため、大腿骨骨折を疑い、その場で救急車を要請した。 |
| 結果 | 救急隊到着まで応急処置を行い、病院へスムーズに引き継いだ。早期の適切な判断と対応により、重症化を防止した。 |
事例③認知症患者の健康相談
日中の様子とは違い、夜になると不安が強くなる認知症の利用者。
その家族から「いつもと様子が違うのですが、どうしたらいいでしょうか」と不安げな声で電話があった。
| 対応 | 内容 |
| 電話対応 | まずは家族の不安な気持ちに寄り添ったうえでヒアリング。さらに「具体的にどのような様子ですか?」「食事や水分は摂れていますか?」など、状況をアセスメントするための質問を実施。 |
| アドバイスと安心感の提供 | BPSD(行動・心理症状)の可能性を考え、部屋を明るくしたり、好きな音楽をかけたりといった環境調整を提案。何よりも「私たちはいつでも連絡が取れるので大丈夫ですよ」と伝え、家族の不安を軽減した。 |
| 訪問判断 | 緊急性は低いと判断し、翌朝一番で訪問して様子を確認することを約束。電話で完結させるが、家族に安心感を与えることで、不要な救急要請を防止する。 |
| 結果 | 家族は安心して夜を過ごし、翌日の訪問であらためてケアの方針を話し合えた。 |
訪問看護オンコールの負担が大きい理由

オンコールが在宅医療に不可欠な一方で、担当するスタッフにとっては大きな負担となる現実があります。
スタッフの負担が大きい理由は以下のとおりです。
- 24時間対応する必要がある
- スタッフにかかる責任が重い
- 休息が取りにくい
- 飲酒ができない
それぞれについて、順番に解説します。
24時間対応する必要がある
24時間対応する必要があるオンコールのもっとも大きな負担は、やはり「いつ鳴るかわからない」という精神的なプレッシャーです。
担当日は、たとえ深夜であっても常に緊張感を持ち続けなければなりません。
これにより、深い睡眠が取れなかったり、休日でも心からリラックスできなかったりすることがあります。
オンコール担当のスタッフが、睡眠不足や精神的ストレスを感じていることは珍しくありません。
この継続的な緊張状態は、心身の疲労や燃え尽き症候群につながる大きな要因となります。
スタッフにかかる責任が重い
オンコールの担当になったスタッフの多くは、重責を感じるものです。
精神的なプレッシャーに加え、電話1本で下さなければならない判断の重さも大きなストレスです。
限られた情報の中で、緊急訪問や救急要請の要否を判断し、その結果に責任を負わなければなりません。
患者情報の保護(個人情報保護法)や医療過誤のリスクといった法的・倫理的な課題も常に意識する必要があり、その責任の重さが負担感を増大させています。
休息が取りにくい
職務の性質上、オンコールは休息が取りにくい点にも注意が必要です。
オンコールの担当となったスタッフは長時間拘束されることも珍しくないため、特に子育てをしているスタッフにとっては大きな負担になりがちです。
家庭の事情でオンコールの対応が難しいスタッフがいれば、離職するリスクが高まります。
安定したオンコールを実施するうえでも、子育て中のスタッフに対するシフトの配慮や、緊急時のサポート体制の整備などの施策が不可欠です。
飲酒ができない
見落とされがちですが、オンコールを担当するスタッフにとって「飲酒ができない」などのようなプライベートな制約もストレスの一因です。
オンコール当番の日は、いつ出動要請があるかわからないため、当然ながら飲酒はできません。
「仕事終わりの一杯」や、友人との食事会でお酒を楽しむといった、ささやかなリフレッシュの機会が制限されてしまいます。
こうしたプライベートな制約の積み重ねが、精神的な息苦しさにつながることも少なくありません。
オンコールの負担を軽減する5つの取り組み

厳しい現実がある一方で、オンコールの負担を軽減するために、以下のような工夫や取り組みも進んでいます。
- シフトの最適化
- 体制づくりと事前の情報共有
- 外部の訪問看護ステーションとの連携
- ICT活用で業務効率化
- オンコール代行サービスの導入
本章ではそれぞれのアプローチを順番に紹介します。
シフトの最適化
もっとも直接的な負担軽減策はシフトの最適化です。
以下のような柔軟なスケジューリングを導入することで、個々のスタッフの負担を分散させられます。
| 体制 | 詳細 |
| 複数名体制 | オンコール担当を常に2名以上配置し、相談しながら対応したり、交代で仮眠を取ったりする体制。 |
| 階層型システム | 経験豊富な看護師をセカンドコール担当とし、ファーストコールの看護師が判断に迷った際に相談できる体制。新人の不安軽減にも繋がります。 |
| 柔軟な勤務体系 | フレックスタイム制や時短勤務、週休3日制などを導入し、個々のライフスタイルに合わせた働き方を可能にする。 |
体制づくりと事前の情報共有
個々の看護師に負担が集中しないよう、組織全体で支える体制づくりが重要です。
特に効果的なのが、日ごろからの密な情報共有です。
毎日のカンファレンスや情報共有ツールを活用し、「誰が電話を取っても、ある程度の状況がわかる」状態を作っておくことが、いざという時の判断の迷いを減らし、精神的な負担を大きく軽減します。
また、経験豊富な看護師と経験の浅い看護師をペアにする「スキルミックス」も有効です。
ベテランの知識や経験を共有することで、チーム全体の対応力が向上し、新人の育成にもつながります。
外部の訪問看護ステーションとの連携
外部の訪問看護ステーションとの連携は、オンコールの負担軽減に大きく貢献する施策です。
自ステーションの対応可能時間外や、対応困難なケースを外部に委託することで、看護師の心身の負担を軽減し、疲弊を防ぎます。
また、専門性の高い看護を提供できるステーションと連携することで、より質の高い在宅医療の提供が可能となり、患者満足度の向上にもつながります。
さらに、連携を通じて得られる知識やノウハウは、自ステーションのスキルアップにも貢献します。
ICT活用で業務効率化
近年、オンコール業務の負担軽減に大きく貢献しているのがICT(情報通信技術)の活用です。
例えば、訪問看護ステーション向けの介護ソフトやスマートデバイスで使用できる訪問職員向けの介護記録ソフトなどを活用すれば、多職種間での情報共有もスムーズになり、より質の高いチームケアの提供が可能です。
また、電子カルテシステム「ワイズマンシステムSP」などを活用すれば、多職種間での情報共有もスムーズになり、より質の高いチームケアが実現できます。
ICTの導入は、移動時間や対応時間の短縮だけでなく、何よりも「判断の迷い」という精神的負担を減らすための強力な武器となります。
オンコール代行サービスの導入
オンコール業務の一部を外部の専門業者に委託する「オンコール代行サービス」も検討しましょう。
オンコール代行サービスとは、利用者からの最初の電話(ファーストコール)を代行業者が受け、内容を整理したうえで、緊急性の高い要件のみを訪問看護師につなぐサービスです。
これにより、看護師は緊急性の低い電話や間違い電話に対応する必要がなくなり、負担が大幅に軽減されます 。
ただし、緊急時訪問看護加算などを算定している場合、代行サービスの利用には一定の制約があるため、導入を検討する際は、自事業所の状況と制度要件を照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

訪問看護におけるオンコールは、勤務時間外に利用者の緊急時対応に備える重要な業務です。これは単なる任意サービスではなく、「緊急時訪問看護加算」や「24時間対応体制加算」として診療報酬・介護報酬で評価され、在宅療養を支えるセーフティーネットとして機能します。オンコールは主に電話対応と緊急訪問の2種類があり、電話で解決するケースが多いものの、状況によっては深夜や早朝の訪問が必要です。
しかし、オンコールはスタッフにとって大きな負担となります。24時間いつ連絡が来るか分からない精神的プレッシャー、重い責任、休息の取りにくさ、飲酒制限などがその理由です。この負担軽減のため、シフトの最適化、情報共有の徹底、外部連携、ICT活用による業務効率化、オンコール代行サービスの導入といった多様な取り組みが進められています。これらの対策により、質の高い在宅ケア継続とスタッフの負担軽減の両立を目指しています。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
効率化によって訪問看護オンコールの負担を軽減しよう
オンコールは、在宅で療養する利用者とその家族の「最後の砦」として、かけがえのない安心を届ける非常に重要な役割を担っています。
一方で、重責を伴うこともあって、オンコールがスタッフにとって大きな負担になる場面も少なくありません。
オンコールを実施する際は、スタッフの負担に配慮しつつ、利用者への最適なケアを効率的に提供できる体制を整えましょう。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。