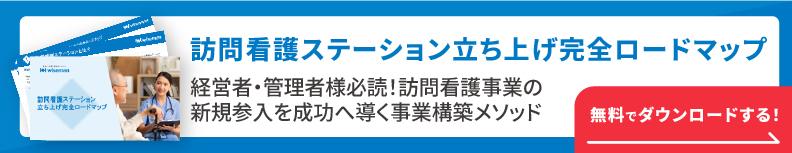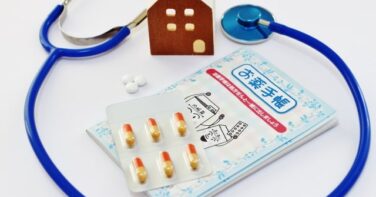【2025年最新版】訪問看護の法律を徹底解説!制度の全体像から実務までを理解しよう
2025.07.20

訪問看護事業所は利用者の在宅療養を支えるためにさまざまな制度を理解し、適切なサービスを提供しています。複雑な制度の中で、利用者やその家族が安心してサービスを受けられるよう法律の知識は欠かせません。
本記事では、訪問看護に関連する法律の全体像を解説します。医療保険と介護保険の違いや利用手続きの流れなど、幅広い情報を網羅しています。利用者にとって最適な選択を支援できるようともに学び、成長していきましょう。
目次
訪問看護に関わる3つの主要法律

訪問看護は、主に3つの法律に基づいて提供されています。どの法律が適用されるかによって、対象者やサービス内容が異なります。
ここでは、それぞれの法律の役割と概要を見ていきましょう。
参考:訪問看護
介護保険法:訪問看護の基本となる法律
介護保険法は、訪問看護の基本となる法律です。65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方、または40歳以上64歳までで特定の疾病を持つ方が対象です。
ケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、日常生活の支援や身体介護が中心のサービスを提供します。介護保険法に基づく訪問看護のポイントは以下のとおりです。
| 対象者 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
| サービス内容 | ケアプランに沿った療養上の世話や診療の補助 |
| 利用限度額 | 要介護度に応じて、1カ月あたりの利用上限額が設定されている |
健康保険法:医療保険適用の訪問看護
医療保険(健康保険)を使った訪問看護は、病状が不安定な方やより専門的な医療処置が必要な場合に利用されます。
介護保険の対象者であっても、厚生労働大臣が定める特定の疾病の方や病状の急性増悪期には医療保険が優先されます。年齢に関わらず、医師が訪問看護の必要性を認めた場合に適用されるのが特徴です。
医療保険が適用される主なケースは以下のとおりです。
- 厚生労働大臣が定める疾病(末期がん、難病など)の方
- 要介護認定を受けていない方
- 精神科訪問看護が必要な方
- 病状の急性増悪や退院直後で、一時的に頻回な訪問が必要な方
高齢者の医療の確保に関する法律
この法律は、主に75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」を定めています。訪問看護を利用する際、75歳以上の方はこの法律に基づく医療保険を使うことが一般的です。
基本的な仕組みは健康保険法と同様ですが、自己負担割合などが異なる場合があります。
参考:高齢者の医療の確保に関する法律 | e-Gov 法令検索
訪問看護の実務で知っておくべき法律の重要ポイント

訪問看護を実際に利用したり、提供したりする場面では、いくつかの重要な書類やルールが設けられています。これらは法律に基づいており、安全で質の高いケアを確保するために不可欠です。
ここでは、特に重要な3つのポイントについて解説します。
法律に基づいた記載例:訪問看護指示書の書き方と注意点
訪問看護は、医師が発行する「訪問看護指示書」がなければ開始できません。訪問看護が医療行為の一環であり、医師の指示のもとで行われることを法律で定めているためです。
指示書には利用者の病状や必要なケアの内容、注意点などが具体的に記載されています。
| 指示書の主な記載項目 | 内容 |
| 指示期間 | ・最大6カ月まで ・定期的な見直しが必要 |
| 利用者の病名・症状 | ケアの根拠となる基本情報が記載されている |
| 必要な処置の内容 | 点滴や褥瘡の処置といった具体的な指示が記載されている |
| 日常生活の注意点 | 食事制限や活動範囲など、療養上の留意事項が記載されている |
訪問看護記録の重要性:法的根拠と記録すべき内容
看護師は、訪問ごとに行ったケアの内容を「訪問看護記録」として詳細に残します。この記録は、単なる業務日誌ではありません。
質の高いケアを継続するための情報共有ツールであると同時に、法的な証拠としての役割も持ちます。訪問看護記録に記載すべき主な内容は以下のとおりです。
- 利用者のバイタルサイン(体温や脈拍、血圧など)
- 実施したケアの内容(清拭や医療処置など)
- 利用者の心身の状態や発言
- 家族への指導や相談内容
- 医師への報告事項
上記の記録はサービスの質を証明し、万が一のトラブルの際に事業者と利用者の双方を守る重要な役割を果たします。
個人情報保護法と訪問看護:患者情報の適切な管理
訪問看護では利用者の病状や生活背景など、非常にプライベートな情報を取り扱います。そのため、個人情報保護法を遵守し、情報を厳格に管理することが法律で義務付けられています。
事業者は情報の取り扱いについて明確なルールを定め、スタッフに周知徹底しなければいけません。
| 個人情報保護で遵守すべきこと | 具体的な対応 |
| 目的外利用の禁止 | ケア以外の目的で個人情報を使用してはいけない |
| 安全管理措置 | 情報の漏えいや紛失を防ぐための対策が必要である |
| 第三者提供の制限 | 本人の同意なく、外部に情報を提供することは原則禁止されている |
| 開示・訂正の請求への対応 | 本人から求められた場合、情報の開示や訂正に応じる義務がある |
【医療保険と介護保険】訪問看護における適用条件の違い

訪問看護を利用する際、医療保険と介護保険のどちらが適用されるかは、利用者にとって大きな関心事です。自己負担額や利用できるサービス量が変わるため、その違いを正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、両者の主な違いを比較しながら見ていきましょう。
対象疾患と年齢制限:医療保険と介護保険の差
適用される保険は、主に年齢と病状によって決まります。基本的には介護保険が優先されますが、特定の条件に当てはまる場合は医療保険が適用されます。
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
| 年齢 | ・65歳以上 (第1号被保険者) ・40~64歳で特定疾病あり (第2号被保険者) | 年齢制限なし |
| 条件 | 要支援・要介護認定を受けていること | 医師が訪問看護の必要性を認めた場合 |
| 優先順位 | 原則として介護保険が優先される | 特定の疾病や急性増悪期などは医療保険が優先される |
利用回数と時間制限:保険種別による違い
利用できる回数や時間にも、保険によって異なります。介護保険はケアプランの範囲内で、医療保険は原則として週3回までと定められています。
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
| 利用回数 | ケアプランの限度額の範囲内であれば制限なし | 原則として週3日まで |
| 1回あたりの時間 | 20分、30分、60分、90分以上など多様な区分がある | 30分~90分が一般的 |
| 例外的な利用 | – | 特別訪問看護指示書が出た場合、週4日以上の訪問が可能(最大14日間) |
自己負担額:医療保険と介護保険の負担割合
自己負担額の計算方法も異なります。介護保険はサービス単位ごとの料金ですが、医療保険は定額の部分と出来高の部分があります。
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
| 自己負担割合 | 原則1割(所得に応じて2割または3割) | ・70歳未満:3割 ・70~74歳:原則2割 ・75歳以上:原則1割(所得に応じて2割または3割) |
| 高額療養費制度 | 「高額介護サービス費」として上限額を超えた分が払い戻される | 「高額療養費制度」として上限額を超えた分が払い戻される |
| その他 | 交通費などが別途自己負担となる場合がある | 交通費などが別途自己負担となる場合がある |
【訪問看護の対象者別】法律・制度の違い

訪問看護は高齢者だけでなく、精神疾患を持つ方や小児、難病患者などの幅広い層に利用されています。対象者によって関連する法律や制度が異なり、より専門的な支援が提供されます。
精神科訪問看護:精神保健福祉法との関連性
精神疾患を持つ方の在宅療養を支えるのが、精神科訪問看護です。このサービスは医療保険が適用され、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の理念に基づいています。
地域社会での自立を支援するため、以下のような専門的なケアが行われます。
- 服薬管理や副作用のモニタリング
- 対人関係や日常生活スキルの維持・向上
- 症状の悪化の予防と早期発見
- 家族からの相談対応や社会資源の紹介
小児訪問看護:児童福祉法との関連性と特徴
生まれつきの病気や障がいにより、医療的ケアが必要な子どもたちも訪問看護の対象です。小児訪問看護は児童福祉法の理念に基づき、子どもの健やかな成長と発達を支援します。
成人の訪問看護とは異なる、以下のような特徴があります。
| 対象 | 0歳から18歳未満の医療的ケア児など |
| ケア内容 | 人工呼吸器の管理や経管栄養、発達支援など |
| 連携 | 学校や地域の支援機関との密な連携が不可欠 |
| 家族支援 | 兄弟姉妹を含めた家族全体のケアも重視 |
難病患者への訪問看護:特定疾患医療受給者証の活用
国が指定する難病を持つ方は、医療費の助成を受けられる制度があります。訪問看護を利用する際も「特定医療費(指定難病)受給者証」を提示すると、自己負担額が軽減されるのが特徴です。
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき、長期にわたる療養生活を経済的・社会的に支える仕組みが整っています。
訪問看護の利用の流れと手続き:法律に基づいた安心利用ガイド

ここからは、訪問看護サービスを提供する際の一般的な流れを紹介します。
訪問看護に関する相談窓口
訪問看護が必要になったら、本人またはその家族が身近な専門家に相談します。
| 相談先 | 役割 |
| ケアマネジャー | ・介護保険利用の最初の窓口 ・ケアプラン作成の中心としての役割を担う |
| 病院の地域連携室・相談室の担当者 | 入院中や退院後の不安がある方の相談に乗り、退院後の訪問看護の手配を担当者がしてくれる |
| かかりつけ医 | ・本人の病状を良く理解しており、訪問看護の必要性を判断してくれる ・訪問看護指示書を発行する |
| 市区町村の窓口の担当者 | ・地域の介護・医療サービスの情報提供や相談に応じてくれる ・訪問看護の情報も提供してくれる |
訪問看護計画の作成と同意:利用者の権利
契約後、訪問看護ステーションの看護師が利用者や家族と面談し「訪問看護計画書」を作成します。この計画書には目標や具体的なケア内容が明記されており、利用者は内容に同意した上でサービスを受ける権利があります。
計画書は定期的に見直しを行い、利用者の状態に合わせて更新します。
契約と費用:法律で定められた重要事項
訪問看護ステーションと正式に契約を結ぶ際には、重要事項説明書が交付されます。これには法律で定められた内容が記載されており、訪問看護サービスを提供する前に十分に理解してもらうことが大切です。
契約時に確認してもらう主な項目は以下のとおりです。
- 運営法人の概要
- サービス内容と料金体系
- スタッフの体制
- 苦情相談の窓口
- 緊急時の対応方法
利用者に説明を行う際は難しい言葉を使用せず、わかりやすい内容で説明しましょう。利用に関する疑問や不安点を解消できるように、説明時間を十分に確保することが大切です。
【訪問看護の義務化】制度改正の最新情報と今後の展望

訪問看護を取り巻く制度は、社会のニーズに合わせて常に変化しています。特に近年では在宅医療の重要性が増す中で、訪問看護ステーションに求められる役割も大きくなっています。
ここでは、最近の動向や今後の見通しについて見ていきましょう。
訪問看護ステーションの義務と責任
訪問看護ステーションは法律に基づいて運営しており、安全で質の高いサービスを提供する義務を負っています。主な基準として、以下の3つが定められています。
| 基準の種類 | 内容 |
| 人員基準 | 看護師などを常勤換算で2.5人以上配置することなどが定められている |
| 設備基準 | 事業の運営に必要な広さの事務室や、感染予防のための設備が必要である |
| 運営基準 | 訪問看護計画書の作成や緊急時対応、記録の整備など運営に関するルールが設けられている |
特に、2024年度からは感染症や災害発生時に備えた業務継続計画(BCP)の策定が義務化されました。
参考:訪問看護
今後の制度改正の動向と訪問看護への影響
国は団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据え、在宅医療の体制強化を進めています。今後の制度改正では、以下のような点が焦点です。
| 対策 | 詳細 |
| 医療と介護の連携強化 | 情報をスムーズに共有し、一体的なサービスを提供する仕組みづくり |
| DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 | オンラインでの情報共有やモニタリングの活用 |
| 看取りへの対応強化 | 人生の最終段階を住み慣れた場所で過ごせるよう、ターミナルケアの充実 |
訪問看護の質向上に向けた取り組み
質の高い訪問看護を確保するため、さまざまな取り組みが進められています。例えば、外部機関による第三者評価や専門分野の知識を深めるための認定看護師制度などがあります。
上記の取り組みは、利用者が安心してサービスを選べる環境づくりにつながるでしょう。

訪問看護は、介護保険法、医療保険法、高齢者医療確保法といった複数の法律に基づいて提供されており、それぞれの制度に応じた適切なサービス提供が求められます。看護師は医師の訪問看護指示書に基づき、診療の補助や療養上の支援を行いますが、これらの実務にはすべて明確な法的根拠が存在します。また、記録の整備や個人情報の管理も法令に沿って行わなければなりません。さらに、精神疾患や小児、難病患者など対象者によって関係法令が異なる点にも十分な理解が必要です。本記事は、制度の全体像から具体的な実務対応、さらには今後の制度改正の方向性まで網羅しており、訪問看護に従事する専門職が現場で必要とされる知識の整理と再確認に非常に有益な内容といえるでしょう。制度理解に基づいた質の高いサービス提供が今後ますます重要になります。
訪問看護における法律を理解しよう

訪問看護は、介護保険法や健康保険法などの法律に基づいた制度であり、利用者を守り質の高いケアを保証するルールです。 訪問看護に関する法律の知識を持つことは、利用者の在宅療養を支援するために不可欠です。制度を理解し、専門家として質の高いケアを提供できるよう努めましょう。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。