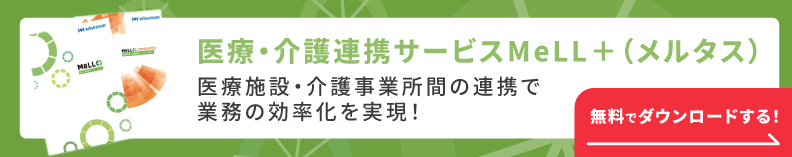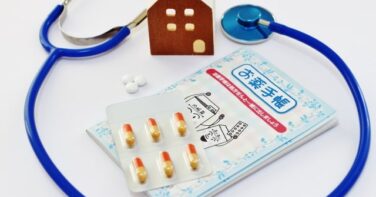【決定版】訪問看護は週何回利用できる?頻度を決める要素から調整方法まで徹底解説
2025.07.20

「訪問看護の導入を検討しているが、利用頻度について具体的な情報が欲しい」とお考えの方もいるでしょう。
訪問看護は、利用者のQOL向上や施設運営のスムーズ化に貢献できる可能性を秘めています。しかし、導入にあたっては、利用できる回数などの条件を把握しておかなければいけません。
本記事では、訪問看護の利用頻度について解説します。保険の種類ごとのルールや、利用者の状況に合わせた頻度の調整方法まで幅広く紹介します。最後までお読みいただければ、最適な訪問看護の導入プランを検討できるはずです。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。
目次
訪問看護の利用頻度を左右する3つの要素

訪問看護を週に何回利用できるかは、主に3つの要素によって決まります。これらの要素が複雑に絡み合い、一人一人に合った利用頻度が設定されます。
まずは、全体像を把握するために、利用頻度を決定する3つの要素を確認しましょう。
1. 適用される保険の種類
訪問看護で利用できる公的保険には、介護保険と医療保険の2種類があります。どちらの保険が適用されるかによって、利用回数のルールが大きく異なります。
基本的には介護保険が優先されますが、特定の条件を満たす場合は医療保険が適用される仕組みです。
| 保険の種類 | 対象となる方の例 | 優先順位 |
| 介護保険 | 65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方 | 優先適用 |
| 40歳~64歳で特定の16疾病により要支援・要介護認定を受けた方 | ||
| 医療保険 | 40歳未満の方 | 介護保険の対象外の場合に適用 |
| 介護保険の対象者だが、厚生労働大臣が定める疾病等の方 | 介護保険より優先適用 | |
| 要支援・要介護認定を受けていない方 | 介護保険の対象外の場合に適用 |
2. 要支援・要介護度
介護保険を利用する場合、要支援・要介護度が利用頻度に大きく関わります。なぜなら、要介護度ごとに1カ月に利用できるサービスの総量(区分支給限度基準額)が定められているからです。
訪問看護だけでなく、デイサービスといった他の介護サービスと組み合わせて、この限度額の範囲内でケアプランを作成する必要があります。
3. 病状や年齢
特定の病状や状態にある方は、医療保険を使ってより手厚い訪問看護を受けられる場合があります。例えば、末期がんや難病などの「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合です。
また、精神疾患をお持ちの方や小児への訪問看護にも、特別なルールが設けられています。
【介護保険編】訪問看護の利用回数と料金

ここでは、介護保険を利用して訪問看護を受ける場合のルールを解説します。多くの方が利用する介護保険の仕組みを正しく理解しましょう。
介護保険における訪問看護の利用限度回数
介護保険制度では、訪問看護の利用回数に「週に何回まで」といった明確な上限はありません。しかし、前述のとおり、要介護度ごとに定められた「区分支給限度基準額」という上限金額があります。
この金額の範囲内でケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて利用回数が決まるため、実質的な上限が存在します。
1日に複数回の訪問看護を利用する際の条件と注意点
介護保険で、1日に複数回の訪問看護を利用する際には「2時間ルール」が適用されます。これは、1回目の訪問と2回目の訪問の間隔を原則、2時間以上空けなければいけないというルールです。本ルールは、短時間の訪問を繰り返すことで不適切な報酬請求が行われるのを防ぐ目的で設けられました。
ただし、以下のようなケースでは、2時間未満の間隔でも訪問看護サービスの提供が認められます。
- 利用者の状態が急変した場合などの緊急時訪問
- 1回の訪問時間が20分未満の場合
- 1回目と2回目で訪問する職種が異なる場合(例:看護師 → 理学療法士)
上限回数を超える例外ケース
前述のとおり、通常、訪問看護は区分支給限度基準額の範囲内で利用します。しかし、以下のような特定の条件下では、この限度額の対象外として算定される場合があります。
| 加算名 | 概要 |
| 緊急時訪問看護加算 | 利用者や家族からの求めに応じて、計画外の緊急訪問を行った場合に算定される |
| 特別管理加算 | 在宅での医療的な管理が必要な状態(留置カテーテル管理、在宅酸素療法など)にある場合に算定される |
| ターミナルケア加算 | 死亡日および死亡日前14日以内に、24時間対応体制でターミナルケアを行った場合に算定される |
したがって、訪問看護サービスを提供する際は、上記の内容に該当しないかどうかをチェックすることが大切です。
介護保険で訪問看護を利用した場合の料金
介護保険を使った訪問看護の料金は、サービス提供時間に応じて単位数が定められています。自己負担額は、所得に応じて原則1割(一定以上の所得者は2割または3割)です。
| サービス提供時間 | 自己負担額の目安(1割負担の場合) |
| 20分未満 | 約318円 |
| 20分以上30分未満 | 約474円 |
| 30分以上1時間未満 | 約834円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 約1,141円 |
※上記は基本的な料金の目安であり、早朝・夜間・深夜の利用や各種加算によって変動します。
【医療保険編】訪問看護の利用回数

次に、医療保険で訪問看護を利用する場合の回数制限について見ていきましょう。介護保険とは異なるルールが適用されるため、注意が必要です。
医療保険における訪問看護の利用回数制限
医療保険で訪問看護を利用する場合、原則として1日1回・週3回までが上限とされています。しかし、利用者が以下のいずれかに該当する場合は、週4回以上の訪問看護が可能な場合があります。
| 条件 | 詳細 |
| 厚生労働大臣が定める疾病等の場合 | 末期がんや多発性硬化症、パーキンソン病関連疾患など、特定の病状の方 |
| 特別訪問看護指示書が交付された場合 | ・主治医が「急性増悪」などにより一時的に頻回な訪問が必要と判断した場合に交付される ・指示期間は最長14日間で、この期間中は毎日でも訪問看護を利用できる |
上記に該当する場合、同じ訪問看護ステーションであれば1日に2〜3回の利用が可能です。別の訪問看護ステーションであれば、複数利用できる点を理解しましょう。
参考:訪問看護のしくみ
【要支援・要介護度別】訪問看護の利用頻度の目安と注意点

ここでは、要支援・要介護度別の訪問看護サービスの利用頻度の目安と注意点を紹介します。あくまで一般的な例であり、実際の頻度は個々の状態によって異なる点に注意しましょう。
要支援1~2の方の利用頻度と注意点
要支援の方は、介護予防を目的とした訪問看護が中心です。個々の状態に合わせたプログラムを作成し、看護師が定期的に訪問して、健康状態の確認や生活指導、リハビリテーションなどを実施します。これにより、要介護状態への移行を遅らせ、可能な限り自立した生活を送れるようサポートします。
| 利用頻度の目安 | 週1回程度 |
| サービス内容の例 | 健康状態のチェック療養生活に関する相談・アドバイス転倒予防の指導 |
| 注意点 | 他の介護予防サービスと組み合わせて、区分支給限度基準額の範囲内で利用できる |
要介護1~5の方の利用頻度と注意点
要介護認定を受けた方への訪問看護は、心身機能の維持・回復、そして病状の悪化防止を主な目的としています。要介護度が高くなるほど、看護師によるより頻繁な訪問が必要となるのが一般的です。利用者だけでなく、家族の負担軽減や、住み慣れた環境での生活を支えることも重要な役割です。
| 要介護度 | 利用頻度の目安 | 主な目的・サービス内容の例 |
| 要介護1~2 | 週1~3回 | 身体介護・服薬管理・医療処置・リハビリテーション |
| 要介護3~5 | 週3~4回以上 | 全身状態の管理・排せつケア・褥瘡予防・家族への介護指導 |
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。
【病状・年齢別】訪問看護の頻度

特定の病状や年齢によっても、訪問看護の利用頻度は変わります。ここでは、代表的な3つのケースを見ていきましょう。
末期がん患者の場合
末期がんなどのターミナル期にある方は医療保険が適用され、毎日でも訪問看護を利用できます。訪問看護では、痛みや不快な症状を和らげる緩和ケアや精神的なサポートが中心となるでしょう。
24時間対応体制を整えているステーションであれば、夜間の緊急時にも対応が可能です。
精神疾患の方の場合
精神疾患をお持ちの方への訪問看護は「精神科訪問看護」として、専門的なケアが提供されます。
通常、医療保険では週3回までの上限が設けられていますが、主治医から「精神科特別訪問看護指示書」が交付された場合は、週4回以上の訪問が可能です。訪問看護時は対人関係の構築や服薬管理、社会復帰に向けた支援などを行います。
ただし、精神科特別訪問看護指示書は原則、月1回に限り交付とされており、指示期間は最大14日間です。
小児の場合
小児(15歳未満)への訪問看護も医療保険の対象です。医療的ケアが必要な子どもや、発達に課題を抱える子どもなどが利用します。
利用回数は週3回が基本ですが、状態に応じて主治医の指示のもと週4回以上の訪問も可能です。
訪問看護の回数を調整する方法

訪問看護サービスを受けながら療養生活を送る利用者の中には「もう少し訪問回数を増やしたい」「状態が良くなったので訪問看護の回数を減らしたい」と感じる方もいるでしょう。
そのような場合は、利用者の状況に応じて訪問看護の回数を柔軟に見直すことが可能です。利用者の声に耳を傾け、より良い療養生活をサポートしましょう。
訪問看護の回数を増やしたい場合
訪問看護を提供する立場として、体調の変化や介護負担の増大などで訪問回数を増やしたいという相談を受けた際には以下の点を意識しましょう。
| 対応 | 詳細 |
| 本人や家族から丁寧に状況を伺う | 現在の状況や希望を具体的かつ丁寧にヒアリングする |
| ケアマネジャーと連携する | ・担当のケアマネジャーと密に連携し、情報共有を行う ・必要に応じて主治医への意見照会も検討する |
| 医学的な観点からの必要性を検討する | 主治医と連携し、医学的な観点から訪問看護の頻度を増やす必要性を検討する |
| ケアプラン・訪問看護計画書の見直しを支援する | 必要性が認められれば、ケアマネジャーとともにケアプランや訪問看護計画書を更新し、新しい頻度でのサービスが開始できるよう支援する |
訪問看護の回数を減らしたい場合
利用者の状態が安定したり、ご自身でできることが増えたりした場合は、訪問回数を減らすことも可能です。回数を増やしたい場合と同様に、ケアマネジャーとの連携を密にしましょう。
利用者の状況を丁寧にヒアリングし、他のサービスへの切り替えやご自身での管理への移行など、次のステップに向けた計画を一緒に立てます。
頻度調整を行う際の注意点
訪問看護における利用頻度の調整をスムーズに進めるためには、以下の点に注意しましょう。
| ルール | 詳細 |
| 利用者の自己判断でサービスを中断させない | ・利用者がサービスの中断を希望する背景には、さまざまな要因が考えられる ・ケアマネジャーや主治医との連携を密にし、客観的な視点からの意見を取り入れ、多角的に状況を評価すると、利用者にとって最善の選択肢を検討できる ・中断以外の選択肢(サービス内容の変更、利用回数の調整、担当者の変更など)を提示し、利用者の意向を尊重しながら継続的なサポートを提供できる方法を見つける |
| 利用者の希望を具体的に聞き取る | ・利用者がサービスを増やしたいと希望する際は「なぜ増やしたいのか」「何に困っているのか」を具体的に聞き取ると、真のニーズを把握できる ・単にサービス量を増やすだけでなく、生活全般の課題解決につながるような、より適切な対応を検討する ・利用者の希望を鵜呑みにするのではなく、客観的な視点から本当に必要なサービスを見極める |
| 関係者との情報共有を大切にする | ・利用者に関わるすべての人が同じ情報を共有することで、一貫性のあるサポートを提供できる ・家族やケアマネジャー、主治医など、関係者間のコミュニケーションを密にし、定期的な情報交換の場を設けることが望ましい ・情報共有の際は個人情報保護に配慮し、必要な範囲での情報共有を徹底する |
訪問看護でより良いサービスを提供するためのポイント

最後に、訪問看護サービスをより効果的に活用するためのポイントを3つ紹介します。
目的を明確にする
重要なことは、利用者が「訪問看護で何を実現したいのか」という目的をはっきりさせることです。例えば「ベッドからの起き上がりを一人でできるようになりたい」「薬の飲み忘れを防ぎたい」といった具体的な目標を一緒に設定しましょう。
利用者の目的が明確であれば、施設側もより的確なサポートを提供できます。
利用者とのコミュニケーションを大切にする
利用者が快適な療養生活を送る上で、訪問看護は重要な役割を果たします。 日々の些細な体調の変化や生活の中での困りごと、不安に思うことなどを、遠慮なく伝えられるような関係性を構築しましょう。
また、日頃から利用者の様子や変化を観察していれば、より良いサービスを検討できます。こまめなコミュニケーションを意識し、より良いケアを提供しましょう。
家族やケアマネジャーとの情報共有を徹底する
訪問看護は、在宅療養を支えるチームの一員であることを常に意識しましょう。訪問時に得た気づきやアドバイス、利用者の状態などを家族やケアマネジャーと情報共有することが、より良い訪問看護サービスにつながります。
「利用者にとって最適なサポートは何か」を常に考えて、快適な療養生活を送れるように支援しましょう。

本記事は、訪問看護の利用頻度を決定する複雑な要素を体系的に解説しており、実務者にとって非常に有用です。保険の種類(医療保険・介護保険)、要介護度、そして病状や年齢が頻度を左右するという基本原則を明確に示しています。特に、医療保険の原則週3回、介護保険の区分支給限度基準額内の利用という原則に加え、厚生労働大臣が定める疾病等や特別訪問看護指示書による例外、さらには緊急時訪問やターミナルケアにおける加算の重要性も詳述されている点は実践的です。2時間ルールなど、実務上の注意点も網羅されており、利用者や家族の状況変化に応じ、ケアマネジャーや主治医との連携を通じて柔軟に回数を調整するプロセスの解説は、質の高いケア提供に不可欠です。利用者との密なコミュニケーション、目的の明確化、関係者との情報共有を徹底することで、より良い在宅療養支援が実現されるでしょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。
法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。
訪問看護の頻度は状況に合わせて柔軟に調整しよう

訪問看護の利用頻度は、保険の種類や要介護度、病状によって異なります。介護保険を利用する際はケアプランに基づき、医療保険を利用するときは原則週3回までです。
しかし、病状によっては例外も認められているため、利用者の状況に合わせて最適な頻度を見つけましょう。利用者の状況は日々変化するため、訪問回数は随時見直しを行い、安心して療養生活を送れるようにサポートしてください。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。