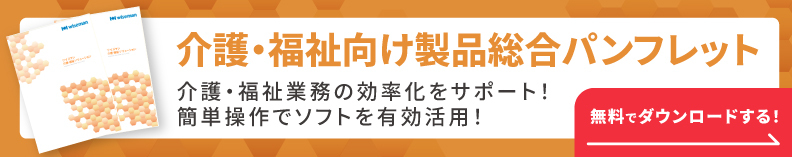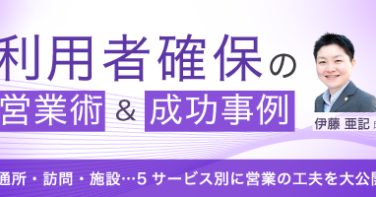サービス開始後のケアプラン同意日の対応方法|日付のルールなどを解説
2025.11.27

ケアマネジャーの業務で、利用者のためにと、急いでサービスを手配した結果、書類上の日付が前後してしまうことは、決して珍しいことではありません。
しかし、ケアプランの同意日がサービス開始後になることは、実地指導での指摘や介護給付費の返還といった、事業所の運営を揺るがしかねない重大なリスクをはらんでいます。
本記事では、そのようなケアプランの日付に関するルール・サービス開始後に同意を得る場合の具体的な対処法・監査を乗り切るための記録の書き方など、網羅的に解説します。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。
目次
ケアプランにおける日付の扱い

ケアプランの日付の問題を理解するためには、まず基本となる3つの日付の定義と、その正しい前後関係を押さえることが不可欠です。
それぞれの言葉が何を指しているのか、あらためて確認していきましょう。
ケアプランの作成日とは
ケアプランの作成日とは、ケアマネジャーが利用者の課題や目標・具体的なサービス内容などを盛り込んだ計画書の「原案を完成させた日」を指します。
事業所内部で計画が形になった日付ですが、基本的にケアプランは作成後に利用者から同意を得て完成します。
そのため、作成日と同意日(事業所によっては担当者会議日)を同一にすることが一般的です。
ケアプランの同意日とは
同意日とは、作成したケアプランの内容を利用者本人および、その家族に丁寧に説明し、計画内容に納得・合意を得た日付のことです。
この同意は、口頭だけでは不十分であり、利用者や家族による署名や記名押印、または法令で認められた電磁的方法によって確定します。
同意があって初めて、ケアプランは法的な効力を持ち、サービス提供の正式な根拠となります。
ケアプランのサービス開始日(適用日)とは
サービス開始日(適用日)とは、同意を得たケアプランに基づいて、実際に介護保険サービスの提供が始まる日付です。
これは、ケアプラン第2表(居宅サービス計画書)に記載される「計画の適用期間」の開始日と一致します。
この日から、計画に位置づけられた各サービス事業者は、利用者へのサービス提供を開始できます。
ケアプランの日付の正しい順番
先述した3つの日付は、介護保険制度の原則に基づき、特定の順序で並ぶ必要があるものです。
その理想的な前後関係は、以下のとおりです。
作成日・同意日→サービス開始日
上記の流れが、手続きの透明性と利用者の自己決定権を保障するための基本となります。
同意日やサービス開始日が作成日より前になることはありません。
同意日遅延が引き起こす重大リスク

同意日の遅れは、単なる書類の不備では済まされず、事業所の運営に深刻な影響を及ぼす以下のリスクを招く可能性があります。
- 実地指導・監査での指摘
- 介護報酬の返還(不正請求)
- 行政指導・行政処分
- 利用者・家族との信頼失墜と損害賠償
本章では、実際に起こりうる重大なリスクについて解説します。
実地指導・監査での指摘
実地指導や監査において、担当者はケアプラン関連書類の日付の整合性を必ず確認するものです。
ケアプラン第1表・第2表に加え、サービス利用票・支援経過記録などを突き合わせ、「同意日がサービス開始日より後になっていないか」を厳しくチェックします。
もし日付のずれが見つかり、その理由を支援経過記録などで合理的に説明できなければ、運営基準減算や不適切なケアマネジメントとして指導の対象となります。
介護報酬の返還(不正請求)
同意がない状態でのサービス提供は、介護保険制度上「契約が成立していない状態でのサービス提供」とみなされる行為です。
そのため、同意日よりも前のサービス提供期間については、介護給付費の返還(返戻)を求められる可能性があります。
これが意図的、または悪質と判断された場合、不正請求として返還額に加えて加算金が課されることもあります。
事業所の経営だけでなく、利用者の信頼も損なうので注意しましょう。
行政指導・行政処分
ケアプランのサービス同意日遅延は、行政指導・行政処分のリスクを高めます。
介護保険法に基づき、サービス提供前に利用者または家族から同意を得ることは義務です。
同意日遅延は、利用者への適切な情報提供と自己決定支援の不足とみなされ、利用者の権利を侵害する可能性があります。
記録や同意プロセスが不十分であれば、監査で指摘を受け、改善命令や指定取り消しといった行政処分につながることも考えられます。
また、遅延によって不適切なサービス提供が行われた場合、介護給付費の返還を求められる可能性もあります。
法令遵守の徹底と、利用者本位の丁寧なケアマネジメントが重要です。
利用者・家族との信頼失墜と損害賠償
適切な手順を踏まないことは、利用者や家族からの信頼を損なう原因となります。
「何も聞かされないままサービスが始まった」といった不信感は、後のトラブルに発展しかねません。
万が一、同意を得ていないサービス提供中に事故が発生した場合、事業者は「適切な説明と同意を得ていなかった」として、安全配慮義務違反などを問われます。
最悪の場合、損害賠償請求に発展するリスクも抱えることになります。
同意日がサービス開始後になった場合の対処法

ケアプランは、原則としてサービス開始前の同意が必要です。
しかし、利用者の状態が急変し緊急でサービス導入が必要になった場合など、やむを得ず同意日がサービス開始後にずれ込むケースも想定されます。
その場合は、以下のような適切な手順を踏めば、例外的にサービス開始後の同意も認められることがあります。
- サービス先行の必要性を判断し、利用者に説明する
- 暫定ケアプランを活用する
- 本プランを作成して正式な同意を得る
本章では、サービス開始後に同意日がずれ込んだ際の具体的な対処フローを解説するので、ぜひ参考にしてください。
サービス先行の必要性を判断し、利用者に説明する
サービスを先行させる必要性があると判断された際は、必ず利用者に説明しましょう。
まず、本当にサービスを先行させる必要があるのか、その緊急性を冷静にアセスメントします。
必要と判断した場合、利用者本人や家族に電話などで速やかに連絡を取ります。
なぜサービスを先行させる必要があるのか・当面のサービス内容・後日あらためて正式な手続きを行うことを丁寧に説明することが重要です。
一連のやり取りは、必ず支援経過記録に詳細に記載しておきましょう。
暫定ケアプランを活用する
要介護認定の結果が出る前にサービスを開始する必要がある場合などには、暫定ケアプランの活用が有効です。
暫定プランは、認定結果を予測して暫定的に作成するプランで、緊急時のサービス提供の根拠となります。
ただし、暫定プランであっても、利用者への説明・プランの写しを交付する一連のプロセスは省略できません。
本プランを作成して正式な同意を得る
サービスを開始した後、利用者の状態が落ち着いたり、家族と連絡が取れたりするなど、やむを得ない事情が解消され次第、速やかに正式なケアプラン(本プラン)を作成しましょう。
サービス担当者会議を開催し、関係者と内容を共有したうえで、利用者・家族に最終的な説明を行い、書面での署名・同意を得ます。
この際、ケアプランの写しを交付することも忘れないようにしましょう。
なお、暫定プランから本プランへの移行は1カ月以内に実施する必要があります。
万が一遅れる際は、正当な理由を監査時に説明できるようにしましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。
サービス開始後の同意日の記載方法
やむを得ない事情で同意がサービス開始後になった場合、その事実と経緯を書類上で明確に証明することが、実地指導を乗り切るための鍵です。
本章では、各種書類への具体的な記載方法について解説します。
第1表・第2表への日付の書き方
ケアプランの様式には、事実に基づいた日付をありのままに記載します。
例えば、サービス開始が4月1日で、やむを得ず同意を得たのが4月5日だった場合、書類上の日付は以下のとおりです。
| 項目 | 記載する日付 | 備考 |
| 作成日 | 例:3月28日 | プラン原案を完成させた日 |
| 同意日 | 例:4月5日 | 実際に同意を得た日付を記載 |
| サービス開始日(適用期間) | 例:4月1日~ | 実際にサービスを開始した日付を記載 |
上記の事実と経緯を支援経過記録で補足しましょう。
支援経過記録に必ず記載すべき4つの必須項目
なぜ同意が遅れたのか、その正当性を第三者(実地指導の担当官など)に説明するためのもっとも重要な書類が支援経過記録です。
単なる感想ではなく、客観的な事実を時系列で記録することが求められます。
以下の4つの項目は、必ず含めるようにしてください。
① なぜ同意が遅れたのか(客観的な理由と経緯)
なぜサービス開始前に同意を得られなかったのか、その理由を5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を意識して具体的に記録します。
「忙しかったから」といった主観的な理由は認められません。
「利用者が緊急入院となり、身元保証人である長男も遠方に居住しており、即日の来所が困難であったため」のように、誰が読んでも状況が理解できるように記載しましょう。
② 口頭同意など暫定的な対応の記録
正式な同意の前に、どのような暫定的な対応を取ったかを記録します。
これが、利用者の自己決定権を尊重しようと努力した証拠になります。
例えば、「〇月〇日〇時、長男△△氏へ電話にて、退院後の生活支援のため訪問介護の暫定利用が必要な旨を説明し、口頭にて同意を得た」といった具体的な記録が不可欠です。
③ 正式な同意取得に向けた具体的なアクションプラン
問題を放置せず、解決に向けて計画的に動いていたことを示すための記録です。
口頭同意を得た後、いつ、どのようにして正式な同意を得る予定なのかを記載します。
「〇月〇日に長男が来所予定のため、その際に本プランの説明を行い、同意手続きを進める予定」のように、具体的な見通しを記録しておくことで、計画的な業務遂行を証明できます。
④ 正式な同意を得た日付と交付記録
一連のイレギュラー対応が完了したことを証明する記録です。
正式な同意取得・交付の事実は以下のように記録しましょう。
「〇月〇日、事務所にて長男△△氏と面談。ケアプランの内容を説明し、第1表に署名にて同意を得た。同日、利用者用と事業者用の写しを交付した」
上記の記載方法なら、一連のプロセスが適切に完了したことの証明が可能です。
同意日がサービス開始後になった際のポイント

本章では、同意日がサービス開始後になった際の対応について、以下のポイントを解説します。
- サービス開始後の同意日でも問題ないケース
- 対面が難しい場合の対応方法
- 本プランへ移行する際の日付の管理方法
それぞれのポイントを理解し、適切な手続きを心がけましょう。
サービス開始後の同意日でも問題ないケース
サービス開始後の同意はあくまで例外的な措置であり、認められるのは「やむを得ない事情」があった場合に限られます。
認められるケース・認められないケースはそれぞれ以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 認められる主なケース | ・利用者の状態急変による緊急のサービス開始 ・家族が遠方に住んでいる、または連絡が困難な状況 ・災害の発生など、物理的に同意手続きが不可能な場合 ・認定結果が出る前の暫定プランによるサービス開始 |
| 認められないケース | ・ケアマネジャーの多忙、業務上の失念 ・単なる事務手続きの遅れ |
対面が難しい場合の対応方法
2021年度の介護報酬改定により、利用者や家族への説明・同意は、書面だけでなく、電磁的な方法(メール・専用の同意システムなど)で実行できるようになりました。
家族が遠方に住んでいる場合など、対面での手続きが難しい際には、ICTツールを活用することで、より迅速かつ確実に同意を得られます。
ただし、どの方法を用いる場合でも、丁寧な説明が不可欠であることに変わりはありません。

本稿にもあるように、ケアプラン(居宅サービス計画)は、利用者と事業者の「合意」を基盤とする重要な記録です。計画に対する同意は、法的契約そのものではないものの、サービス提供の適正性を裏づける根拠資料として不可欠です。同意日が確認できない場合、実地指導や監査で「説明・合意の不十分」とみなされ、返戻・返還などの対象となる可能性があります。したがって、初回面談時の説明内容や同意取得の経過を支援経過記録に残すことが重要です。また、暫定プランから本プランへの移行は速やかに行い、説明・同意のプロセスを文書で明確化しておく必要があります。形式的な署名にとどまらず、利用者や家族が内容を理解し納得しているかを確認する姿勢こそが、ケアマネジメントの信頼性を支える要です。さらに、同意に至るまでのやりとりをチームで共有し、他職種間で情報の齟齬が生じないよう確認体制を整えることも、実地指導対応において極めて有効です。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。
本プランへ移行する際の日付の管理方法
暫定プランから本プランへ移行する際は、それぞれのプランの適用期間が重複しないように注意が必要です。
例えば、暫定プランの適用期間を「4月1日~認定結果通知日まで」などと設定し、本プランの同意を得た後に、その適用開始日を「4月15日~」のように明確に区切ります。
サービス利用票や別表も、本プランの適用開始日に合わせて新たに作成・交付する必要があるため、注意しましょう。
ケアプラン同意日がサービス開始後になっても冷静に対応しよう

ケアプランの同意日がサービス開始日より後になってしまった場合でも、適切に対応すれば問題はありません。
重要なのは、原則を理解したうえで、やむを得ない事情があった際には、それぞれの手順を確実に踏み、その経緯を正確に記録することです。
ぜひ、本記事の内容を参考にしてください。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。