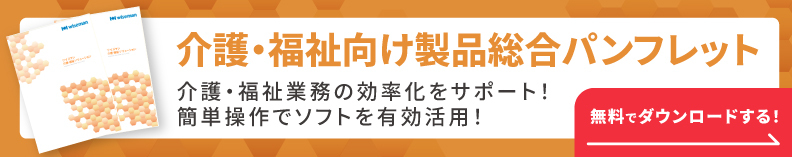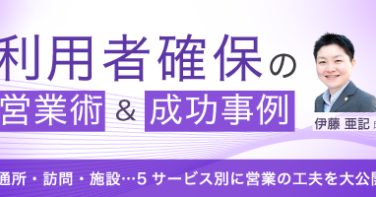ケアプランにおけるモニタリングの書き方ガイド|実地指導で指摘されない記録のコツ
2025.11.27

ケアプランを作成したものの、毎月のモニタリング記録をどのように書けば良いか悩んでいる方もいるでしょう。特に経験の浅いケアマネジャーや、ブランクがある方にとっては、「この書き方で合っているのだろうか」「実地指導で指摘されたらどうしよう」といった不安がつきものです。
この記事では、モニタリングの基本からすぐに使える具体的な文例、実地指導で指摘されないための記録のコツまで、わかりやすく解説します。ケアプランにおけるモニタリングの書き方をマスターしましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。
目次
ケアプランのモニタリングとは

ケアプランにおけるモニタリングとは、提供されているサービスが計画どおりに進んでいるか、利用者の心身の状態や生活への影響を確認・評価するプロセスです。
ケアプランという設計図が、利用者一人一人の生活という現場で正しく機能しているかを検証する重要な業務です。モニタリングを通じて、ケアプランを常に最適な状態に保ち、利用者の生活の質(QOL)の向上を目指します。
モニタリングの3つの目的|利用者の生活を支えるための視点
モニタリングは漫然と行うものではなく、明確な目的意識を持って取り組むことが重要です。その目的は、大きく分けて以下の3つです。
| 目的 | 具体的な内容 |
| 1. ケアプランの効果測定 | ケアプランに設定した目標がどの程度達成されているか、提供サービスが想定とおりの効果を上げているかを評価する |
| 2. ニーズとの不一致(ミスマッチ)の早期発見 | 利用者の心身の状態や生活環境は常に変化する。その変化をいち早く捉え、現在のサービス内容が利用者のニーズに合っているかを確認し、必要であれば迅速にプランを修正する |
| 3. 潜在的なリスクの管理 | 転倒や誤嚥、病状の悪化といったリスクの兆候を早期に発見し、未然に防ぐための対策を講じる。これは、利用者の安全と尊厳を守るための危機管理そのもの |
上記の目的を意識することで、モニタリングは単なる状況確認から、より質の高いケアを実現するための積極的な働きかけにつながります。
モニタリングの実施頻度と法的根拠|月1回の真意
指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準において、ケアマネジャーは少なくとも月に1回は利用者の居宅を訪問し、モニタリングを行うことが義務付けられています。
月1回という頻度は、利用者の状態変化を継続的に把握し、ケアプランの適切性を維持するための最低限のラインです。つまり、モニタリングの実施頻度はあくまで原則であり、利用者の状態や、新しいサービスの導入など、必要に応じてより頻繁な訪問や連絡が求められることもあります。
専門職として、画一的な運用ではなく、個々の利用者の状況に応じた柔軟な対応を心がけることが大切です。
参考:○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)
アセスメントや評価との違い
ケアマネジメントのプロセスには、「アセスメント」「モニタリング」「評価」といった似た用語が登場し、混同されがちです。それぞれの役割を正しく理解し、区別することが重要です。
| プロセス | 役割とタイミング | 主な活動内容 |
| アセスメント | 計画作成前のプロセス | 利用者や家族との面談を通じて、生活状況、心身の状態、意向などの情報を収集し、解決すべき課題(ニーズ)を明確にする |
| モニタリング | 計画実施中のプロセス | ケアプランに基づき提供されているサービスの状況や、利用者の状態変化を継続的に把握・記録する |
| 評価 | 計画期間終了時のプロセス | モニタリングで収集した情報をもとに、ケアプランに設定した目標の達成度を最終的に判断し、次期のプラン作成につなげる |
つまり、アセスメントで課題を見つけ、モニタリングで経過を追い、評価で結果を判断するというのが一連の流れです。モニタリングは、このサイクルを円滑に回すための重要な中間地点と言えるでしょう。
【実践編】モニタリング訪問で確認すべき5つの視点

実際のモニタリング訪問では、何をどのように確認すれば良いのでしょうか。ただ漠然と様子を伺うだけでは、重要な情報を見逃してしまう可能性があります。
ここでは、効果的なモニタリングを行うために、特に意識すべき5つの視点を解説します。
視点1:ケアプラン通りにサービスは提供されているか
基本となるのが、ケアプランに沿ったサービスが適切に提供されているかの確認です。以下の点をチェックしましょう。
- 量:訪問介護の時間やデイサービスの利用日数など、計画通りの量が提供されているか
- 質:サービス提供者の専門性や対応は適切か。利用者との相性は良いか
- 内容:清掃、調理、入浴介助など、計画されたサービス内容がきちんと実施されているか
これらの情報は、サービス提供記録の確認や、サービス担当者からのヒアリングを通じて客観的に把握することが重要です。
視点2:利用者・家族の満足度とニーズに変化はないか
利用者や家族が現在のサービスに満足しているか、また新たなニーズが生まれていないかを確認します。このとき、「満足していますか?」といった漠然とした質問では、遠慮して本音を言えないことも少なくありません。
以下のような具体的な質問で、対話を深めていきましょう。
- このサービスを使い始めてから、生活で楽になったことは何ですか?
- 逆に、もう少しこうだったら良いのに、と思うことはありますか?
- 最近、何か新しく困っていることや、不安に感じていることはありませんか?
何気ない世間話の中に、重要なヒントが隠されていることもあります。リラックスした雰囲気を作り、相手の言葉だけでなく、表情や声のトーンといった非言語的なサインにも注意を払いましょう。
視点3:短期・長期目標の達成状況はどうか
ケアプランに設定した目標がどの程度達成されているかを評価します。この評価は、次のプランニングにつながる重要な情報です。単に「できた」「できない」で判断するのではなく、より具体的に状況を捉えることがポイントです。
| 評価のポイント | 悪い例 | 良い例(具体的で次につながる) |
| 具体性 | 目標達成できた | 手すりを使えば、日中は一人でトイレまで移動できるようになった |
| 条件・状況 | まだ一人では難しい | 夜間や疲れている時はふらつきがあり、見守りや介助が必要な状況である |
| 進捗度 | 少しできるようになった | 先月は5m歩くのがやっとだったが、今月は10mまで休憩なしで歩けるようになった |
このように具体的に記録すると、小さな進歩を本人や家族と共有でき、モチベーション向上にもつながります。
視点4:新たな課題や潜在的なリスクはないか
表面的な変化だけでなく、利用者の生活全般に目を向け、新たな課題やリスクの兆候がないかを確認します。以下の4つの側面から観察すると、変化を捉えやすくなります。
| 観察する側面 | 具体的な観察ポイント・記録例 |
| 身体面 | 歩行状態(ふらつき、歩幅)、食事摂取量、水分摂取量、睡眠状態、排泄状況、皮膚の状態など 例:「最近、右足を少し引きずるように歩いている」「食事を残すことが増え、1日の摂取量が約1,200kcal程度になっている」 |
| 精神面 | 表情、発言内容、興味・関心の変化、意欲、気分の浮き沈みなど 例:「以前より笑顔が減り、返事も上の空のことが多い」「好きだったテレビ番組を見なくなった」 |
| 社会面 | 他者との交流(頻度、内容)、役割意識、デイサービスでの様子など 例:「デイサービスで他者と話さず、一人で過ごす時間が増えていると職員から報告あり」「自分は何もできなくなったという発言が聞かれた」 |
| 環境面 | 家族関係の変化、介護者の負担感、住環境(手すりの設置、段差)、経済状況など 例:「介護している娘さんが疲れ気味の表情をしている」「部屋に物が散乱し、転倒のリスクが高まっている」 |
これらの小さな変化を記録しておくことが、将来の大きな問題を防ぐための第一歩です。
視点5:サービス担当者など多職種からの情報は十分か
ケアマネジャーは、利用者支援チームにおいて中心的な役割を担います。自分一人の視点だけでなく、実際に日々利用者に接している介護スタッフや看護師、リハビリ専門職など、多職種からの情報を積極的に収集し、総合的に状況を判断することが不可欠です。
訪問前に各サービス担当者に連絡を取り、最近の利用者の様子で気になる点がないかを確認しておきましょう。多角的な情報が集まることで、より正確な状況把握が実現します。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。
【文例集】モニタリングシートの書き方とポイント

ここからは、モニタリングシートの書き方について、具体的な文例を交えながら解説します。「なぜそのように書くのか」というポイントを理解することで、どのようなケースにも応用できる力が身につきます。
良い例と悪い例を比較しながら、質の高い記録作成を目指しましょう。
これだけは避けたい|形骸化した記録とそのリスク
まず、モニタリング記録で避けなければならないのが形骸化です。多忙な業務の中で、ついやってしまいがちな形式的な記録は、多くのリスクを含んでいます。具体的な例は、以下のとおりです。
- 前回の記録の日付だけを変えてコピー&ペーストする
- 具体的な記述がなく、「特変なし」「問題なし」とだけ書かれている
- 毎回同じような定型文で済ませている
このような記録は、もはや記録としての意味を成していません。形骸化した記録がもたらすリスクは、 想像以上に深刻です。
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
| 利用者の状態悪化 | 小さな変化や悪化の兆候を見逃し、適切なケアプランの見直しが遅れることで、利用者の状態を悪化させてしまう可能性がある |
| ケアの質の低下 | 利用者一人一人の個性や状況が反映されないため、個別性の高いケアが提供できず、サービスの質が低下する |
| チーム連携の阻害 | 具体的な情報が記録されていないため、多職種間で効果的な情報共有ができず、チームケアが機能不全に陥る |
| 実地指導・監査での指摘 | 適切なモニタリングが行われていないと判断され、介護報酬の返還や指定取り消しといった厳しい処分につながる可能性がある |
忙しいからという理由で記録を疎かにすることは、専門職としての信頼を損ない、利用者と事業所の両方に不利益をもたらすことを肝に銘じておきましょう。
状況・サービス別 文例集
それでは、具体的な状況に応じた文例を紹介します。ここで示すのはあくまで一例です。
ポイントは、具体的な観察事実とそれに基づく専門職としての評価・考察、今後の対応方針をセットで記述することです。ご自身の担当ケースに合わせて、言葉や表現をアレンジして活用してください。
【身体状況】ADLに変化が見られた利用者の文例
ケアプランの目標: 安全に室内を移動できる
| 項目 | 記入例 |
| 本人の状態・発言 | 「最近、立ち上がる時に少しふらつくことがある」との発言あり。日中、居間からトイレへの移動の際、壁や家具に手をつきながら歩行されている様子が見られた。右足をやや引きずるような歩き方になっている |
| 家族・事業者からの情報 | 訪問介護員より「先月と比べて、室内での移動に時間がかかるようになった」との報告あり |
| 評価・考察 | 下肢筋力の低下により、歩行の安定性が損なわれている可能性が考えられる。現状では室内での転倒リスクが高い状態と判断する |
| 今後の対応方針 | 福祉用具専門相談員と連携し、歩行器の導入を検討する。また、訪問リハビリによる筋力維持訓練の必要性について、主治医および本人・家族と相談する |
【認知機能】BPSD(行動・心理症状)が見られる利用者の文例
ケアプランの目標: 日中、穏やかに過ごすことができる
| 項目 | 記入例 |
| 本人の状態・発言 | 16時頃になると「家に帰らないと」と落ち着かなくなり、玄関のドアを開けようとされる行動が週に2~3回見られる。職員が話を聞くと「子供が学校から帰ってくるから」と話される |
| 家族・事業者からの情報 | デイサービス職員より「夕方になると不安そうな表情をされることが多い。昔の歌を歌うと少し落ち着かれる」との報告あり |
| 評価・考察 | 見当識障がいによる不安が、夕暮れ症候群として現れていると考えられる。本人の言動を否定せず、安心できる環境を提供することが重要。音楽が不安軽減のきっかけになる可能性がある |
| 今後の対応方針 | デイサービスの利用時間を16時までとし、帰宅後の時間帯に訪問介護を導入することを検討。本人が好きな音楽を流すなど、落ち着ける環境作りを家族と相談する。サービス担当者会議で情報共有し、対応を統一する |
【訪問介護】サービス利用状況に関する文例
ケアプランの目標: 栄養バランスの取れた食事を1日3食摂取する
| 項目 | 記入例 |
| 本人の状態・発言 | 「ヘルパーさんが作ってくれる食事は、少し味が濃く感じてしまう」との発言あり。訪問時、昼食が半分以上残っていた |
| 家族・事業者からの情報 | 訪問介護員より「薄味を心がけているが、ご本人の好みに合っていないのかもしれない。ご自身で用意された漬物とご飯だけで済まされることもある」との報告あり |
| 評価・考察 | サービス内容は提供されているが、本人の嗜好に合っていないため、食事摂取量が低下し、栄養状態の悪化が懸念される。本人の食べたいという意欲を引き出す工夫が必要 |
| 今後の対応方針 | サービス提供責任者と連携し、再度本人の食事の好みや味付けについて詳細に聞き取りを行う。調理方法の変更(だしを効かせるなど)を依頼する。次回の訪問時に、栄養補助食品のサンプルを持参し提案する |
【デイサービス】社会参加・交流に関する文例
ケアプランの目標: 他者と交流する機会を持ち、孤立感を軽減する
| 項目 | 記入例 |
| 本人の状態・発言 | 「デイサービスに行くのは嫌ではないが、人と話すのは少し疲れる」と話される。しかし、将棋の話をすると表情が和らぐ |
| 家族・事業者からの情報 | デイサービス職員より「当初は一人で窓の外を眺めて過ごされることが多かったが、職員が将棋の相手にお誘いしたところ、応じてくださった。最近では、同じテーブルの〇〇様と週に1~2回、楽しそうに将棋を指されている」との報告あり |
| 評価・考察 | 受動的ながらも、共通の趣味をきっかけに他者との交流が生まれつつある。目標達成に向けて良い変化が見られる。本人のペースを尊重しつつ、交流の機会をさらに広げることが望ましい |
| 今後の対応方針 | 引き続き、デイサービス職員に将棋を通じた交流の機会を設けてもらうよう依頼する。本人に、デイサービスでの様子を具体的に伝え、自信につながるような声かけを行う |
実地指導で指摘されないための3つの原則

モニタリング記録は、利用者のためであると同時に、提供したケアの正当性を証明する公的な記録でもあります。特に実地指導(監査)では、記録内容が厳しくチェックされる点には注意しましょう。
ここでは、指導官の視点を意識し、指摘を受けないための記録作成における3つの大原則を解説します。この原則を守ることで、自信を持って実地指導に臨めます。
原則1:客観的な事実と専門的見解を分けて書く
記録は誰が読んでも状況が理解できるように、客観的な事実に基づいて書くことが基本です。自分の感想や憶測と、観察した事実を混同しないように注意しましょう。
- 悪い例:「少し元気がない様子だった。」(主観的で曖昧)
- 良い例:「(事実)ソファに横になっている時間が長く、問いかけへの返答も少なかった。(見解)季節の変わり目で体調が優れない可能性も考えられるため、バイタル測定を依頼し、注意深く見守る。」
「何があったのか(事実)」と「その事実から専門職としてどう考えたか(見解・考察)」を明確に分けて記述することで、記録の客観性と信頼性が高まります。
原則2:アセスメント・ケアプランとの一貫性を示す
モニタリング記録は、単体で存在するものではありません。アセスメントで明らかになった課題とケアプランの目標が一貫している必要があります。実地指導では、この一連のプロセスの整合性が厳しく見られます。
例えば、アセスメントで転倒リスクが課題として挙げられているにもかかわらず、モニタリングで歩行状態に関する記述がまったくなければ、適切なケアマネジメントが行われていないと判断されかねません。記録を作成する際は、常にケアプランのどの目標に対するモニタリングなのかを意識しましょう。
原則3:サービス担当者会議など多職種連携の記録を残す
モニタリングで得られた情報を基に、多職種とどのように連携し、ケアの改善につなげたかというプロセスを記録することも非常に重要です。
「モニタリングの結果、〇〇という課題が明らかになったため、〇月〇日のサービス担当者会議で協議し、プランを△△に変更した」というように、具体的なアクションを記録に残しましょう。
これはケアマネジャーが単に状況を把握するだけでなく、チームの中心として調整役を果たしていることの証明になります。サービス担当者会議の議事録とモニタリング記録の内容を連携させておくことも有効です。
ケアプランのモニタリングに関するQ&A

ここでは、モニタリングに関する素朴な疑問にお答えします。日々の業務で疑問を感じたときの参考にしてください。
Q1. モニタリングシートに決まった様式はあるか
A1. モニタリングシートには、法律で定められた全国統一の様式はありません。そのため、多くの場合は各事業所や法人が独自に作成した様式を使用しています。ただし、どのような様式であっても、一般的に以下の項目は盛り込むことが推奨されます。
- 利用者氏名、記録日、記録者名
- ケアプランの長期・短期目標
- 各サービスの実施状況
- 目標の達成度
- 利用者本人や家族からの聴き取り内容
- 評価・考察
- 今後の対応方針
ご自身の事業所の様式が、上記の項目を網羅しているか一度確認してみると良いでしょう。
Q2. 利用者さん本人から話が聞けない場合はどうすれば良いか
A2. 認知症の進行や失語症、重度の聴覚障がいなどにより、利用者ご本人から直接、意向や満足度を聴き取ることが難しいケースもあります。そのような場合は、一つの情報源に頼るのではなく、多角的に情報を収集して総合的に判断することが重要です。
- 家族からの情報:身近な存在である家族から、日々の様子や表情の変化、食事や睡眠の状況などを詳しく聴き取る
- サービス担当者からの報告:実際にケアを提供しているヘルパーやデイサービス職員からの客観的な報告も重要である
- 非言語的情報の観察:本人の表情(笑顔、苦痛の表情)や食事の摂取量、リラックスしているか緊張しているかといった行動観察から、その人なりの満足度や不快感を推測する
上記の情報を丁寧に集め、「ご本人からの直接の聴取は困難だが、〇〇の様子から現状のサービスに満足されていると推察される」といった形で記録に残します。

ケアマネジャーにとって、ケアプランのモニタリング記録は、計画の適切性を証明し、利用者の生活の質(QOL)向上に不可欠な業務です。本記事は、この重要なモニタリング業務を実地指導で指摘されないための実践的なガイドです。
まず、モニタリングの「計画の検証」「目標達成度の確認」「新たな課題の発見」という3つの目的と、月1回の実施頻度における法的根拠を明確化。その上で、訪問時に確認すべき「サービス提供状況」「利用者・家族の満足度」「目標達成度」「新たなリスク」「多職種連携の情報」という5つの視点を詳細に解説します。
さらに、実践的な文例集として、ADLやBPSDの変化、各利用状況ごとの具体的な記入方法を紹介。「実地指導で指摘されないための3原則」として、「客観的事実と専門的見解の分離」「アセスメント・ケアプランとの一貫性」「多職種連携記録の徹底」を挙げ、形骸化した記録のリスクと対策を提示します。本記事を通じて、根拠に基づいた質の高いモニタリング記録作成スキルが身につきます。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。
手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。
他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。
まとめ:ケアプランにおけるモニタリングの意味を深く理解しよう

ケアプランにおけるモニタリングは、決して形式的な作業ではありません。利用者のわずかな変化に気づき、その人らしい生活を支え続けるための対話のプロセスです。
今回紹介した目的や視点、記録の原則を意識することで、あなたの日々のモニタリングは、より深く、意味のあるものに変わっていくはずです。質の高いモニタリング記録は、利用者の生活を豊かにするだけでなく、実地指導においてもあなたの仕事を正当に証明し、専門職としてのあなた自身を守る盾となり得ます。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。