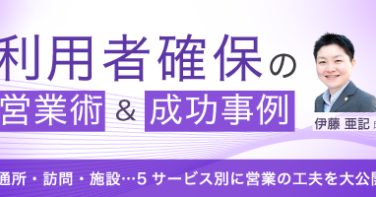介護DXとは|厚生労働省が提示する定義や施策などを解説
2025.09.25

人手不足が深刻化する一方で、日々の記録や請求といった事務作業に追われ、本来のケアに集中できない状況に陥った介護事業所は増加しています。
この課題を解決する鍵として、厚生労働省が強力に推進しているのが介護DXです。
介護DXは単なるIT化ではなく、デジタル技術を通じて介護現場の働き方そのものを変革し、未来の介護を支えるための重要な戦略です。
本記事では、厚生労働省が示す介護DXの公式な方針や目標をわかりやすく解説します。
さらに、具体的な補助金情報・自施設に合ったツールの選び方など、DX推進に必要な情報を紹介します。
目次
介護DXの定義

介護DXとは、単にパソコンやタブレットを導入するに留まらず、介護施設全体の変革を指す用語です。
具体的には、ICT機器・ソフトウェア・介護ロボットといったデジタル技術を積極的に活用し、手作業で行っていた業務プロセスの効率化・記録業務の負担軽減・情報共有の迅速化などを実現します。
さらに、デジタル技術の導入をきっかけに、組織体制や働き方そのものを見直し、職員の負担軽減と専門性の向上を図ることがDXの役割です。
例えば、介護記録ソフトの導入により、記録業務時間を短縮し、より利用者のケアに時間を割けるようになります。
また、センサー技術を活用することで、利用者の状態をリアルタイムに把握し、転倒リスクの早期発見や、夜間の見守り負担の軽減が可能です。
デジタル化による変革を通じて、介護職員はより質の高いケアを提供できるようになり、利用者の満足度向上、ひいては介護事業所の発展に貢献することが、介護DXの最終的な目標です。
介護DXが必要な背景
介護DXが推進される背景には、さまざまな要因が影響しています。
本章では、介護DXが推進される背景について、介護業界の課題・質の高いケアの実現の2つの観点から解説します。
介護業界の課題
介護業界が抱える課題はいずれも深刻であり、早急な解決が求められているものです。
特に注目すべき課題は以下のとおりです。
| 課題 | 具体的な内容 |
| 深刻な人材不足 | 介護業界では、2025年時点に約25万人の介護職員が不足すると予測されており、深刻な人手不足が懸念されています。この背景には、他産業と比較して低い賃金水準があり、介護職員の離職を招いていることが指摘されています。人材確保のためには、賃金改善などの労働環境の見直しが急務です。 |
| 増大する介護ニーズ | 高齢化が進む日本では、認知症患者の増加に伴い、介護サービスの需要が増大の一途を辿っています。地域包括ケアシステムの強化や介護人材の確保、認知症予防の推進など、多角的な対策が急務です。また、家族介護者の負担軽減も重要な課題であり、社会全体で認知症高齢者を支える体制づくりが求められます。 |
| 介護現場の大きな負担 | 介護職員は長時間労働に加え、記録や報告といった事務作業に追われ、大きな負担を抱えているのが現状です。身体的な介助による肉体的負担も深刻であり、離職の原因にもつながります。労働時間の短縮や事務作業の効率化、身体的負担を軽減する対策が急務です。働きやすい環境を整備することで、介護職員の定着率向上を図り、質の高い介護サービスの提供につなげることが重要です。 |
上記の課題は相互に関連し合っており、放置すれば介護サービスの質の低下や、最悪の場合、事業の継続自体が困難になるリスクをはらんでいます。
介護DXによる質の高いケアの実現
介護DXの最終目的は、業務効率化やコスト削減だけでなく、創出された時間やリソースを利用者へのケアの質向上に最大限に活用することです。
例えば、時間と手間がかかっていた記録業務や煩雑な請求業務をデジタル化することで、介護職員は事務作業から解放され、より多くの時間を直接利用者と向き合うために使えます。
これにより、個々の利用者の個性やニーズを尊重した、きめ細やかで丁寧なケアの提供が可能です。
また、利用者の心身の状態を注意深く観察し、小さな変化にも気づき、適切な対応をすることで、安心感と信頼関係を築き、精神的な安定にも貢献できます。
その結果、介護職員は時間に追われることなく、ゆとりを持って業務に取り組め、仕事への満足度やモチベーションの向上につながります。
何よりも、個別性を尊重した質の高いケアは、利用者のQOL(生活の質)の向上に直接つながります。
日々の生活における満足度・幸福感・尊厳の維持といった、人間らしい生活を送るうえで重要な要素を高められます。
介護DXは単なる業務効率化の手段として捉えるのではなく、利用者と介護職員双方にとって、より質の高いケアを提供するための、重要な戦略的ツールとして捉えるべきです。
テクノロジーを最大限に活用し、温かみのある、人間味あふれるケアを実現することこそが、介護DXの目指す未来です。
介護DXの一例

介護DXに該当する施策にはさまざまなものがあります。
特に、以下のようなツールの導入や施策が代表例です。
- 介護ソフト
- 介護ロボット
- コミュニケーションツール
- 介護情報基盤
それぞれについて、順番に解説します。
介護ソフト
介護ソフトは、介護DXの第一歩としてもっとも普及しているツールの一種です。
記録・請求・計画書作成といった、手作業だと多くの時間を要する業務をデジタルで一元管理します。
介護ソフトには、以下のような効果が期待できます。
| 導入による効果 | 具体例 |
| 業務時間の大幅な短縮 | 手書きでの記録や事業所内での転記作業が不要になり、請求業務にかかる時間が削減されます。 |
| 人的ミスの削減 | システムによる自動計算や入力チェック機能により、請求ミスや記録漏れを防ぎます。 |
| 情報共有の円滑化 | 職員間で利用者の最新情報をリアルタイムに共有でき、ケアの質向上につながります。 |
| ペーパーレス化の推進 | 紙の書類の保管場所や管理の手間が不要になり、コスト削減にも貢献します。 |
タブレット端末を使えば、利用者のすぐそばで記録を入力できるため、事務所に戻る手間も省け、より効率的です。
介護ロボット
介護ロボットの技術は目覚ましく進化しており、職員の身体的負担を軽減し、利用者の安全を守るうえで大きな力となります。
介護ロボットに該当するツールは以下のとおりです。
| 介護ロボットの種類 | 主な機能とメリット |
| 見守りセンサー | ベッドからの離床や転倒を検知し、職員の持つ端末に通知します。夜間の巡回負担を大幅に軽減し、利用者の安全を確保します。 |
| 移乗支援ロボット | 利用者をベッドから車椅子へ移乗させる際の身体的負担を軽減します。職員を腰痛のリスクから守る効果が期待できます。 |
| 排泄支援ロボット | 排泄物の処理を自動化し、衛生的な環境を保ちます。利用者の尊厳を守りつつ、職員の負担を減らします。 |
| コミュニケーションロボット | 利用者との対話やレクリエーションを通じて、孤独感の解消や認知機能の維持を支援します。 |
介護ロボットは人手不足の介護業界においても、サービスの質を維持するうえで役に立つツールです。
適切に活用すれば、最低限の人員でも利用者に最適なサービスを提供できます。
コミュニケーションツール
円滑な情報連携は、質の高いケアを提供するうえで不可欠です。
インカム・ビジネスチャットツール・Web会議システムなどのコミュニケーションツールは、施設内外の連携を強化します。
| 活用例 | |
| 施設内での活用 | インカムを使えば、広い施設内でも職員同士がリアルタイムに連携できます。チャットツールで申し送り事項を共有すれば、情報伝達の漏れや間違いを防げます。 |
| 施設外(多職種連携)での活用 | Web会議システムを利用して、地域の医療機関やケアマネジャーと遠隔でカンファレンスを行えます。これにより、地域包括ケアシステムの実現に貢献します。 |
コミュニケーションツールは情報共有を円滑化し、介護職員の連携をより強化できます。
介護情報基盤
厚生労働省が構築を進める全国規模の介護情報基盤は、利用者本人の同意を得たうえで、要介護認定情報やケアプランなどの重要な情報を自治体・介護事業所・医療機関といった関係者間でオンライン共有するためのプラットフォームです。
これにより、情報共有の迅速化と効率化を図り、より質の高い介護サービスの提供を目指します。
2026年4月からの全国展開を目標としており、将来的にはマイナンバーカードの活用も検討されています。
介護情報基盤が整備されることで、介護現場における情報連携が大幅に改善され、事業所間の連携が円滑に進むことが期待されます。
その結果、個々の利用者の状況に合わせた、切れ目のない、より包括的なケアの提供が可能です。
また、情報基盤の活用は、介護サービスの質向上だけでなく、介護に関わる事務作業の効率化にも貢献します。
介護現場の負担軽減を通じて、より多くの時間を利用者のケアに充てられるようになり、介護サービスの更なる充実が期待されます。
高齢化が進む日本において、介護情報基盤は持続可能な介護体制を構築するための重要なインフラとなり得る施策です。
介護DX推進のための厚生労働省の取り組み

国は、介護事業者がDXを円滑に進められるよう、以下のような多角的な支援策を講じています。
- 介護テクノロジー導入支援事業
- 介護DX導入支援の補助金・助成金
- 介護DXに関連する加算の新設
それぞれの支援策について、順番に解説します。
介護テクノロジー導入支援事業
厚生労働省は、介護現場における深刻な人手不足と業務効率化の課題解決を目指し、介護テクノロジー導入支援事業を展開しました。
介護テクノロジー導入支援事業は、介護事業所が業務効率化や介護負担軽減につながる介護ロボットやICT機器を導入する際、初期費用の一部を補助することで、導入を促進するものです。
補助対象となる機器は、見守りセンサー・移乗支援ロボット・排泄支援ロボット・記録・情報共有システムなど多岐にわたります。
補助金額や対象となる事業者の要件は都道府県によって異なり、詳細な情報は各都道府県の担当窓口での確認が必要です。
多くの介護事業所がこの制度を活用し、介護記録の電子化・情報共有の迅速化・職員の負担軽減を実現しており、介護現場のDX推進に大きく貢献しています。
参照:令和7年度介護テクノロジー定着支援事業の実施について|長野県公式サイト
介護DX導入支援の補助金・助成金
上記の導入支援事業以外にも、介護DXの推進で活用できる補助金や助成金が複数存在します。
以下の補助金・助成金をうまく組み合わせることで、初期投資の負担の大幅な軽減が可能です。
| 補助金名 | 対象となる機器・システム | 補助内容の例 |
| 介護ロボット導入支援事業 | 見守りセンサー・移乗支援ロボットなど | 導入費用の一部を補助(例:1台あたり上限30万円) |
| ICT導入支援事業 | 介護ソフト・タブレット端末・Wi-Fi環境整備など | 導入費用の一部を補助 |
| 介護生産性向上推進交付金 | 生産性向上に資する機器・システムの導入や研修 | 取り組み内容に応じて交付 |
最新の情報や申請方法については、各都道府県の担当窓口や公式サイトで確認することが重要です。
介護DXに関連する加算の新設
厚生労働省は、介護報酬においてDXを推進する事業所を評価する仕組みを導入しており、令和6年度の介護報酬改定では「生産性向上推進体制加算」が新設されました。
生産性向上推進体制加算は、見守り機器等のテクノロジーを活用し、委員会設置や職員研修などを通じて業務改善に継続的に取り組む事業所を評価する加算です。
具体的には、介護現場における情報共有の円滑化・記録業務の効率化・コミュニケーションの質向上などを目的とした取り組みが評価されます。
例えば、インカムの導入による迅速な連携や、タブレット端末を活用したリアルタイムな情報共有・AIを活用した介護記録の作成支援などが挙げられます。
加算の新設は、DXへの取り組みが直接的な経営改善にもつながるインセンティブとなる取り組みです。
業務効率化によるコスト削減や、サービスの質の向上による利用者満足度の向上などが期待でき、結果として事業所の収益向上に貢献します。
参照:令和6年度介護報酬改定生産性向上推進体制加算について|厚生労働省

介護DXは、深刻化する人手不足や増大する介護ニーズに対応するため、厚生労働省が強力に推進する重要な戦略です。これは単なるIT化ではなく、デジタル技術を通じて介護現場の働き方そのものを変革し、職員の負担軽減と専門性の向上を目指すものです。具体的には、介護記録ソフトの導入による事務作業の効率化や、見守りセンサー・移乗支援ロボットといった介護ロボットによる身体的負担の軽減が期待されます。これにより、介護職員は利用者と向き合う時間を増やし、個別性を尊重した質の高いケアを提供することが最終目標です。国は、介護テクノロジー導入支援事業や各種補助金、さらには生産性向上推進体制加算の新設など、多角的な支援策でDX推進を後押ししており、持続可能な介護体制構築に不可欠な取り組みと言えるでしょう。
介護DXを推進する際は厚生労働省の指針を参照しよう

介護DXは、人手不足と増大するニーズに対応するために不可欠です。
厚生労働省の支援策を追い風に、まずは自施設の課題を整理しましょう。
記録業務・職員間の連携・身体的負担など、改善したい課題を明確にしたうえで、厚生労働省の公式サイトで補助金情報やガイドラインを確認し、ITベンダーのセミナーや相談窓口で具体的な情報を集めましょう。
厚生労働省の施策を利用すれば、よりスムーズな介護DXの推進が可能です。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。