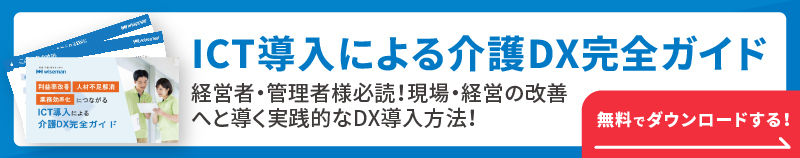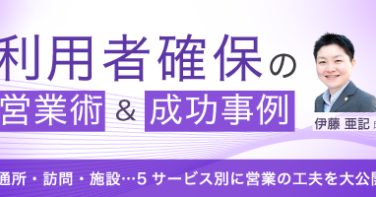介護DXスタートアップとは|介護事業所のDXに役立つヒントを解説
2025.09.25

近年、介護業界が深刻な人手不足や事業所の経営難といった大きな課題に直面していることもあり、介護DXに着手する介護施設が増加しています。
そのような状況で注目を集めているのが、介護DXを専門とするスタートアップ企業です。
介護DXスタートアップは、AIやIoTなどの最新技術を駆使して課題解決に挑むサービスを提供している企業が多く、DXの実現に貢献してくれます。
本記事では、介護DXの最前線で活躍するスタートアップ企業を紹介します。
実際に介護DXに着手する際に役立つサービスも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
介護DXスタートアップが求められる背景

介護DXスタートアップが増加している背景には、介護業界が抱える構造的な課題と、社会全体の変化が大きく影響しています。
本章では、その背景にある以下の要因について解説します。
- 介護人材の不足
- 介護事業所の廃業
- 介護DXの推進
いずれの要因も、多くの介護施設が抱える課題に直結しているものです。
介護人材の不足
介護業界が直面するもっとも深刻な課題は、慢性的な人材不足です。
昨今は高齢化が進行しているうえに、日本全体の人口が減少している状況です。
一方、厚生労働省の推計によると、2026年には約240万人の介護職員が必要とされています。
しかし、人口減少や高齢化の影響により、25万人の介護職員が不足すると見られています。
このような状況下で、少ない人数でも質の高いサービスを提供し続けるためには、人員を確保するだけでなく、テクノロジーを活用した業務効率化が不可欠です。
介護DXは、この人材不足という大きな課題に対するもっとも有効な対策です。
介護事業所の廃業
介護事業所の廃業の増加も無視できない要素です。
人材不足は、介護事業所の経営そのものを圧迫する要因でもあります。
人件費の高騰や採用コストの増大に加え、職員の負担増がサービス品質の低下を招き、結果として利用者の減少につながるケースも少なくありません。
厚生労働省の調査では、2023年時点で2022年度より介護事業所全体の数が減少していることが明らかになりました。
施設の種類によっては増加していますが、介護療養型医療施設のように約3割の施設数が減少したケースもあります。
DXによる経営改善は、コストを抑え、収益を最大化することで事業を継続するうえで不可欠な手段です。
コスト構造を見直し、生産性を向上させることが、多くの事業所にとって喫緊の課題です。
参照:令和5年介護サービス施設・事業所調査の概況|厚生労働省
介護DXの推進
介護業界で多くの課題が生まれたこともあり、政府も積極的にDX推進を後押しするようになりました。
昨今、厚生労働省や経済産業省は、介護現場の生産性向上を目的としたさまざまな支援策を打ち出しています。
例えば、介護ロボットやICT機器の導入に対する補助金制度や、科学的介護情報システム「LIFE」の活用促進などが挙げられます。
補助金制度については、以下の記事もご参照ください。
【介護ソフト向け】ICT補助金の概要まとめ|申請の流れ・IT補助金も解説
このように国が主導してDXを推進する動きは、スタートアップにとって大きな追い風となりました。
その結果、社会課題の解決とビジネス成長の両立が可能な市場として、多くのスタートアップ企業が誕生しています。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
介護DXスタートアップが取り組む事業

介護DXと一言でいっても、その事業領域は多岐にわたります。
ここでは、スタートアップが主にどのような領域で事業を展開しているのか、代表的な以下のカテゴリーに分けて解説します。
- 業務効率化・記録用の介護ソフト
- 見守りシステム・介護ロボット
- コミュニケーション・情報連携ツール
自施設の課題がどの領域のソリューションで解決できるのか、検討する際の参考にしてください。
業務効率化・記録用の介護ソフト
介護DXを実施する際、まず導入を検討するツールは介護ソフトです。
介護現場では、ケアそのものと同じくらい多くの時間を記録や請求といった事務作業に費やしています。
事務作業の負担が増加すると、利用者と向き合う時間やサービスを提供する時間が圧迫される恐れがあります。
負担を軽減するのが、業務効率化や記録用の介護ソフトです。
介護ソフトは、日々の煩雑な業務をデジタル化し、大幅な時間短縮とミス削減を実現します。
介護ソフトを導入すると、以下のようなメリットが期待できます。
| 主な機能 | 導入によるメリット |
| 介護記録の電子化 | 手書きの手間を削減し、どこからでも記録・閲覧が可能に |
| 介護保険請求(レセプト) | 請求業務を自動化し、計算ミスや請求漏れを防止 |
| シフト管理 | 複雑なシフト作成を効率化し、職員の労務管理を適正化 |
| 各種帳票の作成 | 報告書や計画書などの書類作成をサポート |
介護ソフトの導入は、職員が本来のコア業務である利用者とのケアに集中できる環境を整えるうえで、非常に重要な役割を果たします。
見守りシステム・介護ロボット
見守りシステム・介護ロボットは、介護スタッフの負担を軽減するだけでなく、サービスの質を上げるうえでも有効なツールです。
利用者の安全確保と職員の身体的負担軽減は、介護現場における永遠のテーマです。
この課題に対し、AI・IoT・ロボティクスといった先端技術を活用したソリューションが次々と登場しています。
特に注目されているのが、見守りシステムと介護ロボットです。
これらには以下のような効果が期待できます。
| テクノロジーの種類 | 具体的なソリューション例と効果 |
| AI・IoTセンサー | ベッドセンサーやカメラで利用者の睡眠状態や離床を検知し、夜間巡視の効率化や転倒事故の予防に貢献 |
| 移乗支援ロボット | 利用者をベッドから車椅子へ移す際の介助をパワーアシストし、職員の腰痛リスクを大幅に軽減 |
| コミュニケーションロボット | 利用者との会話やレクリエーションを通じて、認知機能の維持や孤独感の解消をサポート |
上記の技術は、24時間体制で利用者の安全を見守り、職員の心身の負担を和らげることで、より質の高いケアの提供と働きやすい職場環境の実現に貢献します。
コミュニケーション・情報連携ツール
コミュニケーション・情報連携ツールは、情報共有を円滑にするうえで欠かせないツールです。
質の高い介護は、スタッフ同士はもちろん、施設と家族、さらには地域の医療機関やケアマネジャーといった多職種間の円滑な連携があって初めて実現します。
この連携をスムーズにするのが、コミュニケーション・情報連携ツールです。
コミュニケーション・情報連携ツールは、関係者間での迅速かつ正確な情報共有を可能にし、チームケアの質を向上させます。
特に、地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の構築において、これらのツールは不可欠なインフラです。
介護DXスタートアップのサポートを得る際の注意点

多くのメリットがある介護DXですが、やみくもにツールを導入してもうまくいきません。
スタートアップのサービスを最大限に活用し、失敗を避けるためには、以下のような注意点があります。
- 自施設の課題にあったサービスを選ぶ
- 費用対効果に注意する
- サポート体制をチェックする
本章では、導入を検討する際に特に重要な3つのポイントを解説します。
自施設の課題にあったサービスを選ぶ
DXは、それ自体が目的ではなく、あくまで自施設の課題を解決するための「手段」です。
まずは、自分たちの施設が抱えるもっとも大きな課題は何かを明確にすることが重要です。
| 課題の例 | 対応するサービス領域の例 |
| 「記録業務に時間がかかり、残業が多い」 | 業務効率化・記録用の介護ソフト |
| 「職員の腰痛が多く、移乗介助の負担が大きい」 | 移乗支援ロボット |
| 「夜間の巡視が大変で、職員が疲弊している」 | AI・IoTを活用した見守りシステム |
| 「家族への連絡や情報共有が煩雑だ」 | コミュニケーション・情報連携ツール |
上記のように、課題を整理し、優先順位をつけることで、本当に必要なソリューションが見えてきます。
スタートアップの担当者と相談する際も、この課題認識が明確であれば、より的確な提案を受けられます。
費用対効果に注意する
介護DXを成功させるうえで、費用対効果は無視できない要素です。
新しいシステムの導入には、初期費用や月額利用料などのコストがかかります。
最新の魅力的な機能に目を奪われがちですが、その投資に見合った効果が得られるかを冷静に判断する必要があります。
費用対効果を考えるうえで重要なのは、以下の2つの視点です。
| 効果の種類 | 詳細 |
| コスト削減効果 | 導入によって残業代がどれだけ削減できるか、消耗品費(紙・インクなど)がどれだけ減るかなど、直接的な金銭的メリットを試算します。 |
| 定性的な効果 | 職員の負担軽減・利用者の満足度向上・ケアの質の向上など、数字では測りにくい価値も考慮に入れます。 |
上記の効果を総合的に評価し、長期的な視点で投資判断を行うことが大切です。
サポート体制をチェックする
特にITに不慣れな職員が多い現場では、導入後のサポート体制がDXの成否を分けます。
どれだけ優れたシステムでも、使いこなせなければ意味がありません。
契約前には、以下のようなサポート体制の有無を必ず確認しましょう。
| 導入時のサポート | ・初期設定やデータ移行を代行してくれるか ・職員向けの操作研修を実施してくれるか |
| 導入後のサポート | ・電話やメールでの問い合わせ窓口はあるか ・トラブル発生時に迅速に対応してくれるか定期的な活用状況のフォローアップはあるか |
手厚いサポートを提供しているか、自施設のITリテラシーに合わせた支援が受けられるかは、重要な選定基準です。

本記事を監修し、介護業界が直面する深刻な人材不足や経営課題に対し、DXが不可欠な解決策だと改めて感じました。AIやIoTなど最新技術を駆使する介護DXスタートアップは、業務効率化、質の高い介護提供、職員負担軽減に貢献しています。政府の後押しもあり、介護現場でのテクノロジー活用は不可欠な要素です。業務効率化ソフト、見守りシステム、情報連携ツールなど多岐にわたるソリューションがあり、Rehab for JAPAN、aba、ウェルモといった注目の企業が活躍しています。DX導入の成功には、まず自施設の具体的な課題を明確にし、最適なサービスを選ぶことが肝要です。費用対効果を慎重に見極め、導入後の手厚いサポート体制の確認も不可欠となります。これらのポイントを踏まえDXを推進することで、職員が利用者との本質的なケアに集中できる環境が整い、持続可能な介護サービスの実現に繋がることを期待しています。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
介護DXスタートアップは自施設に合った企業を選ぼう

介護事業所を継続させるうえで、介護DXは重要な課題です。
しかし、経験値がない介護事業所では、単独で介護DXを推進しても失敗するリスクがあります。
確実に介護DXを進めるためにも、介護DXスタートアップのような企業のサポートは欠かせません。
介護DXスタートアップは、IT技術の発展もあって、近年注目度を高めています。
なかには介護施設の業務を効率化し、サービスの質を向上できる有用なサポートを実施してくれる企業もあります。
介護DXを推進する際は、自施設に適したスタートアップ企業を選択しましょう。
提供しているシステムやサービスだけでなく、サポート体制が充実している企業を選べば、介護DXが成功する可能性が高まります。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。