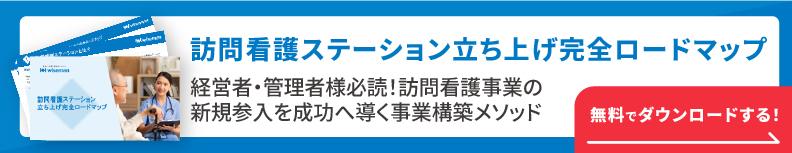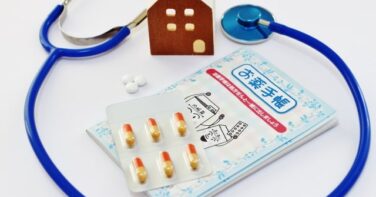訪問看護の一人当たり売上、平均は?計算方法と売上アップの具体策を解説
2025.08.23

訪問看護の運営において、「一人当たり売上が低いのでは」「他の事業所と比べてどうなのか」といった不安を抱えるケースは少なくありません。
現場は日々忙しく回っているのに、経営数字との結びつきが見えないような課題を抱える管理者の方にとって「訪問看護 一人当たり売上」は経営状態を客観的に把握するための有効な指標です。
この数値は、看護職員1人あたりが1か月でどれだけの売上を生み出しているかを示し、全国平均は約60万円とされています。
自社の売上をこの平均と比較すれば、訪問件数や単価、加算取得、稼働率など、改善すべき具体的なポイントが明確になります。
本記事では、一人当たり売上の計算方法から、収益に差が出る5つの要素、すぐに実践できる改善策までを、現場目線でわかりやすく解説しています。
訪問看護現場の一人当たりの売上を見直し、経営改善を図りたい方はぜひ参考にしてください。
目次
訪問看護の一人当たり売上は、全国平均で月約60万円
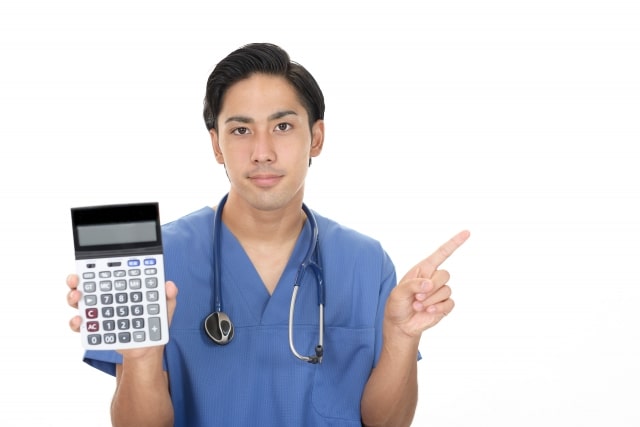
訪問看護ステーションの看護師一人当たりにおける月間売上は、全国平均で約60万円が一つの目安です。
全国の平均値と比較すれば、自社の収益性が業界水準に対してどのような位置にあるかを正確に知ることができます。
感覚に頼った運営ではなく、具体的なデータに基づいた分析が、安定した事業基盤を築くためには必要です。
平均額は、厚生労働省が公表しているデータから具体的に算出できます。
参照元の調査によると、以下の詳細な数値が示されています。
- 訪問1回あたりの平均売上:8,463円
- 常勤看護師1人あたりの月間訪問回数:71.9回
数値を基に計算すると、「8,463円 × 71.9回」となり、一人当たりの月間売上は608,489円と算出されます。
月間訪問回数から1日あたりの訪問件数を計算してみましょう。
月の労働日数を20日と仮定した場合、「71.9回 ÷ 20日」で1日平均約3.6件の訪問となります。
つまり、1日3〜4件の訪問を行うことで、全国平均と同水準の売上が見込めるわけです。
公的な統計データから導き出される詳細な数値を基準にすれば、自社の現状をより正確に分析できます。
自社の数値を把握しよう!一人当たり売上の基本計算式
訪問看護は、スタッフの労働力に依存する「労働集約型」のサービスです。
一人当たりの月間売上は、次の計算式で求めることができます。
- 一人当たり月間売上=月間総売上÷常勤換算看護職員数
※月間総売上:介護保険、医療保険、自費サービスなど、事業所全体の収入の合計額
常勤換算看護職員数:常勤・非常勤問わず、全職員の勤務時間を常勤基準に換算した人員数です。
例えば、以下のような勤務体制のステーションでは、常勤換算は次の通り計算されます。
| 職種 | 勤務形態 | 週労働時間 | 常勤換算人数 |
| 看護師A | 常勤 | 40時間 | 1.0人 |
| 看護師B | 非常勤 | 20時間 | 0.5人 |
| 看護師C | 非常勤 | 32時間 | 0.8人 |
| 合計 | – | – | 2.3人 |
算出した人数で割り戻すことで、ステーションの「生産性」を正しく評価できます。
なぜ差がつく?一人当たり売上を左右する5つの要素

一人当たりの売上が事業所によって異なるのには、明確な理由が存在します。
売上は、複数の要素が複合的に影響し合って生まれるため、その構造を理解しなければなりません。
なぜなら、売上は単純な訪問回数だけで決まるものではないからです。
1回の訪問から得られる収益、利益を上乗せする仕組みの活用度、スタッフがいかに効率的に働いているかといった内部の要因が大きく関わってきます。
それに加えて、事業所を取り巻く外部の環境も無視できない要素となります。
具体的に売上を左右する主な要因は、以下の5つです。
- 訪問件数
- 訪問単価
- 加算取得率
- スタッフ稼働率
- 地域特性
各要素がどのように売上に影響を与えているのかを一つひとつ分解して分析すれば、自事業所の強みと弱みが明確になります。
ここでは、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
訪問件数|生産性の土台
一人当たりの売上を向上させる上で、訪問件数の確保は生産性の土台となります。
付加価値の高いサービスも、提供機会が少なければ売上にはつながりません。
なぜなら、売上は「訪問単価 × 訪問件数」で決まるからです。
訪問件数を増やすことこそが、売上を向上させる直接的な手段といえます。
しかし、訪問件数を増やす上では、以下のような課題が共通して見られます。
- 訪問先間の移動による時間ロス
- 記録や報告書作成などの事務負担
- 非効率なスケジュール調整
上記のような課題は、看護師が本来のケア業務に集中する時間を削いでしまいます。
解決策として、訪問エリアの集中化や、最適なルートを自動算出するツールの活用が有効です。
電子カルテを導入すれば、訪問先で記録を完結でき、事務作業の削減にもつながるでしょう。
訪問件数を増やすとは、非生産的な時間を見直して業務全体の効率を高める取り組みです。生産性の土台をしっかりと固めることが、持続的な売上向上を実現します。
訪問単価|医療・介護保険のバランス
一人当たりの売上を構成する訪問単価は、提供するサービス内容によって変動します。
特に、医療保険と介護保険の利用者バランスを戦略的に考えることが、単価向上には必要です。
保険種別によって報酬体系が異なり、一般的に医療保険の方が高単価となる傾向があります。
医療依存度の高い利用者を積極的に受け入れる体制を整えることが、事業所全体の収益性を高める有効な戦略です。
両者のサービス内容と単価の特徴には、以下のような違いがあります。
| 保険種別 | サービス内容例 | 単価の特徴 |
| 医療保険 | ・特別管理指導 ・ターミナルケア ・精神科訪問看護 | 介護保険より高単価になる傾向 |
| 介護保険 | ・身体介護 ・生活援助 | 提供時間に応じた単価設定 |
表にあるように、ターミナルケアや難病ケアといった、より専門性が求められるサービスは高く評価されます。
自事業所の強みを活かせる専門分野を確立し、計画的に高単価サービスを提供していくことが、訪問単価そのものを引き上げることにつながります。
加算取得率|利益を上乗せ
基本報酬に利益を上乗せするためには、各種加算を戦略的に取得する必要があります。
算定の有無によって、同じ訪問件数でも売上は大きく変動します。
特に経営への影響が大きい加算は、以下のとおりです。
| 加算名 | 概要 | 取得のポイント |
| 緊急時訪問看護加算 | 24時間の緊急時対応体制を評価 | オンコール体制の構築と利用者への事前説明 |
| 特別管理加算 | 特定の医療的ケアが必要な利用者を担当 | 対象者の状態を正確に把握し、算定漏れを防ぐ |
| ターミナルケア加算 | 終末期に手厚い訪問ケアを提供 | 死亡日および死亡日前14日以内に2回以上訪問 |
事業所の体制を整備し、単価の大きい加算を計画的に取得していくことも検討しましょう。
スタッフ稼働率|見えない時間コスト
売上向上の妨げとなる「見えない時間コスト」を削減するためには、スタッフの稼働率に注目しましょう。
給与が発生する勤務時間のうち、直接売上を生み出すのは利用者のケアに充てられている時間だけだからです。
移動や記録といった付帯業務の割合が高いほど、事業所の収益性は低下します。
実際の勤務時間における業務内訳の例を見てみましょう。
| 業務内容 | 時間(例) | 割合 |
| 訪問看護(ケア実施) | 4.0時間 | 50.0% |
| 移動時間 | 1.5時間 | 18.8% |
| 記録・報告書作成 | 1.5時間 | 18.8% |
| カンファレンス・連携 | 0.5時間 | 6.2% |
| 休憩 | 0.5時間 | 6.2% |
| 合計 | 8.0時間 | 100% |
ケア実施以外の時間が半分を占めるケースは少なくありません。
見えない時間コストをいかに短縮し、稼働率を高めるかが経営課題になります。
地域特性|競合と利用者層の状況
訪問看護の一人当たり売上は、地域特性によっても左右されます。
なぜなら、人口構成や競合の有無、医療資源の密度などが、事業運営に直接影響するからです。
例えば都市部では、競合事業所も密集し、利用者数や医療機関が多い一方で、地方では訪問エリアが広範囲に及び、移動時間が長くなる傾向があります。
以下のように、地域ごとの特徴と取るべき戦略は異なります。
| 地域 | 特徴 | 戦略の方向性 |
| 都市部 | ・利用者数、競合が多い ・医療機関との連携が密 ・人材競争が激しい | ・専門性特化で差別化 ・ICT活用による業務効率化 ・高単価自費サービスの導入 |
| 地方 | ・人口密度が低く移動が長距離化 ・競合が少ない ・包括ケアの役割が大きい | ・医療・介護職との強固な連携 ・ゾーン制や直行直帰で移動コスト削減 ・職場定着の工夫 |
地域ごとの市場構造を踏まえた戦略の最適化が必要です。
自事業所が置かれている環境を冷静に分析し、強みを活かせる運営方針を明確にしましょう。
「一人当たり売上」を把握する3つのメリット

一人当たり売上を定期的に確認することで、事業所の経営状態を客観的に把握できます。
収益性の判断、人件費とのバランス調整、業界との比較など、経営のさまざまな場面で活用できるため、意識的に追いかける価値があります。
売上を把握するメリットを、それぞれ確認していきましょう。
事業所の収益性を数値で評価できる
一人当たり売上を算出すれば、事業所の収益性を客観的に評価できます。
売上全体では見えにくい「人材あたりの効率性」が、明確な数値で表れるからです。
例えば、総売上が同じ600万円でも、常勤換算で10人いれば一人当たり売上は60万円、6人であれば100万円になります。
この違いは、単に売上規模ではなく「どれだけ効率よく売上を生み出しているか」を示しています。
一人当たり売上は、事業所の稼働力・効率・運営体制を定量的に把握できる指標となり、感覚に頼らず、数字で判断する姿勢が、安定した経営につながります。
業界平均と比較して、改善点を特定できる
一人当たり売上を業界平均と照らし合わせることで、自事業所の課題を明確にできます。
なぜなら、平均値との比較は、自分たちの立ち位置を客観的に知るための有効な手がかりとなるからです。
例えば、全国平均が月約60万円(出典:厚生労働省 令和5年度 介護事業経営概況調査)とされている中、自社の数値が50万円であれば、何らかの改善余地があることがわかります。
訪問件数が少ないのか、単価が低いのか、あるいは加算取得が不十分なのかなど検証すべき具体的なポイントが見えてくるでしょう。
人件費と売上のバランスを調整できる
一人当たり売上の把握は、人件費とのバランスを見直すための基準になります。
なぜなら、人件費は訪問看護ステーションの固定費であり、利益率に直結する要素だからです。
例えば、一人当たり売上が月60万円、看護職員の平均給与が40万円であれば、残りの20万円で事業運営に必要な経費をまかなう必要があります。
この関係を数値で可視化すれば、昇給や採用の可否、経営余力の有無を冷静に判断できます。
一人当たり売上を最大化する!明日からできる実践的戦略

一人当たり売上を高めるには、日々の業務を見直し、効率と収益性の両立を図る必要があります。
なぜなら、訪問件数・単価・稼働率といった各要素は、工夫次第で改善できる領域だからです。
特別な設備投資や制度変更がなくても、運用の工夫やICTの活用によって、売上の底上げは十分に可能です。
ここでは、すぐに実践できる具体的な3つの戦略を紹介します。
【訪問件数UP】移動時間を効率化する
訪問件数を増やしたいなら、まず取り組むべきは移動時間の短縮です。
なぜなら、スタッフが移動にかける時間を減らすことで、より多くの時間をケアに充てられるからです。
訪問看護は、サービス提供と移動が常にセットです。
移動に1時間かかれば、その分1件の訪問チャンスが失われる可能性もあります。
そこで、現場で実践されている3つの施策を見てみましょう。
| 施策 | メリット | 注意点・デメリット |
| 直行直帰体制 | ・出退勤時間の短縮 ・柔軟な働き方の支援 | ・情報共有の仕組みが必須 ・勤怠管理が煩雑になる可能性 |
| ゾーン別担当制 | ・移動距離の短縮 ・地域特性への理解が深まる | ・業務量に偏りが出る可能性 ・利用者との相性配慮が必要 |
| サテライト拠点 | ・広域エリア対応時の移動を大幅に削減 | ・設置・維持にコストがかかる ・小規模には不向きな場合 |
上記のような施策は、単独で導入するだけでなく、組み合わせることでより効果が高まります。
自ステーションの人員配置やエリア特性に合わせて、最適なスケジュールと体制を検討してみてください。
限られた時間を有効に使い、無理のない範囲で訪問件数を伸ばすことが、安定した売上につながります。
【訪問単価UP】算定率の高い加算を戦略的に取得する
一人当たり売上を伸ばすには、訪問件数だけでなく、1回あたりの単価向上も大切です。
そのためには、各種加算を積極的かつ計画的に取得していくことが欠かせません。
加算とは、基本報酬に上乗せして請求できる報酬のことです。
緊急対応やターミナルケアなど、専門性の高いサービスに対して支給されます。
しかし、体制が整っていなかったり、算定条件を満たしていなかったりすると、加算を逃してしまう可能性があります。
加算取得を強化するためには、以下のような3つのステップを意識しましょう。
| 現状の把握 | 現在取得できている加算をすべて洗い出し、漏れがないか確認する |
| 目標の設定 | 体制整備により取得可能な加算をリストアップし、優先順位をつける |
| 体制の構築 | オンコール体制や記録の整備、スタッフ研修など、取得条件を満たす準備を行う |
例えば「緊急時訪問看護加算」を算定するには、24時間対応の体制が必要です。
この場合、オンコールのルール整備や利用者への事前説明が求められます。
加算取得は、一度仕組みを整えてしまえば継続的に効果を発揮します。
定期的に算定状況を見直すミーティングを設け、スタッフ全体で加算に対する意識を高めることが大切です。
売上向上だけでなく、サービスの質を保つ意味でも有効な取り組みといえるでしょう。
【稼働率UP】デジタル活用で新規利用者を獲得する
スタッフの稼働率を上げるには、利用者数を安定的に確保する必要があります。
そのためには、従来の紹介に加え、デジタルツールを活用した広報が効果的です。
訪問看護ステーションの多くは、地域のケアマネジャーからの紹介に依存しがちです。
しかし、競合も増える中で「選ばれる」ステーションになるには、日頃の情報発信による信頼の積み重ねが必要です。
ここでは、実際に活用されている3つの広報手法と、それぞれの特徴を整理します。
| 手法 | ターゲット | 効果 | 導入のポイント |
| ホームページ/ブログ | 利用者本人、家族、ケアマネ | ・信頼性向上 ・ステーションの強みを詳しく伝えられる | ・実績や専門性が伝わる内容 ・問い合わせフォームの設置 |
| SNS(Facebookなど) | 地域住民、若年層の家族 | ・認知度アップ ・親しみやすさの演出 | ・定期的な投稿 ・空き状況や日常の発信が効果的 |
| オンライン相談 | 遠方の家族、外出が難しい利用者候補者 | ・潜在層の掘り起こし ・相談のハードルを下げる | ・予約制の導入 ・プライバシーに配慮した環境づくり |
上記手段を通じて、紹介に依存しない「自走型の利用者獲得チャネル」を整えることができます。
情報発信は単なる宣伝ではなく、安心や共感を届ける手段でもあります。
デジタル広報を通じて、地域との信頼関係を築いていきましょう。

訪問看護ステーションの経営において、「一人当たり売上」は職員の生産性や収益構造を客観的に評価するための重要な指標です。平均値と比較することで、自事業所の稼働率・訪問単価・加算取得率など、具体的な改善ポイントが見えてきます。本記事では、国の統計に基づいた計算方法から、売上に差が出る5つの要因までを丁寧に解説しており、実務に直結する内容となっています。特に訪問件数や加算取得の工夫、稼働率向上のための業務効率化、地域特性に応じた戦略など、経営改善のヒントが多く含まれています。数字に苦手意識を持つ方にも理解しやすい内容ですので、日々の運営を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしていただきたいです。現場と経営をつなぐ視点を持つことが、持続可能な訪問看護の実現につながります。
まとめ|訪問看護の一人当たり売上をあげるためには効率的な運営が大切
訪問看護の経営を持続可能なものにするには「一人当たり売上」を軸とした数値管理が欠かせません。
売上全体では見えにくい生産性や稼働状況を、明確な指標として捉えることで、収益の健全性を把握できます。
訪問件数・単価・加算取得率・稼働率・地域特性といった複数の要素を整理し、どこに課題があり、どこに改善の余地があるのかを見極めなければなりません。
そのうえで、訪問スケジュールや体制の見直し、ICT導入による業務効率化、加算の戦略的取得、デジタル広報などを具体的に進めていくことで、一人当たり売上は着実に改善できます。
まずは自社の数値を可視化し、現場全体で改善の方向性を見直してみましょう。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。