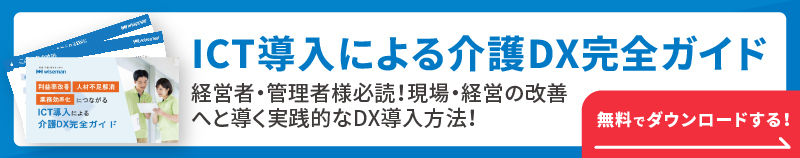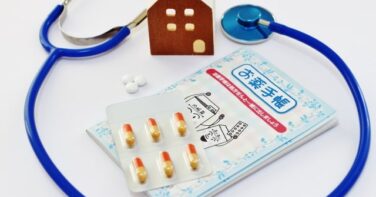【2025年最新版】訪問看護の退院時共同指導加算とは?算定要件・単位数・必要書類を徹底解説
2025.08.23

退院時共同指導加算は、病院と訪問看護ステーションが連携して利用者の在宅療養を支援するための加算です。
制度としての重要性は高い一方で、医療保険と介護保険での算定要件の違いや、初回加算・退院支援指導加算との関係性など、実務上で混乱しやすいポイントも少なくありません。
本記事では、訪問看護ステーションの管理者・実務担当者に向けて、退院時共同指導加算の算定ルールや制度改定ポイント(2024年度対応)をわかりやすく解説します。
訪問看護の退院時共同指導加算の内容を整理したい方や、加算請求などしたい方は、ぜひ参考にしてください。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
訪問看護の退院時共同指導加算を正しく理解する

退院時共同指導加算とは、利用者が病院や施設から退院・退所する際に、病院の医師や看護師と訪問看護師が共同で、在宅療養に関する指導や情報共有を行った場合に算定できる加算です。
この加算は、退院後の在宅生活を安全にスタートするための引き継ぎを評価するもので、医療保険と介護保険の両方に存在します。
加算の金額は以下のとおりです。
| 【医療保険】 | 8,000円/回(診療報酬点数:800点) |
| 【介護保険】 | 600単位/回(訪問看護の初回訪問時に加算) |
算定には、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 退院・退所前(または当日)に、病院と訪問看護師が共同で指導を行う
- 訪問看護の初回訪問時に加算を上乗せして算定する
- 退院後に実際に訪問看護サービスを提供する
- 指導内容を訪問看護記録書に記録として残す
なお、テレビ電話等での共同指導も可能ですが、利用者の同意を得る必要があります。
原則1回限りの加算ですが、人工呼吸器管理など特別な管理が必要なケースでは2回まで算定可能です。
制度を正しく理解し、手順通りに実施すれば、利用者支援と事業収益の両立につながります。
加算の目的を理解する
退院時共同指導加算は、介護保険・医療保険の両制度において、退院直後のケアを切れ目なく行うための連携強化を目的とした加算です。
入院していた利用者が自宅に戻るとき、病院側と在宅側(訪問看護ステーションなど)の連携が不十分だと、再入院や状態悪化といったリスクが高まります。
この加算はそうした事態を防ぐため、退院前から両者が協力し、必要な情報・指導を共有する取り組みを評価する仕組みです。
特に2024年度の制度改定では、オンラインでの指導や複数ステーションの関与に関するルールも明確化され、より柔軟な連携が求められています。
具体的には、以下のような目的があります。
- 利用者が退院後すぐに適切な在宅ケアを受けられる体制を整える
- 医療と在宅が情報を共有し、再入院や事故のリスクを減らす
- 家族や介護スタッフへの指導・支援を退院前に行う
- 多職種が関与することで、より質の高い在宅支援を実現する
退院時共同指導加算をきっかけに、病院と在宅との引き継ぎを仕組みとして整えることが、スタッフの負担軽減と利用者の安心につながります。
2024年改定の変更点を知る
2024年の診療報酬改定では、退院時共同指導加算に関して文書提供に関する要件が緩和され、現場の業務負担軽減が図られました。
これまでは「共同指導の内容を文書での提供」が必須要件とされていましたが、今回の改定でこの文書提供の義務が廃止されました。
その結果、書類作成にかかっていた時間や手間を削減し、利用者や家族への退院支援そのものに、より多くの時間を割けるようになっています。
改定の要点は以下のとおりです。
| 文書提供義務の廃止 | ICTや口頭説明など柔軟な方法での指導が可能に |
| 業務効率の向上 | 記録業務の負担軽減と、支援の質向上が期待 |
| 算定要件そのものに変更はなし | 共同指導の実施や記録は引き続き必要 |
今回の改定では訪問・通所リハビリテーションでも退院時共同指導加算が算定可能になり、退院支援における多職種間の情報連携強化がより一層求められるようになっています。
なお、医療保険と介護保険の両方でこの加算は算定できますが、点数や単位数に違いがあるため、制度ごとに正確な理解が必要です。
混同しやすい「退院支援指導加算」との違いとは?
退院時共同指導加算と退院支援指導加算は、いずれも退院後の在宅療養を支援する目的で設けられた加算ですが、実施のタイミングや内容、算定方法が異なるため、制度上は別の加算として扱われます。
退院時共同指導加算は、退院前に病院の医師や看護師と訪問看護師が共同で行う指導に対して算定される「事前連携型」の加算です。
一方、退院支援指導加算は、退院当日に訪問看護師が単独または医療機関と連携して行う「初動支援型」の指導に対して算定されます。
保険制度も異なり、退院時共同指導加算は医療保険と介護保険の両方で算定可能ですが、退院支援指導加算は医療保険のみでの取り扱いとなっています。
以下に違いをまとめると、以下のとおりです。
| 比較項目 | 退院時共同指導加算 | 退院支援指導加算 |
| 実施タイミング | 退院前(入院中) | 退院当日 |
| 実施者 | 病院+訪問看護が共同で実施 | 訪問看護が単独または連携で実施 |
| 内容 | 在宅療養に向けた引継ぎと指導 | 在宅開始に向けた生活支援的指導 |
| 算定場所 | 訪問看護ステーションなど | 保険医療機関等 |
| 保険区分 | 医療保険・介護保険 | 医療保険のみ |
| 算定タイミング | 初回訪問時に加算 | 退院日当日に加算 |
加算の背景や実施内容が明確に分かれているため、条件を満たせば同一の利用者に対して両方算定もできます。
ただし、指導内容や記録が重複していたり、曖昧な実施報告しかない場合は、返戻の対象になるリスクもあるため注意が必要です。
制度の違いを正しく理解し、現場での役割分担と記録体制を整えておくことで、加算の取りこぼしを防ぎながら、質の高い退院支援につなげていくことができます。
同時算定できる場合とは?
退院時共同指導加算と退院支援指導加算は、条件を満たせば同一の利用者に対して同時に算定できます。
両者は、対象となる患者や指導の内容、実施のタイミング・場所が異なるため、別の評価として扱われるからです。
制度上も、内容が重複しておらず、独立した指導として成立していれば同時算定が可能です。
退院時共同指導加算と退院支援指導加算は、以下のような場合に同時算定が可能です。
- 退院前に、病院と訪問看護が共同で指導を行っている(→退院時共同指導加算)
- 退院当日に、訪問看護が単独または連携して指導を行っている(→退院支援指導加算)
- 実施のタイミング・場所・内容が明確に分かれている
- それぞれの指導に関する記録が個別に残されている
両加算は一見似ていますが、制度上は別の評価軸に基づいているため、条件を正しく理解して対応すれば、同時算定は十分可能です。
ただし、要件の確認漏れや記録不備による返戻リスクを避けるためにも、「いつ」「誰が」「どこで」「何をしたか」を明確に残しておきましょう。
【医療保険】と【介護保険】の退院時共同指導加算の算定要件
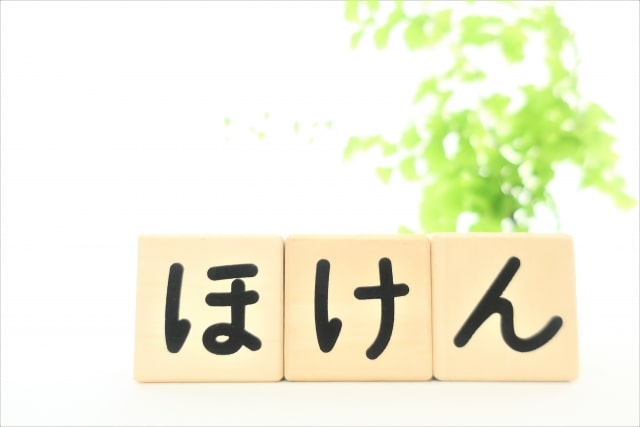
退院時共同指導加算は、利用者が利用する保険の種類によって算定要件や単位数(料金)が異なります。
医療保険と介護保険、それぞれのルールを正確に把握する必要があります。
ここでは、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。
医療保険の算定要件
医療保険は、病気やケガをしたときに医療費の一部をカバーしてくれる制度です。退院時共同指導加算は、その中でも 退院後の療養生活を支えるための連携 を評価する加算であり、在宅医療を円滑にスタートさせるために重要な役割を果たします。
医療保険で退院時共同指導加算を算定するには、対象や実施方法に関する明確な条件を満たす必要があります。
以下に、2024年度対応の主な算定要件を整理しました。
| 項目 | 内容 |
| 算定料金 | 8,000 円/回 |
| 特別管理加算対象者 | 上記に加えて 2,000 円/回 を別途算定可能 |
| 算定回数 | 原則、退院・退所時に 1回(※一部疾患で 2回算定可) |
| 例外条件 | 厚労省が定める疾病(例:がん末期、ALSなど)の場合に 2回まで算定可 |
| 指導の参加者 | 訪問看護ステーションの看護師等(※准看護師は不可)、入院・入所先の医師・看護師等 |
| 必要なこと | 利用者または家族の同意を得て共同指導 |
医療保険の退院時共同指導加算は、連携による支援の質と安全性を高めるための加算です。
対象者や記録の方法までしっかり押さえ、請求漏れや返戻を防ぎましょう。
介護保険の算定要件
介護保険における退院時共同指導加算は、要介護・要支援認定を受けた利用者が対象で、退院・退所後の在宅療養を円滑に始めるための支援に対して算定される加算です。
この加算は、訪問看護ステーションの看護師等が、病院や施設の医師・看護師と共同で指導を行うことが要件となっており、初回加算との併用ができない点には特に注意が必要です。
以下に、2024年度基準に基づいた具体的な算定要件を整理しました。
| 項目 | 内容 |
| 単位数 | 600 単位/回(※1単位 ≒ 約10円、地域区分により変動) |
| 算定回数 | 原則、退院・退所につき 1回 |
| 例外(2回算定) | 特別管理加算の対象者に限り、2回まで算定可能 |
| 指導の参加者 | 訪問看護ステーションの看護師等(※准看護師は除く)と、医療機関等の医師や看護師等 |
| 必要なこと | 利用者または家族の同意を得る |
介護保険における退院時共同指導加算は、医療保険との違いをきちんと把握し、要件を丁寧に満たすことで、返戻や算定ミスを防ぐことができます。
退院時共同指導加算と併用できる加算
退院時共同指導加算は、条件を満たせば一部の加算と併用が可能ですが、すべての加算と組み合わせられるわけではないため、注意が必要です。
ただし、すべての加算と組み合わせられるわけではないため、注意が必要です。
退院支援の場面では複数の支援が同時に必要になることが多く、指導内容や実施タイミングが異なれば、別の加算として評価されることがあります。
一方で、性質が重複する加算については併用が制限されます。
| 加算名 | 併用の可否 | 理由・注意点 |
| 退院支援指導加算 | ◯ 可能 | 実施タイミング(退院当日)と目的が異なるため、要件を満たせば併用可能。 |
| 初回加算(介護保険) | ✕ 不可 | 同一月内に退院時共同指導加算を算定すると、初回加算は算定できない。 |
併用可否は、算定タイミング・目的・保険制度の違いをもとに判断されます。
請求時の誤りを防ぐためにも、各加算の特性と要件を正確に把握しましょう。
一目でわかる!医療保険と介護保険の算定要件|比較早見表
退院時共同指導加算は医療保険と介護保険の両方で算定できますが、報酬やルールに細かな違いがあります。
間違いやすい点だからこそ、実務では比較整理が大切です。
同じ「退院時共同指導加算」であっても、保険制度が異なれば金額や算定条件、併用できる加算の可否が変わります。
制度ごとの理解を深めることで、算定ミスや返戻を防ぐことができます。
それぞれの違いを改めてまとめてみましょう。
| 比較項目 | 医療保険 | 介護保険 |
| 報酬 | 8,000 円/回 | 600 単位/回(約6,000円相当) |
| 2回算定できる利用者 | 厚労省が定める疾病(別表7) | 特別管理加算の対象者 |
| 特別管理加算対象者への追加評価 | +2,000 円/回 | なし(2回算定の条件になる) |
| 初回加算との併用 | (制度なし) | 不可 |
| その他 | 退院支援指導加算と併用可能 | ― |
制度の違いを把握すれば、加算の取りこぼしや請求漏れを防ぐことができます。
上記早見表を活用して、訪問看護の報酬請求を正確に行いましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
退院時共同指導加算の算定における注意点
退院時共同指導加算は、制度の理解と実務上の細かなルールが直結するミスの起きやすい加算です。
加算の仕組みを理解していても、実施のタイミングや記録の取り扱い、保険制度の区別などでミスが起こりやすく、返戻や算定漏れにつながることがあります。
特に、介護保険と医療保険の切り分けや、初回加算・特別管理加算との関係性には注意が必要です。
ここでは、以下のような 見落としがちなポイント を押さえながら、正確な算定を行うための実務的な注意点をまとめます。
算定タイミングは退院後の初回訪問時
退院時共同指導加算は、退院前に指導を実施しても「退院後の初回訪問時」に算定されるのが原則です。
訪問看護の加算の多くは実施日当日に算定されますが、退院時共同指導加算は訪問の実施に基づいて算定するため、指導日ではなく訪問日が基準になります。
例えば、病院と訪問看護ステーションが退院前に共同指導を行ったとしても、訪問看護師が実際に自宅を訪問するまでは加算を請求できません。
訪問がなければ加算は無効です。
実施と算定のタイミングのズレを正確に理解し、記録や請求処理に反映しなければなりません。
算定業務のミス防止と効率化を実現するICT活用術【ワイズマン】
退院時共同指導加算をはじめとした複数の訪問看護加算は、算定タイミングや制度上の細かい要件を正しく理解しなければ、返戻・請求漏れにつながりやすいものです。
ここで頼りになるのが、ICT(電子カルテ・介護ソフト)です。
ワイズマンの「訪問看護ステーション管理システムSP」をはじめとするICTツールを活用すれば、以下のような課題を効率的に解決できます。
ここでは、日々の業務負担を軽減し、より質の高いケアに繋げるためのICT活用法として、ワイズマンのソリューションを紹介します。
複雑な算定ルールも安心!請求ソフト「ワイズマンシステムSP」で業務負担を軽減
介護報酬や診療報酬の制度は年々複雑化しており、正確な請求を行うには高度な知識と細かな確認作業が求められます。
特に、退院時共同指導加算のような要件が厳格な加算では、ミスによる返戻や算定漏れのリスクがつきまといます。
ワイズマンの「システムSP」なら、法改正にも自動対応し、複雑な算定ルールを自動で反映可能です。
さらに、算定要件のチェック機能や返戻防止機能も搭載しており、業務の質とスピードを同時に高めることができます。
- 診療報酬・介護報酬改定時には、システムが自動で最新ルールを反映
- 利用者情報から算定可能な加算を自動で提示し、漏れや誤りを防止
- 請求時のエラーチェック機能で返戻リスクを低減
請求業務の「正確さ」と「効率」を両立させたいなら、ワイズマンシステムSPは強力なツールになります。
制度改定にも慌てず、加算漏れのない安心運用を実現できるでしょう。
多職種連携を加速させる「MeLL+」で質の高い共同指導を実現
退院時共同指導加算を算定するには、医療と介護の関係者が円滑に情報を共有し、連携して支援を行うことが必要です。
しかし、実際の現場では情報の伝達ミスや連絡調整の負担が、質の高い共同指導を妨げる要因になりがちです。
ワイズマンの医療・介護連携サービス「MeLL+(メルタス)」を活用すれば、施設内・地域間・家族間それぞれの立場を超えた情報共有とコミュニケーションが可能になります。
そのため、訪問看護師や病院スタッフがリアルタイムに利用者情報を確認でき、共同指導の質も格段に向上できるでしょう。
加算の要件を満たすだけでなく、「本当に意味のある共同指導」を実現するなら、ICTを活用した連携環境の整備も整えていきましょう。

本記事では、2024年診療報酬改定に基づき、訪問看護ステーションが退院時共同指導加算を算定する際の要件や算定単位、必要書類まで網羅的に解説されており、実務者にとって非常に実用的な内容となっています。
なお、退院時共同指導加算の算定には、指導を実施した日時や訪問看護指示書との整合性、医師との連携記録などが厳密に求められるため、事前準備と記録の整備が欠かせません。また、加算の対象は「在宅療養を前提とした退院」であることが原則であり、対象患者の選定やタイミングも重要です。
今後、地域包括ケアの推進に伴い、病院と訪問看護の円滑な橋渡しはますます求められることになります。訪問看護師がこの加算を正しく理解し、チーム医療の一員として積極的に連携に関与していく姿勢が、患者のQOL向上に大きく寄与するでしょう。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
まとめ:退院時共同指導加算を正しく算定し健全なステーション運営を目指そう
退院時共同指導加算は、病院と訪問看護ステーションの連携を評価する制度であり、退院直後の在宅支援を円滑に進めるための加算です。
医療保険・介護保険での算定要件や報酬体系の違い、他加算との関係性を正しく理解しなければなりません。
特に、「退院支援指導加算」や「初回加算」との混同、実施と算定のタイミングのズレなどは現場でミスが起きやすいポイントです。
ICTを活用すれば、業務の属人化や手作業によるリスクを軽減し、請求の正確性とスタッフの負担軽減の両立が図れます。
制度の仕組みを正しく把握し、確実に算定できる体制づくりを進めることが、事業所運営の安定とサービス品質の向上につながります。

監修:斉藤 圭一
主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)
神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。