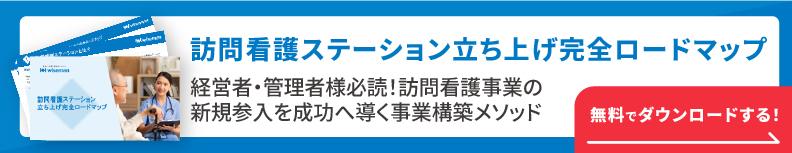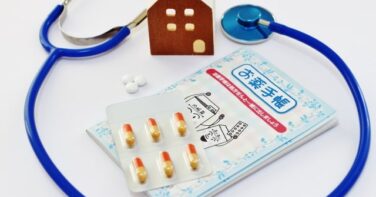訪問看護の服薬管理とは|手順や法的範囲などについて解説
2025.08.23

訪問看護の現場で、利用者の服薬管理に悩む看護師は少なくありません。
服薬管理は利用者の健康維持において、大きな影響を与えるものです。
本記事では、訪問看護における服薬管理の基本的な考え方・具体的な手順などについて解説します。
また、服薬管理を適切に行ううえで重要なポイントも紹介します。
目次
訪問看護における服薬管理

訪問看護における服薬管理は、単に利用者が薬を飲むのを確認するだけではありません。
医師の指示に基づき、利用者が処方された薬を正しく安全に服用し、治療効果を最大限に引き出せるように支援する一連の専門的なプロセスを指します。
服薬管理は、看護師が薬の種類・量・服用方法・服用時間などを丁寧に説明し、利用者が自己管理できるようサポートします。
さらに、副作用の早期発見と対応も重要な役割です。
訪問看護師は多職種と連携しながら、利用者が安心して在宅療養を継続できるよう、きめ細やかな服薬管理を提供する必要があります。
訪問看護の服薬支援サービス一覧

訪問看護師が行う服薬管理には、多岐にわたる支援内容が含まれます。
服薬支援サービスの一覧は以下のとおりです。
| サービス分類 | 具体的な支援内容 |
| 状況把握・アセスメント | ・内服・残薬状況の確認副作用 ・体調変化の観察服薬に関する理解度 ・自己管理能力の評価生活習慣や家族の協力体制の確認 |
| 直接的な服薬支援 | ・薬のセッティング内服介助 ・見守り服薬の声かけ |
| 教育・情報提供 | ・薬の効果・副作用・服用方法の説明服薬の重要性に関する指導 ・服薬管理方法の工夫の提案 |
| 多職種連携 | ・主治医への服薬状況 ・副作用の報告薬剤師との情報共有 ・服薬指導の相談ケアマネジャーとのケアプラン調整 |
| 環境整備 | ・お薬カレンダーやピルケースの導入支援保管場所の整理 ・提案薬局との連携(薬の受け取り代行の検討など) |
訪問看護における服薬管理の3つの目的

訪問看護師が服薬管理を行う目的は、大きく分けて以下の3つがあります。
- 治療効果の最大化
- 副作用の早期発見と防止
- 利用者の自己管理能力の向上
上記の目的を意識することで、より質の高い看護実践につながります。
治療効果の最大化
服薬管理のもっとも基本的な目的は、処方された薬の治療効果を最大限に引き出すことです。
薬は決められた量を決められた時間に正しく服用することで、初めて期待される効果を発揮します。
処方薬の飲み忘れ・飲み間違い・自己判断での中断は、病状の悪化や治療の遅延に直結するものです。
訪問看護師が介入し、確実な服薬を支援することで、治療計画がスムーズに進み、利用者の健康状態の維持・改善に貢献できます。
副作用の早期発見と防止
副作用の早期発見・防止も服薬管理の重要な目的です。
薬には主作用だけでなく、必ず副作用のリスクが伴います。
特に高齢者は複数の薬を服用していることが多く、予期せぬ副作用や薬物相互作用が起こりやすい状態にあります。
定期的に利用者のもとを訪れ、専門的な視点で体調変化を観察することは、訪問看護師の大切な役割です。
些細な変化を捉え、副作用を早期に発見し、速やかに医師や薬剤師に報告することで、重篤化を防止できます。
利用者の自己管理能力の向上
訪問看護の最終的な目標は、利用者が可能な限り自立した生活を送れるように支援することです。
服薬管理においても、ただ薬をセットして飲ませるだけでは不十分です。
「なぜこの薬が必要なのか」「飲むとどのような効果があるのか」を利用者が理解できるよう、根気強く説明を続けることが大切です。
お薬カレンダーの使い方を一緒に練習するなど、利用者自身の「できること」を増やしていく関わりが、その人らしい生活の継続につながります。
訪問看護における服薬管理の法的範囲

本章では、安心して業務にあたるために知っておくべき法的範囲と責任の所在について解説します。
現場で働く看護師にとって、服薬管理に伴う法的責任は無視できない要素です。
医師・訪問看護師・薬剤師それぞれの役割と責任を正確に把握しましょう。
責任の所在と役割分担
訪問看護での服薬管理は、多職種がそれぞれの専門性に基づいて役割を担っています。
責任の所在を正しく理解し、各職種と適切に連携することが重要です。
| 職種 | 主な役割と責任 | 連携のポイント |
| 医師 | 診断と処方服薬に関する最終的な指示・副作用発生時の診断と治療方針の決定 | 看護師からの客観的な報告(残薬・バイタル・症状変化など)に基づき、処方の調整を判断します。正確な情報伝達が不可欠です。 |
| 訪問看護師 | 医師の指示に基づく服薬管理の実践服薬状況と副作用の観察・アセスメント利用者・家族への指導と精神的支援多職種への情報提供と連携調整 | 医師の指示の範囲内で業務を行います。指示内容に疑問がある場合は必ず確認し、自己判断で行為を行わないことが鉄則です。 |
| 薬剤師 | 調剤と鑑査薬学的知見に基づく情報提供(副作用・相互作用など)・在宅患者訪問・薬剤管理指導の実施 | 薬の専門家として、看護師では判断が難しい薬学的疑問に答えます。処方内容の確認や一包化の相談など、積極的に連携します。 |
看護師は、医師の具体的な指示の下で医療行為を行う職種です。
したがって、服薬管理に関するすべての行為は、医師の指示に基づいて行われる必要があります。
薬のセット・受け取り代行の可否
現場で特に判断に迷う「薬のセット」と「薬の受け取り代行」について、その可否を整理します。
まず、「薬のセット」とは、処方されたPTPシートから薬を取り出し、お薬カレンダーやピルケースに日付や時間帯に合わせて配置する行為です。
これは、原則として医療行為に該当します。
医師の指示があれば、訪問看護師が薬のセットを実施できます。
ただし、インシデントのリスクが高いため、事業所内で手順を標準化し、ダブルチェックなどの安全対策を徹底することが不可欠です。
対して、薬局からの薬の受け取り代行は医療行為には該当しません。
しかし、これも無条件に行えるわけではありません。
薬の受け取り代行は利用者本人、またはその家族から明確な依頼があった場合に限られます。
また、薬局の薬剤師による受け取り代行の了承も必要です。
利用者が身体的な理由でどうしても薬局に行けないなど、やむを得ない事情がある場合に限定して検討すべきです。
まずは、家族や地域のサポートサービス(配薬サービスなど)の活用を検討・提案することが優先されます。
訪問看護で服薬管理を実施する際のポイント

服薬管理を実施する際は以下のポイントを意識しましょう。
- アセスメントで問題を洗い出す
- 適切な看護計画を策定する
- インシデント発生時の対応マニュアルを作成する
- お薬カレンダー・ピルケースなどを活用する
- 医師・薬剤師への報告とフィードバックを欠かさない
- 正確な看護記録を作成する
- 利用者の状態に合わせて対応を工夫する
- 多剤併用に注意する
- アプリやアラームなどICTツールを導入する
それぞれのステップを丁寧に行うことが、質の高いケアにつながります。
アセスメントで問題を洗い出す
効果的な服薬管理は、正確なアセスメントから始まります。
薬が飲めない・飲まない背景には、さまざまな要因が隠されているものです。
アセスメントを行う際は、以下の視点を意識することが重要です。
| アセスメントの視点 | 確認すべき項目例 |
| 利用者本人に関する因子 | 疾患・症状: 病識の有無・症状による服薬への影響(痛み・吐き気など) 認知機能: 記憶力・理解力・判断力の低下の有無 身体機能: 視力・聴力・嚥下機能・手指の巧緻性 心理・社会的因子: 服薬への意欲・薬に対する思い込み・独居・経済状況 |
| 治療に関する因子 | 処方内容: 薬剤の数・服薬回数・剤形・複雑な手技の有無 薬の効果・副作用: 治療効果の自覚、副作用の経験 医療者との関係: 医師や看護師との信頼関係 |
| 環境に関する因子 | 住環境: 薬の保管場所・整理状況・生活動線 家族・支援者: 同居家族の有無・介護力・協力度 利用中のサービス: ヘルパー・デイサービスなど他サービスの利用状況 |
適切な看護計画を策定する
アセスメントで明らかになった問題点に基づき、具体的な看護計画(OP/TP/EP)を立案します。
本章では、読者の状況に近い「軽度の認知機能低下があり、服薬が困難なうえに多剤併用となっている高齢者」を例に、看護計画の立て方を見ていきましょう。
| 計画項目 | 具体的な計画内容(例) |
| O-P (Observation Plan)観察計画 | 1. 残薬の有無と数・服薬状況 2. バイタルサイン・一般状態(活気・表情・言動) 3. 副作用の有無(ふらつき・便秘・食欲不振など) 4. 薬識(薬の必要性・効果・副作用の理解度) 5. 認知機能・身体機能の変化 6. 家族の関わり方・サポート状況 |
| T-P (Therapeutic Plan)援助計画 | 1. 医師の指示に基づき、1週間分ずつお薬カレンダーに薬をセットする 2. 服薬時間になったら電話で声かけを行う 3. 訪問時に、その日の服薬が済んでいるかカレンダーで一緒に確認する 4. 薬の効果や副作用について、わかりやすい言葉で繰り返し説明する 5. 副作用が疑われる症状が見られた際は、速やかに主治医に報告する 6. 利用者が服薬できた際には、肯定的な声かけで意欲を引き出す |
| E-P (Education Plan)教育計画 | 1. 家族に対し、お薬カレンダーの確認方法と、飲み忘れ発見時の連絡方法を説明する 2. 利用者本人と家族に、副作用の初期症状について説明し、異変があればすぐに連絡するよう伝える 3. 確実な服薬が治療において重要であることを、パンフレットなどを用いて説明する |
インシデント発生時の対応マニュアルを作成する
インシデント(ヒヤリハット)が発生した際に備えて、対応マニュアルを作成しておくことも重要です。
注意深く支援していても、誤薬や服薬忘れといったインシデントが起こる可能性はゼロではありません。
万が一の事態に備え、冷静かつ迅速に対応するための手順をあらかじめ明確にしておきましょう。
以下に、インシデント発生時の基本的な対応フローを示します。
| ステップ | 内容 |
| 第一報と事実確認 | 利用者や家族からインシデント発生の連絡を受ける、または訪問時に発見する。まずは利用者の安全確保を最優先し、バイタルサインや意識レベル、全身状態を確認する。「いつ・どの薬を・どのくらい」間違えたのか、客観的な事実を冷静に確認する。 |
| 主治医への報告・指示 | 速やかに主治医(または指示を出した医師)に連絡する。SBARなどの報告フレームワークを用い、状況を正確かつ簡潔に伝える。医師の指示を仰ぎ、必要な処置や今後の観察項目について確認する。 |
| 利用者・家族への対応 | 医師の指示に基づき、必要なケアを実施する。状況を誠実に説明し、謝罪する。今後の対応策についても伝えることで、不安の軽減に努める。 |
| 関係各所への報告 | 事業所の管理者やケアマネジャーに状況を報告し、情報を共有する。今後の対応について連携を図る。 |
| 記録と再発防止策の検討 | インシデント報告書に、発生状況・対応・結果・今後の対策などを詳細に記録する。事業所内でカンファレンスを開き、原因を分析して具体的な再発防止策を立案・共有する。 |
お薬カレンダー・ピルケースなどを活用する
お薬カレンダーやピルケースは、服薬管理における定番のツールです。
しかし、ただ導入するだけでなく、利用者に合わせた工夫を凝らすことで、その効果を最大限に高められます。
| 工夫 | 詳細 |
| 設置場所の工夫 | 利用者の生活動線を考慮し、必ず目に入る場所に設置します。 |
| 視覚的な工夫 | 視力が低下している利用者には、曜日や時間をマジックで大きく書いたり、朝・昼・夕で色分けしたりします。 |
| 服薬の習慣化 | 「朝食が終わったら薬を飲む」など、日々の生活習慣と服薬を結びつけて声かけを行います。 |
| ダブルチェックの仕組み | 家族にもカレンダーの確認を依頼し、飲み忘れがないかチェックしてもらう体制を作ります。 |
| ツールの選択 | 1 日分ずつ取り外せるタイプや、アラーム機能付きのピルケースなど、利用者の能力に合ったツールを選定します。 |
上記の小さな工夫が、利用者の「うっかり忘れ」を防ぎ、服薬の確実性を高めます。
医師・薬剤師への報告とフィードバックを欠かさない
訪問時に得た情報を的確にフィードバックすることが、より良い治療につながります。
報告の際は、SBAR(エスバー)のようなフレームワークを活用しましょう。
| SBAR | 報告内容の例 |
| S (Situation)状況 | 「〇〇様(利用者名)の服薬状況についてご報告します。」 |
| B (Background)背景 | 「〇〇様は高血圧と糖尿病で内服治療中です。1 週間前から新しい降圧剤が追加されています。」 |
| A (Assessment)アセスメント | 「訪問時に確認したところ、新しい降圧剤が 3 日分残っていました。本人に伺うと、『飲むとめまいがして怖い』とのことです。実際に、訪問時の血圧は収縮期 98mmHg と低めでした。」 |
| R (Recommendation)提案 | 「副作用による服薬中断の可能性があるため、一度診察していただき、処方の見直しをご検討いただけないでしょうか。」 |
正確な看護記録を作成する
看護記録は多職種との情報共有や、万が一の際の法的証拠となる重要な書類です。
服薬管理に関する記録は、以下のポイントを押さえて具体的に記載しましょう。
| 項目 | 詳細 |
| 5W1Hを明確に | 日時・場所・看護師名・利用者・薬剤名・介助方法などを記載します。 |
| 客観的な事実を記載 | 「残薬 〇錠」「血圧 〇〇/〇〇mmHg」「ふらつきあり」など、具体的な数値や観察項目を記載します。 |
| 利用者の主観的な訴えも記載 | 「『薬を飲むと気持ちが悪い』との発言あり」など、利用者の言葉をそのまま引用符で記載します。 |
| 計画と評価を記載 | 看護計画で立てたケアを実施したこと、その結果どうだったかを記録します。 |
| 経時的な変化がわかるように | 前回の訪問時と比較して、状態がどのように変化したかを記載することで、アセスメントの精度が高まります。 |
利用者の状態に合わせて対応を工夫する
錠剤やカプセルが飲みにくい、薬の数が多いなど、利用者ごとに服薬を妨げる要因はさまざまです。
マニュアルに沿った対応だけでなく、利用者の状態に合わせた個別的な工夫が求められます。
| 困りごと | 対応の工夫(例) |
| 錠剤が大きくて飲みにくい | 服薬補助ゼリーやとろみ剤を使用する。医師・薬剤師に相談し、口腔内崩壊錠や粉薬、貼り薬など剤形の変更を検討してもらう。自己判断で錠剤を砕かない。 |
| 嚥下機能が低下している | 上体を起こした正しい姿勢で服用してもらう。簡易懸濁法(温湯で薬を溶かして服用する方法)を医師・薬剤師に確認の上で試す。 |
| 認知症で服薬を拒否する | 無理強いせず、時間を変えて再度試みる。なぜ飲みたくないのか、気持ちを傾聴し、共感する。好きな飲み物と一緒に服用してもらうなど、本人が受け入れやすい方法を探る。 |
| インスリン自己注射などへの対応 | 手技の手順を写真やイラストで図解し、見える場所に貼る。訪問時に一緒に手技を行い、都度確認・修正する。利用者の手技が安定するまで、訪問頻度を上げることを検討する。 |
多剤併用に注意する
6種類以上の薬を服用している状態は「ポリファーマシー」と呼ばれ、高齢者において特に注意が必要です。
訪問看護師は、ポリファーマシーのリスクを念頭に置き、以下のような視点で関わることが重要です。
| 項目 | 内容 |
| お薬手帳の一元化 | 複数の医療機関にかかっている場合は、お薬手帳を 1 冊にまとめるよう促し、処方の全体像を把握します。 |
| 残薬の正確な把握 | 「何の薬が、どのくらい余っているか」を正確に確認し、医師・薬剤師に情報提供します。これは処方見直しの重要な根拠となります。 |
| 減薬の提案 | 有害事象(ふらつき・食欲不振など)が薬によるものではないかと疑われる場合、アセスメントに基づき、医師に減薬や中止の検討を提案します。 |
| 機能食品との相互作用 | サプリメントや健康食品を摂取していないか確認し、薬との相互作用の可能性がある場合は薬剤師に相談します。 |
アプリやアラームなどICTツールを導入する
近年では、ICT(情報通信技術)を活用した服薬支援ツールも増えています。
利用者や家族がスマートフォンやタブレットの操作に慣れている場合は、有効な選択肢となり得ます。
| 名称 | 説明 |
| 服薬支援アプリ | 服薬時間になるとアラームと薬の種類を通知してくれるアプリです。飲んだかどうかを記録する機能もあり、家族が遠隔で服薬状況を確認できるものもあります。 |
| スマートスピーカー | 「〇時の薬の時間を教えて」のように設定することで、音声で服薬時間を知らせてくれます。 |
| オンライン服薬指導 | 薬剤師がビデオ通話を通じて、服薬指導や残薬の確認を行います。薬局に行くのが困難な場合に有効です。 |
上記のツールを導入する際は利用者のITリテラシーやプライバシーに配慮し、本人の同意を得たうえで、無理なく使えるものを選ぶことが大切です。

この記事は、服薬管理の基本的な考え方から具体的な手順、法的範囲、さらには実践的なポイントまで、極めて詳細かつ網羅的に解説されており、在宅医療を支える専門職の皆様にとって大変有益な指針となるでしょう。治療効果の最大化、副作用の早期発見と防止、そして利用者の自己管理能力向上という服薬管理の三つの目的が明確に示されている点は、質の高いケアを提供する上で深く認識すべき要素です。
医師・看護師・薬剤師それぞれの役割と責任の所在を法的な視点から整理し、薬のセットや受け取り代行に関する判断基準が具体的に提示されていることは、現場の安全な業務遂行に直結します。アセスメントに基づいた看護計画の策定、インシデントマニュアルの整備、多職種連携、そしてポリファーマシーへの注意喚起といった実践的なアプローチは、事業所の安定経営と質の高いサービス提供に貢献すると思われます。
まとめ:スムーズな服薬管理でより良い訪問看護サービスを提供しよう

本記事では、訪問看護における服薬管理について解説しました。
服薬管理は、在宅療養を安全かつ安心して続けるための要となる非常に専門性の高い看護実践です。
本記事で得た知識と視点を、ぜひ日々のケアに活用してください。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。