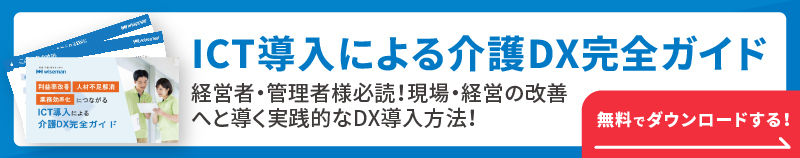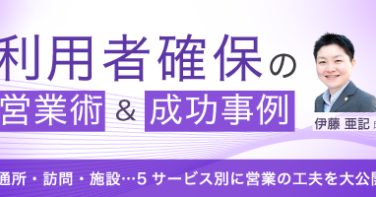ADL維持等加算とは?令和6年度最新情報と算定要件・計算方法を徹底解説
2025.04.27

「ADL維持等加算って何だろう」
「ADL維持等加算はどうやって計算すれば良いのだろうか」
上記のような疑問をお持ちの方もいるでしょう。介護現場で必須となるこの制度を理解して適切に利用すれば、利用者の生活の質を保つための支援を提供できます。
本記事では、ADL維持等加算の概要や算定要件を紹介します。介護の質を高めるための重要な要素とも言えるADL維持等加算の理解を深め、日々のサービスに活かしましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
ADL維持等加算とは

ADL維持等加算とは、介護サービスにおける利用者の日常生活動作(ADL)の維持・改善を目的とした介護報酬の加算制度です。利用者の自立支援と重度化防止を促進し、介護サービスの質向上を図ることを目指しています。
ADL維持等加算の目的
ADL維持等加算の主な目的は以下のとおりです。
- 利用者のADL(日常生活動作)の維持・向上を図り、可能な限り自立した生活を支援すること
- 介護サービスの質の向上を促進し、根拠に基づいた介護の実践を推進すること
- 介護事業所における自立支援への取り組みを評価し、インセンティブを与えること
- 高齢者のQOL(生活の質)の向上に貢献すること
ADL維持等加算は利用者のADLを維持または改善することで重症化を予防し、自立した生活を支援することを目的としています。また、この加算を通じて、介護事業所は自立支援への取り組みを可視化し、介護サービスの質を向上させることができます。
ADL維持等加算の対象となるサービスと施設
2024年現在、ADL維持等加算の対象となる主なサービスと施設は以下のとおりです。
| サービスの種類 | ・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 |
| 施設の種類 | ・介護老人福祉施設 ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(各市町村が管轄) ・地域密着型特定施設入居者生活介護(各市町村が管轄) |
上記以外にも、保険者が所管するサービスについては各自治体への確認が必要です。
ADL維持等加算の算定対象となる利用者
ADL維持等加算の算定対象となる利用者は、主に要介護認定を受けている方です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 評価対象となる利用期間が6カ月を超える者
- ADLの評価を適切に行える者
ADLの評価は、一定の研修を受けた者がバーセルインデックス(BI)を用いて行う必要があります。ADL維持等加算を算定すると介護サービスの質を利用者やケアマネジャーに示すことができ、事業所の営業活動にもつながります。
ADL維持等加算の算定要件

ADL維持等加算を算定するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件は、利用者様のADLを適切に評価し、維持・改善するための取り組みを促進することが目的です。
ここでは、ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件の違いやバーセルインデックス(BI)の活用、LIFEへのデータ提出、PDCAサイクルの重要性について解説します。
ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件の違い
ADL維持等加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があり、それぞれ算定要件と単位数が異なります。算定を行うには、バーセルインデックスにてADL値を適切に評価し、LIFEにてデータ提出しなければいけません。
| 算定要件 | ADL維持等加算(Ⅰ) | ADL維持等加算(Ⅱ) |
| 単位数 | 30単位/月 | 60単位/月 |
| ADLの評価 | バーセルインデックスを用いてADL値を測定 | バーセルインデックスを用いてADL値を測定 |
| LIFEへのデータ提出 | 必要 | 必要 |
| ADL値の改善 | 一定以上の改善が見られること | より高い水準の改善が見られること |
ADL維持等加算におけるバーセルインデックス(BI)の活用
ADL維持等加算を算定する上で、バーセルインデックス(BI)は非常に重要な役割を果たします。BIは利用者の日常生活動作(ADL)を評価するための指標であり、以下の10項目で構成されています。
- 食事
- 更衣
- 整容
- 排便
- 排尿
- トイレ動作
- 移乗
- 移動
- 階段昇降
- 入浴
上記の項目を評価することで利用者のADLの状態を客観的に把握し、適切な介護計画の作成や効果測定に役立てられます。
ADL維持等加算の算定は、評価対象期間中の初回と7カ月目の合計2回の結果をもとに、バーセルインデックスを用いて利用者(要介護者)のADL値を測定し、LIFEに情報を提出します。
LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出とフィードバック
ADL維持等加算を算定するためには、LIFEへのデータ提出が必須です。LIFEは、介護サービス利用者の状態やサービス内容に関するデータを収集・分析し、科学的根拠に基づいた介護の実現を支援するシステムです。
LIFEへのデータ提出を通じて、事業者は利用者のADLに関する情報を国に提供します。国は提出されたデータを分析し、各事業者の取り組み状況や効果をフィードバックします。このフィードバックを参考にPDCAサイクルを回し、介護サービスの質の向上につなげることが重要です。
ADL維持等加算の申請・届出を行う場合、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行う必要があります。
ADL維持等加算におけるPDCAサイクルの重要性
ADL維持等加算の算定においては、PDCAサイクルを回すことが重要です。PDCAサイクルとは以下の4つの段階を経て、継続的に改善を図るためのフレームワークです。
| Plan(計画) | 利用者のADLの状態を評価し、目標を設定する |
| Do(実行) | 目標達成のために、具体的な介護計画を実行する |
| Check(評価) | 定期的にADLを評価し、計画の進捗状況や効果を検証する |
| Act(改善) | 評価結果に基づき、計画や実施方法を改善する |
PDCAサイクルを回すとADL維持等加算の効果を最大限に引き出し、利用者様の生活の質を向上させることができます。
ADL維持等加算の計算方法

ADL維持等加算を算定するためには単位数や計算方法、LIFEへのデータ提出といった一連の流れを理解しておく必要があります。ここでは、それぞれの項目について詳しく解説します。
ADL維持等加算の単位数と介護報酬
ADL維持等加算は、利用者のADLの維持・改善度合いに応じて、以下の2種類に区分されています。それぞれの単位数と算定要件は以下のとおりです。
| 加算の種類 | 単位数(月額) | 主な算定要件 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位 | ADL利得が1以上であること |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位 | ADL利得が3以上であること |
ADL利得とは、利用者のADLがどれだけ改善したかを示す指標であり、バーセルインデックス(BI)を用いて測定します。ADL維持等加算(Ⅰ)は現状維持、ADL維持等加算(Ⅱ)は改善に対して支給される加算という点が大きな違いです。
ADL維持等加算の計算シートと活用方法
ADL維持等加算の計算には、厚生労働省が提供する計算シートや、介護ソフトに搭載されている計算機能を利用すると便利です。これらのツールを活用すると、煩雑な計算を効率的に行えます。
計算シートは、以下の項目を入力すると自動的にADL利得を算出できます。
- 利用者の基本情報(氏名、年齢、要介護度など)
- バーセルインデックス(BI)の測定結果(利用開始時と6カ月後)
- 調整係数
調整係数は利用者の状態に応じて設定されるもので、計算シートの説明書に詳細が記載されています。LIFEにADL値を入力すれば、ADL利得の計算ができます。
計算シートや介護ソフトを活用すると、ADL維持等加算の算定に必要な情報を簡単に把握し、適切な介護報酬を請求することが可能です。
LIFEへのデータ提出の流れと注意点
LIFEへのデータ提出は、以下の流れで行います。
- LIFEのID・パスワードを取得する
- LIFEにログインし、利用者の基本情報を登録する
- バーセルインデックス(BI)の測定結果を入力する
- データを提出する
データ提出の際には、以下の点に注意が必要です。
- 提出期限を守る(既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日までとなっており、2回目以降の情報提供は、6カ月後の翌月10日までの合計2回と少ない頻度での提出ができる)
- 入力内容に誤りがないか確認する
- BIの項目ごとに提出する必要がある
LIFEへのデータ提出はADL維持等加算の算定だけでなく、介護サービスの質向上にもつながる重要な取り組みです。正確なデータを提出し、フィードバックを参考にすると、より効果的な介護サービスを提供できます。
LIFEへのデータ入力手順は以下のとおりです。
- 管理ユーザーまたは操作職員のアカウントでログイン
- トップメニューから「令和〇年度ADL維持等加算算定」をクリック
- 「対象サービス」の右にある「▼」をクリックし、加算算定の判断を行うサービスを選択すると利用者一覧が表示
- 各介護サービス利用者のADL維持等加算情報の入力(「初月」「6月後」「初月ADL」「6月後ADL」)
- 全対象者の入力完了後、計算ボタンをクリック
入力操作は20分以内でこまめに一時保存することを推奨します。また、データ提出においてバーセルインデックス(BI)以外からの読み替えデータを使用することも可能です。
ただし、測定者がバーセルインデックス(BI)係る研修を受け、バーセルインデックス(BI)への読み替え精度などを踏まえたうえで、必要に応じて別途評価をするなどの対応を行い提出する必要があります。
ADL評価のポイントと研修情報

ADL(日常生活動作)の評価は利用者の状態を把握し、適切な介護計画を立てる上で非常に重要です。客観的な評価を行うことで、利用者の自立支援に向けた具体的な目標設定が実現します。
ここでは、ADL評価に用いられる主要な指標であるバーセルインデックス(BI)について詳しく解説するとともに、評価のポイントや研修情報を紹介します。
バーセルインデックス(BI)とは
バーセルインデックス(Barthel Index:BI)は、日常生活動作(ADL)を評価するための代表的な指標の一つです。BIは以下の10項目で構成されており、それぞれの項目について利用者の自立度を評価します。
具体的な評価は、以下のとおりです。
| 項目 | 評価 | 点数 |
| 食事 | 自立、部分介助、全介助 | 0~10点 |
| 車椅子からベッドへの移動 | 自立、一部介助、ほとんど介助、不可能 | 0~15点 |
| 整容 | 自立、介助 | 0~5点 |
| トイレ動作 | 自立、一部介助、全介助 | 0~10点 |
| 入浴 | 自立、介助 | 0~5点 |
| 歩行 | 自立、一部介助、不可能 | 0~15点 |
| 階段昇降 | 自立、一部介助、不可能 | 0~10点 |
| 着替え | 自立、一部介助 | 0~10点 |
| 排便コントロール | 失禁なし、時々失禁、失禁 | 0~10点 |
| 排尿コントロール | 失禁なし、時々失禁、失禁 | 0~10点 |
各項目の点数を合計すると、総合的なADLの自立度を評価できます。なお、合計点が高いほど自立度が高いことを示します。
ADL評価におけるバーセルインデックスの重要性
バーセルインデックスは、ADL維持等加算の算定においても重要な役割を果たします。加算の算定要件として利用者のADLを定期的に評価し、その結果をLIFEに提出することが求められるからです。
BIを活用することで、以下のメリットが期待できます。
| 客観的な評価 | ・BIは明確な評価基準に基づいている ・評価者による主観的な判断を排除できる |
| 変化の把握 | ・定期的な評価により、利用者のADLの変化を客観的に把握できる ・改善が見られれば介護方法が適切であることを示し、悪化が見られれば、介護計画の見直しが必要となる |
| 情報共有の円滑化 | ・BIの結果は多職種間で共有しやすい ・チーム全体で利用者の状態を把握し、共通の目標に向かって取り組める |
ADL維持等加算の算定だけでなく、利用者の自立支援に向けた介護サービスを提供する上で、バーセルインデックスは非常に有効なツールです。
バーセルインデックスに関する研修情報
バーセルインデックスを正確に評価するためには、適切な知識と技術が必要です。そのため、BIに関する研修を受講することをおすすめします。
研修では、以下のような内容を学べます。
- バーセルインデックスの概要と目的
- 各項目の評価基準と評価方法
- 評価の実践(事例検討など)
- 評価結果の解釈と活用
研修の種類としては各都道府県や市区町村が主催するものや、介護関連団体が主催するものなどがあります。また、参考資料として、各学会や研究機関が作成したバーセルインデックスに関するガイドラインやマニュアルなども活用できます。
適切な研修を受講し、バーセルインデックスの知識と技術を習得すれば、より質の高い介護サービスを提供できるでしょう。
正確なADL評価は、利用者の状態を正しく理解し、適切な支援を提供するための第一歩です。バーセルインデックスを有効活用し、利用者様の自立支援に貢献しましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
ADL維持のための介護:具体的な方法と事例を紹介

ADL(日常生活動作)の維持・向上は、利用者が可能な限り自立した生活を送るために非常に重要です。ここでは、具体的な方法を紹介します。
ADL維持のためのリハビリテーション:専門職の役割
ADL維持のためのリハビリテーションは理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの専門職が中心となって行われます。それぞれの専門性を活かし、利用者の状態に合わせたプログラムを提供することが重要です。
| 専門職 | 役割 |
| 理学療法士(PT) | ・基本的な動作能力の改善を目指す ・歩行訓練や筋力トレーニングなどを通して、移動能力の向上を図る |
| 作業療法士(OT) | ・日常生活における具体的な動作の練習を行う ・食事や更衣、入浴など、個々の利用者が困難と感じる動作の改善をサポートする |
| 言語聴覚士(ST) | ・嚥下機能の改善やコミュニケーション能力の維持・向上を目指す ・食事の際の誤嚥防止や、円滑なコミュニケーションを支援する |
上記の専門職が連携し、多角的な視点からリハビリテーションを提供すれば、より効果的なADL維持が可能です。
日常生活動作(ADL)訓練の具体的な方法
ADL訓練は、利用者が日常生活で行うさまざまな動作を練習し、維持・向上させるための訓練です。以下に具体的な方法を紹介します。
| ADL項目 | 訓練方法 | ポイント |
| 食事 | 箸やスプーンの持ち方、食事姿勢の練習 | 安全に食事ができるよう、姿勢や嚥下(えんげ)の状態に注意する |
| 更衣 | 着脱しやすい衣服の選択、ボタンやファスナーの練習 | できるだけ自分でできるよう、段階的にサポートを減らす |
| 入浴 | 浴槽への出入り、身体の洗い方の練習 | 転倒防止のため、手すりの設置や滑り止めマットの使用を検討する |
| 排泄 | トイレへの移動、衣服の着脱、排泄後の処理の練習 | ポータブルトイレの利用や夜間のトイレ誘導など、状況に応じた支援を行う |
| 移動 | 歩行訓練、車椅子操作の練習 | 安全な歩行をサポートするため、歩行器や杖の利用を検討する |
上記の訓練は、利用者の身体機能や認知機能に合わせて個別に計画しなければいけません。また、訓練を行う際は利用者の意欲を高めることが重要です。
成功体験を積み重ねれば、自信を持ってADLに取り組めます。
ADL維持を促進する介護環境の整備
ADL維持のためには、適切な介護環境の整備も不可欠です。安全で快適な環境を提供すると、利用者が積極的にADLに取り組めます。
| 対策 | 詳細 |
| バリアフリー化 | 段差の解消や手すりの設置、滑り止めマットの使用など、転倒のリスクを減らすための対策を行う |
| 適切な福祉用具の活用 | 歩行器や車椅子、入浴補助具など、利用者様の状態に合わせた福祉用具を選定し、適切に使用する |
| 明るく開放的な空間 | 日光が入りやすく風通しの良い空間は、利用者の気分を高め、活動意欲を促進する |
| コミュニケーションの促進 | スタッフや他の利用者との交流を促すと社会的孤立を防ぎ、精神的な健康を維持できる |
上記の環境整備に加えて、利用者のADL能力を評価することも重要です。Barthel Index(バーセルインデックス)を用いた評価では、食事や入浴、歩行などの項目を評価し、ADLの状態を把握します。
ADL維持は利用者の生活の質を向上させるだけでなく、介護者の負担軽減にもつながります。専門職との連携や適切な訓練、介護環境の整備を通じて、ADL維持を積極的に支援しましょう。
ADL維持等加算を活用して質の高い介護サービスを提供する

ADL維持等加算は、介護サービスの質を向上させるための重要な指標です。この加算を適切に活用すれば利用者の自立支援を促進し、より質の高い介護サービスを提供できます。
ここでは、ADL維持等加算を介護サービスの質向上につなげるためのポイントや多職種連携によるADL維持の取り組み、ADL維持等加算に関する最新情報と今後の展望について解説します。
ADL維持等加算を介護サービスの質向上につなげるためのポイント
ADL維持等加算を介護サービスの質向上につなげるためには、以下のポイントが重要です。
| 強調ポイント | ADL維持・改善のためのポイント |
| 適切なADL評価の実施 | ・バーセルインデックス(BI)などを用いて、利用者のADLを正確に評価することが基本・ADL評価は、一定の研修を受けた者が行う |
| 個別ケア計画の作成 | ADL評価の結果に基づき、利用者一人一人の状態に合わせた個別ケア計画を作成する |
| 目標設定とモニタリング | ケア計画にはADL維持・改善の具体的な目標を設定し、定期的に進捗状況をモニタリングする |
| LIFEへのデータ提出と活用 | LIFEへデータを提出し、フィードバック情報を活用してケアの質を継続的に改善する |
| 多職種連携の推進 | 医師や看護師、リハビリ専門職、介護職など、多職種が連携してADL維持・改善に取り組む |
上記のポイントを実践するとADL維持等加算は、単なる加算算定のためのツールではなく、介護サービスの質を向上させるための有効な手段としても活用できます。
多職種連携によるADL維持の取り組み
ADL維持は、多職種がそれぞれの専門性を活かしながら取り組むことがポイントです。以下に、具体的な取り組み事例を紹介します。
| 職種 | 役割 | 具体的な取り組み |
| 医師 | 医学的な管理・指示 | ・利用者の基礎疾患やADLに影響を与える可能性のある疾患の管理 ・リハビリテーション計画への医学的な指示 |
| 看護師 | ・健康状態の観察・医療ケア | ・バイタルチェック ・服薬管理 ・褥瘡予防 ・創傷ケア ・感染症対策 |
| 理学療法士 (PT) | ・運動機能の評価・リハビリ計画の立案・実施 | ・歩行訓練 ・筋力トレーニング ・バランス訓練 ・関節可動域訓練 |
| 作業療法士 (OT) | ・日常生活動作の評価・リハビリ計画の立案・実施 | ・食事、更衣、排泄、入浴などの日常生活動作訓練 ・福祉用具の選定 ・使用指導 |
| 言語聴覚士 (ST) | ・摂食・嚥下機能の評価・訓練 | ・嚥下訓練 ・発声訓練 ・コミュニケーション支援 |
| 介護職 | ・日常生活の支援・ADL訓練のサポート | ・食事介助 ・排泄介助 ・入浴介助 ・更衣介助 ・移動介助 ・レクリエーションの実施 |
| 管理栄養士 | ・栄養状態の評価・栄養指導 | ・食事内容の改善 ・栄養補助食品の提案 |
| ケアマネジャー | ・ケアプランの作成・多職種連携の調整 | ・利用者のニーズに基づいたケアプランの作成 ・サービス担当者会議の開催 ・関係機関との連携 |
上記の職種がそれぞれの専門知識や技術を共有し、利用者のADL維持・改善に向けて協力することで、より効果的なケアを提供できます。
ADL維持等加算に関する最新情報と今後の展望
ADL維持等加算は介護報酬改定のたびに、算定要件や単位数が見直されています。
2024年の介護報酬改定では、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件が「2以上」から「3以上」に見直されました。これにより、より高いADL改善効果が求められるようになったと判断できます。
また、今後はADL維持等加算の対象サービスが拡大される可能性や、LIFEへのデータ提出の義務化が進むことも予想されます。さらに、AIやICTを活用したADL評価やリハビリテーション技術の開発も進み、より効果的かつ効率的なADL維持・改善が期待されるでしょう。
ADL維持等加算は、介護サービスの質の向上を促進するための重要な制度です。最新情報を常に把握し、適切に活用すれば利用者の自立支援を推進し、より質の高い介護サービスを提供できます。
Q&A:ADL維持等加算でよくある質問

最後に、ADL維持等加算に関する質問をまとめました。それぞれの回答を参考に、算定に活かしてください。
Q. ADL維持等加算の対象外となるケース
A. ADL維持等加算は、原則として要介護認定を受けている方が対象です。以下のようなケースでは対象外となる場合があります。
| 除外条件 | 理由 |
| 要支援の方 | ADL維持等加算は、要介護者の方を対象としている |
| 評価対象期間が6カ月に満たない利用者 | ADLの維持・改善を評価するため、一定期間のサービス利用が必要 |
| LIFEへのデータ提出を行っていない場合 | LIFEへのデータ提出は算定要件に含まれている |
| ADL利得が一定の基準に満たない場合 | ADL維持等加算(Ⅰ)と(Ⅱ)では、それぞれADL利得の基準が設けられている |
Q. ADL維持等加算の算定を途中で終了する場合の手続き方法
A. ADL維持等加算の算定を途中で終了する場合、速やかにその旨を保険者に届け出る必要があります。具体的な手続きは以下のとおりです。
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の変更:ADL維持等加算の算定状況を「なし」に変更する
- 保険者への届け出:変更後の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を保険者に提出する
また、算定を終了する理由(例:利用者の状態変化、事業所の体制変更など)を明確に伝えることが重要です。
Q. 利用者のADLが改善しない場合の加算について
A. ADL維持等加算は、ADLの維持または改善が見られた場合に算定できる加算です。そのため、利用者のADLが改善しない場合でも、現状維持ができていればADL維持等加算(Ⅰ)の算定対象となる場合があります。
ただし、ADL利得が基準に満たない場合は、加算の対象外となる点に注意が必要です。

高齢者は、予期せぬうちに身体機能が低下していきます。このような状況を未然に防ぐためにも意図的なADLの維持や向上にむけた取り組みが必要です。ADL維持等加算は、利用者が自身の望む生活を送るための自立支援や身体機能の低下の防止を促し、介護サービスの質の向上を図ることを目的とした取り組みです。
ADL維持等加算は、利用者の日常生活における自立を主眼に置いていますので、例えば(地域密着型・認知症対応型)通所介護であれば、通所介護施設での日中のご様子だけではなく、ご自宅(在宅)での生活状況の把握もとても重要になってきます。
また介護老人福祉施設であれば、機能訓練のための機能訓練にならないように、身近な生活上の目標を持ちつつ、ご本人が意欲的に取り組める環境づくりも大切になってくるのではないかと思います。
なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。
介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。
ADL維持等加算の理解を深めてより良いサービスを提供しよう

ADL維持等加算は、利用者のADL(日常生活動作)の維持・向上を支援する介護サービス事業所を評価する制度です。この加算を適切に活用すると利用者の生活の質を高め、自立した生活をサポートできます。
ADL維持等加算の算定は、介護サービスの質を利用者やケアマネジャーに示す指標です。また、事業所にとっては営業活動の一環として、自社の介護サービスの質をアピールできるでしょう。

監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。